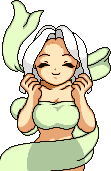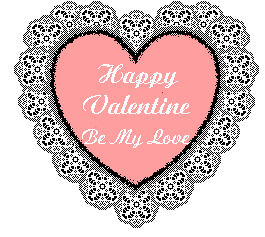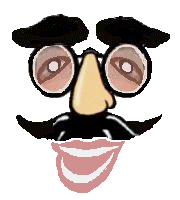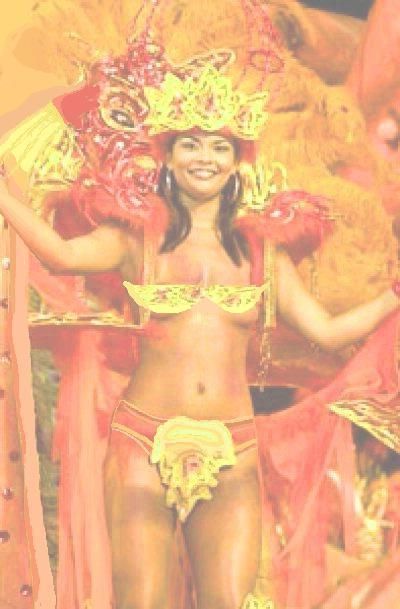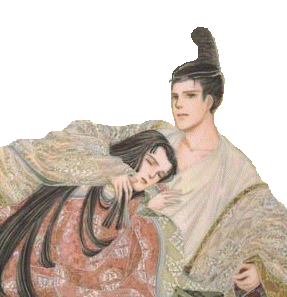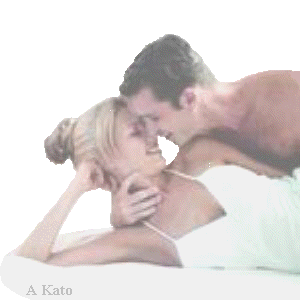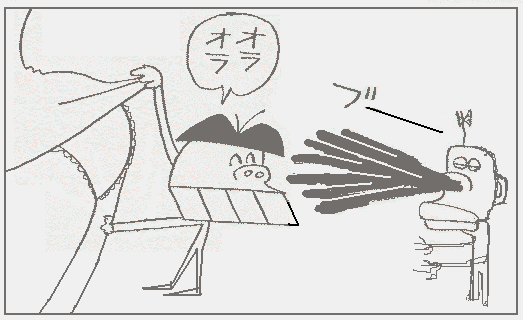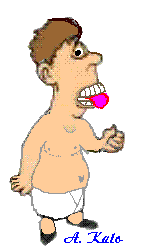らくだ

(rakuda10.jpg)

(rakuda12.jpg)

(rakuda13.jpg)

(junko05.gif)

(junko11.jpg)
デンマンさん。。。、 どういうわけでラクダを取り上げたのですか?

(kato3.gif)
実は、昨夜、三遊亭圓生の「らくだ」を聴いたのですよ。。。

(rakuda14.jpg)

三遊亭圓生の「らくだ」は名人芸です。。。僕は古今亭志ん生と、その息子の古今亭志ん朝と並んで、この三遊亭圓生がお気に入りの落語家なんですよ。。。暇があると、この三人の落語をしばしば聴きます。。。

どういうお話なのですか?
次のようなあらすじです。。。
らくだ (あらすじ)

(rakuda13.jpg)
とある長屋に馬という乱暴者が住んでいる。なりが大きくてのそのそしているので「らくだ」と呼ばれ、長屋中に嫌われている。
そのらくだの家に兄貴分の「手斧目の半次」がやってくる。
返事がないので入ってみると、らくだは前日食った河豚(フグ)にあたって死んでいた。
葬儀を出してやりたいが金のない半次が考え込んでいると屑屋の久六がやってきたので、室内の物を買い取ってもらおうとするが、屑屋が買えそうなものは何もない。
半次は久六を脅して無理矢理 月番の所に行かせ、長屋の住人から香典を集めてくるよう言いつけさせる。
気の弱い久六は乱暴な半次に逆らえない。
役目を終えて久六が戻ってくると、今度は大家の所に通夜に出す酒と料理を届けさせるよう命令される。
もし大家が断ったら「死骸のやり場に困っております。ここへ背負ってきますから、どうか面倒を見てやってください。ついでに『かんかんのう』を踊らせてご覧にいれます」と言え、と半次に言われた久六は仕方なく大家の家に向かい、その通りのことを伝えるが、大家は相手にしない。
久六が帰ってそのことを伝えると、半次は久六にらくだの死骸を担がせ、大家の所へ乗り込むと、かんかんのうの歌にあわせて死骸を文楽人形のように動かして見せる。

(rakuda12.jpg)
本当にやると思っていなかった大家は縮み上がってしまい、酒と料理を出すよう約束する。
これで解放されると思った久六だが、今度は八百屋に行って棺桶代わりの漬物樽を借りてこいと命令される。
しぶしぶ八百屋へ行き、らくだの死骸で大家を脅したことを伝えると、八百屋も怖れおののいて樽をくれる。
久六が戻ると大家の所から酒と料理が届いている。
半次に強引に勧められてしぶしぶ酒を飲んだ久六だったが、酔いが回ると性格が豹変し、半次に対して暴言を吐き始めて立場が逆転してしまう。
酒が無くなったと半次が言うと久六は「酒屋へ行ってもらってこい! 断ったらかんかんのうを踊らせてやると言え!!」と怒鳴りつける。
酔った二人はらくだの死骸を漬物樽に放り込んで荒縄でしばり、天秤棒を差し込んで二人で担ぎ、久六の知人がいる落合の火葬場に運び込むが、道中で樽の底が抜けてしまったらしくらくだの死骸がない。
探しに戻ると、橋のたもとで願人坊主(にわか坊主)がいびきをかいて眠っている。
二人はそれを死骸と勘違いし、樽に押し込んで焼き場に戻るとそのまま火の中へ放り込んでしまった。
熱さで願人坊主が目を覚ます。
「ここは何処だ!?」
「焼き場だ、日本一の火屋(ひや)だ」
「うへー、冷酒(ひや)でもいいから、もう一杯頂戴……」

この噺がデンマンさんのお気に入りなのですか?

他の落語家が演じた噺を聞いてないのだけれど、白面(しらふ)だと気の弱い屑屋の久六が酒を遠慮して飲みながら、やがて酒好きの本性を表して豹変してゆく様子を実に見事に演じているのですよ。。。
確かに、一人で演じているのに、色々な人物に成りすまして1時間近くも語るのは並の人間にはできませんよねぇ〜。。。
そうなのですよ。。。三遊亭圓生は、まさに名人の名に恥じない演技を見せています。。。この噺は、人物の出入りが多い上に、酔っ払いの芝居が入るなど演者にとって難解な話で、よく「真打の大ネタ」と呼ばれているのです。。。だから真打ちでも、うまい落語家じゃないとできない演目ですよ。。。次のようなエピソードが残っているのです。。。

(shokaku2.jpg)
東京では5代目古今亭志ん生、8代目三笑亭可楽、6代目三遊亭圓生、上方では戦中、戦後は4代目桂文團治、4代目桂米團治、6代目笑福亭松鶴が得意としたが、その中でも、6代目松鶴の「らくだ」は特に評価が高い。
3代目古今亭志ん朝は、若き日に、7代目立川談志とともに来阪した際に、松鶴の『らくだ』を見て、そのあまりの完成度の高さに、しばらく二人とも口がきけなかったと述懐している。

(shincho-danshi.jpg)
3代目(人間国宝の)桂米朝も「らくだ」を演じているが、松鶴存命中はあえて演じなかった。
また、6代目松鶴から稽古を付けられた4代目林家小染は1979年に初の独演会でこれを演じ、見ていた松鶴は感涙したという(ただし、中入りの対談でダメ出しはしている)。
松鶴自身『らくだ』を物にするにはかなりの苦労があった。
若い頃演じた時は、始め勢いがあったのが終わり近くの葬礼あたりで目に見えて力が落ち散々な出来となり、居合わせたお囃(はや)しの林家とみらは声も掛けられなかった。
そんな研鑽(けんさん)を経て、1969年(昭和44年)12月17日大阪大淀ABCホールでの「第38回上方落語をきく会」と1973年(昭和48年)6月12日、大阪難波高島屋ホールでの「第50回上方落語を聞く会」で演じた『らくだ』は松鶴にとって双璧(そうへき)といえる出来であった。
特に後者はライバルの桂米朝との二人会という事情もあり、力のこもったものであった。

(shokaku-beicho.jpg)
出典:「らくだ (落語)」
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

今度は、笑福亭松鶴の「らくだ」を聴いてみようと思いますよ。。。

ところで、「らくだ」を取り上げたのには、他にも理由があるのですか?
あのねぇ〜、三遊亭圓生が「まくら(噺の出だし)」で語っているのだけれど、ラクダが文政4年(1821年)に江戸にやって来たのですよ。。。両国で見世物として庶民に見せた。。。

(rakuda13.jpg)

砂漠でその本領を発揮するラクダだけれど、それを知らない江戸っ子達は、その大きな図体を見て「何の役に立つんだ?」と思ったらしい。そこで、図体の大きな人や、のそのそした奴を「ラクダ」と呼ぶようになった。それがこの噺の下敷きになっている。。。

ラクダが日本にやって来なかったら、この噺はなかったのですわねぇ〜。。。
そういうことです。。。1821年に2頭のヒトコブラクダがオランダ商人の船で出島に運ばれてきたのだけれど、この時が初めてではなかった。
あらっ。。それ以前にもラクダが日本にやってきていたのですか?
そうなのです。。。『日本書紀』に、推古天皇の代の599年に百済からラクダが一匹献上されたと書いてある。。。ところが、日本にはサハラ砂漠のような砂漠がなかったのでラクダがキャラバン隊の役畜として普及することはなかったのですよ。。。だから、それ以降、ラクダを求めることもなかった。。。
でも、現在では観光用にラクダが鳥取の砂丘で活躍しているようです。。。私の友達が写真を送ってくれましたわ。。。

(rakuda30.jpg)

なるほどォ〜。。。ラクダを金儲けの道具に使っているのですねぇ〜。。。

ところで「カンカンノウ」という歌が100年以上も流行歌として明治の頃まで庶民に歌われた、と三遊亭圓生さんが話してますけれど どういうわけではやり始めたのですか?
あのねぇ〜、そもそも、この歌が初めて歌われたのは文政4年(1821年)3月15日でした。。。つまり、ラクダがやってきた年ですよ。。。この日、深川の永代寺(今の富岡門前町)で、成田の不動の出開帳があった時に、唐人踊という見せ物が出たのです。これが大評判で5月29日まで引き続いて興行した。永代寺で興行する前に、葺屋町河岸でもやったけれども、その時はまだ人気もなかった。それが一時に流行出して、四月には江戸の市中を、「唐人おどりかんかん節」などと「かわら版」が出た。。。歌詞は次のようなものだった。。。
かんかんのう(看々那)きう(九)のれんす(連子)
きう(九)はきうれんす(九連子)
きはきうれんれん(九九連々)さんしょならへ(三叔阿)
さァいィほうにくわんさん(財副儞官様)
いんぴいたいたい(大々)やんあァろ
めんこんぽはうでしんかんさん(面孔不好的心肝)
もゑもんとはいゝぴいはうはう(屁好々)
てつこうにくわんさん(鉄公儞官様)
きんちうめーしなァちうらい(京酒拿酒来)
びやうつうほしいらァさんぱん(嫖子考杉板)
ちいさいさんぱんぴいちいさい(杉板屁)
もゑもんとはいゝぴいはうぴいはう(屁好々)
この上の歌に合わせて踊ったようです。。。

(kankan10.jpg)

(kankan11.jpg)
『かんかん踊』より

三遊亭圓生も噺の中で、上のクリップのように最初のサワリの部分を唄ってます。。。

この歌が大流行をしたということですけれど、当時の江戸政府が猥褻な歌だから唄うのを禁止したと「まくら」で三遊亭圓生さんが話してますけれど、どこが猥褻なのですか?
あのねぇ〜、上の踊りの「振り」を見ると四つん這(ば)いになって女の寝床の中に入って夜這いするしぐさはないのだけれど、三遊亭圓生の「まくら」では、そういう仕草が踊りの中にあったと言うのです。。。それが卑猥だというわけですよ。。。だから、「かんかんのうをきめる」と言うと「夜這いをする」という意味で使われたと言うのです。。。
「夜這い」というのは、江戸時代には、それほど流行(はや)ったのですかァ〜?
ところによると太平洋戦争の頃まで行われていた風習だということです。。。
夜這い

(yobai10.jpg)
夜這い(よばい)は、古代日本の婚姻当初の一形態。
求婚する女のもとへ通う妻問婚のこと。
後には、強姦まがいに夜中に性交を目的に他人の寝ている場所を訪れる行為をも意味するようになった。
語義は「呼び続ける」こと。
古代の言霊信仰では、相手の名を呼び続けることで言霊の力で霊魂を引き寄せることができると考えられた。
国文学関係の研究者の間では、一般には夜這いは古代に男が女の家へ通った「よばう」民俗の残存とする考え方が多い。
語源は、男性が女性に呼びかけ、求婚すること(呼ばう)であると言われる。
古くは、759年に成立した『万葉集』巻12に「他国に よばひに行きて 大刀が緒も いまだ解かねば さ夜そ明けにける」と歌われている。

(yobai13.jpg)
大正時代まで農漁村中心に各地で行われていた習俗。
戦後、高度成長期直前まで、各地の農漁村に残存していた。
徳川時代には、法令、藩法、郷村規約などで、しばしば夜遊びや夜這いの禁令を出したが、婚姻制的な強制ではなく、風俗的な取締りにすぎないものであった。
明治維新には近代化が図られ、明治政府が富国強兵の一環として国民道徳向上の名目で、一夫一妻制の確立、純潔思想の普及を強行し夜這い弾圧の法的基盤を整備した。
また農漁村への電灯の普及などもあと押し、明治以降は衰退する傾向にあった。
明治政府は資本主義体制の発展を図り、農村、とくに貧農民を農村から離脱させ、都市部に吸収して安価な労働力として利用し、農村では小作農として定着、地主の封建的地代の収奪を強行し、地主対小作の対抗を先鋭化させた。
その結果、都市や新興の工業地帯の男性の性的欲求の解消のために遊廓、売春街、三業地などの創設、繁栄を図り、資本主義的性機構の発達によって巨大な収益を期待した。
農村地帯で慣行されていた夜這いやその他の性民俗は、非登録、無償の原則であり、国家財政に対する経済的寄与が一切なかった結果、明治、大正の頃まで夜這いが盛んだったのは、山深い山間部の村落中心となった。
多くの場合、男性が、女性の元へ通うものだが、女性が通う風習を持つ地域もあった。
婚、嫁、結婚などの字を古くは「よばふ」「よばひ」と呼んだ。
これは「呼ぶ」の再活用形で「つまどい」「つままぎ」などの語と共に求婚のために男が女のもとに通うことを意味した。
昔の婚姻は結婚後も男が女のもとに通うのが普通であり、このことも「よばい」と言われた。
古代日本の夫婦関係は「妻問い婚」であり、男女はそれぞれに住んでいて妻の元へ夫が通ってゆく形態であった。
結婚というのは、家族に隠れてこっそりと夜這いを行うのではなく、堂々と通えるようになることを意味した。
そもそも各地の共同体(村社会)においては『一夫一婦制』と言う概念も希薄で、重婚、夜這いは当たり前であった。

(yobai11.jpg)
かつての農村では、「村の娘と後家は若衆のもの」という村落内の娘の共有意識を示す言葉があった。
近代化以前の農村には若者組があり、村落内における婚姻の規制や承認を行い、夜這いに関しても一定のルールを設けていた。
ルールには未通女や人妻の取り扱いなどがあり、細かい点は地域によって差がみられた。
下川耿史によれば、夜這いが盛んになったのは、南北朝時代から鎌倉時代にかけての中世であり、村落共同体の若者組は、風流と呼ばれる華やかな祭りのリーダーだったという。
江戸など都市部では、村落と異なる形に発達していった。
これが『夜這いの衰退に繋がったと考えられる』とする見方がある。
1876年(明治9年)、現在の新潟県(相川県)で、夜這いを禁止する条例ができた。
1938年(昭和13年)に起きた津山事件について、大阪毎日新聞が「山奥にいまなお残されている非常にルーズな男女関係の因習」と報道し、サンデー毎日が「娯楽に恵まれない山村特有の『男女関係』」と報じるなど、夜這いは否定的に見られるようになっていった。
出典:「夜這い」
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

あらっ。。。夜這いの風習は 戦後、高度成長期直前まで、各地の農漁村に残存していたのですわねぇ〜。。。驚きですわァ〜。。。

確かに、昔は夜這いは普通に行われていたんでしょう。。。でもねぇ〜、「一夫一婦制」が当たり前になってくると、夜這いを禁止する条例ができるようになった。。。夜這いが殺人事件に発展するようになると夜這いは否定的に見られるようになっていったのですよ。。。
今では、お互いが同意の上で行わない限り、性犯罪になりますよねぇ〜。。。
そういうことです。。。

(laugh16.gif)
【ジューンの独り言】

(bare02b.gif)
ですってぇ~。。。
あたなたも、もし夜這いしたくなったら、相手の女性に予め電話をかけて了解を得てからにしてくださいねぇ〜。。。
じゃないと、警察沙汰になって新聞で報道されてしまいますわァ〜。。。
ええっ。。。 「そんなことは どうでもいいから、他に何か面白いことを話せ!」
あなたは、そのように わたしにご命令なさるのですかァ~?
分かりましたわ。。。 じゃあ、面白い動画をお目にかけますわァ。。。
ワンワンちゃんが人間の言葉をしゃべります!

(dog810.jpg)
ええっ。。。? 「そんな馬鹿バカしい動画など、どうでもいいから、何か他に面白い話をしろ!」
あなたは、また そのような命令口調で わたしに強要するのですか?
わかりましたわァ。。。
では、たまには日本の歴史の話も読んでみてくださいなァ。
日本の古代史にも、興味深い不思議な、面白いお話がありますわァ。
次の記事から興味があるものをお読みくださいねぇ~。。。
■天武天皇と天智天皇は
同腹の兄弟ではなかった。
■天智天皇は暗殺された
■定慧出生の秘密
■藤原鎌足と長男・定慧
■渡来人とアイヌ人の連合王国
■なぜ、蝦夷という名前なの?
■平和を愛したアイヌ人
■藤原鎌足と六韜
■古事記より古い書物が
どうして残っていないの?
■今、日本に住んでいる人は
日本人でないの?
■マキアベリもビックリ、
藤原氏のバイブルとは?
ところで、他にも面白い記事がたくさんあります。
興味のある方は次の記事も読んでみてくださいね。
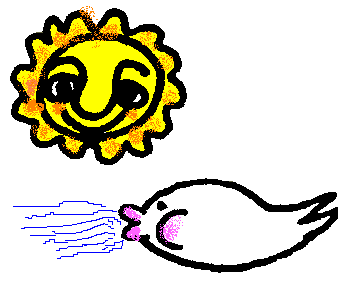
(sunwind2.gif)

(sylvie500.jpg)
■『シャフリ・ソフタ』
■『閨房でのあしらい』
■『漱石とグレン・グールド』
■『女性の性欲@ラオス』
■『美学de愛と性』
『女の本音』
■『にほん村からの常連さん』
■『日本初のヌードショー』
■『可愛い孫』
■『ネットで広まる』
■『なぜブログを書くの?』
■『アルゼンチンから』
■『潮吹き』
■『ヨッパライが帰ってきた』
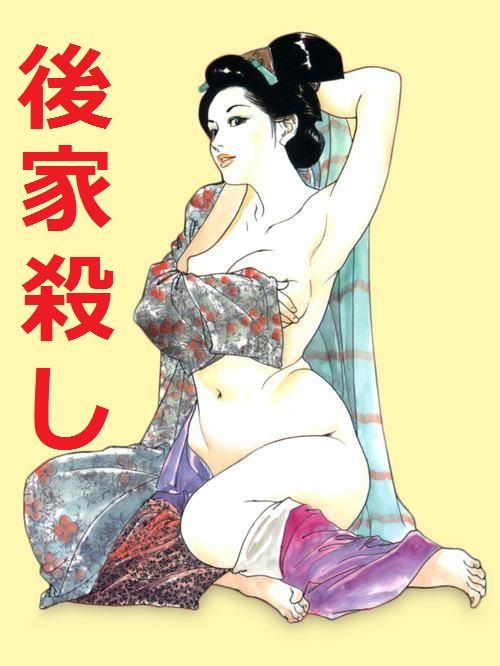
(ken203h.jpg)
■『後家殺し』
■『奇想天外』
■『下女のまめは納豆』
■『オペラミニ』
■『三角パンツ』
■『サリーの快楽』
■『ラーメン@ゲブゼ市』
■『安心できない@病院』
■『ブルマー姿@自転車』
■『女性の性欲研究』
■『頭のいい馬』

(miya08.jpg)
■『トランプ@マラウイ』
■『きれじ』
■『コッペパン』
■『くだらない話』
■『大蛇が破裂』
■『グルーヴ』
■『タスマニアデビル』
■『女と反戦』
■『裸女に魅せられ』
■『素敵な人を探して』
■『カクセンケイ』
■『博士の異常な愛情』

(teacher9.jpg)
■『パレートの法則』
■『こんにちわ@ブリュッセル』
■『いないいないばあ』
■『食べないご馳走』
■『10分間に900件を越すアクセス』
■『5分間に340件のアクセス』
■『縦横社会』
■『村上春樹を読む』
■『パクリボット』
■『露出狂時代』
■『露出狂と反戦』
■『オナラとサヴァン症候群』
■『検疫の語源』
■『共産党ウィルス』
■『馬が合う』
■『オックスフォードの奇人』
■『風馬牛』
■『未亡人の苦悶』
■『群青の石deロマン』
■『露出で検索』
■『テレポーテーション』
■『露出狂』
■『第6感』
■『大邱の読者』
■『無重力の性生活』
■『純子さんのクローン』
■『肥後ずいき使用感』
■『アナスタシア』
■『検察が裏金作り』
■『ガリポリから愛を込めて』
とにかく、今日も一日楽しく愉快に
ネットサーフィンしましょう。
じゃあね。バーィ。

(hand.gif)




(spacer.gif+betty5de.gif)
(hiroy2.png+betty5d.gif)
『スパマー HIRO 中野 悪徳業者』

(surfin2.gif)
ィ~ハァ~♪~!
メチャ面白い、
ためになる関連記事

(himiko92.jpg)
■『卑弥子の源氏物語』
■『平成の紫式部』
■ めれんげさんの『即興の詩』
■ めれんげさんの『極私的詩集』

(bagel702.jpg)
■ "JAGEL - Soft Japanese Bagel"

(linger65.gif)
■ 『センスあるランジェリー』
■ 『ちょっと変わった 新しい古代日本史』
■ 『面白くて楽しいレンゲ物語』

(beach02.jpg)
■ 『軽井沢タリアセン夫人 - 小百合物語』
■ 『今すぐに役立つホットな情報』

(rengfire.jpg)

(byebye.gif)