東舞鶴の式内社3社のうちのひとつ阿良須神社は福井方面に走る国道27号線沿いに鎮座する神社である。
【創建】伝 崇神天皇10年
【ご祭神】豊受大神 木花開夜姫命
【社格】延喜式内小社 正三位 郷社
【境内】鳥居1柱 灯籠2対 狛犬1対 手水舎 境内摂社3社 拝殿 本殿など
【場所】舞鶴市小倉
「正一位一宮大明神」の額がかかる鳥居。石標には「郷社阿良須神社」とある。



先年の台風で被害を受けた。 手水舎の水盤には明和壬辰(=明和9年(1772))の銘


手前は交通量の多い国道だが境内は静寂な森の中である。

廻廊付の拝殿。享和元年(1801)の造営である。

本殿は文政12年(1829)の造営。彫刻が見事である。平成16年に上掲の写真のとおり台風被害を受けたが復興を遂げた。

本殿前の石標に「式内阿良須神社」とある。隣の大江町にも式内阿良須神社があるが、比定地としては
舞鶴の阿良須神社は分が悪いそうだ。


本殿前の狛犬は寛政6年(1794)に奉納された。後姿がとてもかわいい。



同じく本殿前の灯籠は安永9年(1780)に奉納された。

境内摂社。左から二柱神社・神明神社

<参拝メモ>
自動車で阿良須神社へ向かう。神社の鳥居の横に入り口があり、社務所らしき建物の前に車が数台置ける
スペースがあった。国道は車の往来が多くてちょうどカーブの中間に入り口があるので、進入するときは
急ブレーキなどは要注意である。
車を降りて一旦鳥居前に出ると鳥居が横並びに2柱ある。後で調べてみると向かって左側が阿良須神社で
右側は「布留山神社」という隣接しながらも別の神社であるそうだ。しかしその本殿は阿良須神社の境内から
境なくいけるので、はじめは境内社かと思っていた。しかも布留山神社の方がこの地に鎮座したのが古くて
阿良須神社は戦災して江戸初期に引っ越してきたそうである(上掲の由緒板より)
布留山神社の鳥居と本殿


境内はけっこうきれいに整備されている。拝殿には廻廊がついているが、横脇のみなので本殿の前にまで
行くことができる。覆屋もなく彫刻で施された本殿を近くで見ることができる。社殿および灯籠・狛犬なども
江戸時代のものが残る。本殿向かって左側には「愛宕大神」の鳥居がありその奥に参道らしきものがあるが
草深くてとても行けそうになかった。
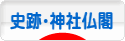 ←ポチリとクリック応援お願いします
←ポチリとクリック応援お願いします
【創建】伝 崇神天皇10年
【ご祭神】豊受大神 木花開夜姫命
【社格】延喜式内小社 正三位 郷社
【境内】鳥居1柱 灯籠2対 狛犬1対 手水舎 境内摂社3社 拝殿 本殿など
【場所】舞鶴市小倉
「正一位一宮大明神」の額がかかる鳥居。石標には「郷社阿良須神社」とある。



先年の台風で被害を受けた。 手水舎の水盤には明和壬辰(=明和9年(1772))の銘


手前は交通量の多い国道だが境内は静寂な森の中である。

廻廊付の拝殿。享和元年(1801)の造営である。

本殿は文政12年(1829)の造営。彫刻が見事である。平成16年に上掲の写真のとおり台風被害を受けたが復興を遂げた。

本殿前の石標に「式内阿良須神社」とある。隣の大江町にも式内阿良須神社があるが、比定地としては
舞鶴の阿良須神社は分が悪いそうだ。


本殿前の狛犬は寛政6年(1794)に奉納された。後姿がとてもかわいい。



同じく本殿前の灯籠は安永9年(1780)に奉納された。

境内摂社。左から二柱神社・神明神社

<参拝メモ>
自動車で阿良須神社へ向かう。神社の鳥居の横に入り口があり、社務所らしき建物の前に車が数台置ける
スペースがあった。国道は車の往来が多くてちょうどカーブの中間に入り口があるので、進入するときは
急ブレーキなどは要注意である。
車を降りて一旦鳥居前に出ると鳥居が横並びに2柱ある。後で調べてみると向かって左側が阿良須神社で
右側は「布留山神社」という隣接しながらも別の神社であるそうだ。しかしその本殿は阿良須神社の境内から
境なくいけるので、はじめは境内社かと思っていた。しかも布留山神社の方がこの地に鎮座したのが古くて
阿良須神社は戦災して江戸初期に引っ越してきたそうである(上掲の由緒板より)
布留山神社の鳥居と本殿


境内はけっこうきれいに整備されている。拝殿には廻廊がついているが、横脇のみなので本殿の前にまで
行くことができる。覆屋もなく彫刻で施された本殿を近くで見ることができる。社殿および灯籠・狛犬なども
江戸時代のものが残る。本殿向かって左側には「愛宕大神」の鳥居がありその奥に参道らしきものがあるが
草深くてとても行けそうになかった。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます