参観ルートは御幸門~外腰掛を通って御茶屋である「松琴亭」(しょうきんてい)に到ります。池を中心に
その周りを歩いて鑑賞する庭ですが、この松琴亭からの眺めが最も感動しました。池を挟んで古書院と月波楼。

天の橋立。日本三景の天の橋立を模したものです。

天の橋立の奥に州浜と岬灯篭。手前の石橋は水面すれすれです。

松琴亭の内部。加賀奉書で張られた市松模様が見どころです


茶事の他、料理も客人の目の前で作って楽しませた御茶屋なのでお竈さんがあります。

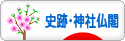 ←ポチッとクリック応援お願いします!
←ポチッとクリック応援お願いします!
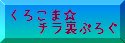 ←こちらもよろしく!
←こちらもよろしく!
その周りを歩いて鑑賞する庭ですが、この松琴亭からの眺めが最も感動しました。池を挟んで古書院と月波楼。

天の橋立。日本三景の天の橋立を模したものです。

天の橋立の奥に州浜と岬灯篭。手前の石橋は水面すれすれです。

松琴亭の内部。加賀奉書で張られた市松模様が見どころです


茶事の他、料理も客人の目の前で作って楽しませた御茶屋なのでお竈さんがあります。

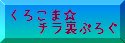 ←こちらもよろしく!
←こちらもよろしく!
桂離宮の参観中の写真撮影は移動中は危険なためNGで、撮影ポイントはだいたい決められています。
なのでどれもこれも撮影ができるわけではないのですが、そんな中撮影できたものをUPしていきます。
桂離宮の参観ルートは庭園ほぼ1周(約700m)を約1時間かけて歩きます。桂離宮の庭園は回遊式庭園で
池の周りを散策して点在する御茶屋で休みながら庭の眺めを楽しみます。御茶屋の待合腰掛が2ヶ所あります。
「外腰掛」と「四ツ腰掛(卍亭)です。外腰掛の前には薩摩島津家から献上された当時は珍しかったソテツが
植えられて(蘇鉄山)思いがけない風景で楽しませてくれます。

外腰掛前の「行の飛石」とその視界の先に生込寄灯篭。歩く人の視線を意識した造りです。

参観ルートからははずれますが、外腰掛のほかにもうひとつの待合が4ツ腰掛(卍亭)

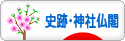 ←ポチッとクリック応援お願いします!
←ポチッとクリック応援お願いします!
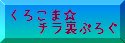 ←こちらもよろしく!
←こちらもよろしく!
なのでどれもこれも撮影ができるわけではないのですが、そんな中撮影できたものをUPしていきます。
桂離宮の参観ルートは庭園ほぼ1周(約700m)を約1時間かけて歩きます。桂離宮の庭園は回遊式庭園で
池の周りを散策して点在する御茶屋で休みながら庭の眺めを楽しみます。御茶屋の待合腰掛が2ヶ所あります。
「外腰掛」と「四ツ腰掛(卍亭)です。外腰掛の前には薩摩島津家から献上された当時は珍しかったソテツが
植えられて(蘇鉄山)思いがけない風景で楽しませてくれます。

外腰掛前の「行の飛石」とその視界の先に生込寄灯篭。歩く人の視線を意識した造りです。

参観ルートからははずれますが、外腰掛のほかにもうひとつの待合が4ツ腰掛(卍亭)

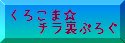 ←こちらもよろしく!
←こちらもよろしく!
桂離宮には多くの建物も残りますが、種別すると書院(4棟)・宴や茶事を催す御茶屋(4棟)・持仏堂(1棟)・
待合腰掛(2棟)があります。このうち居住空間になるのが書院です。初代智仁親王によって一番初めに
古書院が造られ、二代智忠親王によって中書院・楽器の間・新御殿が造られました。残念ながら書院の室内は
見物ができませんが、写真では見ることができます。凝ったつくりがあちこちにされていて、それを見つけて
鑑賞することも当時この山荘を訪れた人々の楽しみのひとつだったそうです。
古書院は丸みをおびた屋根が印象的です。

古書院には観月するための月見台が設けられています。丸竹を敷き延べただけの簡素な簀子で、池に向って
張り出していますが高欄などの仕切りがなく書院と庭との結界を無くして直結させた独創的な造りとなっています。

月見台あたりから見る眺望はこのようになります。月が中空に浮かぶと池にも月が映り、二つの月が楽しめる趣向です。

古書院に連なって中書院(右)楽器の間(中)新御殿(左)が建ちます。古書院は接客の座敷で中書院は
日常的な生活の座敷、楽器の間はその名のとおり楽器を置いた部屋で、写真にも見える広縁から前の広場で
行なわれる蹴鞠を見物したそうです。新御殿は後水尾院を迎えるための御幸御殿です。屋根はいずれも桧皮葺。

参考文献:小学館『日本庭園をゆく』
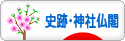 ←ポチッとクリック応援お願いします!
←ポチッとクリック応援お願いします!
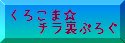 ←こちらもよろしく!
←こちらもよろしく!
待合腰掛(2棟)があります。このうち居住空間になるのが書院です。初代智仁親王によって一番初めに
古書院が造られ、二代智忠親王によって中書院・楽器の間・新御殿が造られました。残念ながら書院の室内は
見物ができませんが、写真では見ることができます。凝ったつくりがあちこちにされていて、それを見つけて
鑑賞することも当時この山荘を訪れた人々の楽しみのひとつだったそうです。
古書院は丸みをおびた屋根が印象的です。

古書院には観月するための月見台が設けられています。丸竹を敷き延べただけの簡素な簀子で、池に向って
張り出していますが高欄などの仕切りがなく書院と庭との結界を無くして直結させた独創的な造りとなっています。

月見台あたりから見る眺望はこのようになります。月が中空に浮かぶと池にも月が映り、二つの月が楽しめる趣向です。

古書院に連なって中書院(右)楽器の間(中)新御殿(左)が建ちます。古書院は接客の座敷で中書院は
日常的な生活の座敷、楽器の間はその名のとおり楽器を置いた部屋で、写真にも見える広縁から前の広場で
行なわれる蹴鞠を見物したそうです。新御殿は後水尾院を迎えるための御幸御殿です。屋根はいずれも桧皮葺。

参考文献:小学館『日本庭園をゆく』
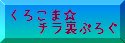 ←こちらもよろしく!
←こちらもよろしく!


















