桂の地は古来より月の名所でした。地名の「桂」も中国の故事「月桂」(月の樹)からとられたと言われます。
そしてこの桂の山荘も時とともに場所を変えて月を楽しめるように工夫されています。まず月の出を楽しむ
場所がその名も「月波楼」(げっぱろう)と呼ばれる観月のための茶亭です。月波楼全景。

月波楼には東と北に簀の子縁があり、東面では庭園の池と月を鑑賞し、北面では紅葉山の紅葉を愛でました。

月波楼の内部は天井を張らない開放的な造りで、霊元院(天皇)宸筆の「歌月」の扁額がかかります。
視界の先に見えるのが紅葉山。

月波楼から東面を見る。観月の時ははこのような眺望でした。奥の茶屋は松琴亭。

さらに時が過ぎて月が中空に浮かぶ頃、月波楼の隣に建つ「古書院」の月見台が次の観月の場となります。
参考文献:小学館『日本庭園をゆく』
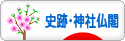 ←ポチッとクリック応援お願いします!
←ポチッとクリック応援お願いします!
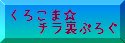 ←こちらもよろしく!
←こちらもよろしく!
そしてこの桂の山荘も時とともに場所を変えて月を楽しめるように工夫されています。まず月の出を楽しむ
場所がその名も「月波楼」(げっぱろう)と呼ばれる観月のための茶亭です。月波楼全景。

月波楼には東と北に簀の子縁があり、東面では庭園の池と月を鑑賞し、北面では紅葉山の紅葉を愛でました。

月波楼の内部は天井を張らない開放的な造りで、霊元院(天皇)宸筆の「歌月」の扁額がかかります。
視界の先に見えるのが紅葉山。

月波楼から東面を見る。観月の時ははこのような眺望でした。奥の茶屋は松琴亭。

さらに時が過ぎて月が中空に浮かぶ頃、月波楼の隣に建つ「古書院」の月見台が次の観月の場となります。
参考文献:小学館『日本庭園をゆく』
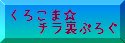 ←こちらもよろしく!
←こちらもよろしく!



























 葛井寺も本堂横の桜が満開。
葛井寺も本堂横の桜が満開。