レンタサイクルで奈良市内を走ってた日、せっかく自転車なので奈良市山町にある尼門跡(比丘尼御所)の
円照寺まで行きました。経路としては東大寺大仏殿からまっすぐ道を南下して、円照寺バス停前に
参道入り口があり、さらにそこを進むと山門が見えてきます。大仏殿からは距離にすると5km近くは
ありますかね。参道はうっそうとした森林の中にあって俗界とは完全に遮断された空間に境内があります。


円照寺門跡寺史
開基は後水尾院(天皇)第一皇女の梅宮、法名は文智大通大師。寛永18年(1641)修学院に草庵を
結んでこれが円照寺の始まりであるが、後水尾院の修学院山荘造営の時に奈良の八嶋村に移転する。
さらに寛文9年(1669)に八嶋村から近くの山村に移転して現在にまで至る。代々皇女をもって
住持とした。寺領300石。臨済宗妙心寺派、本尊は如意輪観音菩薩。
幸薄い皇女梅宮
開基の梅宮は後水尾院の第一皇女として生まれましたが、生母がおよつ御寮人(将軍息女の東福門院入内
の前にいた後水尾院の愛妾でその存在が幕府の忌諱に触れていた)であったために内親王宣下もなく
日陰的な存在でした。摂家の鷹司家に降嫁しましたが、やがて離縁となり出戻りになります。
そして生母のおよつ御寮人が没した後に剃髪して仏門に入りました。そのときはまだ22才の若さです。
父帝である後水尾院とは仏道を通じて父娘の情愛を深め、継母にあたる東福門院や異腹の妹たちとも
交流があったようです。最初に草庵を結んだ修学院も山里ですが、さらに京洛から離れた草深き地を求めて
大和の八嶋村、さらには山村に移居して80歳近い天寿を全うしました。
境内には内裏の旧殿を移築した宸殿の他に書院や奥御殿などがあるそうですが非公開です。写真は書院の玄関で
右側に少し見える茅葺屋根の建物が本堂(円通殿)です。結界があるので境内も深くは入れません。


修学院にある林丘寺と同じく外とはあまり交わらないガードの固い尼門跡のようです。しかし境内は
整然としていて江戸時代からの建物も外見では特に痛んでいる様子もなかったですが、檀家もなく観光収入も
なくて寺観を保持しているのは不思議です。他の拝観謝絶尼門跡寺院も同様ですが・・・。
円照寺は山村御流という華道の家元だそうです。入門したら御殿に昇殿できるのでしょうかね。
これで京洛・南都に残る尼門跡13ヶ寺はすべて訪れました。そのうち拝観ができたのは中宮寺・宝鏡寺・曇華院・
霊鑑寺・法華寺の5ヶ寺で、拝観はできなかったもののご朱印がいただけたのは大聖寺・光照院の2ヶ寺、
その他の拝観謝絶でご朱印もないのが三時知恩寺・慈受院・宝慈院・本光院・林丘寺・円照寺の6ヶ寺。
尼門跡寺院は幕末には15ヶ寺あり、慈受院と併合した総持院を除いて14ヶ寺が現在まで法灯を継いでいます。
皇子親王の門跡とは異なって皇女や摂家子女の隠棲御所としての側面をも持つためか、江戸時代の寺領も
数十石~数百石と少なくて現在もこじんまりとした境内が印象的ですが、定規筋の入った塀に
菊の御紋の瓦を頂く門や宸殿などの御殿、庭の造作などに格式高い独特な雰囲気を感じました。
御所人形が多く残るのも尼門跡特有と言えますか。
拝観を行なわない寺院はそれなりの理由があると思いますが、期間限定でもなにかの機会で拝観できる日が
来ることを希望して待ちます。尼門跡(比丘尼御所)は残り1ヶ寺、近江八幡に瑞龍寺門跡があります。
こちらは少し遠いのでまたの機会に訪れたいと思います。
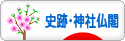 ←ポチッとクリック応援お願いします!
←ポチッとクリック応援お願いします!
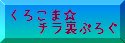 ←こちらもよろしく!
←こちらもよろしく!
円照寺まで行きました。経路としては東大寺大仏殿からまっすぐ道を南下して、円照寺バス停前に
参道入り口があり、さらにそこを進むと山門が見えてきます。大仏殿からは距離にすると5km近くは
ありますかね。参道はうっそうとした森林の中にあって俗界とは完全に遮断された空間に境内があります。


円照寺門跡寺史
開基は後水尾院(天皇)第一皇女の梅宮、法名は文智大通大師。寛永18年(1641)修学院に草庵を
結んでこれが円照寺の始まりであるが、後水尾院の修学院山荘造営の時に奈良の八嶋村に移転する。
さらに寛文9年(1669)に八嶋村から近くの山村に移転して現在にまで至る。代々皇女をもって
住持とした。寺領300石。臨済宗妙心寺派、本尊は如意輪観音菩薩。
幸薄い皇女梅宮
開基の梅宮は後水尾院の第一皇女として生まれましたが、生母がおよつ御寮人(将軍息女の東福門院入内
の前にいた後水尾院の愛妾でその存在が幕府の忌諱に触れていた)であったために内親王宣下もなく
日陰的な存在でした。摂家の鷹司家に降嫁しましたが、やがて離縁となり出戻りになります。
そして生母のおよつ御寮人が没した後に剃髪して仏門に入りました。そのときはまだ22才の若さです。
父帝である後水尾院とは仏道を通じて父娘の情愛を深め、継母にあたる東福門院や異腹の妹たちとも
交流があったようです。最初に草庵を結んだ修学院も山里ですが、さらに京洛から離れた草深き地を求めて
大和の八嶋村、さらには山村に移居して80歳近い天寿を全うしました。
境内には内裏の旧殿を移築した宸殿の他に書院や奥御殿などがあるそうですが非公開です。写真は書院の玄関で
右側に少し見える茅葺屋根の建物が本堂(円通殿)です。結界があるので境内も深くは入れません。


修学院にある林丘寺と同じく外とはあまり交わらないガードの固い尼門跡のようです。しかし境内は
整然としていて江戸時代からの建物も外見では特に痛んでいる様子もなかったですが、檀家もなく観光収入も
なくて寺観を保持しているのは不思議です。他の拝観謝絶尼門跡寺院も同様ですが・・・。
円照寺は山村御流という華道の家元だそうです。入門したら御殿に昇殿できるのでしょうかね。
これで京洛・南都に残る尼門跡13ヶ寺はすべて訪れました。そのうち拝観ができたのは中宮寺・宝鏡寺・曇華院・
霊鑑寺・法華寺の5ヶ寺で、拝観はできなかったもののご朱印がいただけたのは大聖寺・光照院の2ヶ寺、
その他の拝観謝絶でご朱印もないのが三時知恩寺・慈受院・宝慈院・本光院・林丘寺・円照寺の6ヶ寺。
尼門跡寺院は幕末には15ヶ寺あり、慈受院と併合した総持院を除いて14ヶ寺が現在まで法灯を継いでいます。
皇子親王の門跡とは異なって皇女や摂家子女の隠棲御所としての側面をも持つためか、江戸時代の寺領も
数十石~数百石と少なくて現在もこじんまりとした境内が印象的ですが、定規筋の入った塀に
菊の御紋の瓦を頂く門や宸殿などの御殿、庭の造作などに格式高い独特な雰囲気を感じました。
御所人形が多く残るのも尼門跡特有と言えますか。
拝観を行なわない寺院はそれなりの理由があると思いますが、期間限定でもなにかの機会で拝観できる日が
来ることを希望して待ちます。尼門跡(比丘尼御所)は残り1ヶ寺、近江八幡に瑞龍寺門跡があります。
こちらは少し遠いのでまたの機会に訪れたいと思います。
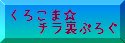 ←こちらもよろしく!
←こちらもよろしく!
大和三尼門跡のうちのひとつ、法華寺の本尊十一面観音が開帳されているので初めてお参りに行きました。
法華寺は奈良市内中心部からは少し離れていまして、近鉄新大宮から北西方向に平城宮跡の並びに
あります。JR奈良駅からはバスも運行されていますが、よく晴れた春の日なのでレンタサイクルで
行きました。JR奈良駅からは自転車で約15分ほどで到着します。途中の佐保川周辺も桜満開です。

4月初旬は「ひな会式」という法要が毎日午前中に本堂であるので、その時間帯は本堂には入れません。
あわせて献茶・献花などの催しものもあるので人が多いです。
法華寺赤門(通用門) 法華寺南門(切妻造本瓦葺の四脚門・重文)


法華寺門跡寺史
奈良朝の天平13年(741)光明皇后が藤原不比等の邸宅跡に創建した。東大寺が聖武天皇発願の
総国分寺であるのに対して法華寺は皇后発願の総国分尼寺である。「法華滅罪之寺」とも称する。
平安遷都後は衰微して荒廃するが、鎌倉中期の寛元3年(1245)に奈良西大寺の叡尊によって
諸堂が復興されて西大寺末寺となる。室町期には興福寺末寺。戦国期に三好松永の兵火で伽藍を
焼失するが、豊臣秀頼によって再興されて本堂・南門・鐘楼などが現在に残る。江戸時代には
寺領220石。真言律宗を経て現在は光明宗。
ご本尊を拝しました。厨子の中で蓮華座に立っておられる十一面観音ですが、目鼻立ちがはっきりと
した男顔の観音像だと思いましたが、後に調べると光明皇后の御顔を写した天平の女人顔ということで
大変失礼しました(笑) 口にかすかに紅色が残るのがわかります。本尊を守護する四天王像が
厨子の四方に立ち、聖武天皇と光明皇后の御尊牌が安置されていました。法華寺本堂は重文です。

境内は桜をはじめ花盛りです。鐘楼(写真左)も秀頼寄進で重要文化財。




奈良の古寺院では珍しく本堂脇手・裏手に江戸初期に作庭された庭園があります。国指定名勝。
池のまわりを景色を楽しみながらまわります。建物は客殿の書院。



ご朱印

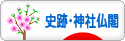
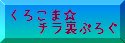
法華寺は奈良市内中心部からは少し離れていまして、近鉄新大宮から北西方向に平城宮跡の並びに
あります。JR奈良駅からはバスも運行されていますが、よく晴れた春の日なのでレンタサイクルで
行きました。JR奈良駅からは自転車で約15分ほどで到着します。途中の佐保川周辺も桜満開です。

4月初旬は「ひな会式」という法要が毎日午前中に本堂であるので、その時間帯は本堂には入れません。
あわせて献茶・献花などの催しものもあるので人が多いです。
法華寺赤門(通用門) 法華寺南門(切妻造本瓦葺の四脚門・重文)


法華寺門跡寺史
奈良朝の天平13年(741)光明皇后が藤原不比等の邸宅跡に創建した。東大寺が聖武天皇発願の
総国分寺であるのに対して法華寺は皇后発願の総国分尼寺である。「法華滅罪之寺」とも称する。
平安遷都後は衰微して荒廃するが、鎌倉中期の寛元3年(1245)に奈良西大寺の叡尊によって
諸堂が復興されて西大寺末寺となる。室町期には興福寺末寺。戦国期に三好松永の兵火で伽藍を
焼失するが、豊臣秀頼によって再興されて本堂・南門・鐘楼などが現在に残る。江戸時代には
寺領220石。真言律宗を経て現在は光明宗。
ご本尊を拝しました。厨子の中で蓮華座に立っておられる十一面観音ですが、目鼻立ちがはっきりと
した男顔の観音像だと思いましたが、後に調べると光明皇后の御顔を写した天平の女人顔ということで
大変失礼しました(笑) 口にかすかに紅色が残るのがわかります。本尊を守護する四天王像が
厨子の四方に立ち、聖武天皇と光明皇后の御尊牌が安置されていました。法華寺本堂は重文です。

境内は桜をはじめ花盛りです。鐘楼(写真左)も秀頼寄進で重要文化財。




奈良の古寺院では珍しく本堂脇手・裏手に江戸初期に作庭された庭園があります。国指定名勝。
池のまわりを景色を楽しみながらまわります。建物は客殿の書院。



ご朱印

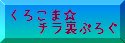
霊鑑寺は寺地も広くて庭園が見事です。椿が有名らしいですが、苔も大変きれいでした。
書院や本堂の前の池泉鑑賞式庭園が主庭ですが、境内をほぼ1周して庭園があるので回遊式ともいえます。
書院に面した庭園 かつては池には山中からの谷水によって滝が造作されていたが今は枯渇している


書院から本堂へと上がるふもとには将軍家斉から寄進された「硯石」と銘する石がある

各所に灯篭が配されてアクセントになっている 本堂上裏手には長椅子があってのんびり鑑賞できる


書院・本堂の裏にあたる庭園


霊鑑寺は秋にも期間限定で特別公開があります。秋はやはり紅葉ですね。特別公開中は随所に
ボランティアの案内人がいて説明をしてくれます。このスタイルは宝鏡寺門跡と同じです。
最後に霊鑑寺のご朱印。小さい紙切れに印が押されているだけのものです。

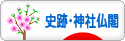 ←ポチッとクリック応援お願いします!
←ポチッとクリック応援お願いします!
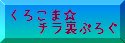 ←こちらもよろしく!
←こちらもよろしく!
書院や本堂の前の池泉鑑賞式庭園が主庭ですが、境内をほぼ1周して庭園があるので回遊式ともいえます。
書院に面した庭園 かつては池には山中からの谷水によって滝が造作されていたが今は枯渇している


書院から本堂へと上がるふもとには将軍家斉から寄進された「硯石」と銘する石がある

各所に灯篭が配されてアクセントになっている 本堂上裏手には長椅子があってのんびり鑑賞できる


書院・本堂の裏にあたる庭園


霊鑑寺は秋にも期間限定で特別公開があります。秋はやはり紅葉ですね。特別公開中は随所に
ボランティアの案内人がいて説明をしてくれます。このスタイルは宝鏡寺門跡と同じです。
最後に霊鑑寺のご朱印。小さい紙切れに印が押されているだけのものです。

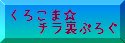 ←こちらもよろしく!
←こちらもよろしく!

















