コロナ危機と言われる今の世の中ですが、江戸時代にも自然災害や財政破綻と幕府も各藩も危機はたくさんありました。危機に遭遇した時、一番影響を受けるのは弱い立場の庶民です。為政者はいかに弱い立場の庶民に目を配り自ら率先して節制し行動で示しながら救済策を実施していくことが求められます。
天明・天保の大飢饉により農民生活はどん底に落ち百姓一揆が起きた後に老中になった白河藩主の松平定信は寛政の改革により農村復興や財政再建に職を失った浮浪者を収容する人足寄場や飢饉に備える基金の七分積金を創設しました。
財政破綻をきたしていた米沢藩では藩主上杉治憲(鷹山)が自らも衣服を木綿を着ながら積極的に節制して藩士にも殖産興業に従事させ藩收を増やして将来を見据えた教育機関興譲館を創設しました。
危機に際して一番しわ寄せがくる弱い立場の庶民に目を配り自らも率先して節制し素早く救済策を打ち出して危機を乗り越えた松平定信や上杉鷹山。現代の危機に今このような為政者が求められているのではないでしょうか。
天明・天保の大飢饉により農民生活はどん底に落ち百姓一揆が起きた後に老中になった白河藩主の松平定信は寛政の改革により農村復興や財政再建に職を失った浮浪者を収容する人足寄場や飢饉に備える基金の七分積金を創設しました。
財政破綻をきたしていた米沢藩では藩主上杉治憲(鷹山)が自らも衣服を木綿を着ながら積極的に節制して藩士にも殖産興業に従事させ藩收を増やして将来を見据えた教育機関興譲館を創設しました。
危機に際して一番しわ寄せがくる弱い立場の庶民に目を配り自らも率先して節制し素早く救済策を打ち出して危機を乗り越えた松平定信や上杉鷹山。現代の危機に今このような為政者が求められているのではないでしょうか。












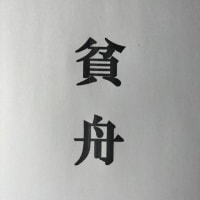










危機的状況の下、庶民のために支出を惜しまない事は、回り回って為政者自身の身をも助ける。
(フランスの場合、凶作・飢饉以前からの放漫財政のせいで、殆ど身動き取れなかったようですけど)。