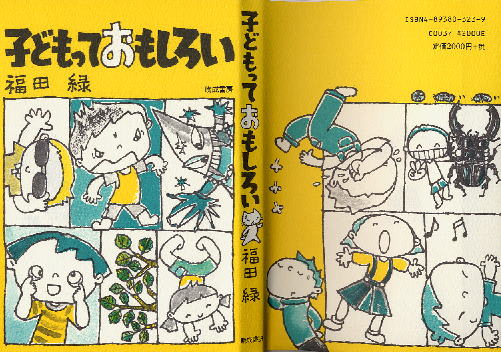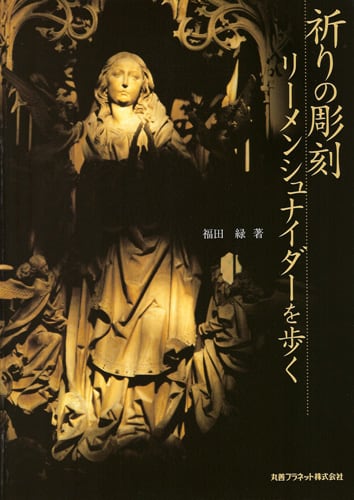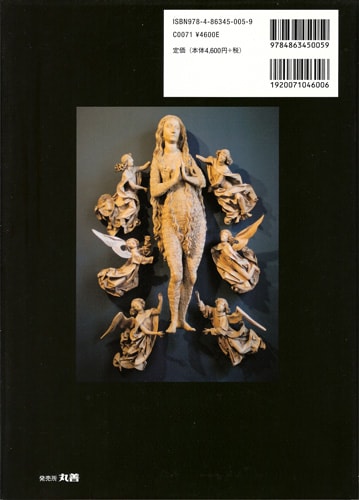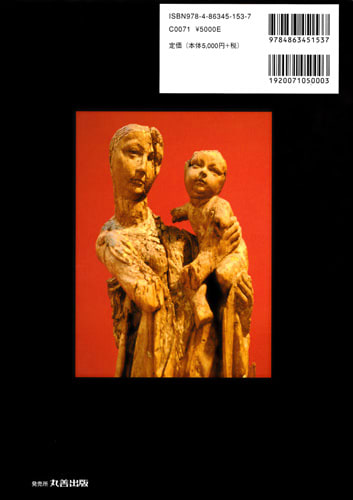日本全国に優れた演劇教育の仲間がいますが、千葉の久我良三さんもその一人です。かつて彼に、日本演劇教育連盟が主催する全国演劇教育研究集会でワークショップを開いてもらったことがあります。岩国でのことでした。その様子を少しのぞいてみましょう。
□全国演劇教育研究集会の記録□
講座M 楽しい教室をつくろうー独楽と人形劇とピタゴラスイッチ
講師 久我良三(独楽と人形劇のクマゴロウ)
世話人 村中昌恵(山口・岩国市立平田小学校)
福田三津夫(東京・日本演劇教育連盟)
参加者 大人15人 子ども7人
午後1時30分から4時30分までの半日講座。
午前中、講師の久我さんが講座に必要な独楽や人形劇の仕掛けなどをワゴン車に積んで到着。3階の会場までエレベーターで荷物を何度も運び、すべてをセッティングするのに1時間半ほどかかる。小学校の教室ほどのスペースはまるでおもちゃ箱をひっくり返したよう。ほぼ準備完了した頃、開け放ったドアから何事があったのかと、中を覗き込む人が引きも切らない。
「見るだけじゃおもしろくないからやってみてください。」大道芸人に衣装変えした久我さんが誘い水を掛ける。興味津々の見学者たちが増え、まるで祭りの様相。子ども親も教師たちも独楽回しに興じている。ほとんど独楽回し大会のようだ。
一応、私の方から簡単な講師紹介をして、時間どおりに講座はスタートする。あとは講師ににすべてお任せだ。
●まずは、挨拶がわりに
久我さんは自己紹介もそこそこに、いきなり独楽の実演から始める。勢いよく回した独楽を糸にからげて独楽が四角い小さな手作り神輿まで到達すると、パンと破裂して、犬の人形が現れて、あらあら不思議、犬が何回もでんぐり返るという仕掛け。まずは参加者の度肝をぬく演出からスタートだ。みんな大喜び。
次は先端がしなる棒の上に回した独楽をのっけて、隣の人に次々と渡していく。独楽が止まっていつ落ちてしまうか、はらはらどきどき。子どもも大人も神経がとぎすまされて心地よい時間と空間が過ぎる。
釣り糸に独楽を絡め、独楽が4,5メートルの空中を渡っていく。これぞまさしく空中独楽だ。いつも上手くいくとは限らない真剣勝負がいい。
●今回の目玉は、ピタゴラスイッチ
床1面に準備された仕掛けは、ピタゴラスイッチ、つまりドミノ倒しのことだ。20の仕掛けを親子やグループで作り上げることから始める。仕掛けはすべて久我さんの手作りである。途方もない時間をかけて、おもしろがって作り出す久我さんの姿が垣間見えるようだ。作り方を説明して回る久我さん。試してみての成功、不成功にいちいち歓声が沸く。
なにやらヘソを曲げすねている小さな男の子のお母さん、手を焼いて困ったふう。すかさず久我さん、
「君、10,9,8,7…って言えるかな。…では全部つなげて1回やってみましょう。」 何とか男の子にカウントダウンさせて、講座に参加させる。さらに元気な2人の男の子には、弓を持った人形を持たせてリンゴを射る役を与える。さすがの名演出家。
みんなが注目するなか、ドミノがスタート。何度も途切れながらも最後のくす玉割りまで届く。みんな大喝采。
「今度はもっと上手くいくようにやってみようか。」
流れがわかった参加者、再度挑戦だ。やる気十分だが、またもやパーフェクトにはいかない。でも満足感が漂うから不思議だ。
●人形劇の実演
いよいよ自作自演の人形劇の始まりだ。ことの起こりは、小学校の担任をしているときに、子どもの誕生日ごと、全員に異なる人形劇をしてあげたことだという。レパートリーがどんどん広がっていったのだ。「必要は発明の母」か。
・ 発明博士…水をコップに注ぐと、あらあら不思議、ジュース(色水)に変身してしまう。そのジュースをクルクルストローで飲む人形。
・次は、世界で初めての独楽を回す人形だという。しかし今回は不調でうまくいかない。講師の名誉のためにつけ加えるが、筆者は何度も<成功>を目撃している。
・「ヘビのからだはなぜ長い」…講師の十八番の1つ。なぜヘビはからだが長くなったかという話。絶妙の独演会。
・ 一番うける出し物は「ミミズクの散歩」。ミミズクの親子の登場。バージョンアップして、海篇と山篇が加わる。常におもしろいことを見つけようとしている講師の存在がすごい。
・「酒飲みおじさん」…なぜか酒(液体)が消えてしまうのだ。まさに手品師。
・「わたしはだあれ?」…手袋人形の登場だ。しっとりと参加者を引きつける。こちらは子どもにも大受けだ。
●最後は独楽に戻って…
人形劇を楽しんだあと、講師の卓越した独楽回し演技に酔いしれた。手のっけなんてお茶の子さいさい、「かまいたち」「おろち」「水の中で回る独楽」「空中に浮く独楽」と続く。それぞれの技はことばでの説明はかなり難しい。その実際を見てみたい方は、是非この講座を受講されることを勧めたい。
そして、独楽回しをやりたそうな子どもやお母さんの雰囲気をいち早く察知した講師、講座の最後の30分は独楽回し練習に戻る。最初と最後は独楽回しだった。 独楽回しの魅力にとりつかれた親子と教師たち、時間いっぱいまで独楽回しに興じていた。
会場の復元と道具の運び出しは参加者が積極的に担ってくれた。彼らの満足度を示しているようだった。
(報告:福田三津夫)
*『日本の演劇教育2012』(日本演劇教育連盟編集)より
□全国演劇教育研究集会の記録□
講座M 楽しい教室をつくろうー独楽と人形劇とピタゴラスイッチ
講師 久我良三(独楽と人形劇のクマゴロウ)
世話人 村中昌恵(山口・岩国市立平田小学校)
福田三津夫(東京・日本演劇教育連盟)
参加者 大人15人 子ども7人
午後1時30分から4時30分までの半日講座。
午前中、講師の久我さんが講座に必要な独楽や人形劇の仕掛けなどをワゴン車に積んで到着。3階の会場までエレベーターで荷物を何度も運び、すべてをセッティングするのに1時間半ほどかかる。小学校の教室ほどのスペースはまるでおもちゃ箱をひっくり返したよう。ほぼ準備完了した頃、開け放ったドアから何事があったのかと、中を覗き込む人が引きも切らない。
「見るだけじゃおもしろくないからやってみてください。」大道芸人に衣装変えした久我さんが誘い水を掛ける。興味津々の見学者たちが増え、まるで祭りの様相。子ども親も教師たちも独楽回しに興じている。ほとんど独楽回し大会のようだ。
一応、私の方から簡単な講師紹介をして、時間どおりに講座はスタートする。あとは講師ににすべてお任せだ。
●まずは、挨拶がわりに
久我さんは自己紹介もそこそこに、いきなり独楽の実演から始める。勢いよく回した独楽を糸にからげて独楽が四角い小さな手作り神輿まで到達すると、パンと破裂して、犬の人形が現れて、あらあら不思議、犬が何回もでんぐり返るという仕掛け。まずは参加者の度肝をぬく演出からスタートだ。みんな大喜び。
次は先端がしなる棒の上に回した独楽をのっけて、隣の人に次々と渡していく。独楽が止まっていつ落ちてしまうか、はらはらどきどき。子どもも大人も神経がとぎすまされて心地よい時間と空間が過ぎる。
釣り糸に独楽を絡め、独楽が4,5メートルの空中を渡っていく。これぞまさしく空中独楽だ。いつも上手くいくとは限らない真剣勝負がいい。
●今回の目玉は、ピタゴラスイッチ
床1面に準備された仕掛けは、ピタゴラスイッチ、つまりドミノ倒しのことだ。20の仕掛けを親子やグループで作り上げることから始める。仕掛けはすべて久我さんの手作りである。途方もない時間をかけて、おもしろがって作り出す久我さんの姿が垣間見えるようだ。作り方を説明して回る久我さん。試してみての成功、不成功にいちいち歓声が沸く。
なにやらヘソを曲げすねている小さな男の子のお母さん、手を焼いて困ったふう。すかさず久我さん、
「君、10,9,8,7…って言えるかな。…では全部つなげて1回やってみましょう。」 何とか男の子にカウントダウンさせて、講座に参加させる。さらに元気な2人の男の子には、弓を持った人形を持たせてリンゴを射る役を与える。さすがの名演出家。
みんなが注目するなか、ドミノがスタート。何度も途切れながらも最後のくす玉割りまで届く。みんな大喝采。
「今度はもっと上手くいくようにやってみようか。」
流れがわかった参加者、再度挑戦だ。やる気十分だが、またもやパーフェクトにはいかない。でも満足感が漂うから不思議だ。
●人形劇の実演
いよいよ自作自演の人形劇の始まりだ。ことの起こりは、小学校の担任をしているときに、子どもの誕生日ごと、全員に異なる人形劇をしてあげたことだという。レパートリーがどんどん広がっていったのだ。「必要は発明の母」か。
・ 発明博士…水をコップに注ぐと、あらあら不思議、ジュース(色水)に変身してしまう。そのジュースをクルクルストローで飲む人形。
・次は、世界で初めての独楽を回す人形だという。しかし今回は不調でうまくいかない。講師の名誉のためにつけ加えるが、筆者は何度も<成功>を目撃している。
・「ヘビのからだはなぜ長い」…講師の十八番の1つ。なぜヘビはからだが長くなったかという話。絶妙の独演会。
・ 一番うける出し物は「ミミズクの散歩」。ミミズクの親子の登場。バージョンアップして、海篇と山篇が加わる。常におもしろいことを見つけようとしている講師の存在がすごい。
・「酒飲みおじさん」…なぜか酒(液体)が消えてしまうのだ。まさに手品師。
・「わたしはだあれ?」…手袋人形の登場だ。しっとりと参加者を引きつける。こちらは子どもにも大受けだ。
●最後は独楽に戻って…
人形劇を楽しんだあと、講師の卓越した独楽回し演技に酔いしれた。手のっけなんてお茶の子さいさい、「かまいたち」「おろち」「水の中で回る独楽」「空中に浮く独楽」と続く。それぞれの技はことばでの説明はかなり難しい。その実際を見てみたい方は、是非この講座を受講されることを勧めたい。
そして、独楽回しをやりたそうな子どもやお母さんの雰囲気をいち早く察知した講師、講座の最後の30分は独楽回し練習に戻る。最初と最後は独楽回しだった。 独楽回しの魅力にとりつかれた親子と教師たち、時間いっぱいまで独楽回しに興じていた。
会場の復元と道具の運び出しは参加者が積極的に担ってくれた。彼らの満足度を示しているようだった。
(報告:福田三津夫)
*『日本の演劇教育2012』(日本演劇教育連盟編集)より