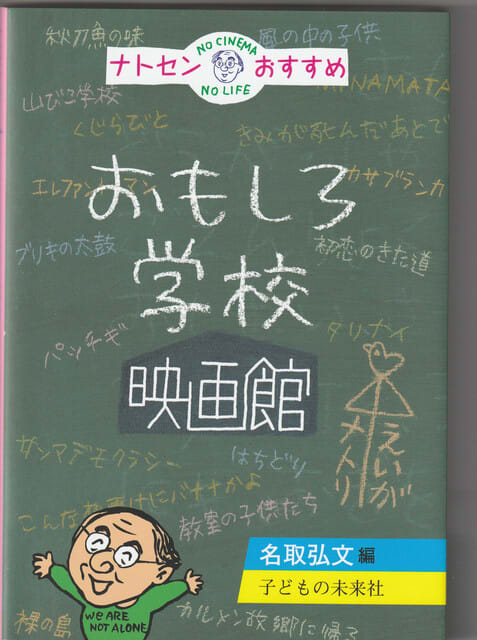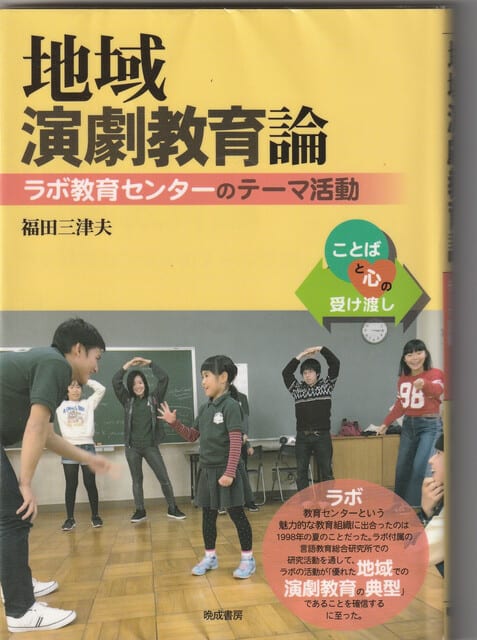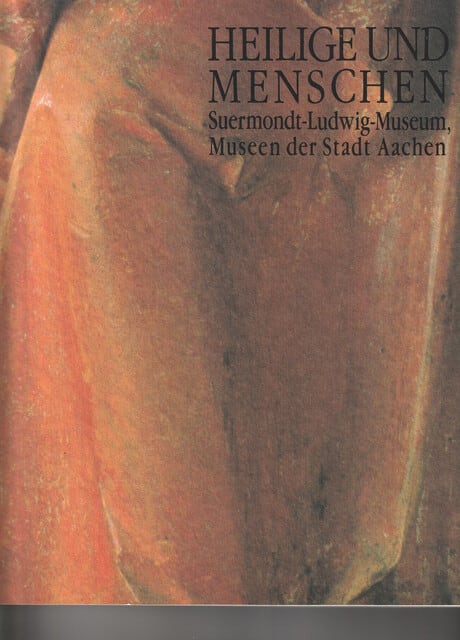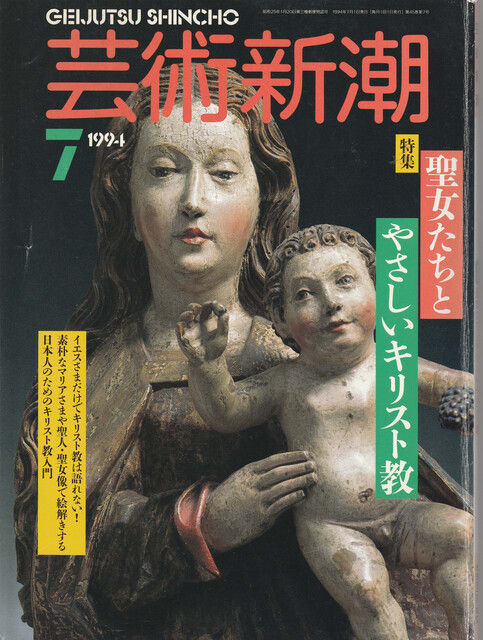山﨑隆夫は東京学芸大学で出会った親友であり、畏友です。2人とも教育学部小学校教員養成課程社会科所属、入学式で出会い意気投合しました。バドミントン経験者の山﨑とバドミントンの部屋を訪れ即入部、ダブルスも組んだ仲間です。
山﨑は東京都で38年間教師を勤め、定年退職と同時に都留文科大学で教職支援センター特任教授になりました。私と同様に約50年にわたって小学校と大学で教育の現場にいたことになります。すでに数冊の著書をものにしていますが、今回、新たに『危機の時代と教師のしごと』を出版しました。半世紀にわたる教育の実践と理論を1冊の本にしたためたことになります。
まずはどのような本なのか、出版元のHPを紐解いてみましょう。
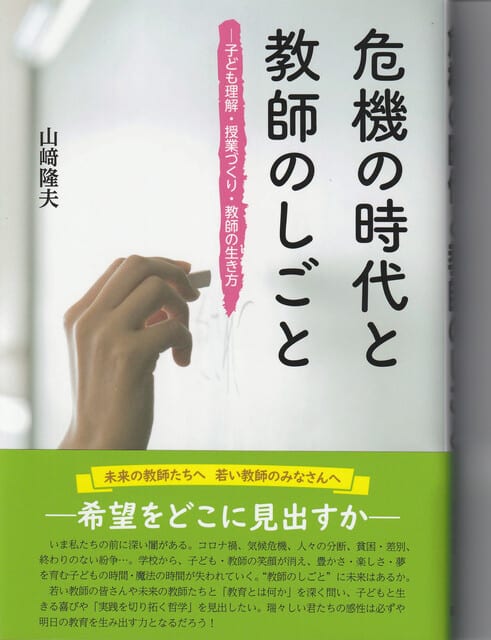
◆『危機の時代と教師のしごと』(高文研HPより)
山﨑 隆夫(著/文) 発行:高文研 四六判
○紹介
コロナ禍でさらに困難な時代を生きる子どもたちの悲鳴と生きづらさに寄り添いながら悩み、葛藤し未来を生みだしていく教育の真実がある。教師が〝本物教師〟になっていく真の姿がここにある!
私たちの前には、いま深い闇がある。5年、10年先の未来が見えない。コロナウィルスの問題や核戦争に対する不安、気候変動による災害や環境問題も待ったなしに迫っている。子どもたちも「未来」から不安や見えない危機が忍び込み、希望が見えにくくなっている。
この危機の時代に何が教育や教師に求められているのか。
現在、「情報器機」を利用した「個別最適化された学び」「協働的な学び」が文科省から提案され具体化が始まっている。その子に相応しい学習の学びが達成されていくという理由だ。果たしてそれは子どもの心の琴線に触れるような、そして子どもと教師の心を熱く揺るがすような教育が生まれるのだろうか。
著者は、いまを生きる教師こそ、安易に何かに委ねることやマニュアルにたよったりせず、試行錯誤を重ね子どもの抱えるものや思いに共感しながら時代を切り拓いて欲しいと説く。
○目次
はじめに
Ⅰ章 いま問われる〝教師のしごと〟
1 教師のしごと 命を守り、命を育む
2 教師のしごとは「奇跡」の連続
Ⅱ章 子どもを理解するとは
1 教育実践において子どもを理解するとは
2 教師の「いま」と教育実践
3 今日の教師にとっての子ども理解の問題
4 子ども期を夢中に生きること、人生を肯定し憧れを刻むこと
Ⅲ章 授業と子ども
1 授業に流れる時間と質を問う
2 子どもが授業の中で夢中を生きるとき
3 聴く、聴き合う授業で広がる子どもの世界
4 学びとつながり合うもうひとつの世界
Ⅳ章 扉の向こうは子どもの時間
○著者プロフィール
山﨑 隆夫 (ヤマザキタカオ)
1950年静岡県生まれ。東京都公立小学校教師として38年間勤務。生きづらさを抱える多様な子どもたちを教室で受け止めながら、楽しく豊かな授業づくりを目指し、日々努力をしてきた。現在、都留文科大学教職支援センター特任教授。教育科学研究会常任委員。学びをつくる会世話人。主な著書に『希望を生み出す教室』(旬報社)『パニックの子、閉じこもる子達の居場所づくり』(学陽書房)『学級崩壊』(共著、高文研)『教室は楽しい授業で いっぱいだ!』(高文研)など。
55歳で自主退職した私は、大学の授業の合間を見て、小学校の3つの現場を訪れました。故・鳥山敏子さん(立川市の賢治の学校)、霜村三二さん(朝霞市)、そして山﨑(大田区)の教室でした。
山﨑の退職前に一度授業を見ておきたいと思って連絡を取りました。当日は千葉の大学の学生たちも多く訪れていました。国語か道徳の授業だったでしょうか。子どもたちとの当意即妙のやり取りが絶妙でした。彼らの意見を細大漏らさず聴き取り、手際よく黒板にまとめていきます。学生時代から得意だった絵も描きながらの見事な板書でした。私はその様子を珍しく写真に収め、それを山﨑に送ったのでした。
休み時間も彼と話す時間はありません。彼は子どもたちが校庭でエスケン(?)をするのを見守っているのでした。
本を捲りながらこの時の授業を思い出していました。
本の各章のトビラに山﨑の絵が掲載されています。どれも柔らかなタッチの子どもを描いたものです。とりわけ、学級通信「なかよし いっぱい!」の最終号が素敵です。おそらく学級通信を書き続けてきた彼の最終号だったのではないでしょうか。ドラゴンの形の船に子どもたちがいっぱい乗船し、これから出港するのでしょうか。本文によると子どもたちは自分がどれか、どうやら特定できるようなのです。そういえば山﨑の年賀状も彼の手描きの絵で飾られていましたっけ。
山﨑の特技は絵を描くことだけではなく、詩を作ることもその1つです。このことも学生時代からたびたび目にしていたことなのです。本では教師の仕事をわかりやすく詩で表現しています。子どもたちも詩や作文が大好きのようです。それが本にたびたび登場し、実践記録に豊かな彩りを添えています。
この本で一番感心するのは、すべてが実践に裏付けされた文章だということです。だから仮名で登場する子どもたちの眼差しや息づかいまでも伝わってくるのです。
そして文章に凄みを与えているのは実践の光と影を描き出しているからです。単なる成功談ではなく、時には痛みを伴った実践報告の様相を呈しているということなのです。ここに教育の深層やリアルが立ち現れてくるのでしょう。
この本には教室風景が数多く報告されていますが、その中でもとりわけ秀逸なのは「春の歌」(草野心平)の授業です。この20頁ほどの文章を読みあって校内研究にかけてもおもしろいかもしれません。自分ならこうする、という意見も誘発する優れた実践です。
山﨑から送られた本を通読して良かったと実感しているのは、彼の教育思想の全貌をトータルに知り得たことでした。雑誌『教育』掲載の文章はけっこう読んでいたのですが、毎日新聞「新・教育の森」、新聞赤旗などに掲載された論考は初見でした。
この本は教師を目指している学生、悩みを抱えている教師、自分の実践を見つめ直してみたい教師などにお勧めです。
さて、これから山﨑隆夫は何処に向かうのでしょうか。注視していきたいと思います。
山﨑は東京都で38年間教師を勤め、定年退職と同時に都留文科大学で教職支援センター特任教授になりました。私と同様に約50年にわたって小学校と大学で教育の現場にいたことになります。すでに数冊の著書をものにしていますが、今回、新たに『危機の時代と教師のしごと』を出版しました。半世紀にわたる教育の実践と理論を1冊の本にしたためたことになります。
まずはどのような本なのか、出版元のHPを紐解いてみましょう。
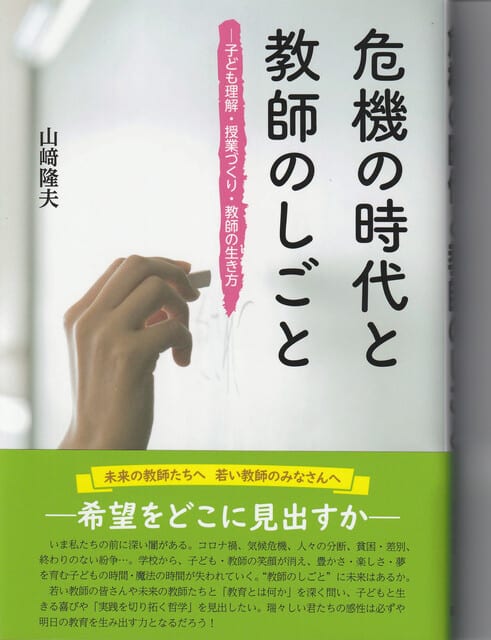
◆『危機の時代と教師のしごと』(高文研HPより)
山﨑 隆夫(著/文) 発行:高文研 四六判
○紹介
コロナ禍でさらに困難な時代を生きる子どもたちの悲鳴と生きづらさに寄り添いながら悩み、葛藤し未来を生みだしていく教育の真実がある。教師が〝本物教師〟になっていく真の姿がここにある!
私たちの前には、いま深い闇がある。5年、10年先の未来が見えない。コロナウィルスの問題や核戦争に対する不安、気候変動による災害や環境問題も待ったなしに迫っている。子どもたちも「未来」から不安や見えない危機が忍び込み、希望が見えにくくなっている。
この危機の時代に何が教育や教師に求められているのか。
現在、「情報器機」を利用した「個別最適化された学び」「協働的な学び」が文科省から提案され具体化が始まっている。その子に相応しい学習の学びが達成されていくという理由だ。果たしてそれは子どもの心の琴線に触れるような、そして子どもと教師の心を熱く揺るがすような教育が生まれるのだろうか。
著者は、いまを生きる教師こそ、安易に何かに委ねることやマニュアルにたよったりせず、試行錯誤を重ね子どもの抱えるものや思いに共感しながら時代を切り拓いて欲しいと説く。
○目次
はじめに
Ⅰ章 いま問われる〝教師のしごと〟
1 教師のしごと 命を守り、命を育む
2 教師のしごとは「奇跡」の連続
Ⅱ章 子どもを理解するとは
1 教育実践において子どもを理解するとは
2 教師の「いま」と教育実践
3 今日の教師にとっての子ども理解の問題
4 子ども期を夢中に生きること、人生を肯定し憧れを刻むこと
Ⅲ章 授業と子ども
1 授業に流れる時間と質を問う
2 子どもが授業の中で夢中を生きるとき
3 聴く、聴き合う授業で広がる子どもの世界
4 学びとつながり合うもうひとつの世界
Ⅳ章 扉の向こうは子どもの時間
○著者プロフィール
山﨑 隆夫 (ヤマザキタカオ)
1950年静岡県生まれ。東京都公立小学校教師として38年間勤務。生きづらさを抱える多様な子どもたちを教室で受け止めながら、楽しく豊かな授業づくりを目指し、日々努力をしてきた。現在、都留文科大学教職支援センター特任教授。教育科学研究会常任委員。学びをつくる会世話人。主な著書に『希望を生み出す教室』(旬報社)『パニックの子、閉じこもる子達の居場所づくり』(学陽書房)『学級崩壊』(共著、高文研)『教室は楽しい授業で いっぱいだ!』(高文研)など。
55歳で自主退職した私は、大学の授業の合間を見て、小学校の3つの現場を訪れました。故・鳥山敏子さん(立川市の賢治の学校)、霜村三二さん(朝霞市)、そして山﨑(大田区)の教室でした。
山﨑の退職前に一度授業を見ておきたいと思って連絡を取りました。当日は千葉の大学の学生たちも多く訪れていました。国語か道徳の授業だったでしょうか。子どもたちとの当意即妙のやり取りが絶妙でした。彼らの意見を細大漏らさず聴き取り、手際よく黒板にまとめていきます。学生時代から得意だった絵も描きながらの見事な板書でした。私はその様子を珍しく写真に収め、それを山﨑に送ったのでした。
休み時間も彼と話す時間はありません。彼は子どもたちが校庭でエスケン(?)をするのを見守っているのでした。
本を捲りながらこの時の授業を思い出していました。
本の各章のトビラに山﨑の絵が掲載されています。どれも柔らかなタッチの子どもを描いたものです。とりわけ、学級通信「なかよし いっぱい!」の最終号が素敵です。おそらく学級通信を書き続けてきた彼の最終号だったのではないでしょうか。ドラゴンの形の船に子どもたちがいっぱい乗船し、これから出港するのでしょうか。本文によると子どもたちは自分がどれか、どうやら特定できるようなのです。そういえば山﨑の年賀状も彼の手描きの絵で飾られていましたっけ。
山﨑の特技は絵を描くことだけではなく、詩を作ることもその1つです。このことも学生時代からたびたび目にしていたことなのです。本では教師の仕事をわかりやすく詩で表現しています。子どもたちも詩や作文が大好きのようです。それが本にたびたび登場し、実践記録に豊かな彩りを添えています。
この本で一番感心するのは、すべてが実践に裏付けされた文章だということです。だから仮名で登場する子どもたちの眼差しや息づかいまでも伝わってくるのです。
そして文章に凄みを与えているのは実践の光と影を描き出しているからです。単なる成功談ではなく、時には痛みを伴った実践報告の様相を呈しているということなのです。ここに教育の深層やリアルが立ち現れてくるのでしょう。
この本には教室風景が数多く報告されていますが、その中でもとりわけ秀逸なのは「春の歌」(草野心平)の授業です。この20頁ほどの文章を読みあって校内研究にかけてもおもしろいかもしれません。自分ならこうする、という意見も誘発する優れた実践です。
山﨑から送られた本を通読して良かったと実感しているのは、彼の教育思想の全貌をトータルに知り得たことでした。雑誌『教育』掲載の文章はけっこう読んでいたのですが、毎日新聞「新・教育の森」、新聞赤旗などに掲載された論考は初見でした。
この本は教師を目指している学生、悩みを抱えている教師、自分の実践を見つめ直してみたい教師などにお勧めです。
さて、これから山﨑隆夫は何処に向かうのでしょうか。注視していきたいと思います。