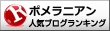【もう一つの2024年問題】・・いよいよ団塊世代がすべて後期高齢者に・・政府の切り札として進める全世代型社会保障の高い壁・・・
物流・運送業界の2024年問題が取り沙汰されているが、それとは異なる問題がある‥2024年は、いわゆる団塊世代がすべて75歳の後期高齢者になる
節目の年だというのだ‥今も600万人ちかい人口規模をもつ団塊が、より手厚い医療・介護を必要とすることで、いま以上に社会保障が膨れると予想、
そこで政府が打ち出した【切り札】が【全世代型社会保障】なる制度である。・・・年明けて2024年になると、団塊世代がすべて75歳以上となり、
【2025年問題】が到来との誤解が定着しているが厳密には2024年なのである75歳を超えると医療や介護を巡る公費負担の急伸が懸念される。
ところで、75歳以上の人口はどれくらいか❔総務省調べでは、2023年9月15日現在で2005万人、2000万人が突破したのは初めてであり・・
高齢者全体3623万人に占める割合は55.3%である・・・平均寿命が延び75歳以上のなかでもより【年配者の高齢者】が増えており80歳以上を
例にとると、総人口に占める割合は10.1%だ‥国民の10人に1人が80歳以上という超長寿国家であり、【給付は高齢者・負担は現役世代中心】という、
構造を改め年齢を問わず個々の負担能力に応じて支える形が全世代型社会保障である・・・その検討は安部政権で始まったが、本腰が入ったのは
岸田政権になり、後期高齢者医療制度の保険料の引き上げ、出産育児の一時金を45万円から50万円に財源の一部負担も後期高齢者医療制度が
負担することで決着異次元の少子化の財源も、75歳以上を含めて徴収されることになり、75歳以上の医療窓口負担も2割に引き上げられる。
本来ならもっと早い段階で社会保障制度を改革すべきを、進んでこなかった背景には政治の不作為がある、選挙への影響を懸念する国会議員には
高齢有権者に不人気な政策を敬遠する人が少なくないためだ・・・増税は世論の反発が強く給与天引きで国民が気づきにくい社会保険料を引き上げる
という姑息な手段を繰り返してきたのである…このため、現役世代が負担する社会保険料が急上昇し、報酬に占める割合は2000年には22.7%だが、
2023年は30.1%だ、2040年には32.6%になる見込みである…この結果、2022年度の国民負担は47.5%と所得の半分を占めるに至っている・・・・
収入の半分は近くが税金や社会保険料として消えていく現状は,現役世代の意欲を削ぐ、SNS上では【五公五民】と言った若い世代の不満の声多しである。
一方で、世帯人員1人当たり平均所得金額は、65歳以上が206万5000円・29歳以下は245万1000円・30代は221万9000円・40代は239万5000円で
大きな差があるわけではない、こうした点が全世代型を目指す理由の1つとなっている・・・とはいえ、年齢を重ねるにつれて所得は減り・・・
70歳以上は194万6000円だ‥厚労省の別資料では75歳以上の過半数は150万未満である・・・
しかも、公的年金には将来の年金財政・現役世代の負担を考え賃金の伸び率よりも抑制する『マクロ経済スライド』という仕組みで、物価高の伸びに
年金額の上昇に追いつかないということはも実質的な減額であるスライド年金受給世帯における・・・・
(相対的貧困率等価可処分所得の中央値の半分に満たない世帯員割合)高まることを懸念する声もある・・ロング文面閲覧・・ありがとう!span>