中学受験で疲弊しないために、親子で楽しむ受験になるヒントを綴っていきたいと思います。
中学受験で子どもと普通に幸せになる方法
春期講習の試練
春休みや夏休みの日程は、全国どこでも同じ、というわけではありません。
地方自治体によって違うので、講習の日程を決めるのは結構塾にとっては大変なことです。いろいろな地域で教室展開をしている塾はこのカリキュラムを揃えないといけない。都道府県で長さが違う、ということになるとやはり保護者からクレームがくるので、だいたいどこの塾も全国一律に決めます。ただし、これは講習期間だけ。例えば4日と決めれば、全国どこでも4日にする、ということで、あとは自治体の休みと合わせて日程が決まっていきます。
だから、休みの割に講習が短い、という場合があり得るわけです。特に春期講習は短くなりがちで、6日間程度になることが多いようです。
しかし、短い、といっても普段の授業よりはよほど長い。特に新6年生は初めて6年生の講習時間を体験するのが春期講習です。だから、結構くたびれる。しかも、宿題もあるし、復習もあるから、家に帰ってからも息が抜けない、ということになります。
授業が終わって、次の日までに結構、やることが多いとなると、つい夜遅くまでになりがちですが、多くの新6年生の授業は午後からになっていることが多いので、(午前中は他の学年の講習が行われます。)午前中を上手に使う。
ここでも朝型が良いでしょう。夜遅くまで起きているよりは、早めに切り上げて、次の日、朝早く起きて勉強する。その方が効率も能率も上がります。
多くの塾では間に休みを1日入れます。
これは、やはり疲れる子どもたちを配慮してのこと。ハードな塾だと8日間ぶっ通し、ということになりますが、こうなると息がつけないので、かなりくたびれてしまうことになるでしょう。
春期講習はこれから先の講習のならし運転という意味合いもあるのです。
1か月後にゴールデンウィークがありますが、ゴールデンウィークで合宿や特訓授業をやる塾は、このころから先生たちのピッチが上がってくるでしょう。
だから、春期講習で講習中の復習の仕方や宿題のやり方に慣れておくことです。5年生までと新6年生ではボリュームが全く違いますから、もし、全部終わらない、ということであるならば上手に優先順位を決めていってください。
子どもたちは先生から言われたから、というのでがんばりますが、最近の塾は各科目で先生が違い、かつその先生たちが横で連絡していないので、突然ボリュームの多い宿題が出る日があったりするから、子どもたちから状況を良く聞いてやることをしぼっていきましょう。

「映像教材、これでわかる電気」(田中貴)
===========================================================
今日の田中貴.com
受験人口減少期の特徴
==============================================================
中学受験 算数オンライン塾
3月21日の問題
==============================================================

==============================================================
お知らせ
算数5年前期第9回 算数オンライン塾「差集め算」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================


にほんブログ村
地方自治体によって違うので、講習の日程を決めるのは結構塾にとっては大変なことです。いろいろな地域で教室展開をしている塾はこのカリキュラムを揃えないといけない。都道府県で長さが違う、ということになるとやはり保護者からクレームがくるので、だいたいどこの塾も全国一律に決めます。ただし、これは講習期間だけ。例えば4日と決めれば、全国どこでも4日にする、ということで、あとは自治体の休みと合わせて日程が決まっていきます。
だから、休みの割に講習が短い、という場合があり得るわけです。特に春期講習は短くなりがちで、6日間程度になることが多いようです。
しかし、短い、といっても普段の授業よりはよほど長い。特に新6年生は初めて6年生の講習時間を体験するのが春期講習です。だから、結構くたびれる。しかも、宿題もあるし、復習もあるから、家に帰ってからも息が抜けない、ということになります。
授業が終わって、次の日までに結構、やることが多いとなると、つい夜遅くまでになりがちですが、多くの新6年生の授業は午後からになっていることが多いので、(午前中は他の学年の講習が行われます。)午前中を上手に使う。
ここでも朝型が良いでしょう。夜遅くまで起きているよりは、早めに切り上げて、次の日、朝早く起きて勉強する。その方が効率も能率も上がります。
多くの塾では間に休みを1日入れます。
これは、やはり疲れる子どもたちを配慮してのこと。ハードな塾だと8日間ぶっ通し、ということになりますが、こうなると息がつけないので、かなりくたびれてしまうことになるでしょう。
春期講習はこれから先の講習のならし運転という意味合いもあるのです。
1か月後にゴールデンウィークがありますが、ゴールデンウィークで合宿や特訓授業をやる塾は、このころから先生たちのピッチが上がってくるでしょう。
だから、春期講習で講習中の復習の仕方や宿題のやり方に慣れておくことです。5年生までと新6年生ではボリュームが全く違いますから、もし、全部終わらない、ということであるならば上手に優先順位を決めていってください。
子どもたちは先生から言われたから、というのでがんばりますが、最近の塾は各科目で先生が違い、かつその先生たちが横で連絡していないので、突然ボリュームの多い宿題が出る日があったりするから、子どもたちから状況を良く聞いてやることをしぼっていきましょう。

「映像教材、これでわかる電気」(田中貴)
===========================================================
今日の田中貴.com
受験人口減少期の特徴
==============================================================
中学受験 算数オンライン塾
3月21日の問題
==============================================================

==============================================================
お知らせ
算数5年前期第9回 算数オンライン塾「差集め算」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================

にほんブログ村
コメント ( 0 )
ノートの右側だけを使う方法
この時期は、子どもたちのノートも試行錯誤が続いています。
相変わらず、きっちり詰めて書こうとする子。
もう、罫も何もなく、走り書きのように式やメモが連なる子。
板書がどんどん進んでいき、間に合わないので殴り書きになる、というのはわからないでもないですが、しかし、ウチに帰って何が書いてあるのか、わからなければ復習のしようもありません。
だんだん勉強のやり方が身についてくるにつれて、ノートの使い方もそれぞれ工夫が出てくるわけですが、ノートの右側だけを使う、という方法があります。
そんな、もったいないと思うかもしれませんが、左側があいているというのは、実は大変便利なことが多いのです。
もちろん問題を解くときに、計算のページに使える、という場合もあるでしょうが、実際は復習の時に便利なのです。
何を間違えたのか。どうして、そういうミスをしたのか。といった、復習のときに気付いた点をメモするのも良いし、また、「ここは大事だ」というところを強調するのも良い。
よくわからない部分を、あとから自分で調べてさらに書き足す、ということにも使えるでしょうし、理科とか、社会では、これだけを覚えようという項目を整理するのにもいいでしょう。
ノートをつめて書く、という子も多いのですが、私はノートは空白が多い方が後で勉強するのに便利だと思っています。つめて書く子はノートをきれいに書こう、ということに力が行く分、書いてしまうとそれだけで満足してしまいがちで、あとからそのノートが活かされるということがあまりないようです。
ノートは見返して、あとでさらに利用するために使うものですから、ある程度余白を作りながら使ってください。
===========================================================
今日の田中貴.com
第75回 卒業式
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
慶應湘南藤沢中等部 学校別対策の考え方(3)
==============================================================

==============================================================
お知らせ
算数5年前期第9回 算数オンライン塾「差集め算」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================

にほんブログ村
コメント ( 0 )
東大の推薦入試
ここのところ東大の推薦入試が話題になっております。
近年地方からの進学者が減少し、首都圏の私立中高出身者の増加を憂慮していた、東大はやはり大きく舵を切ったと言えるでしょう。
学問と研究の立場からすれば同質化は最も避けなければいけない事態であるという認識は、受験する側からはなかなか理解できないことかもしれません。
しかし、発想というのはやはりいろいろな個性から生まれてくる。例えば、慶應湘南という学校が高校で首都圏からの受験枠を作らず、全国枠という形で地方からの受験生を集めようとしているのと同じ狙いがあります。
つまり、個が個を刺激するから、ユニークな発想が生まれてくる。同質がそろえばさらに同質化が進むだけであって、そこから独自な発想は生まれてこない。
これはある意味その通りだと思います。
東大の危機感として考えれば、ついに推薦まで使わないと多様性を担保できなくなったということなのです。
以前東大が一高だったころ、4年ほど推薦が行われた時期があるそうです。(芥川龍之介もその一人だったという話を聞きました。したがって初めての推薦入試というのは事実と反すようですが。)
これから大学自体が国際競争の中にさらされていき、東大もまたどんな研究成果を出す機関なのかが問われていく以上、単に偏差値の高い生徒だけを集めることが大学の発展にプラスにはならない、と考えられているように思えます。
以前、東大の関係者からは女性と地方校出身者を何とか増やしたい、という話を聞きました。
そんなにいないの?と思ったのですが、確かに同質化が進んでいることは間違いないようです。
私の手元にある今年の前期ベスト10を見ると、
1位 開成 2位 灘 3位 麻布 4位 東京学芸大附属 5位 聖光 6位 渋谷幕張 7位 桜蔭 8位 駒場東邦 9位 栄光学園 10位 県立浦和
ということなので、何だ、Sのαか?みたいな話になってきているのでしょう。
東大がローカルな国立大学とあまり変わらない、とすればそれは大学にとっての危機感は強いでしょう。アメリカの大学は確かに費用はかかるが、その分、全寮で全国から生徒を集めている、ということを考えていると、今回の制度改革は最早がけっぷちなのだ、という認識に立った方が良いのかもしれません。
===========================================================
今日の田中貴.com
場合の数の問題
==============================================================
中学受験 算数オンライン塾
3月19日の問題
==============================================================

==============================================================
お知らせ
算数5年前期第9回 算数オンライン塾「差集め算」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================

にほんブログ村
コメント ( 0 )
食べる子
受験勉強を始めると、当然のように、子どもにはストレスがかかります。
試験があれば、成績が出て、順位が出る。組み分けでクラスが上下したり、席が決まったり。
しかし、子どもがストレスを自覚するということはあまりありません。初めての経験だから、よくわからない。ただストレスをため込んでしまうと、チックが出てしまったり、いろいろなところに波及する。
ので、自己防衛本能が働いて、そのストレスを解消しようとするので、その結果として特異な方向に進みます。
例えば、妙にいろいろなものを集め出す。同じシャープペンシルを色違いでそろえてみたり、ノートをたくさん用意してみたり。
一番端的に出るのは、食欲です。
何か知らないが、良く食べる。食事以外にもお菓子に手が出たり、ジュースを飲んだり。
子どもは一気に食べることができないので、おやつは大事な習慣ですが、しかしその習慣が逆に仇となる場合があって、おやつがおやつでなくなってきたりします。
ところがこれが大人から見ていてわかりにくい。
というのは、当然成長期ですから、おなかはすくはずなのです。だから「良く食べて当然」と思いがちですが、実はストレスによる食欲だったりするのです。
まして受験勉強は運動不足になりやすく、かつ、甘いものが多かったり、カロリーが多すぎたりすると体調が悪くなってきます。
良く食べる、ということはまた良く運動する、ということでバランスが取れます。しかし、外に遊びに行ける機会が多いわけではないので、アンバランスな食生活になりがちです。
食べて動かなければ、当然太る。ひどくなると糖尿が出る場合もあります。
だから、上手にストレスを解消する方法を考えておくべきです。
1週間に1度サッカーの練習に出かけるのは、だから決して悪いことではない。上手にバランスを取る、ということは子どもにはなかなかできないので、お父さん、お母さんが気を付けてあげてください。
===========================================================
今日の田中貴.com
我が家流
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
慶應湘南藤沢中等部 学校別対策の考え方(2)
==============================================================

==============================================================
お知らせ
算数5年前期第9回 算数オンライン塾「差集め算」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================


にほんブログ村
試験があれば、成績が出て、順位が出る。組み分けでクラスが上下したり、席が決まったり。
しかし、子どもがストレスを自覚するということはあまりありません。初めての経験だから、よくわからない。ただストレスをため込んでしまうと、チックが出てしまったり、いろいろなところに波及する。
ので、自己防衛本能が働いて、そのストレスを解消しようとするので、その結果として特異な方向に進みます。
例えば、妙にいろいろなものを集め出す。同じシャープペンシルを色違いでそろえてみたり、ノートをたくさん用意してみたり。
一番端的に出るのは、食欲です。
何か知らないが、良く食べる。食事以外にもお菓子に手が出たり、ジュースを飲んだり。
子どもは一気に食べることができないので、おやつは大事な習慣ですが、しかしその習慣が逆に仇となる場合があって、おやつがおやつでなくなってきたりします。
ところがこれが大人から見ていてわかりにくい。
というのは、当然成長期ですから、おなかはすくはずなのです。だから「良く食べて当然」と思いがちですが、実はストレスによる食欲だったりするのです。
まして受験勉強は運動不足になりやすく、かつ、甘いものが多かったり、カロリーが多すぎたりすると体調が悪くなってきます。
良く食べる、ということはまた良く運動する、ということでバランスが取れます。しかし、外に遊びに行ける機会が多いわけではないので、アンバランスな食生活になりがちです。
食べて動かなければ、当然太る。ひどくなると糖尿が出る場合もあります。
だから、上手にストレスを解消する方法を考えておくべきです。
1週間に1度サッカーの練習に出かけるのは、だから決して悪いことではない。上手にバランスを取る、ということは子どもにはなかなかできないので、お父さん、お母さんが気を付けてあげてください。
===========================================================
今日の田中貴.com
我が家流
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
慶應湘南藤沢中等部 学校別対策の考え方(2)
==============================================================

==============================================================
お知らせ
算数5年前期第9回 算数オンライン塾「差集め算」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================

にほんブログ村
コメント ( 0 )
付属校のメリット
慶應や早稲田のような大学付属校のメリットは何か?と言えば、一番最初に思う浮かぶのはやはり大学受験がない、ということではないかと思うのです。
そこそこ学校での成績を取っていれば、だいたいは大学の推薦はしてもらえる。もちろん、志望の学部に入るためには、それなりの競争があるわけですが、しかし、それは外から受験するよりもやはり楽な部分はある。
浪人しなくて済む、という考えは最初に浮かぶかもしれません。
しかし、今は実際に浪人する子どもたちはかなり減ってきています。
これは少子化の影響もあるが、一番大きいのは「浪人してまでがんばる」学生が少なくなってきたこと。各大学がそれぞれに底上げを図ってきた部分もあり、大学教育も多様化してきたので、「ここでなければ」と考えるよりはむしろ「早く大学に進もう」という傾向が強くなってきています。
だから、現役の時からいろいろな大学を受けるようになってきているので、浪人する率も減少してきています。
私は付属校のメリットとして一番大きいのは人間関係が長い、ということではないかと思います。中学から入ったとして大学まで同じ学校で10年。勿論学部が違うし、人数もそれなりにいるので、同じクラスでずっとくるということはまれでしょうが、例えばクラブ活動だとずっと同じとか、長く続く友達や先輩、後輩というのは受験校に比べると強いように思うのです。
もちろん、これはデメリットと考えられもします。つまり、比較的似たような環境でずっと育つわけだから、刺激がない。変化に乏しい。その分、自分が成長する伸びしろが少ない、と感じられる場合もあるかもしれません。
何事にも確かに二面、あるのでそれが我が子にとってプラスになるか、マイナスになるかを親は考えなければいけないわけですが、少なくも付属校に進む子どもたちを見ていると、やはりネットワークはかなり長く続いているように思うので、それが我が子にプラスになると考えれば、付属校の選択も悪くはない、ということになるでしょう。
特に中学から同じ部活を続けていくと、同じ釜の飯を食う仲間が多いことは事実で、それが良くてわが子を同じ付属に入れたいと思われる方も多いようです。

中学受験 これで成功する!母と子の「合格手帳」+デジタル手帳利用編 [Kindle版]
===========================================================
今日の田中貴.com
なぜ復習が大事なのか
==============================================================
中学受験 算数オンライン塾
3月17日の問題
==============================================================

==============================================================
お知らせ
算数5年前期第9回 算数オンライン塾「差集め算」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================


にほんブログ村
そこそこ学校での成績を取っていれば、だいたいは大学の推薦はしてもらえる。もちろん、志望の学部に入るためには、それなりの競争があるわけですが、しかし、それは外から受験するよりもやはり楽な部分はある。
浪人しなくて済む、という考えは最初に浮かぶかもしれません。
しかし、今は実際に浪人する子どもたちはかなり減ってきています。
これは少子化の影響もあるが、一番大きいのは「浪人してまでがんばる」学生が少なくなってきたこと。各大学がそれぞれに底上げを図ってきた部分もあり、大学教育も多様化してきたので、「ここでなければ」と考えるよりはむしろ「早く大学に進もう」という傾向が強くなってきています。
だから、現役の時からいろいろな大学を受けるようになってきているので、浪人する率も減少してきています。
私は付属校のメリットとして一番大きいのは人間関係が長い、ということではないかと思います。中学から入ったとして大学まで同じ学校で10年。勿論学部が違うし、人数もそれなりにいるので、同じクラスでずっとくるということはまれでしょうが、例えばクラブ活動だとずっと同じとか、長く続く友達や先輩、後輩というのは受験校に比べると強いように思うのです。
もちろん、これはデメリットと考えられもします。つまり、比較的似たような環境でずっと育つわけだから、刺激がない。変化に乏しい。その分、自分が成長する伸びしろが少ない、と感じられる場合もあるかもしれません。
何事にも確かに二面、あるのでそれが我が子にとってプラスになるか、マイナスになるかを親は考えなければいけないわけですが、少なくも付属校に進む子どもたちを見ていると、やはりネットワークはかなり長く続いているように思うので、それが我が子にプラスになると考えれば、付属校の選択も悪くはない、ということになるでしょう。
特に中学から同じ部活を続けていくと、同じ釜の飯を食う仲間が多いことは事実で、それが良くてわが子を同じ付属に入れたいと思われる方も多いようです。

中学受験 これで成功する!母と子の「合格手帳」+デジタル手帳利用編 [Kindle版]
===========================================================
今日の田中貴.com
なぜ復習が大事なのか
==============================================================
中学受験 算数オンライン塾
3月17日の問題
==============================================================

==============================================================
お知らせ
算数5年前期第9回 算数オンライン塾「差集め算」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================

にほんブログ村
コメント ( 0 )
どのくらい伸びるのか?
例えば、現在の偏差値が50の子がいたとしましょう。
この子が合格可能性80%偏差値60の学校を第一志望とするのは、無謀でしょうか?
悲観論で言えば、今が50で、本人がそれなりにがんばったとしても、みんな、それなりにはがんばるのだからやはり最終的な偏差値は50前後で収まるからやめておいた方が良いという考え方。
楽観論で言えば、今は気持ちも乗っていないし、そんなに勉強していないが、これから本気になれば10ポイントぐらいは乗り越えられるだろう、という考え方。
さて、みなさんどちらを取りますか?
これまでの経験で言えば、悲観論の結果になる子も当然いますが、楽観論の結果になる子もいる。こればかりはやってみなくてはわからない。
今の偏差値はあくまで今の状態を表しているだけなので、将来の子どもの姿を映すものではないのです。
だから、私は楽観論を決め込みます。
なぜ中学受験をするのか。端的に言えば、第一志望に入りたいから、です。
だとすれば、そこを狙うためにやりたいゲームも我慢するし、春休みだって講習に行くわけだから、狙った方が良い。
ただ、ひとつの目標ラインを考えておきたいとは思うのです。
例えばずーっと50で最後に60になる、という子も、いなくはないが、やはりめずらしい方でしょう。
だから伸ばす10ポイントを3つの時期に分ける。
夏休み前までに何とか53にしよう。
10月までには57に。
そして最後の12月で60がとれれば。
というイメージを描きます。
で、では夏休み前に53になるためには、何をするか?
と考えなくてはいけない。今まで通りやっていたのでは、50をとる勉強しかしていない、と言ってもいいわけだから、何かを変えないといけない。
とはいってもそういろいろパワーアップできるわけでもないので、例えば算数をもう少しがんばってみるために、テキストを増やしてみるとか、考えるわけです。
でも時間は限られているので、一杯いっぱいであるとすれば何かを削らないといけない。削るマイナスは当然出てくるわけです。
そのプラスマイナスで、夏休み前に53になる勉強法とは何か?
これを具体的に考えていかないと、子どもの成績は変わりません。
「勉強しなさい」
ではだめなのです。具体的に作戦を考えていかないと。中学生、高校生になれば本人が塾の先生と相談して決めていくが、小学生ですからお父さん、お母さんが知恵を出してあげないとなかなか進まない。
間もなく3学期が終わるので、ここでひとつ総括して次にどうするか、子どもたちと話してみてください。
もちろん塾の先生とも相談してほしいと思います。

中学受験、合格して失敗する子、不合格でも成功する子 [Kindle版]
===========================================================
今日の田中貴.com
炭酸水に関する問題
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
慶應湘南藤沢中等部 学校別対策の考え方(1)
==============================================================

==============================================================
お知らせ
算数5年前期第8回 算数オンライン塾「売買損益の問題」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================


にほんブログ村
この子が合格可能性80%偏差値60の学校を第一志望とするのは、無謀でしょうか?
悲観論で言えば、今が50で、本人がそれなりにがんばったとしても、みんな、それなりにはがんばるのだからやはり最終的な偏差値は50前後で収まるからやめておいた方が良いという考え方。
楽観論で言えば、今は気持ちも乗っていないし、そんなに勉強していないが、これから本気になれば10ポイントぐらいは乗り越えられるだろう、という考え方。
さて、みなさんどちらを取りますか?
これまでの経験で言えば、悲観論の結果になる子も当然いますが、楽観論の結果になる子もいる。こればかりはやってみなくてはわからない。
今の偏差値はあくまで今の状態を表しているだけなので、将来の子どもの姿を映すものではないのです。
だから、私は楽観論を決め込みます。
なぜ中学受験をするのか。端的に言えば、第一志望に入りたいから、です。
だとすれば、そこを狙うためにやりたいゲームも我慢するし、春休みだって講習に行くわけだから、狙った方が良い。
ただ、ひとつの目標ラインを考えておきたいとは思うのです。
例えばずーっと50で最後に60になる、という子も、いなくはないが、やはりめずらしい方でしょう。
だから伸ばす10ポイントを3つの時期に分ける。
夏休み前までに何とか53にしよう。
10月までには57に。
そして最後の12月で60がとれれば。
というイメージを描きます。
で、では夏休み前に53になるためには、何をするか?
と考えなくてはいけない。今まで通りやっていたのでは、50をとる勉強しかしていない、と言ってもいいわけだから、何かを変えないといけない。
とはいってもそういろいろパワーアップできるわけでもないので、例えば算数をもう少しがんばってみるために、テキストを増やしてみるとか、考えるわけです。
でも時間は限られているので、一杯いっぱいであるとすれば何かを削らないといけない。削るマイナスは当然出てくるわけです。
そのプラスマイナスで、夏休み前に53になる勉強法とは何か?
これを具体的に考えていかないと、子どもの成績は変わりません。
「勉強しなさい」
ではだめなのです。具体的に作戦を考えていかないと。中学生、高校生になれば本人が塾の先生と相談して決めていくが、小学生ですからお父さん、お母さんが知恵を出してあげないとなかなか進まない。
間もなく3学期が終わるので、ここでひとつ総括して次にどうするか、子どもたちと話してみてください。
もちろん塾の先生とも相談してほしいと思います。

中学受験、合格して失敗する子、不合格でも成功する子 [Kindle版]
===========================================================
今日の田中貴.com
炭酸水に関する問題
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
慶應湘南藤沢中等部 学校別対策の考え方(1)
==============================================================

==============================================================
お知らせ
算数5年前期第8回 算数オンライン塾「売買損益の問題」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================

にほんブログ村
コメント ( 0 )
できた!と言って帰ってきたが
組み分けテストや月例テストから帰ってきた子どもたちに、「どうだった?」と聞くと、たまに「できた!」という子がいます。
しかし、実際に帰ってきた点数を見るとそうでもない。というか、あちこち×だらけ。
子どもたちの感覚はそういうものです。
つまり「できた!」というのは「解けた!」であって「正解した!」ではない。
答えを書いた以上、本人としては正解を書いた、と思うのは当たり前のことで、だから「できた!」と答えるわけです。
しかし実際には問題文を読み違えたり、計算ミスをしたり、まあ、いろいろやっている。
ただ、私はそれが普通だと思います。
だからテスト直しは非常に大事で、実際にやり直してみると、やっぱりできることは多いのです。ただ初見で正解にならない。これは入試ではやはりだめなので、少しずつ「正確さ」「ていねいさ」というものを身につけていくように、練習していけばいいのです。
「どうだった?」と聞かれて
「まあまあ」とか「普通」とか答える子も多いでしょう。
実際に本人としては自信がない。でも「できなかった」と答えるのもいやだし、「まあまあ」と言っておけばいいか、という感じでしょう。だから、聞いても仕方がない部分はあるわけですが、最近はテストが帰ってくるのも早くなったし、しっかしWEBで答案が見られる塾も増えたので、聞かずに答案を精査しましょう。
親は細かいことはさておき、つい点数や順位、偏差値、ということに眼が行きがちですが、やはり大事なのは答案。
空欄が多くてだめなのか、答えは書いているが×が多いのか、でも対策は違ってきます。
同じ点数でも解いている過程にある問題はさまざまなので、今の時期は点数や偏差値よりも、答案を気にしてください。
理想形は、手を付けた問題は全部合っている、です。
空欄はあっていいが、答えを書いたら正解、というタイプは合格しやすい。正解率が高くなれば、あとはできる問題の幅を広げていけばいいだけですが、この時期はなかなかそうならない。
だからまずは正解率を気にしてください。答えを書いた問題のうち、どれだけ○がついたか。
100%であればたとえ60点しか取れなくとも、良い感じだと思います。

中学受験 これで成功する!母と子の「合格手帳」+デジタル手帳利用編 [Kindle版]
===========================================================
今日の田中貴.com
科目のバランス
==============================================================
中学受験 算数オンライン塾
3月15日の問題
==============================================================
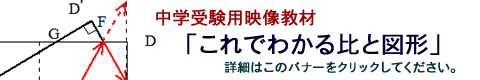
==============================================================
お知らせ
算数5年前期第8回 算数オンライン塾「売買損益の問題」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================

にほんブログ村
コメント ( 0 )
漢字練習の間違い
漢字を覚える、というので子どもたちの練習を横で見ていたことがあります。
マス目の入ったノートに、1つの熟語を5回ずつ書いていく子。
その字をずーっとにらんでいる子。
へんやつくりを分解している子。
まあ、いろいろやり方はあるのですが、一般には最初の子のやり方をしている事が多いでしょう。学校の宿題でも5回ずつ書くとか、10回ずつ書くとか。
そういえば最近出た知識を覚える本で、同じ言葉をなぞるようにできている本がありました。
で、これらの練習は間違っています。
え? と思われるかもしれない。
というのは、子どもたちの意識の問題なのですが、5回書きなさい、と言われると覚えることが本来の目的なのに5回書くことが目的に変わってしまう。10回書く、ということになると、さらに悪い。
もう5つ目ぐらいから惰性です。したがって漢字を覚えるという意識はさらさらなくなってしまう。これは時間のムダです。
書くのは1回か、2回。それであとは、何も見ずに書けるかを試す。
5回ずつ書くのは上に模範の字があるから、情報はインプットされてしまう。だから意識が「覚える」方に行かないのです。
じっと見ているのもだめ。というのは、書くことで字の構造が理解できることが多いからです。
そういう意味では3番目の子のやり方は理にかなっている。
つまり覚えるきっかけをいくつか作っているわけです。へんだったり、つくりだったりを分解して、この時はこう構成されている、という意識になっているので、比較的短い時間で覚えられるでしょう。
確かにものを写す、というのは理解する、覚えるということでは有効なのですが、それは1回か2回の話。5回以上になると、明らかに終わることが目的にすり替わりますから、気を付けてください。
あくまで覚えるためにやるのですから。

「第2回 母親講座 家庭学習をどう充実させるか」(田中貴)
===========================================================
今日の田中貴.com
条件を整理する問題
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
古典を知る機会を作る
==============================================================
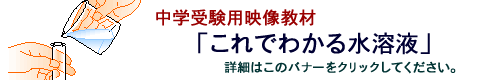
==============================================================
お知らせ
算数5年前期第8回 算数オンライン塾「売買損益の問題」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================


にほんブログ村
マス目の入ったノートに、1つの熟語を5回ずつ書いていく子。
その字をずーっとにらんでいる子。
へんやつくりを分解している子。
まあ、いろいろやり方はあるのですが、一般には最初の子のやり方をしている事が多いでしょう。学校の宿題でも5回ずつ書くとか、10回ずつ書くとか。
そういえば最近出た知識を覚える本で、同じ言葉をなぞるようにできている本がありました。
で、これらの練習は間違っています。
え? と思われるかもしれない。
というのは、子どもたちの意識の問題なのですが、5回書きなさい、と言われると覚えることが本来の目的なのに5回書くことが目的に変わってしまう。10回書く、ということになると、さらに悪い。
もう5つ目ぐらいから惰性です。したがって漢字を覚えるという意識はさらさらなくなってしまう。これは時間のムダです。
書くのは1回か、2回。それであとは、何も見ずに書けるかを試す。
5回ずつ書くのは上に模範の字があるから、情報はインプットされてしまう。だから意識が「覚える」方に行かないのです。
じっと見ているのもだめ。というのは、書くことで字の構造が理解できることが多いからです。
そういう意味では3番目の子のやり方は理にかなっている。
つまり覚えるきっかけをいくつか作っているわけです。へんだったり、つくりだったりを分解して、この時はこう構成されている、という意識になっているので、比較的短い時間で覚えられるでしょう。
確かにものを写す、というのは理解する、覚えるということでは有効なのですが、それは1回か2回の話。5回以上になると、明らかに終わることが目的にすり替わりますから、気を付けてください。
あくまで覚えるためにやるのですから。

「第2回 母親講座 家庭学習をどう充実させるか」(田中貴)
===========================================================
今日の田中貴.com
条件を整理する問題
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
古典を知る機会を作る
==============================================================
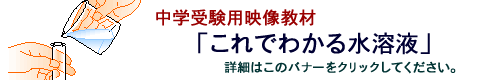
==============================================================
お知らせ
算数5年前期第8回 算数オンライン塾「売買損益の問題」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================

にほんブログ村
コメント ( 0 )
グラフを書きなれる
今年の入試で、いろいろな学校でグラフを描く問題が出題されていました。
複雑な形をした容器に水を入れていったり、しきり板の高さを変えてみたり、あるいは回転させてみたり、という条件もあれば、速さの問題でも出題されていました。
速さの問題は文章が長くなります。いろいろな条件が出てくるので、それが整理できなくて問題の解法が思いつかない、あるいはポイントに気がつかないということがおこるわけです。
ですから私は、速さの問題では出来る限りグラフを書くように指導しています。
すぐ問題の解法が思いつく場合は別ですが、そうでない場合は問題の条件をグラフにしてみる。比で解く速さの問題の場合、同じ時間動いているところ、か同じ距離を動いているところが問題を解く鍵になるのですが、それが見つかりやすくなります。
ただ、図形といっしょでグラフも書きなれていなければ、上手になりません。今は、まだ真似でいいと思うのです。私はホワイトボードに自分でグラフを書き、それを子どもたちに写させています。真似るから始まって自分でできるようにする、というのが一番の早道です。
ですから、ご自宅では解説のグラフを、ノートに写すことをお勧めします。
写せばなぜこういうグラフになるのか、少しずつわかってきます。たくさんの問題をやるよりも、こういう作業をすることによって、子どもの可能性は広がるので、今はあわてずに、ひとつひとつの作業を大切にしてください。
グラフを描く問題は今後も多く出題されるでしょう。定規を持ってくるように指示が出ている学校では、定規を使えますが、そうでない場合もあり得るので、フリーハンドでグラフを書けることも学校によっては必要になります。
慣れないうちは方眼罫を使っていくと便利です。そして慣れてきたら全く白紙のノートを使って勉強してください。そういう日頃の勉強が、やがて入試で役立ちますから。

「映像教材、これでわかる比と速さ」(田中貴)
===========================================================
今日の田中貴.com
第74回 揺れる心
==============================================================
中学受験 算数オンライン塾
3月13日の問題
==============================================================
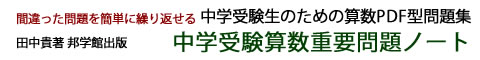
==============================================================
お知らせ
算数5年前期第8回 算数オンライン塾「売買損益の問題」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================

にほんブログ村
コメント ( 0 )
孟母三遷
というわけではないが、4月から行く学校が決まったので、今月引っ越しをされるご家庭があるでしょう。
これまで地域の小学校にいたので、なかなか動きづらい面もあったが、子どもの学校も決まったし、おばあちゃんのことも気になるから、というので今まで住んでいた地域から新しい生活が始まるのは、子どもたちにとっても家族にとっても楽しみなことではあると思います。
同じように考えて、志望校を決めていかれるご家庭もあるかもしれません。
実際に、ここに合格したら、引っ越そうね、という話は当然、子どもたちにしていただいてかまわないのですが、ただ、それがあまりプレッシャーにならないようにしてください。
「あなたが合格しないと、おばあちゃんの近くには行けないからね。」
となってしまうと、子どもは妙な義務感を背負うことになる。
それを糧にするのならプラスになるが、全員がそうだとは言えないでしょう。
「合格したら、考えなくもない」
というぐらいにとどめておいて、でもそれが子どもたちにとっても楽しいことになれば、勉強する動機がちょっとふくらんでいいのではないかと思います。
我が家も下の子の合格とともに、引っ越しをしましたから、そのときはなかなかばたばたしましたが、今思い出すとそれはそれでなかなか楽しい経験でした。
いずれにしても、新中学1年生の新しい生活が来月からスタートします。
楽しい学校生活を送ってください。
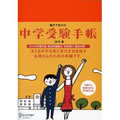 親子で受かる! 中学受験手帳
親子で受かる! 中学受験手帳
===========================================================
今日の田中貴.com
暗算のワナ
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
中等部男子の一次合格者数
==============================================================

==============================================================
お知らせ
算数5年前期第8回 算数オンライン塾「売買損益の問題」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================


にほんブログ村
これまで地域の小学校にいたので、なかなか動きづらい面もあったが、子どもの学校も決まったし、おばあちゃんのことも気になるから、というので今まで住んでいた地域から新しい生活が始まるのは、子どもたちにとっても家族にとっても楽しみなことではあると思います。
同じように考えて、志望校を決めていかれるご家庭もあるかもしれません。
実際に、ここに合格したら、引っ越そうね、という話は当然、子どもたちにしていただいてかまわないのですが、ただ、それがあまりプレッシャーにならないようにしてください。
「あなたが合格しないと、おばあちゃんの近くには行けないからね。」
となってしまうと、子どもは妙な義務感を背負うことになる。
それを糧にするのならプラスになるが、全員がそうだとは言えないでしょう。
「合格したら、考えなくもない」
というぐらいにとどめておいて、でもそれが子どもたちにとっても楽しいことになれば、勉強する動機がちょっとふくらんでいいのではないかと思います。
我が家も下の子の合格とともに、引っ越しをしましたから、そのときはなかなかばたばたしましたが、今思い出すとそれはそれでなかなか楽しい経験でした。
いずれにしても、新中学1年生の新しい生活が来月からスタートします。
楽しい学校生活を送ってください。
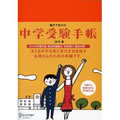 親子で受かる! 中学受験手帳
親子で受かる! 中学受験手帳 ===========================================================
今日の田中貴.com
暗算のワナ
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
中等部男子の一次合格者数
==============================================================

==============================================================
お知らせ
算数5年前期第8回 算数オンライン塾「売買損益の問題」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================

にほんブログ村
コメント ( 0 )
| « 前ページ | 次ページ » |





