長野県木曽町日義でサクラを見たあと、近くでランチをしました。
やって来たのは同じ町内にあった、ここ。国道19号沿いの阿羅屋(あらや)。そば屋です。

「もしかして希少名字の阿羅さん?」
店内に入ると、道路に面した小テーブル2つ、座敷にテーブルが2つ。
座敷に腰を下ろして、入口方向をパチリ。

座敷は、向こうの端と、こっちの端にテーブル。
まるで、プーチンとマクロンの会談の時のように、席が離れていました。
「アクリル板はないけれど、この距離、感染対策は万全だ」
メニュー拝見。
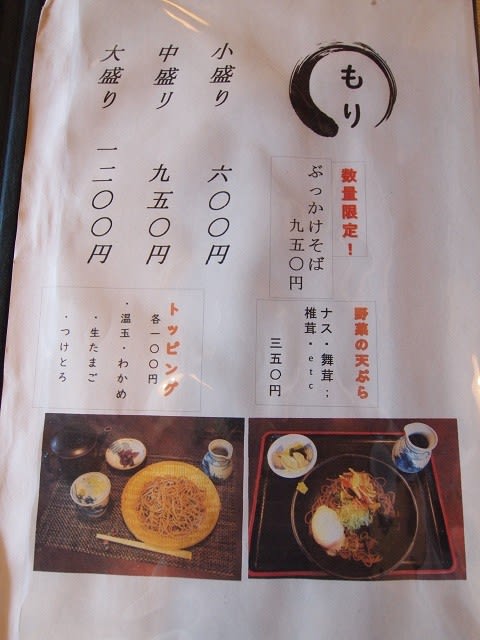
「中盛り1つ、野菜の天ぷら1つ」
「早~っ!」
注文後、間もなく出てきました。
見てガッテン。そばは極細でした。遅れて、天ぷらがやって来ました。

そば猪口に、すでに汁が入っていました。それにそば徳利と胡桃汁がついて、つけ汁十分。天ぷらは、マイタケ・ナス・カボチャが各2つ、肉厚のシイタケとピーマンが各1つ。
まず、そばだけをいただきました。極細ですが、腰がありました。
つぎに、汁にちょっと浸してすすると、
「美味いっ!」
さらに、胡桃汁にどっぷり浸して食べてみると、
「これも、良しっ!」
天ぷらは、カボチャを除き、厚切りで、長さは10センチと大物。ころもは多すぎず、適度。
食べたあと、濃厚どろどろのそば湯を飲みながら、始めたばかりのスマホで検索すると、
「食べログ評価、低っ!! なぜ??」
この評価、あてにならないと言いますよね。































































