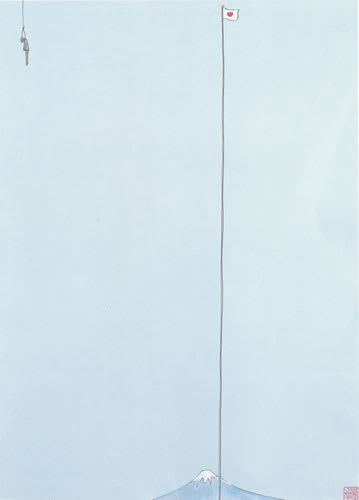「DOMANI・明日展」は、文化庁による海外派遣事業によって派遣された作家の成果発表の場としいて開催され、今年で15回目になるという。今回は、近年、美術部門で派遣され、これまでの「DOMANI・明日展」に未出品の作家から、曽根裕、米正万也、塩田千春、神彌佐子、橋爪彩、行武治美、澤田知子、糸井潤、平野薫、青野千穂、池田学、小尾修の12名の研修の成果発表として開催されている。もちろん、どの作家も私には未見の芸術家である。
分野、表現手法が多様なので、私の受容範囲を超える作家が多いということもあって、ここでは印象に残ったいくつかの作品だけに限って触れてみる。引用の中のページは、図録『DOMANI・明日展2013』(文化庁、2013)に掲載されている箇所を示す。
会場は、作家ごとに区割りされた小部屋に展示されている。最初の部屋は、神彌佐子(日本画、派遣年/2006年度、派遣国/フランス、1962年生まれ)の作品群で、そのほとんどは華麗な印象を与える抽象画である。抽象画ということから、神は洋画部門の作家だろうと思っていたが、分野は日本画ということであった。
たしかに、画材は紙本、墨、顔料など日本画のそれを用いている。考えてみれば、洋画に抽象と具象があるように、日本画にも抽象と具象があってもよいはずだが、理由もなく日本画は具象と思い込んでいた。

神彌佐子 《stride 2012》 2012年、麻製蚊帳、楮紙、墨、顔料、箔、他、400.0×730.0cm [p. 57]。
紙本着色の作品群の最後に、蚊帳に楮紙を貼り込んだインスタレーシヨン作品《stride 2012》が展示されている。50年前の蚊帳だそうである。蚊帳という透ける素材のせいか、紙本着色の作品より一段と幻想的な華麗さが表現されていて、目を引いた。
橋爪彩(油彩、派遣年/2006年度、派遣国/ドイツ、1980年生まれ)は、私には不思議な作家である。

左:橋爪彩 《Toilette des Filles》 2011-2012年、油彩、パネル、112.0×162.0cm、個人蔵 [p. 65] 。
右:橋爪彩 《Toilette des Filles 2》 2012年、油彩、パネルにエマルジョン地、130.3×194.0cm [p. 63]。
はじめに左の《Toilette des Filles》を見て、マネキンと人間を写した写真作品だと思ってしまったのである。そして、《Toilette des Filles 2》は、同じ二人の違った構図の作品だろうと見当をつけたのだが、どちらがマネキンか生身の人間か、わからなくなってしまった。愚かなことに、作品脇に「油彩、パネル」と明記されていたにもかかわらず、しばらく二つの作品を見比べながら考え込んでしまったのだった。
マネキンのような皮膚感、目は必ず隠されていてけっして人間らしい表情というものが表出されない顔、それでいて極度にリアリティの高い身体の陰影、そういうことがらのすべての不思議に惹かれる作品群である。図録解説に「不安とエロティシズムを圧倒的な描写力で描き異彩を放つ」 [p. 58] とある。

糸井潤 《Cantos Familia》 2011-2012年、アーカイバルピグメントプリント、90.0×90.0cm [p. 87]
糸井潤(写真、派遣年/2009年度、派遣国/フィンランド、1971年生まれ)の写真作品群は、フィンランドという緯度の高い北欧の闇、あるいは闇の中のかすかな光を表現しようとしているように見える。
《Cantos Familia》は、高度の低い太陽が月に見えるほどに弱い光をさしている森の写真である。焦点は手前の草に厳しく制限され、幻想性を際立たせている。
《Kaamos》は、人の住む空間の写真で、なかでも下の写真に心を奪われる感じがした。とりわけ、珍しい光景ではない。闇の中の人が通る圧雪の道、街灯でスポットライトで照らされているように浮かびがる雪をまとった潅木、向こうには一部に暖かそうな火影を宿した建物。そう、とりたてて何かではなく、人が暮らす場所にこのような美しい光の配置があることを描き出していて見事である。
なお、作者によれば、Kaamosとは極夜の事で、太陽が全く昇らない時期を指すフィンランド語だという[p. 90]。

糸井潤 《Kaamos》 2011-2012年、アーカイバルピグメントプリント、65.7×97.5cm [p. 90]。
細部を徹底的に描きこむ緻密な描写は、池田学(ペン画、派遣年/2010年度、派遣国/カナダ、1973年生まれ)の特徴で、そのモティーフには社会や歴史に対する批評性に満ちているように見える。

池田学 《巌ノ王》 1998年、ペン、インク、紙、195.0×100.0cm、
おぶせミュージアム・中島千波館蔵 [p. 114]。
《巌ノ王》は、芸大卒業制作でまだ社会や歴史へのコミットメントが希薄な時代のようであるが、描法はすでに確立されている。山岳部で登った山々の記憶をもとに描かれた空想の岩山ということだが、岩の〈王〉であるということは、岩の多種、多様性を内包しつつ自ら体現する〈巌〉でなければならないという〈王〉概念に基づいていると思えるほど、さまざまな岩の形態と質が細密に描きこまれている。

池田学 《漂流者》 2011年、ペン、インク、紙、61.0×61.0cm、個人蔵 [p. 121] 。
《漂流者》は幻想的で美しい作品だが、作者はこう記している。
震災後、バンクーバーで優雅に漂うクラゲを見た。津波で流された人達が巨大なクラゲの体内で生き延び、生活を再建している。悲しすぎる現実に、せめて絵の中だけでも希望をとの願いを込めて描いた作品 [p. 121]。
〈3・11〉で何人かの知人、友人を失った東北で生まれ育った私には、美しいが切実な作品である。

小尾修 《跡》 1992年、油彩、テンペラ、キャンバスにエマルジョン地、162.0×194.0cm [ p. 124] 。
小尾修(油彩、派遣年/2010年度、派遣国/フランス、1965年生まれ)は、極めて写実性の高い画家である。本人の言によれば、「現実と作品とが明らかに異質なものである以上、完全な再現というものはあり得ない。そこには必ず「置き換える」、「切り取る」といった作家の意思、解釈が伴う。それは全く機械的な作業とは異なる領域を持つものだ」[p. 124]という。
《跡》の前に立つと、こちらを見つめている少女の顔から目が離せなくなる。これは《空き地》という作品でも同じであった。茶褐色に塗られた波板トタンで囲まれ、フォークリフトが置かれた工場の裏手のような空き地で、青年が低い椅子に腰掛けてこちらを見つめている。その青年の顔から目が離せなくなる。青年も少女も取り立ててなにがしかの感情を表しているわけではない。かといって無表情でもない。そこにいて生きている人間がただ普通にこちらを見つめているだけである。これが、優れた写実の持つ力というものであろうか。

小尾修 《休息》 2004年、油彩、キャンバスにエマルジョン地、97.0×162.2cm、倉吉博物館蔵 [p. 125] 。
《休息》は寓意に満ちた作品のように思えるのだが、私には何の寓意なのかはまったくわからない。頑丈そうな編上げ靴、無造作に置かれた上着とバッグ、1個の林檎、そして渡りの途中のような1羽の鳥。人はこのような狭い不安定な岩上で安らぐのか。なにもかも寓意的で心惹かれる美しい絵である。
ありていに言えば、私はこういう絵が好きだ。