世界的に有名な物理学者であるホーキング博士は、今は亡くなっているが、「車椅子に乗った天才」として知られていた。若い頃にALS(筋委縮性側索硬化症)を発症し、手足を動かすことができない障害者であった。
ホーキング以前に身体の自由が利かない著名な科学者が存在したという話を聞いたことがない。ホーキングは、声が出せなくなった後、車椅子に装着されているパソコンで文章を作り、それを音声合成装置に送り会話したという。おそらく20世紀になって科学技術が進歩し、このような障害をもつ科学者が仕事できるような環境になったのであろう。
ホーキングの仕事は頭脳労働であるとはいえ、手足が利かない体で論文を書いたり、学会などでプレゼンテーションすることがどれほど大変な苦労であったか、健常者には想像もできないのではなかろうか。
しかし、健常者といっても年寄ともなれば、視力は衰え、脳は疲労しやすくなる。その程度には個人差があるだろうが、年寄になるということは、多かれ少なかれ障害者の仲間入りをすることであると考える。
そうであれば、仕事から引退した年寄であっても、ホーキングにははるかに及ばないにしても、充分な時間さえかければ、頭を使う作業によって何かを成せるのではないかという気になる。
ただ、年寄の頭脳は疲れやすいので、一に休息、二に瞑想、三に作業の優先順序となるだろう。特に瞑想の効果は大きく、作業よりも重要である。
何の作業をするかは、人それぞれであると思うが、私は、科学と数学、特に論理的あるいは数学的思考が伴うもの、または計算が伴う作業を選んでいる。
数学的思考と計算を伴う作業は、計算結果の検証を行ったり、別の視点から再計算を行うなど検証の機会があり、計算ミスや転記ミスの多い年寄には向いているように思えるのである。
理論物理学者であったホーキングも、理論や数式が正しいことを確認するために多くの計算作業を行って検証したと想像する。健常者と同様に、あるいはそれ以上に、ホーキングにとっても計算作業とその検証は時間のかかる作業であったに違いない。しかし、ホーキングは、計算手順を少なくするような数学的思考や技法を考える能力を持ち合わせていたと思う。
高校数学を履修した人であれば誰でも経験したことであるが、それが何の役に立つのか知らされることもなく無味乾燥な代数計算を延々と実行せねばならなかった。参考文献の森田さんの言葉を借りれば、もともと計算する人とは、人間が機械になることであるという。計算とは、同じ入力に対して同じ出力を返す手続きであるから、外部からの入力に支配されたシステム、つまり他律的なシステムであるとのことである。
代数計算の負担を軽減するためには、いろいろな数学的思考法や技法を試みる必要があると考える。例えば、複雑な代数式の代わりによりシンプルな代数式で目的を達成できないか検討する場合もあるだろう。あるいは計算を簡単にするために、0,1,-1などシンプルな数値を使って計算するよう考慮する場合もあるだろう。
年寄が数学的思考を伴う作業を行うとき、高校生並みの代数計算しかせず、より高度な数学的思考法を試みないとすれば、達成感も少なく、先に進みたいというモチベーションも涌かないであろう。数学が教えている基本概念を考慮せずに、ただ公式に従って計算しているだけでは、高校時代の習性そのままの作業をしているということであり、その公式の適用を誤っているときには誤った結果を出力することになる。
高度の数学的思考能力を身につけるまでには、その作業を長期間に亘って継続する必要がある。そのような期間を経た後には、誰でもある程度の達成感を実感し、数学的思考を楽しむことができるものと信じる。
それにしても、世の中には長期の修行なしで楽しめる趣味・娯楽や生涯教育の類であふれている。一方、江戸時代に普及した和算とは異なり、高度化かつ抽象化した現代数学を応用する分野は広がる一方である。その筋の専門家でもそれについていくのが難しくなっている現在、一般市民がついていくのは無理という悲観的な意見もあるだろう。私は、そのような意見には組せず、他の趣味・娯楽などと同様に、日常生活に欠けているわくわく感を体験できるならば、それでよいではないかと思う。
参考文献
スティーヴン・ホーキング著、佐藤勝彦訳「ホーキング、未来を語る」(アーティストハウス)
森田真生著「計算する生命」(新潮社)
ホーキング以前に身体の自由が利かない著名な科学者が存在したという話を聞いたことがない。ホーキングは、声が出せなくなった後、車椅子に装着されているパソコンで文章を作り、それを音声合成装置に送り会話したという。おそらく20世紀になって科学技術が進歩し、このような障害をもつ科学者が仕事できるような環境になったのであろう。
ホーキングの仕事は頭脳労働であるとはいえ、手足が利かない体で論文を書いたり、学会などでプレゼンテーションすることがどれほど大変な苦労であったか、健常者には想像もできないのではなかろうか。
しかし、健常者といっても年寄ともなれば、視力は衰え、脳は疲労しやすくなる。その程度には個人差があるだろうが、年寄になるということは、多かれ少なかれ障害者の仲間入りをすることであると考える。
そうであれば、仕事から引退した年寄であっても、ホーキングにははるかに及ばないにしても、充分な時間さえかければ、頭を使う作業によって何かを成せるのではないかという気になる。
ただ、年寄の頭脳は疲れやすいので、一に休息、二に瞑想、三に作業の優先順序となるだろう。特に瞑想の効果は大きく、作業よりも重要である。
何の作業をするかは、人それぞれであると思うが、私は、科学と数学、特に論理的あるいは数学的思考が伴うもの、または計算が伴う作業を選んでいる。
数学的思考と計算を伴う作業は、計算結果の検証を行ったり、別の視点から再計算を行うなど検証の機会があり、計算ミスや転記ミスの多い年寄には向いているように思えるのである。
理論物理学者であったホーキングも、理論や数式が正しいことを確認するために多くの計算作業を行って検証したと想像する。健常者と同様に、あるいはそれ以上に、ホーキングにとっても計算作業とその検証は時間のかかる作業であったに違いない。しかし、ホーキングは、計算手順を少なくするような数学的思考や技法を考える能力を持ち合わせていたと思う。
高校数学を履修した人であれば誰でも経験したことであるが、それが何の役に立つのか知らされることもなく無味乾燥な代数計算を延々と実行せねばならなかった。参考文献の森田さんの言葉を借りれば、もともと計算する人とは、人間が機械になることであるという。計算とは、同じ入力に対して同じ出力を返す手続きであるから、外部からの入力に支配されたシステム、つまり他律的なシステムであるとのことである。
代数計算の負担を軽減するためには、いろいろな数学的思考法や技法を試みる必要があると考える。例えば、複雑な代数式の代わりによりシンプルな代数式で目的を達成できないか検討する場合もあるだろう。あるいは計算を簡単にするために、0,1,-1などシンプルな数値を使って計算するよう考慮する場合もあるだろう。
年寄が数学的思考を伴う作業を行うとき、高校生並みの代数計算しかせず、より高度な数学的思考法を試みないとすれば、達成感も少なく、先に進みたいというモチベーションも涌かないであろう。数学が教えている基本概念を考慮せずに、ただ公式に従って計算しているだけでは、高校時代の習性そのままの作業をしているということであり、その公式の適用を誤っているときには誤った結果を出力することになる。
高度の数学的思考能力を身につけるまでには、その作業を長期間に亘って継続する必要がある。そのような期間を経た後には、誰でもある程度の達成感を実感し、数学的思考を楽しむことができるものと信じる。
それにしても、世の中には長期の修行なしで楽しめる趣味・娯楽や生涯教育の類であふれている。一方、江戸時代に普及した和算とは異なり、高度化かつ抽象化した現代数学を応用する分野は広がる一方である。その筋の専門家でもそれについていくのが難しくなっている現在、一般市民がついていくのは無理という悲観的な意見もあるだろう。私は、そのような意見には組せず、他の趣味・娯楽などと同様に、日常生活に欠けているわくわく感を体験できるならば、それでよいではないかと思う。
参考文献
スティーヴン・ホーキング著、佐藤勝彦訳「ホーキング、未来を語る」(アーティストハウス)
森田真生著「計算する生命」(新潮社)










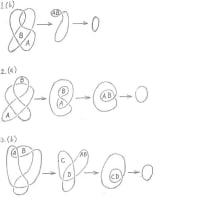


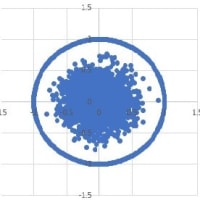
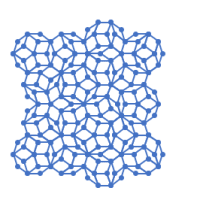
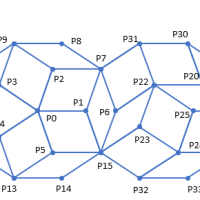
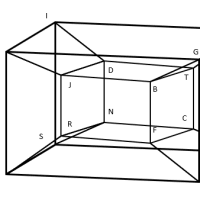
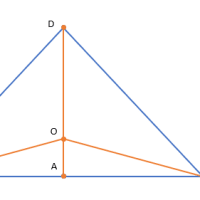
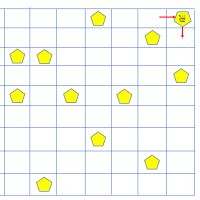
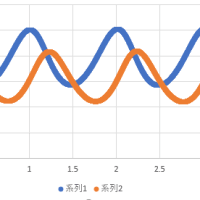
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます