今週は、この2冊。
三秒間の死角(上・下)/象牙色の嘲笑 新訳版/
■三秒間の死角(上) 2016.12.24
身近にいたらうんざりさせられるだろうけど、物語のなかでは、なんとも魅力的なエーヴェルト・グレーンス。
エリック・ウィルソンとピート・ホフマンの強い絆は、いつしか友情らしきものに育つ、このことにほっとさせられたのは、ぼくだけだろうか。
物語の最後(下巻)に、エリック・ウィルソンがしみじみと漏らすのだ。
弱々しい音を風が飲み込んでしまう夜には、ここまで音が届かない。
こんな夜にはいつも、自分で曲を選んで録音したカセットテープに耳を傾け、べつの時代に包まれて眠りに落ちていたのだ。
昼の光が消え、自宅が孤独と同義語になるときに。
スヴェーア通りと眠らない首都を望む自宅のバルコニーで、長い夜を過ごさずにすむ。
人はだれしも、その人なりの理由があって選択する。理由を話したがらない相手にしつこく尋ねても無駄でしかない、と彼は学んでいた。
彼女の部屋にはもう、べつのだれかが住んでいるにもかかわらず。彼女のものだった窓に近寄る。彼女はこの窓辺に座り、外の世界で進行する人生を眺めていた。エーヴェルトはその傍らに座って、彼女はほんとうのところ、いったいなにを見ようとしているのだろうと考えていた。
「手放すことです。前に進んでください。こんな習慣はやめて」
「あいつに会いたいんだ」
「もう、ここであなたにお会いしたくはありません」
スウェーデンの潜入捜査員には、女性名のコードネームがつけられる。
コードネーム、パウラは、何故潜入捜査員という困難な仕事に執着するのか。
妻とふたりの可愛い幼子がいるのに。
月、1万クローネ(15万円~18万円程か)の報酬で。
"役を演じ切れ"。結局、それがすべてだ。力を誇示し、侮れない相手だと思わせること。手に入れたものは、けっして手放さないこと。"役を演じきるか、死ぬか、ふたつにひとつだ"
うつろな日々。思い出すことはできるが、なにも感じない。あのころ大切だと思っていたこと、大きく、揺るぎなく見えたものが、実はなんの意味もないことに気づいたのは、自分を見つめ、パパ、と呼んでくれる存在が現れたあとのことだった。
人が、絶対に超えないと自ら誓った境界線を、超えてしまったとき。
あの人は、いったい何者になるのだろう?
今年読んだミステリーのなかでは、最高に面白い一冊でした。
『 三秒間の死角(上)/アンデシュ・ルースルンド&ベリエ・ヘルストレム
/ヘレンハルメ美穂訳/角川文庫 』
■三秒間の死角(下) 2016.12.24
長い人生のなかで、もし一人でもこんな出会いがあったなら、人生はなんと豊になることだろうか。
もし自分に子供がいたら、まさに彼女のようだったにちがいない、と思う。
夜の静寂に詩的文章が流れる出る、登場人物達のさまざまな生き様が綴られている。
長いあいだ、家族の寝室だった部屋の窓。彼はいま、そこにひとりで暮らしている。いろいろなものを捨ててきた。捨ててはいけないものを捨ててきた。やり直したいと思ったところで、手遅れのこともある。
風変わりなところは、風変わりなところとして放っておくのが、波風が立たなくていちばんいい。自分はそういったふうがわりなところのない、退屈な人間だと自覚している。
ほんとうになにかが変わったのかもしれない。自分たちはもしかするとこれから、互いの存在をほんの少し耐えられるようになるのかもしれない。
傍役ではあるが、アスプソース刑務所の看守長マルティン・ヤコブソンが、ぼくにはなんとも魅力的な男に思えた。
生き抜くとは、自分の仕事をしっかりと勤め、家族を養い、いつしか渋い魅力的な男に成長すること。
『制裁』、『ボックス21』を読みたいと思い、アマゾンで古本を調べたが、文庫で\2000-以上もした。あきらめた。読みたかったのになあ。
『 三秒間の死角(下)/アンデシュ・ルースルンド&ベリエ・ヘルストレム
/ヘレンハルメ美穂訳/角川文庫 』
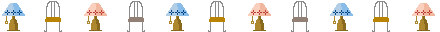
■象牙色の嘲笑 新訳版 2016.12.24
ほんとにおかしいのはね
愛している相手は絶対にこっちを愛してくれないってこと。
こっちを愛してくれる人、そういう人たちはこっちが愛せない。
長い人生のなかで、いやというほど見聞きしてきましたよね、あるいは体験した? この真実。
ここに、未練が加わると、もう大変、地獄ですね。
身もこころも、ぼろぼろだよ。
「訳者(片割れ)によるあとがき/松下祥子」
本書が出版された一九五二年といえば、ミッキー・スピレインが超ベストセラー作家として君臨していたころだ。
マクドナルドの伝記でトム・ノーランはこの時代の出版状況に触れ、スピレインの荒っぽい私立探偵小説が何百万部と売れまくっていて、ハメット=チャンドラー系の洗練された作品を買うような読者の多くが怖気づいて書店に寄りつかなくなった、と書いている。
出版社から『象牙の嘲笑』にはもっとアクション場面を加えたほうがいいと指摘され、修正を試みたこともあったが、最終的にはマクドナルドが説得して、出版社はバイオレンスはスピレインに任せ、マクドナルド本はもっと文学のわかる読者に売っていくと決めたという。
マクドナルドは「(彼を創造したとき)私はアーチャーそのものではなかったが、アーチャーは私だった」と「ボヴァリー夫人は私だ」と言ったフローベルにならった表現をしている。
あとがきを読む楽しさは、このような説明が読めることです。
「やれやれ、自分の人生だもの、すべてを含めて生きていくしかないわね。さてと、時間を無駄にしているわ。私が言うとおりにやってくださるの、それ以上でもそれ以下でもなく?」
街の上流地区から脱走してきた数人は、酒にいつもの自分を溺れさせて、別人に生まれ変わる
なにをするときでも優しく、ほとんど後悔するような仕草で、行動とはすなわち危険なギャンブルだとでも思っているようだった。
このような詩的な文章を作品中の随所で拾うことが出来ます。
『 象牙色の嘲笑 新訳版/ロス・マクドナルド
小鷹信光・松下祥子訳/ハヤカワ・ミステリ文庫 』
三秒間の死角(上・下)/象牙色の嘲笑 新訳版/
■三秒間の死角(上) 2016.12.24
身近にいたらうんざりさせられるだろうけど、物語のなかでは、なんとも魅力的なエーヴェルト・グレーンス。
エリック・ウィルソンとピート・ホフマンの強い絆は、いつしか友情らしきものに育つ、このことにほっとさせられたのは、ぼくだけだろうか。
物語の最後(下巻)に、エリック・ウィルソンがしみじみと漏らすのだ。
弱々しい音を風が飲み込んでしまう夜には、ここまで音が届かない。
こんな夜にはいつも、自分で曲を選んで録音したカセットテープに耳を傾け、べつの時代に包まれて眠りに落ちていたのだ。
昼の光が消え、自宅が孤独と同義語になるときに。
スヴェーア通りと眠らない首都を望む自宅のバルコニーで、長い夜を過ごさずにすむ。
人はだれしも、その人なりの理由があって選択する。理由を話したがらない相手にしつこく尋ねても無駄でしかない、と彼は学んでいた。
彼女の部屋にはもう、べつのだれかが住んでいるにもかかわらず。彼女のものだった窓に近寄る。彼女はこの窓辺に座り、外の世界で進行する人生を眺めていた。エーヴェルトはその傍らに座って、彼女はほんとうのところ、いったいなにを見ようとしているのだろうと考えていた。
「手放すことです。前に進んでください。こんな習慣はやめて」
「あいつに会いたいんだ」
「もう、ここであなたにお会いしたくはありません」
スウェーデンの潜入捜査員には、女性名のコードネームがつけられる。
コードネーム、パウラは、何故潜入捜査員という困難な仕事に執着するのか。
妻とふたりの可愛い幼子がいるのに。
月、1万クローネ(15万円~18万円程か)の報酬で。
"役を演じ切れ"。結局、それがすべてだ。力を誇示し、侮れない相手だと思わせること。手に入れたものは、けっして手放さないこと。"役を演じきるか、死ぬか、ふたつにひとつだ"
うつろな日々。思い出すことはできるが、なにも感じない。あのころ大切だと思っていたこと、大きく、揺るぎなく見えたものが、実はなんの意味もないことに気づいたのは、自分を見つめ、パパ、と呼んでくれる存在が現れたあとのことだった。
人が、絶対に超えないと自ら誓った境界線を、超えてしまったとき。
あの人は、いったい何者になるのだろう?
今年読んだミステリーのなかでは、最高に面白い一冊でした。
『 三秒間の死角(上)/アンデシュ・ルースルンド&ベリエ・ヘルストレム
/ヘレンハルメ美穂訳/角川文庫 』
■三秒間の死角(下) 2016.12.24
長い人生のなかで、もし一人でもこんな出会いがあったなら、人生はなんと豊になることだろうか。
もし自分に子供がいたら、まさに彼女のようだったにちがいない、と思う。
夜の静寂に詩的文章が流れる出る、登場人物達のさまざまな生き様が綴られている。
長いあいだ、家族の寝室だった部屋の窓。彼はいま、そこにひとりで暮らしている。いろいろなものを捨ててきた。捨ててはいけないものを捨ててきた。やり直したいと思ったところで、手遅れのこともある。
風変わりなところは、風変わりなところとして放っておくのが、波風が立たなくていちばんいい。自分はそういったふうがわりなところのない、退屈な人間だと自覚している。
ほんとうになにかが変わったのかもしれない。自分たちはもしかするとこれから、互いの存在をほんの少し耐えられるようになるのかもしれない。
傍役ではあるが、アスプソース刑務所の看守長マルティン・ヤコブソンが、ぼくにはなんとも魅力的な男に思えた。
生き抜くとは、自分の仕事をしっかりと勤め、家族を養い、いつしか渋い魅力的な男に成長すること。
『制裁』、『ボックス21』を読みたいと思い、アマゾンで古本を調べたが、文庫で\2000-以上もした。あきらめた。読みたかったのになあ。
『 三秒間の死角(下)/アンデシュ・ルースルンド&ベリエ・ヘルストレム
/ヘレンハルメ美穂訳/角川文庫 』
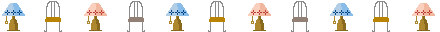
■象牙色の嘲笑 新訳版 2016.12.24
ほんとにおかしいのはね
愛している相手は絶対にこっちを愛してくれないってこと。
こっちを愛してくれる人、そういう人たちはこっちが愛せない。
長い人生のなかで、いやというほど見聞きしてきましたよね、あるいは体験した? この真実。
ここに、未練が加わると、もう大変、地獄ですね。
身もこころも、ぼろぼろだよ。
「訳者(片割れ)によるあとがき/松下祥子」
本書が出版された一九五二年といえば、ミッキー・スピレインが超ベストセラー作家として君臨していたころだ。
マクドナルドの伝記でトム・ノーランはこの時代の出版状況に触れ、スピレインの荒っぽい私立探偵小説が何百万部と売れまくっていて、ハメット=チャンドラー系の洗練された作品を買うような読者の多くが怖気づいて書店に寄りつかなくなった、と書いている。
出版社から『象牙の嘲笑』にはもっとアクション場面を加えたほうがいいと指摘され、修正を試みたこともあったが、最終的にはマクドナルドが説得して、出版社はバイオレンスはスピレインに任せ、マクドナルド本はもっと文学のわかる読者に売っていくと決めたという。
マクドナルドは「(彼を創造したとき)私はアーチャーそのものではなかったが、アーチャーは私だった」と「ボヴァリー夫人は私だ」と言ったフローベルにならった表現をしている。
あとがきを読む楽しさは、このような説明が読めることです。
「やれやれ、自分の人生だもの、すべてを含めて生きていくしかないわね。さてと、時間を無駄にしているわ。私が言うとおりにやってくださるの、それ以上でもそれ以下でもなく?」
街の上流地区から脱走してきた数人は、酒にいつもの自分を溺れさせて、別人に生まれ変わる
なにをするときでも優しく、ほとんど後悔するような仕草で、行動とはすなわち危険なギャンブルだとでも思っているようだった。
このような詩的な文章を作品中の随所で拾うことが出来ます。
『 象牙色の嘲笑 新訳版/ロス・マクドナルド
小鷹信光・松下祥子訳/ハヤカワ・ミステリ文庫 』

























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます