
東京国立近代美術館フィルムセンターのアーカイブ活動において、映画フィルムとならんで重要な位置を占めるのが、ポスター・スチル写真・シナリオ・関連文献など映画関連資料の収集・保存事業。
無声映画時代後期のソビエト連邦で制作され、ロシア・ソビエト文化研究家・翻訳家の袋一平によって日本にもたらされたソビエト映画の140点にわたるポスターコレクション全体を一挙にまとめて紹介。
ソビエト無声映画といってもこっちは「戦艦ポチョムキン」さえ観たことないんだから・・・
映画を良く観るようになってから、ロシア映画(トーキー)っていうのはなかなか面白いという事を感じているので歴史的な無声作品は機会があったら観ておきたいね。
京橋 東京国立近代美術館フィルムセンター展示室
第1期2009年1月8日~2月1日
第2期2009年2月3日~3月1日
第3期2009年3月3日~3月29日
1920から1930年代の映画ポスター
この頃はゲイジュツ方面のロシア・アヴァンギャルド、ロシア構成主義なんてのと相まって新しい映画芸術様式を開拓して行ったんだと。
ロシア・アヴァンギャルド展などという展覧会も多く開催されているようだけど、映画ポスター展という切り口で見ていくとロシア・アヴァンギャルドに捉われないでまた一興なんだと。
確かに大きなポスターの構図は大胆なものもあり、文字表現なども面白い(これはアルファベットと異なる独特のロシア文字にもよります)また、劣化したポスターが味わい深い。
展示にはその映画がどんな映画であるかの記載が無いところが残念。
ポスターから想像して、興味をそそられるものを以下に
「トルジュクから来た仕立て屋」1925年
「帽子箱を持った少女」1927年
「十月」1927年
「農奴の翼」1926年
「渦巻」1927年
「スヴェニゴーラ」1928年
「レース織り」1928年
チラシにもなっている「カメラを持った男」1929年は第2期展示(2/3~)で今回は常設展で見られました。
ちょうど今、アテネフランセ文化センターで「フセヴォロド・ブドフキン映画祭」をやっておりますが・・・
チラシから興味を感じるのは「ポリシェヴェキの国におけるウエスト氏の異常な冒険」1924年、「チェス狂」1925年、ポスター展示もあった「母」1926年、「聖ペテルブルクの最後」1927年・・・・これはスケジュール的に無理そうです。
フィルムセンター大ホールでの上映映画半券を持っていると100円です。次の上映までの暇つぶしに最適。
以下Wikipediaから
「ロシア・アヴァンギャルドとは、19世紀末以来とりわけ1910年代から、ソビエト連邦誕生時を経て1930年代初頭までの、ロシア帝国・ソビエト連邦における各芸術運動の総称である。」
「ロシア構成主義とは、キュビスムやシュプレマティスムの影響を受け、1910年代半ばにはじまった、ソ連における芸術運動。絵画、彫刻、建築、写真等、多岐にわたる。1917年のロシア革命のもと、新しい社会主義国家の建設への動きと連動して大きく展開した。
その特徴は、抽象性(非対象性・幾何学的形態)、革新性、象徴性等である。平面作品にとどまらず、立体的な作品が多いことも、特徴の1つ。」
もっと詳しく
ポスターのユートピア~ロシア構成主義のグラフィックデザイン byマガジンひとり

無声映画時代後期のソビエト連邦で制作され、ロシア・ソビエト文化研究家・翻訳家の袋一平によって日本にもたらされたソビエト映画の140点にわたるポスターコレクション全体を一挙にまとめて紹介。
ソビエト無声映画といってもこっちは「戦艦ポチョムキン」さえ観たことないんだから・・・

映画を良く観るようになってから、ロシア映画(トーキー)っていうのはなかなか面白いという事を感じているので歴史的な無声作品は機会があったら観ておきたいね。

京橋 東京国立近代美術館フィルムセンター展示室
第1期2009年1月8日~2月1日
第2期2009年2月3日~3月1日
第3期2009年3月3日~3月29日
1920から1930年代の映画ポスター
この頃はゲイジュツ方面のロシア・アヴァンギャルド、ロシア構成主義なんてのと相まって新しい映画芸術様式を開拓して行ったんだと。
ロシア・アヴァンギャルド展などという展覧会も多く開催されているようだけど、映画ポスター展という切り口で見ていくとロシア・アヴァンギャルドに捉われないでまた一興なんだと。
確かに大きなポスターの構図は大胆なものもあり、文字表現なども面白い(これはアルファベットと異なる独特のロシア文字にもよります)また、劣化したポスターが味わい深い。

展示にはその映画がどんな映画であるかの記載が無いところが残念。
ポスターから想像して、興味をそそられるものを以下に
「トルジュクから来た仕立て屋」1925年
「帽子箱を持った少女」1927年
「十月」1927年
「農奴の翼」1926年
「渦巻」1927年
「スヴェニゴーラ」1928年
「レース織り」1928年
チラシにもなっている「カメラを持った男」1929年は第2期展示(2/3~)で今回は常設展で見られました。
ちょうど今、アテネフランセ文化センターで「フセヴォロド・ブドフキン映画祭」をやっておりますが・・・
チラシから興味を感じるのは「ポリシェヴェキの国におけるウエスト氏の異常な冒険」1924年、「チェス狂」1925年、ポスター展示もあった「母」1926年、「聖ペテルブルクの最後」1927年・・・・これはスケジュール的に無理そうです。

フィルムセンター大ホールでの上映映画半券を持っていると100円です。次の上映までの暇つぶしに最適。

以下Wikipediaから
「ロシア・アヴァンギャルドとは、19世紀末以来とりわけ1910年代から、ソビエト連邦誕生時を経て1930年代初頭までの、ロシア帝国・ソビエト連邦における各芸術運動の総称である。」
「ロシア構成主義とは、キュビスムやシュプレマティスムの影響を受け、1910年代半ばにはじまった、ソ連における芸術運動。絵画、彫刻、建築、写真等、多岐にわたる。1917年のロシア革命のもと、新しい社会主義国家の建設への動きと連動して大きく展開した。
その特徴は、抽象性(非対象性・幾何学的形態)、革新性、象徴性等である。平面作品にとどまらず、立体的な作品が多いことも、特徴の1つ。」
もっと詳しく
ポスターのユートピア~ロシア構成主義のグラフィックデザイン byマガジンひとり





















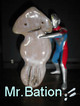






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます