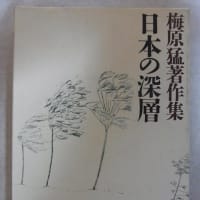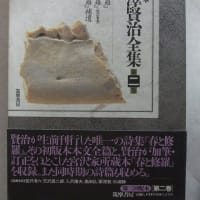『小学館版 日本の歴史 第8巻』(以下同じ)
『小学館版 日本の歴史 第8巻』(以下同じ)

『岩波講座 能・狂言 Ⅲ』 「観阿弥の能」
“猿楽能の開拓者観阿弥清次の生涯はほぼ『太平記』の時代と重なる。鎌倉幕府が滅んだ一三三三年、当時奈良盆地を中心に活動していた山田猿楽美濃大夫の養子の三男として生れた観阿弥は、通称を三郎、芸名を観世という。長兄に宝生(ほうしょう)、次兄に生市(しょういち)がいた。観阿弥は、多武峰(とうのみね)神社・妙楽寺や春日神社・興福寺の神事猿楽や法会に勤仕した大和猿楽四座のひとつ結崎(ゆうざき)座に所属し〔他は外山(とび)・円満井(えんまんい)・坂戸(さかど)の三座〕、若くして看板役者の地位にあったようである。猿楽の座は元来、神事猿楽等に「式三番(翁)」を担当した長(おさ)〔長老〕を中心とする、いわゆる「翁グループ」を基礎として発展してきたようであるが、一方に、しだいに人気を集めつつあった猿楽の能を演ずる、いわゆる「乱舞(らつぷ)グループ」も形成されてきていて、観阿弥はその新しい「乱舞グループ」を率いる大夫であった。棟梁の為手(して)ともいう。さきに看板役者といったのは、このことである。大夫は一座のスターであり、当時はどの演目でも主役(シテ)を勤めるのを常とし、芸域の広さが要求された。田舎遠国はもちろん、何よりも京都で名をあげなければならない。”




叔父唄う「上海ブルース」路地に咲くアプレゲールの哀しき花よ
福島泰樹 『2013.8.17 東京新聞』