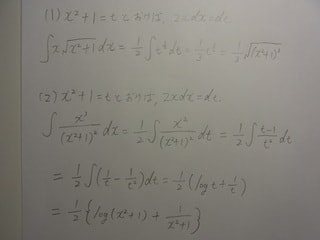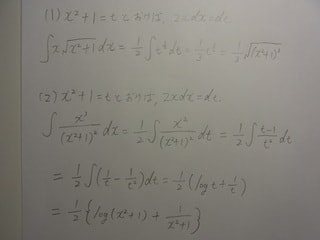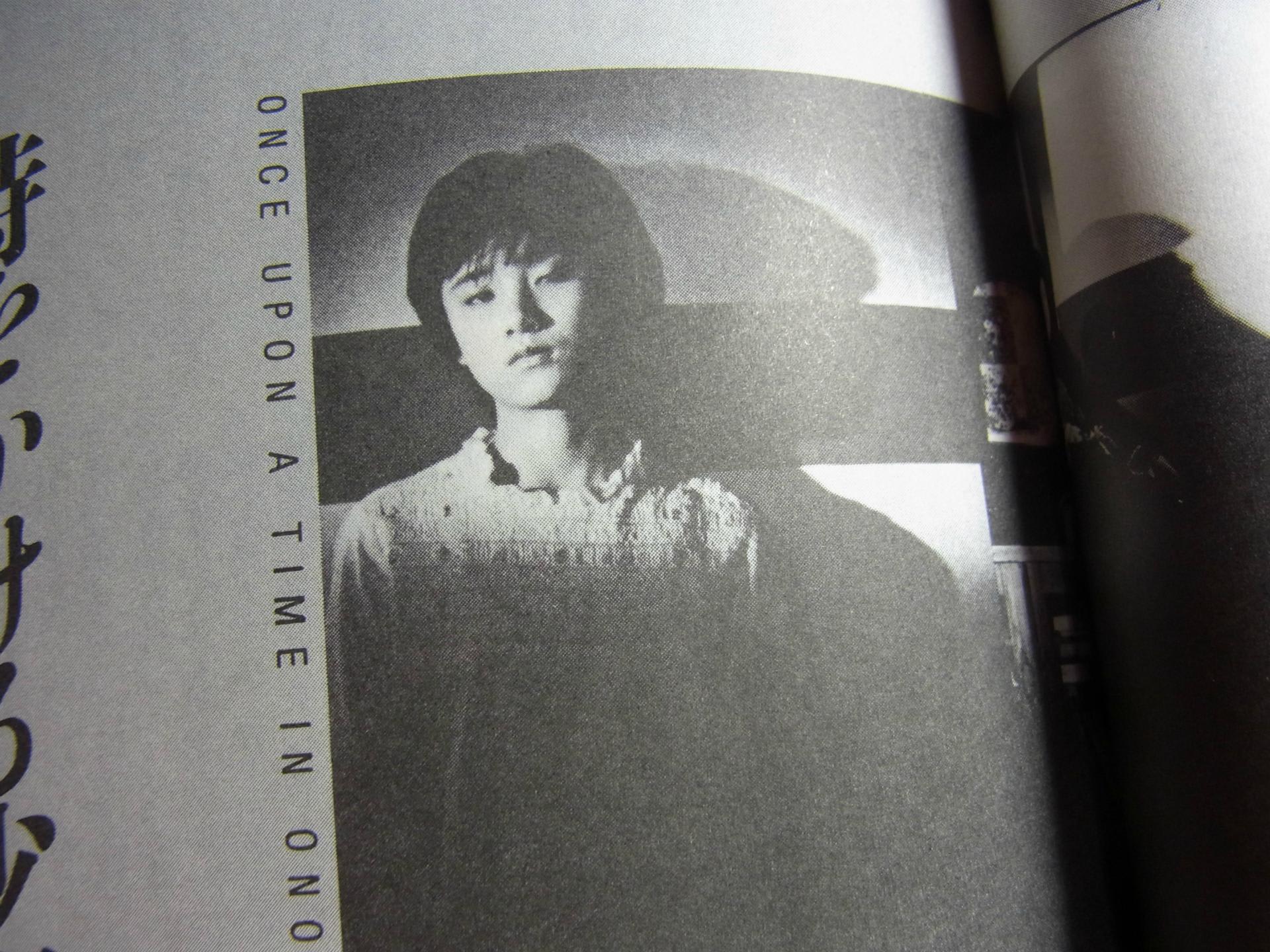音楽を学んだ人や、演奏する人たちと、機会があると話しの流れで、「12音のなかで、あなたが一番好きな音は何か?」と私は聞く。
この質問は意外なようで、明確に音名を答える人はいなかった。しかしサンプル数が少なく、一般化はできないので、これからも調査を続けたい(笑)。
そのなかで、「好きな音…、というより、音の関係性が重要だから…」という答えがあった。
これは「平均律」の考え方である。
A
A♯=B♭
B
C
C♯=D♭
D
D♯=E♭
E
F
F♯=G♭
G
G♯=A♭
これが12音である。
それを、ドレミファ順に並べ替える。
C
C♯=D♭
D
D♯=E♭
E
F
F♯=G♭
G
G♯=A♭
A
A♯=B♭
B
和名だとこうなる。
ハ
嬰ハ=変ニ
ニ
嬰ニ=変ホ
ホ
ヘ
嬰ヘ=変ト
ト
嬰ト=変イ
イ
嬰イ=変ロ
ロ
音階には長音階と短音階があるから、12音それぞれの音を主音とすると、24種類できる。
J.S.バッハ(1685-1750)が仕事をした頃、鍵盤楽器に「平均律」で調律をする考え方がだいたい完成した。そしてこの転調が自由自在にできる調律法は、直接現在につながっている。
この24種類のすべてに、「プレリュード」と「フーガ」を書いた、理論と実践に記録が、全48曲の『平均律クラヴィーア曲集』である。『第2集』も作ったので、計96曲。
バッハの曲は、弾く人が弾くと、精神が深いところまで安らいでいくのを感じることができる。
ところで、現在、わたしたちがカラオケ店へ行くと、原曲の歌が自分の声域よりも高かったり低かったりする場合、機械の操作で簡単に半音ずつ上下できる便利な機能が付いている。これも「平均律」の実践である。しかしそうすると、原曲とは不思議に印象が違い、場合によっては間の抜けたような歌になる事もある。これは決して、各自の歌唱力のせいばかりではない。「調」には性格があり、ひいては「主音」にも性格があり、性格があるなら好き嫌いもあるだろう、というのが、冒頭の質問の意味である。
しかし、論を急いではいけない。ピタゴラスから始めよう(笑)。
ピタゴラス(前570頃)は、モノコルド(一弦琴)をはじき、「2つの音の振動数の比が単純であればあるほど音がよく調和することに目をつけ、モノコルドの弦を 2:1 に分割する作業を続けた。
まず、開放弦(仮にドとしよう)をはじいた後で、弦を 2:1 に分け、長い方をはじくと、開放弦の5度上の音が出る(ソ)。次に、その長いほうをまた 2:1 に分けてはじくと、ソの5度上の音(レ)が出る。この作業を繰り返し、オクターブを高いほうに外れた音をオクターブ内に戻すと、ドレミファソラシの音階ができる。」
『事典世界音楽の本』 徳丸吉彦・高橋悠治・北中正和・渡辺裕 編 (岩波書店)
「さて、ピタゴラス音律の問題点は2つあって、ひとつは、半音が2種類できること、もうひとつは、音程によっては振動数に比が大きくなってあまりよい響きが得られないことである。」
『同上』
問題点の前者は、上の12音の表で、=で結んだ音は、歴史的にはイコールではなく、実に13世紀ぐらいまでは問題にならなかったので、ほうっておかれた。
問題点の後者は、ピタゴラス直後からいくつかの改良が重ねられ、そのひとつの成果が、「純正律音階」だ。
「純正律に貢献したとされる人物はアルキタス(紀元前4世紀ごろ)だが、彼は、ピタゴラス音律だと81/64という大きな比になってしまうドとミ(長3度)の振動数比を、近似値の5/4に読み替え、各音の振動数比が単純な整数比になるよう工夫した。純正律は、旋律面でも協和面でもきわめて美しい響きをもっているので、楽器の性能が許せばたいへん好ましい調律法であると言える。」
『同上』
私もこの「純正律」に調律されたピアノの音を聴いた事があるが、それはほんとうに、譬えようもない美しさだった。これに比べると、現代の「平均律」は、雑音騒音の類だと思えてしまう(笑)。まあ、それは言い過ぎであり、歴史には理由がある。その後幾多の問題を克服しながら、「中全音律」→「改良版中全音律」→「十二平均律」となる。しかし、高松晃子さんのこの記事の後半が、いまひとつ納得できないところがあったので、もう少し調べてみたい。
ただ中世以前の西洋、そこで歌い、奏でられていた美しい響きの音、その想像に魅惑される。
さあ、ここで「Confession」。私のいちばん好きな音は「B」、ドレミファソラシの「シ」である。
「この曲(『平均律クラヴィーア曲集 第1巻 ロ短調のプレリュード』)、実に、まさに、完璧に、ロ短調的なのだ。その感じをどうコトバで言っていいかわからぬのだが、同じ調性の有名な曲を挙げてみればある程度お分かりいただけるかもしれない。 同じくバッハの《管弦楽組曲第2番》や《ロ短調ミサ》。シューベルト《未完成交響曲》。ショパン《ピアノ・ソナタ第3番》や《スケルツォ第1番》。リスト《ピアノ・ソナタ》。ブラームス《クラリネット五重奏曲》。チャイコフスキー《悲愴交響曲》。ドヴォルザーク《チェロ協奏曲》……。 何か共通の感性を想いませんか。 繊細さ、淡い哀しさ、艶やかだがひそやかなロマンティシズム……。僕だけかもしれない。告白すると僕は子供の頃から、ピアノを弾いていてHつまりロの音だけなぜ他の音と音質が違うのだろうと思っていたから。これはピアノ以外の音楽を聴くようになっても変わらなかった。」
『バッハの音符たち』 池辺晋一郎
作曲家池辺氏のこの記述に、バッハの《フルートとオブリガートのチェンバロのためのソナタ BWV1030》を加えて、私も同じ想いをここに告白する(笑)。
H(ハー)はドイツ音名で、=B=ロ である。
ここで先日写譜した『草の想い』を見てほしい。
調性はホ短調であるから、属音は5度上のロ。つまり、あの淡くひそやかに秘めた哀しみの「B」。
主音のEを赤で、属音のBを青で示した。
たいせつな言葉が、なぜ、こんなにも響き、伝わってくるのか、その理由がわかると思う。
むかし
ひとのこころに
ことばひとつ
うまれて
つたえてねこのこ
えを
くさのおもい
かぜに
このてかざして
みえないもり
たずねて
あなたのうたをさ
がして
かくれん
ぼ
わた
しのあしおとをきい
てね
た
しかなまゆをみてね
そし
ていまは
いわ
ない
で
かぜに
このてかざして
みえないもり
たずねて
あなたのうたをさ
がして
かくれんぼ
ひとり
すなにねむれば
ふたりつゆに
ゆめみて
よろこびとかなし
みの
はなの
うた
げ
この曲には2番がある。
時は移ろいゆきて
ものはみな失われ
朧に浮かぶ影は
ひとの想い
いまは遠い心に
寂しく憧れ来て
あなたの夢にはぐれて
かくれんぼ
わたしの唄声を聴いてね
遥かな笑顔見てね
そしていまは
抱きしめて
時は移ろいゆきて
ものはみな失われ
朧に浮かぶ影は
草の想い
ひとり砂に生れて
ふたり露に暮らせば
よろこびとかなしみの
花の形見
『草の想い』 大林宣彦 詞 / 久石譲 曲
ここまできたら、もうひとつ「Confession」してしまおう。
私は原田知世が好きである(笑)。
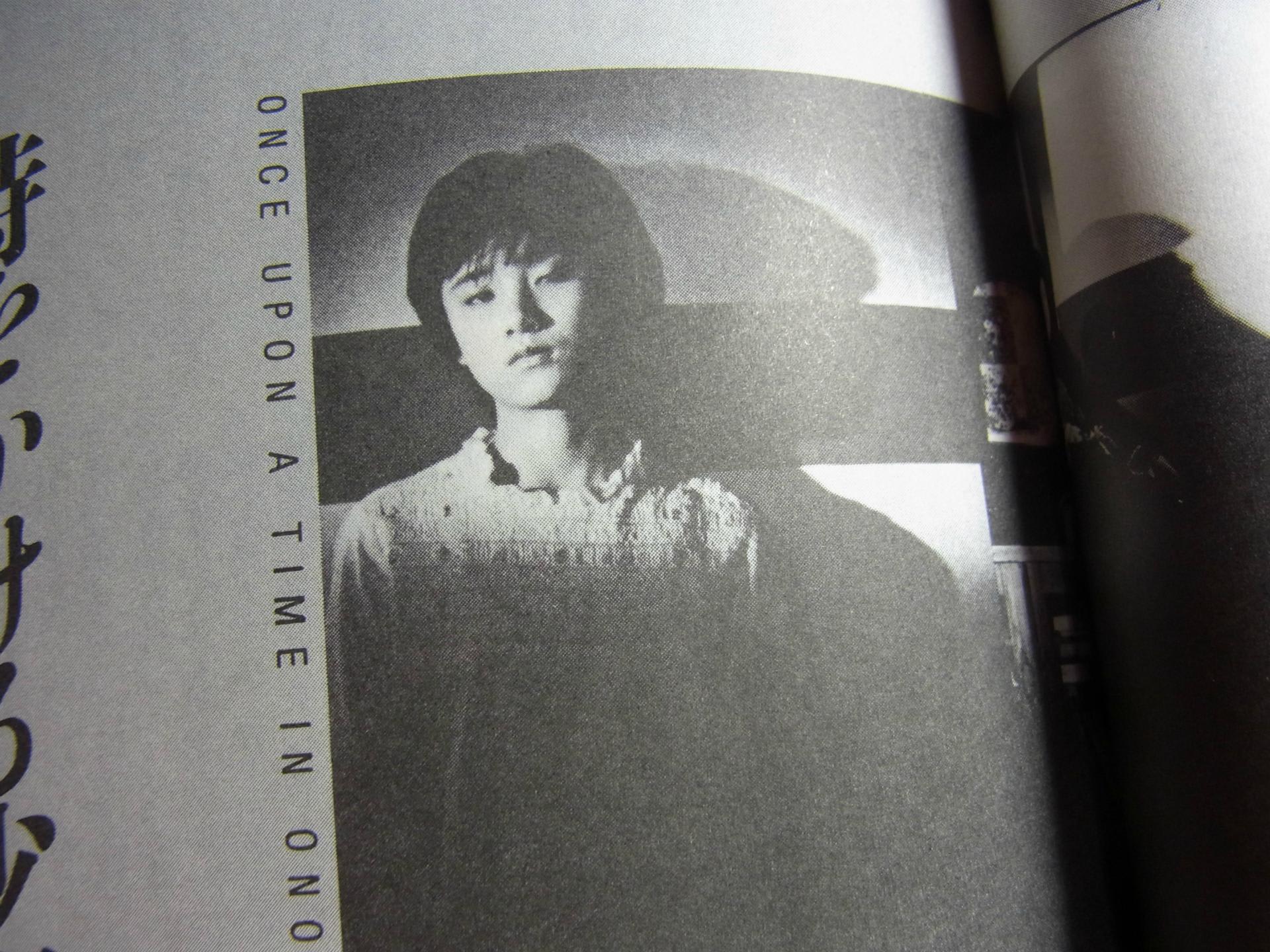
『ワンス・アポン・ア・タイム・イン尾道』 大林宣彦
次回は冷静に論述する(笑)。