みなさん、こんにちは!英語の勉強は進んでいますか?
気が付けば、今年も椿の季節がやってきました。写真は英会話教室English and Beyond の入口にあるお花です。毎年この季節にきれいな花を咲かせて楽しませてくれているのですが、気のせいか、今年はいつもより沢山咲いている気がします。
さて、今回は、当ブログでお馴染み Reader's Digest のQuotes(クオーツ:引用)コーナーから、コメディアンのW.C. Fieldさんが残した有名な言葉をご紹介します♪
それでは、さっそく、引用から♪
I always cook with wine. Sometimes I even add it to the food. -W.C. Fields-
こちら、どんなことを伝えている文章でしょうか。
私は、これを読んで、思わず、「そっちかー! 」となりました。
」となりました。
その理由をお伝えする前に、まずは、出だしの、I always cook with wine. に関して、
cook with ~ のwith には、【道具】や【食材】が後に続いて「~を使って」という意味になります。
ここでは、cook with wine とありますので、「ワインを使って料理する」という意味になるのかな?と思いながら読み進めていきます。ですが、この文章には続きがあります。そのため、英文読解の鉄則!英語の意味のカギを握っている文脈のことを忘れずに、"こんな意味かな~"とふわっと思いながら、続きに目をやります。
すると、続いて見えてくるのが、Sometimes I even add it to the food. です。addは「加える」という意味が基本です。
え??ということは. . . ?!
この引用の特徴は、後半の文章で、食事にワインを入れることが特筆されていることです。
前の文章のcook with wineに登場するwith を、ワインを調味料として使うことだなと決めて読んでしまうと、前半も後半も料理にワインを入れると言っていることになります。
しかも、そうすると、even(意味:さえ)があることが妙なことになります。「時々それ(ワイン)を料理に入れさえもするんだよ」と言っている、ということは、前半の文章は、”料理に使う”という意味じゃないのかな?と受け取るほうが自然です。
ここで思い出していただきたいのが、withが持っている忘れてはいけない大切な役割、【~と一緒に、~を持って、~しながら】という様態や付帯状況を示す意味です。
実は、前半の文章に登場するwithは、今回は「ワインを飲みながら」という意味で使われていました。
そのことを念頭に置きつつ、再度全文をご覧ください♪
I always cook with wine. Sometimes I even add it to the food. -W.C. Fields-
(いつもワインを飲みながら料理するんだ。時々、それ(ワインを)料理に入れさえもするんだ。)
通常、cook with (食材・ドリンク)と並んでいたら、それを使って料理すると理解するのが一般的です。ですので、続きの文を読んだとき、思わず「そっちかー!」と突っ込んでしまいそうになりました。
さすが、有名なコメディアンの方が残した言葉とあって、文の流れで、後半の文章がオチになっているのがすごく面白いです
☆今回のお勧め表現☆
・cook with ~ ≒ make with ~ の基本の表現
【~を使って料理する(作る)、~で料理する(作る)】
・I cook chicken with lemon juice. (lemon juice: レモン汁)
・I cook Chinese food with pork.
・I cook rice with chestnuts. (chestnuts :栗 -複数形- 読み方:チェスナッツ)
・I cook pork with ginger. (ginger:ショウガ)
・I cook cucumbers with salt. (cucumber : きゅうり)
・I make gyoza with Chinese cabbage and minced pork. (Chinese cabbage :白菜、minced pork :豚ミンチ )
・I make miso soup with a lot of vegetables.
・I make fried rice with eggs and green onions. (green onions :青ネギ、spring onions とも言います)
などなど色々使えます。
※cookのほうは、食材はもちろんのこと、味付け(調味料)に何を使うかなど、make のほうは、具体的な料理や食べ物を何で作るかと言う時に、より使えます。

ジョークにもstay home的なネタが入ってきました。今回の引用は、少し前の号からご紹介しましたが、また最新号からも色々ご紹介できたらと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーー
英会話スクール English and Beyond のホームページは、こちらEnglish and Beyond
そろそろ、上達する英会話、始めませんか? Reader's Digest の記事を使ったレッスンも行っています。スカイプレッスンも受付中♪
気が付けば、今年も椿の季節がやってきました。写真は英会話教室English and Beyond の入口にあるお花です。毎年この季節にきれいな花を咲かせて楽しませてくれているのですが、気のせいか、今年はいつもより沢山咲いている気がします。
さて、今回は、当ブログでお馴染み Reader's Digest のQuotes(クオーツ:引用)コーナーから、コメディアンのW.C. Fieldさんが残した有名な言葉をご紹介します♪
それでは、さっそく、引用から♪
I always cook with wine. Sometimes I even add it to the food. -W.C. Fields-
こちら、どんなことを伝えている文章でしょうか。
私は、これを読んで、思わず、「そっちかー!
 」となりました。
」となりました。その理由をお伝えする前に、まずは、出だしの、I always cook with wine. に関して、
cook with ~ のwith には、【道具】や【食材】が後に続いて「~を使って」という意味になります。
ここでは、cook with wine とありますので、「ワインを使って料理する」という意味になるのかな?と思いながら読み進めていきます。ですが、この文章には続きがあります。そのため、英文読解の鉄則!英語の意味のカギを握っている文脈のことを忘れずに、"こんな意味かな~"とふわっと思いながら、続きに目をやります。
すると、続いて見えてくるのが、Sometimes I even add it to the food. です。addは「加える」という意味が基本です。
え??ということは. . . ?!
この引用の特徴は、後半の文章で、食事にワインを入れることが特筆されていることです。
前の文章のcook with wineに登場するwith を、ワインを調味料として使うことだなと決めて読んでしまうと、前半も後半も料理にワインを入れると言っていることになります。
しかも、そうすると、even(意味:さえ)があることが妙なことになります。「時々それ(ワイン)を料理に入れさえもするんだよ」と言っている、ということは、前半の文章は、”料理に使う”という意味じゃないのかな?と受け取るほうが自然です。
ここで思い出していただきたいのが、withが持っている忘れてはいけない大切な役割、【~と一緒に、~を持って、~しながら】という様態や付帯状況を示す意味です。
実は、前半の文章に登場するwithは、今回は「ワインを飲みながら」という意味で使われていました。
そのことを念頭に置きつつ、再度全文をご覧ください♪
I always cook with wine. Sometimes I even add it to the food. -W.C. Fields-
(いつもワインを飲みながら料理するんだ。時々、それ(ワインを)料理に入れさえもするんだ。)
通常、cook with (食材・ドリンク)と並んでいたら、それを使って料理すると理解するのが一般的です。ですので、続きの文を読んだとき、思わず「そっちかー!」と突っ込んでしまいそうになりました。
さすが、有名なコメディアンの方が残した言葉とあって、文の流れで、後半の文章がオチになっているのがすごく面白いです

☆今回のお勧め表現☆
・cook with ~ ≒ make with ~ の基本の表現
【~を使って料理する(作る)、~で料理する(作る)】
・I cook chicken with lemon juice. (lemon juice: レモン汁)
・I cook Chinese food with pork.
・I cook rice with chestnuts. (chestnuts :栗 -複数形- 読み方:チェスナッツ)
・I cook pork with ginger. (ginger:ショウガ)
・I cook cucumbers with salt. (cucumber : きゅうり)
・I make gyoza with Chinese cabbage and minced pork. (Chinese cabbage :白菜、minced pork :豚ミンチ )
・I make miso soup with a lot of vegetables.
・I make fried rice with eggs and green onions. (green onions :青ネギ、spring onions とも言います)
などなど色々使えます。
※cookのほうは、食材はもちろんのこと、味付け(調味料)に何を使うかなど、make のほうは、具体的な料理や食べ物を何で作るかと言う時に、より使えます。

ジョークにもstay home的なネタが入ってきました。今回の引用は、少し前の号からご紹介しましたが、また最新号からも色々ご紹介できたらと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーー
英会話スクール English and Beyond のホームページは、こちらEnglish and Beyond
そろそろ、上達する英会話、始めませんか? Reader's Digest の記事を使ったレッスンも行っています。スカイプレッスンも受付中♪











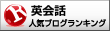


 と思ったのではないかな?と思います。
と思ったのではないかな?と思います。










