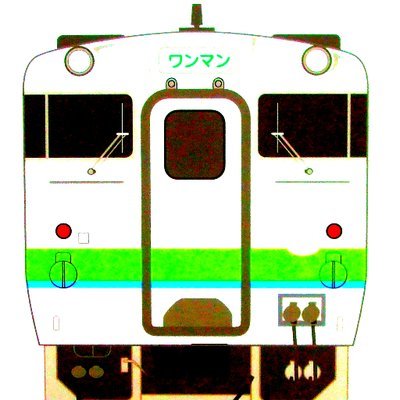株式会社の仕組みを知らない人は意外と多い。
株主が資金(資本金)を出資し、経営は選任した取締役が行う。
取締役の業務は、同じく選任した監査役によって監視される。
最近は執行役員という役職を設ける法人も増えているが、JR北海道は一般的な取締役のみを選任している。
JR北海道の取締役は誰が選んだのか。上記のとおり株主である政府が選任したのだ。
石井国土交通相は、現在のJR北海道の経営危機について、歴代のJR北海道の経営陣を批判しているが、選任したのは、鉄道建設・運輸施設整備支援機構すなわち日本国政府が自ら選任したのであるから、任命責任は免れないのではないか。ブーメランだ
北海道、九州、四国については分割民営化時において、赤字経営が予想されたので、経営安定基金を各社に預け、その運用益で損失を補てんするというスキームを取り入れた。
時、まさにバブルの真最中で当初は運用益も予定通りに上がり、損失を埋めることができた。ところがバブル崩壊から続く景気低迷で金利は下がるばかり、運用益はどんどん減少していった。
ここで聞かれるのは、「まさか、こんなに低金利になるとは予想できなかった」という声だ。これは責任逃れだろう。
特に経済関係誌がJR北海道の問題を論するときに決まり文句にしている。
低金利になってきた段階で、基金の積み増し等、政府は何らかの手を打つことができたはずだ。
JR北海道も、座して眺めていたわけではない。関連会社を立ち上げ副業に打ち込み、全収益に対する割合も50%近くに上る。
さらに、経費削減にも取り組み、鉄道設備の保守費用の削減まで行ってしまった。自死された坂本元社長は鉄道を疎かにしたことはないと語っておられたが、実態、そして結果は安全軽視と言われるような状態になっていた。
今回の問題で、良く聞くのは沿線住民が鉄道を利用しないという言葉だが、ある意味当たってはいる。しかし、閑散路線は利用しずらいダイヤであるという事も追い打ちをかけている。
10日の新聞によると、与党自民党がJR北についてのPTを立ち上げたようだ。夏ごろには中間報告とのことだが、基本的にはJRと自治体の協議次第という。実に切迫感のないことではないか。
基本的に、政府は支援は渋っており、特に官僚出身の石井国交大臣は消極的で、経営陣を批判するばかりだ。
麻生財務大臣のリップサービス?はともかく、企業の経営など全く知らない方なので仕方がないかな