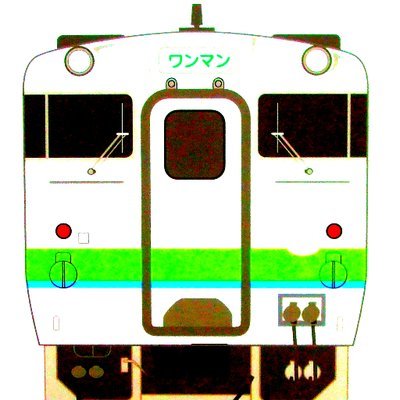JR北海道の「当社単独では維持することが困難な線区」の発表に伴って道が設置した「JR北海道の鉄道事業見直しに対応する鉄道ネットワークワーキングチーム(WT)の検討結果の概要が報道された。
WTの報告書は、議論の回数も少ない上に、交通ビジョンを検討する委員会の補完的な位置づけなので、あくまで今後の論議の叩き台を提供する内容となっている。
具体的な路線名を挙げることはせず、北海道の鉄道路線を、各路線が果たすべき役割によって6つに区分した考え方を提示している。
早期に決着させてしまいたい高橋知事の意に沿った内容で道側が作成した原案を確認したに過ぎないのではないかと思わせる内容だ。
鉄道は票にならないし、目立ったリーダーシップを取ろうとしない高橋知事。
人件費の削減を、道内の他企業の平均より給与水準が低いJRに求め、指摘されて後日取り消したり、JR北海道に対する関心のなさが目立つ知事ならではだ。
残念ながら、高橋知事によって北海道の開拓における先人の成果は捨て去られてしまうのであろう。
これは多選の弊害であることは間違いない。
WTは昨年11月に設置され、有識者や首長らが議論を続け、1月30日の会合で最終的な考えをまとめ、2月5日に高橋知事に答申し、同15日の道の地域公共交通検討会議に於いて報告書を提出する。
その後、見直し対象地域で、沿線市町村とJRなどの協議が本格化する。複数の自治体の思惑が複雑に絡んで、意見調整はかなり難航するだろう。
WTは各路線が果たすべき役割を以下のように区分した。
1札幌と中核都市等を結ぶ(重点的に存続を検討するべき)
石北本線を指しているらしい
2国境周辺地域や北方領土隣接地域の振興
宗谷線、花咲線(根室線)かと思われる
3広域観光
富良野、釧網線であろうが、地元の負担は免れないか。
4広域物流
室蘭本線の東線かと思われる
5地域の生活路線
採算の厳しい路線が多く、バス等への転換は免れないであろう
札沼線非電化区間、留萌線、災害で不通の根室線一部、日高線
6札幌近郊の都市圏輸送
収益の源泉として、一層の充実と拡充が望まれる
JRが主張する収支面による存廃基準とは、異なる基準としたい考えだ。。ただし報告書ではの路線がどれに当てはまるのかは明示はしていない。非常に曖昧で不完全な仕上がりとなっているのは心配されたとおりだ。
一部メディアは富良野線と釧網線は存続の順位が低いと報道をしているが憶測が先行するような報告書は期待外れだ。
路線名を明確にして、関係自治体から追及されることを嫌ったのだろう。これは高橋知事の支持なのかもしれない。八方美人知事らしい。就任当時の切れ味はすっかり影をひそめた感がある。
また、国に対して要望する支援策として、 JR貨物 からJR北海道に支払われる線路使用料の見直しや資金繰り対策を挙げている。
JRが提案した「上下分離方式」を巡っては「費用負担を自治体に求めることは現実的ではなく困難」だととしている。
さらに、民間資本などが鉄道施設を保有する形の上下分離を議論することに含みを持たせている。この場合の民間資本は北海道の経済界と自治体などによる第三セクターが考えられる。はたして出資する民間資本が現れるのかは疑問だが、富良野線などは収益を生み出す可能性があると思う・・・。
2020には資金繰りができなくなると昨年の秋ごろから、ことあるごとに公言する経営陣だが、借入金は国からの借入であり、返済には一定の猶予があるはずだし、さらなる資金援助を要請するべきかと思う。
WTの報告書では経営安定基金の積み増しの要請をすることにも言及している
JR北海道は運行が止まってしまうというようなことを言うなど、利用者の不安あおることは厳に慎んでほしい。
JR北海道は四面楚歌が如く感じているようだが、北海道の利用者は味方であり応援していることを忘れないでほしい。
今後は、沿線市町村が国や道そしてRなどのステークホルダーが地域の交通網のあり方を議論するべきだと強く訴えている。
論議は相当の困難が予想されるが、資金繰りが云々というようにJRが様々な煽動行為で揺さぶってくるだろうが、あくまで利用者の利便性を第一に議論を進めてほしいものだ。
残り1月くらいで姿を消す、キハ183によるサロベツ(稚内)