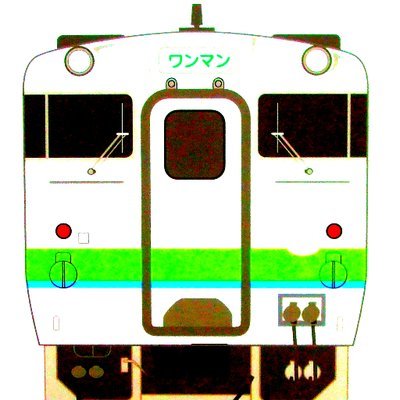先日の定例記者会見でJR北海道の島田社長は北海道の高橋知事が提案し、国に働きかけた支援策に対して、これまで自ら提案してきた上下分離方式にはこだわらずに受け入れる旨の発言をした。
これを受けて高橋知事も、翌日の会見で歓迎の意向を示した。
この動きは、先日の東京で国、道、JRの三者による協議が行われたのを受けて、支援の内容と実現性が見えてきたからだろうと思われる。
高橋知事は先月18日に上京し、石井国交相に対し鉄道運輸機構の特例業務勘定を利用するという形での支援の要請をしているが、その内容によってはこれを受け入れるという事だろう。
JR北が、独自には維持できないとする路線等を公表してから約一年。
高橋知事が積極的に動かないことに、私を含めメディアや支持者も疑念を抱いていたのだが、おそらくは国交省の鉄道局や政府関係者・政権との根回しに時間を費やしていたという事なのだろう。
まあ、そう信じたいところだが、政治家の動きはこのようなものなのだろうか。4期目ともなれば、なかなか老獪ではある(笑)
当初JR北は上下分離を提案した。欧米では、国が線路等の施設を保有する形で広く行われており、日本でも若桜鉄道などで一部行われている。
私も、期待をしたものだったが、いろいろと調べてみると、簡単には実現できないのではないかと懐疑的になってきていた。
実際、欧米諸国では各国の財政にその負担が重くのしかかり、一部の国では見直しの声も上がっている。
対象路線には過疎と財政難に苦しむ複数の自治体が関わるため、その実現は当初から困難とされた。実現するとしても国が主導しなければ、ほぼ困難であろう。
国には、上下分離に積極的ではないことは明らかであった。しかし、JR北に上下分離を言わせたのは国交省の官僚であることも明らかなのだ・・・。官僚というのは時に自己矛盾に陥る不思議な人たちだ。
また、上下分離はJR北海道の社員にとっても雇用問題にかかわる大問題である、現在のネット上ではJR北海道を擁護し、メディアと行政を批判するだけの意見が多く見受けられ、上下分離以外に方策は無いと言い切るものもある。
しかし、そこに働く社員の雇用問題に思いをはせてほしい。
私は、経営陣は上下分離は労働組合の体力を奪うという効果を期待したのではないかと、疑っている。
現在のJR北海道の社員の働き方を見聞きする限り、は労働基準法の「第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇〈第三十二条-第四十一条>及び、第五章 安全及び衛生〈第四十二条-第五十五条〉に関してはしっかりと労働条件は守られていくように感じるが、下の部分を第三セクターなどに移管され、該当する部署の社員が移籍した場合に、このような労働条件下に置かれるかどうかは心配の残るところだ。
ただ、現在の労働環境(突然にバスやホテル・販売への移籍を求められる社員がいるとか、東日本に取り込まれるのではという将来への不安)は多少は改善されるかもしれないが・・。
いずれにしても30年前の分割民営化のスキームを見直すことは自らの政策を否定することになると官僚と政権は考えているであろうから、上下分離などを積極的に取り入れるとは思えない。
結果はともあれJR九州が上場し(鉄道会社としては衰退していくだろうが)残った四国と北海道は何とか今の経営形態ままで通したいと言うのが国の本音だろう。
そこに、その意を汲んだ高橋知事からの提案があったという事か。
支援がどの程度の規模になるのか、一時的なのか恒久的なものなのか、今の段階では全くわからない。
内容によっては、JR北の態度も、今後変わっていくかもしれない。島田社長の受け入れ表明は、無条件とは思えない。
とにかく、無条件で国の支援を仰ぐのではなく、本当に将来に渡って、子子孫孫の世代まで維持できるような交通体系を構築すべく議論を交わした上で支援を仰ぐべきであり、急ぐあまりに一時しのぎのようなことになってはいけない。
さらに、鉄道路線が今のままで残すと言うのは非現実的である。設備、車両の更新と、鉄道の特性が生かせる再度の高速化への挑戦を前提にした上で、残すべき路線は残し、各地域においてはバスや乗合タクシーと融合した交通体系なども早急に構築すべきだろう。
駅を降りたらバスも何もないのでは、まさに元の木阿弥である。
残念だが、一部路線の廃止はやむを得ないと考える。
石炭の輸送のために敷設された留萌線、製紙工場のための木材輸送のために敷設された日高線、国会議員の我田引鉄によって採算無視で敷設された札沼線は産業構造の変化と他の交通機関の発達に伴って役目を終えたと言える。
根室線の富良野・落合間に関しては石勝線の完成と共に役目は終えているが富良野・幾寅間は何らかの形で残せないものだろうか。
鉄道ファンとしては残念極まりないが、今の日本の国力では鉄道を支えることは難しいことを受け入れなければならない。もう日本は経済衰退国であると言う学者もいるくらいだが、国が少子高齢化を放置してきたつけが回ってきたのだろう。
来年度初めには発表される道の総合交通政策検討会議の答申を基に議論を重ねて一定の方針を示し、国の支援を具体的に策定し、2019年度の予算要求に計上することになるだろう。
国に支援を要請するだけではなく、北海道民、特に道央圏の市民が我が事として議論を重ねなければならない。
JRの公共交通としてもメリットをもっとも教授している道央圏の市民は、地方の公共交通についても心を馳せなければならない。
以前にも書いたが、次の知事選挙に向けた政争の具にするなどという呑気なことを言っている時間は無い。