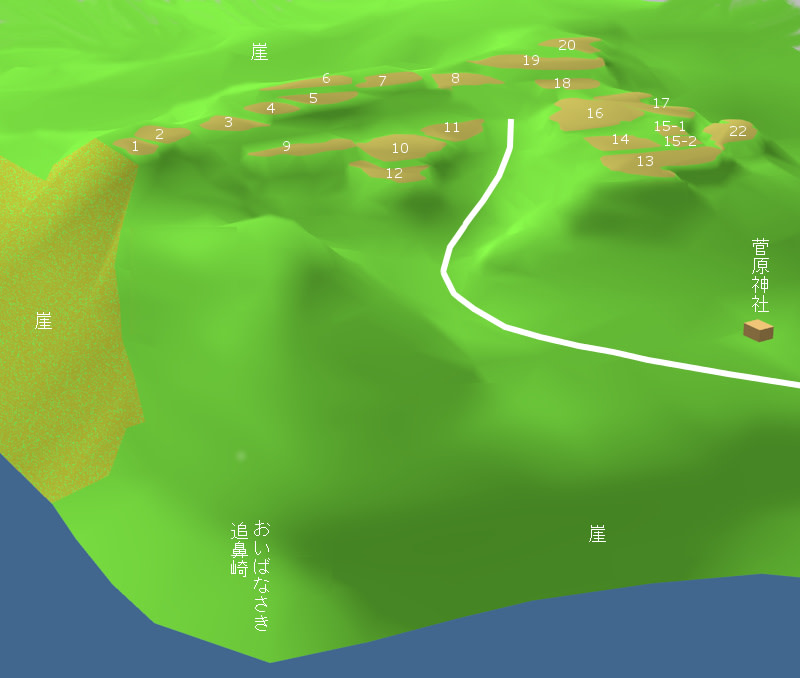2004. 3.28

2004. 3.28

2004.10.21
「細葉の椿」の傍らにある説明板
天神様の細葉の椿
菅江真澄の男鹿遊覧記に
「天満宮の新垣(しんがき)にはいって額(ぬか)づく。
実季(さねすえ)も友季(ともすえ)も、この神を朝夕に祈り敬い、
その社前に占いなどし たことだろう。
細葉の椿という古木がある。
生い茂る、細葉の椿ふとまにの、うらなみかけて、八千代経 ぬらし」
という一節を残している。
ヤブツバキの一種で、葉が細く、4月中旬頃からピンク色の花弁をつける。
長い年月の風雪に耐え、脇本城の栄枯盛衰を見守ってきたことであろう。
樹齢400年以上と推定される。
男鹿市教育委員会
この説明板には4月に咲くと書かれているが、2月19日に、
なんとなく咲いているような気がして神社へ行った。
坂道に雪が残っていたので、車ではなく、徒歩で階段を登った。
細葉のツバキを見ると、いくつかの花と大きく膨らんで
今にも咲きそうな蕾(つぼみ)がついていた。
今咲いているのは、暖冬だからか。そうではないように思える。
毎年、今ごろから咲き始めるのだが、こんな時期にツバキの花を見るために、
ここまで登って来る人などほとんどいなかっただけなのだろう。

菅原神社 2004.10.21
祭神:
■菅原道真大神(すがわらみちざねおおかみ)
■天照皇大神(あまてらすすめおおかみ)
■白山媛大神(しらやまひめおおかみ)
■保食大神(うけもちのおおかみ)
菅原神社の説明板を改変
1290年頃(正応年中)
鎌倉時代、安東氏の氏神として建てられた。
主祭神は、学問の神として有名な菅原道真公である。
京都北野天満宮の祭神をこの神社でも祀(まつ)ることにした。
当初の位置は、脇本城本丸南山上であった。
安東愛季(ちかすえ1539-1587)や実季(さねすえ1576-1659)もあがめうやまった。
1591年(天正19年)
再建。
1602年(慶長7年)
関ヶ原の戦いで豊臣方についた実季は、
常陸(茨城県)へ国替えになった。
このとき、神様もいっしょに移動しようとしたが、
神様は「この場所から動きたくない」と告げられた。
それ以後は、地元脇本村で維持管理することになった。
当神社午王獅子(ごおうじし?)が安東氏の許可のもとに春秋二度、
男鹿島中、湖東 、能代や桧山までまわった。
この獅子廻村は佐竹藩になっても旧例通り認められ 江戸中期まで続いた。
(午王獅子は厄よけのお札を配って歩いたのだろうか?)
1603年(慶長8年)
脇本城は佐竹家の命により廃城となる。
1627年(寛永4年)
佐竹義宣公参拝。
1653年(承応2年)
生鼻崎は地震により山が崩れ、佐竹藩家老真崎兵庫介が
飯村開田の祈願成就のお礼として、村人と話し合って社殿を再建した。
1804年頃(文化年中)
1804-1818年の間に佐竹義和公三度参拝。
1810年(文化7年)
地震生鼻崎は承応の地震と、この地震で大半が海中に没し形態を失ったといわれる。
菅江真澄が男鹿で遭ったのはこの地震である。
また、寒風山の地震塚はこの地震の犠牲者を供養している。
1868年(明治元年)
3月17日神仏分離令。
1982年(昭和57年)
現社殿竣工。権現造りの建築様式で氏子内外のまごころによって建てられた。
明治以前には社家(伊藤家)と山伏修験(安後坊、宝倉坊など)は
共存していたが、明治維新に修験道が廃止させられた。
山伏は仏教である。
明治以降、村内に祀(まつ)られていた
村社新明社(天照皇大神あまてらすすめおおかみ、伊勢皇大神宮)
保食神社(豊受大神とようけのおおかみ、伊勢豊受大神宮)
白山神社(白山媛大神しらやまひめのおおかみ、加賀白山比神社)
を合併し、金比羅大神も祀ることになった。
産土神(うぶすながみ)と して農業、漁業を初め諸業発展、
交通安全、縁結び、安産などを祈願する人が多い。
氏神は一族の神様であり、産土神は、その土地を守護してくれる神様であったが、
いつのまにか、氏神や産土神、鎮守神(ちんじゅがみ)の区別がなくなってしまった。
説明板で氏神と産土神を使い分けていることは、
「いまは、皆さんの神様」といってるようである。
神社の説明版を眺めていて幻想した。
菅原道真大神(すがわらみちざねおおかみ)と
白山媛大神(しらやまひめおおかみ)が
祀られて、白山媛大神は明治に合祀されたとなっている。
しかし、はるか以前から合祀されていて、
菅江真澄が辿る雛の回廊のひとつだったのではないだろうか。