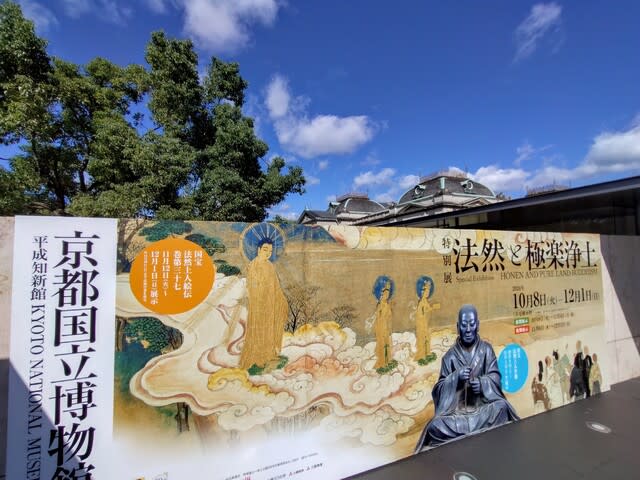今日は、どこへも行かずに、家で『京都検定』の勉強をしていました。
毎日コツコツと勉強をしていますが、忘れる量も半端なく、ざるのように抜けていきます。
記憶する量と忘れる量はどちらが多いのでしょうか?
というか、覚えなければいけないことが多すぎます・・・。
ぼやいても仕方がないですが・・・。
気分転換に少し前に行った二条城のことを思い出しました。



以前から行きたいと思っていたのですが、ここは観光客が多いと思って、敬遠していました。
特に外国人観光客と修学旅行生が多いような気がします。


子どもの頃と、若い頃に行った記憶がありますが、その頃はまったく勉強していなくて、特に感動もなく通り過ぎました。
今回は、事前に勉強をしていったので、いろいろと見たいものがありました。


これは唐門です。
大変綺麗な門ですね。



秀吉が作った唐門も綺麗でしたが、さすが徳川と言う感じですね。
家康さんも、家光さんも将軍の宣下を受けたのは、伏見城だったそうですが、新しく京都における拠点として、この二条城を作ったんですね。
秀吉を上回るものを作ろうとしていたのでしょうね。



あまりに綺麗なので、内側からも撮影してみました。
大変綺麗でした。


唐門から中に入ると二の丸御殿がありました。


この二の丸御殿は、徳川の時代につくられたものが、そのまま残っているらしくて、狩野派の絵が数多く描かれていました。
以前は、そういった絵には興味が無かったのですが、この間『狩野永徳』の物語や『長谷川等伯』の物語を読んでいるので、ぜひ見たいと思っていました。


残念ながら内部は写真撮影ができないので、しっかりと目で見て堪能することにしました。
入ってすぐの間には、虎の絵が描かれていて、将軍家の権威を見せつけるような空間になっていました。
ただし・・・、狩野派の人たちは実際に虎を見たことが無かったらしくて、中国から伝わった見本(粉本)を頼りに書いたようです。
いつも思いますが、この時代の虎の絵は、顔の部分がちょっとおかしい感じを受けます。
おそらく、虎を見たことが無いので、見本を頼りに、後はほかの動物を参考にして描いたのでしょう。。。
ちなみに、二条城ができた時代には狩野派は永徳の孫の探幽の時代になったいたと思います。
そして・・・。
もう一つ見たかった場所が・・・。

大政奉還が行われた『大広間』です。。。
まさに、その時歴史が動いたといった感じですね。
実物は撮影出来ないので、絵葉書を買いました。
将軍が座る部屋は畳が一段高くなっていて、天井も高くなっています。
これこそ上から目線・・・、これでもかというくらい権威を見せつけていたのでしょうね。
3代将軍の家光が来て以来、14代将軍の家茂まで全く使われることが無かったそうですね。
この二条城は、江戸時代の最初と最後を象徴すると言えるような場所だと思いました。
しばし、157年前を想像・・・。
この部屋の前では、ちょっと感動してしばらく立っていました。