第4巻は、大槻伝蔵、天一坊、田沼意次、鳥居耀蔵、高橋お伝、井上馨、である。
印象としては「小物」というカンジだ。
大槻伝蔵は、加賀騒動の登場人物である。
天一坊は、徳川8代将軍吉宗の隠し子騒動である。
いずれも、たいした事件ではないが(と思う)「悪人」としてとらえられているから、筆者はとりあげたのだと思う。
歴史は勝者の歴史である、ということもあり、敗者が悪人になることが多い。
特に、この時代は出自とか身分・家柄が社会の秩序となったことから、この秩序を乱すものが悪人となったのかもしれない。
著者は「田沼時代」に一揆強訴がやたら起きることについて
「太平が長くつづき、文化がいつの間にか浸潤し、人権的なものに目ざめて来たからであろう」
としている。ナルホド、である。
田沼意次も異例の出世が秩序を乱したことになり、それが評判を悪くしたのだと思う。
異例の出世をする人は、仕事ができる、仕事ができるから人が集まる、その集まった人は何かの願い事があるので「お土産=賄賂」を贈る、という循環らしい。
仕事のできる人は何に気をつけなければならないか、ということの見本であるが、その後あまり参考にされていないらしい。
鳥居耀蔵を著者は大嫌いである。
江戸時代後期・末期に幕府で活躍した人の出世街道を走る車の両輪が「賄賂行使」と「スパイ利用」と著者は言う。
そのスパイ利用のしかも陰険な利用をした最たるものが鳥居だと言う。
平岩弓枝の「妖怪」というのは鳥居耀蔵を描いたものだが、それを読んでもあまり好感をもてなかったくらいだから、ここに出てくる話を読むと腹が立つくらいである。
ちなみに「妖怪」というのは耀蔵が甲斐守であったことからついたあだ名である。
高橋お伝は可哀そうな女である。
当時は生まれと育ちと生きる環境を甘んじて受けなければならない時代であった、それを甘んじて受けない者は「悪人」なのである。
井上馨は幕末期と明治期ではエライ違いであるように思えるが、幕末期の志士たちの遊びと金遣いは、今の感覚で言えば「とんでもない」ことに思える。
志士たちでも、明治に入り自らの責任を自覚した者がマアマアであった、しかし志士感覚が抜けない者がいた。それが高官のままでいたことが、その後の日本の衰亡となったように思えるのである。
天皇家やそれを取り巻く公卿たち、或いは徳川幕府が長く続いたのは、その創建時において「清廉」差があったからではないか、幕府を倒した後の明治の体制が昭和の戦争で負け、長く続かなかった一つの要因は維新の中心となった者たち「性格」が影響しているのではないだろうか。
私の持っている「悪人列伝」はふるい版であり、第4巻に筆者のあとがきと綱淵謙錠の解説がある。
これもお勧めである。
印象としては「小物」というカンジだ。
大槻伝蔵は、加賀騒動の登場人物である。
天一坊は、徳川8代将軍吉宗の隠し子騒動である。
いずれも、たいした事件ではないが(と思う)「悪人」としてとらえられているから、筆者はとりあげたのだと思う。
歴史は勝者の歴史である、ということもあり、敗者が悪人になることが多い。
特に、この時代は出自とか身分・家柄が社会の秩序となったことから、この秩序を乱すものが悪人となったのかもしれない。
著者は「田沼時代」に一揆強訴がやたら起きることについて
「太平が長くつづき、文化がいつの間にか浸潤し、人権的なものに目ざめて来たからであろう」
としている。ナルホド、である。
田沼意次も異例の出世が秩序を乱したことになり、それが評判を悪くしたのだと思う。
異例の出世をする人は、仕事ができる、仕事ができるから人が集まる、その集まった人は何かの願い事があるので「お土産=賄賂」を贈る、という循環らしい。
仕事のできる人は何に気をつけなければならないか、ということの見本であるが、その後あまり参考にされていないらしい。
鳥居耀蔵を著者は大嫌いである。
江戸時代後期・末期に幕府で活躍した人の出世街道を走る車の両輪が「賄賂行使」と「スパイ利用」と著者は言う。
そのスパイ利用のしかも陰険な利用をした最たるものが鳥居だと言う。
平岩弓枝の「妖怪」というのは鳥居耀蔵を描いたものだが、それを読んでもあまり好感をもてなかったくらいだから、ここに出てくる話を読むと腹が立つくらいである。
ちなみに「妖怪」というのは耀蔵が甲斐守であったことからついたあだ名である。
高橋お伝は可哀そうな女である。
当時は生まれと育ちと生きる環境を甘んじて受けなければならない時代であった、それを甘んじて受けない者は「悪人」なのである。
井上馨は幕末期と明治期ではエライ違いであるように思えるが、幕末期の志士たちの遊びと金遣いは、今の感覚で言えば「とんでもない」ことに思える。
志士たちでも、明治に入り自らの責任を自覚した者がマアマアであった、しかし志士感覚が抜けない者がいた。それが高官のままでいたことが、その後の日本の衰亡となったように思えるのである。
天皇家やそれを取り巻く公卿たち、或いは徳川幕府が長く続いたのは、その創建時において「清廉」差があったからではないか、幕府を倒した後の明治の体制が昭和の戦争で負け、長く続かなかった一つの要因は維新の中心となった者たち「性格」が影響しているのではないだろうか。
私の持っている「悪人列伝」はふるい版であり、第4巻に筆者のあとがきと綱淵謙錠の解説がある。
これもお勧めである。











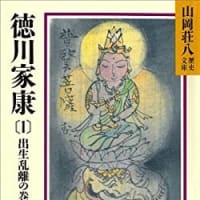
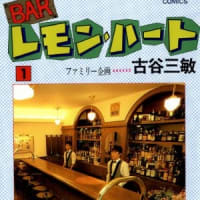
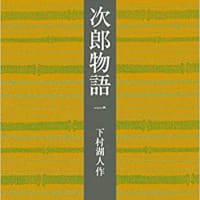
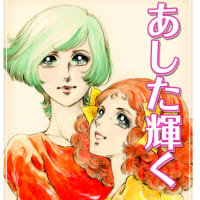
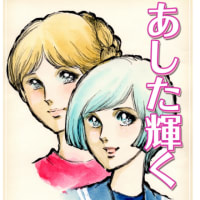
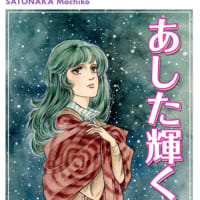
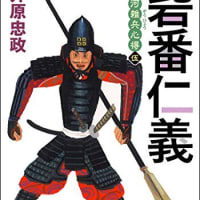
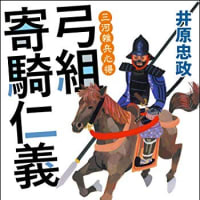
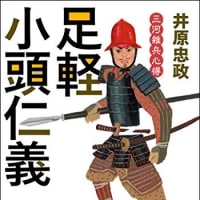
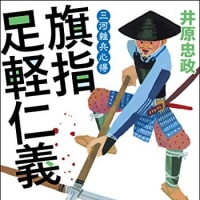





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます