先週、近くの日系レンタルDVDのお店にやっと並んだ、昨年(2011)最後の経済トーク番組 カンブリア宮殿、早速借りてきて観てみた。
普段生活をしながらも常に頭の隅っこの方に小さく存在する大きな課題、それは日本の復興である。311後の復興も含めて今後日本はどのような形で存在するのか?そして現在は長期に渡る円高のあおりを喰らい、特に製造業は試練の中にある。以前のようにしていてはメシが食えん、と聞くが...。
我々の生活の糧であったものつくり

このグラフをご覧下さい。
これは日本経済新聞において、『ものつくり』のキーワードが新聞の記事に記載された数の統計を示したグラフです。細かい数字はどうでもよいのですが、だいたい2000年頃を境に急激に増えている事が分かります。
なぜ?
それは、2000年頃を境にニッポンのものつくリがダメになっていった結果です。
ものつくりが血気盛んな時代はものつくりなんて言わなかったのです。
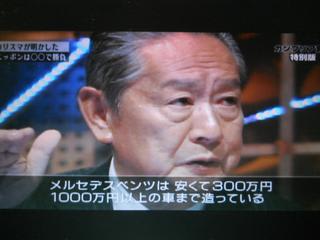
『だいたい私は、ものつくりなんて言葉が嫌いだ!』
元ソニーのCEO出井伸之氏の言葉が印象に残った。
そして 彼はハッキリと告白した。
アップル的な事が出来なかった事が悔しい! と述べた。
と述べた。
その理由は、腹が座っていなかったんですね...。
なぜ?

成功体験が人(会社)を保守的にしてしまったんです。
だからこそ(苦い思いをした)、皆さんに知ってほしい。
 20世紀の成功と、21世紀の成功は、分けて考えろ。
20世紀の成功と、21世紀の成功は、分けて考えろ。
 21世紀の成功は、20世紀の成功の延長線の上にはない。
21世紀の成功は、20世紀の成功の延長線の上にはない。
そして、自動車においても、
日本は中級品を沢山生産する、このままだと 日本の自動車産業は今の家電のようになる可能性があります。

80年代、1ドルを払って日本車をハンマーで叩き潰す人。
即ち、アメリカの自動車産業が衰退したのは、技術力やオイルショックなども要因だが、
その根、幹は、
過去の成功体験...だった。

じゃーどしたらいいんだ?
まとめてみた。
各個人で考えろ!が一つのつぶやき。
覚悟を入れ替えないといけない!がもう一つのつぶやき。
そして、
おやじの言う事を聞くな!がアドバイスである。
誰も未来に対して、ああしろ、こうしろとは言えない、と知りながら。一方では誰かが人指し指を振りながらああしろ、こうしろと言ってくれるのを待つ。こんなジレンマが存在する。また、未来の未知な行くべき先を模索するのに、過去の成功者の意見を聴拝し重視する。
最後に龍さんの言葉。
今の制度そのものの中で、自分達はどう生きるか、(を)どう守ろうかではない。
破綻するか、或いは自ら大きく変われるか、のどちらかである。
指針はあっても答えはない、
...こうやって人間は何時の時代も生きて来たのである。
















