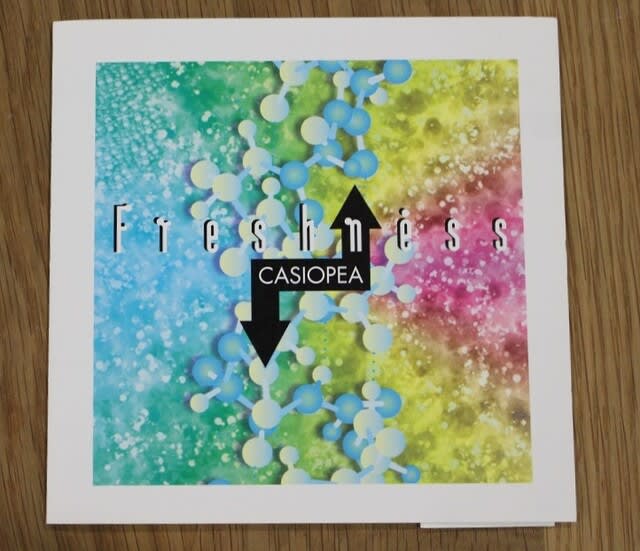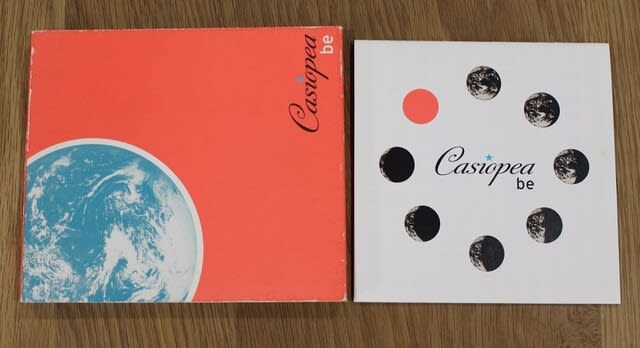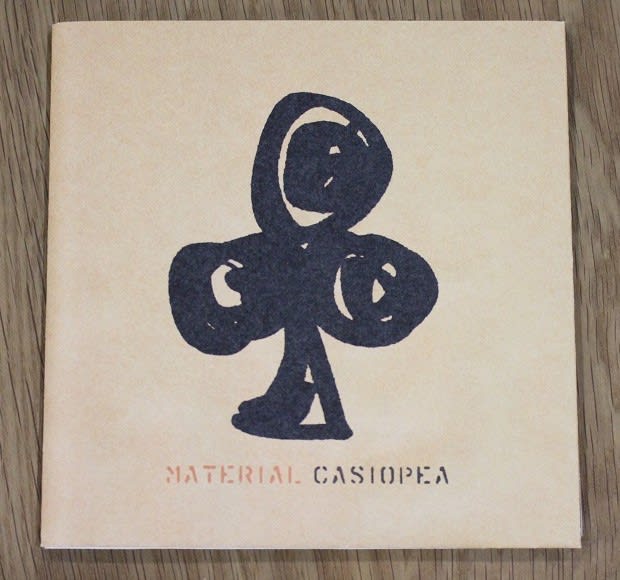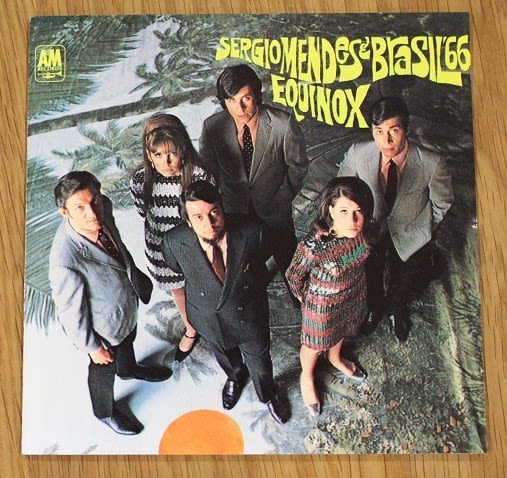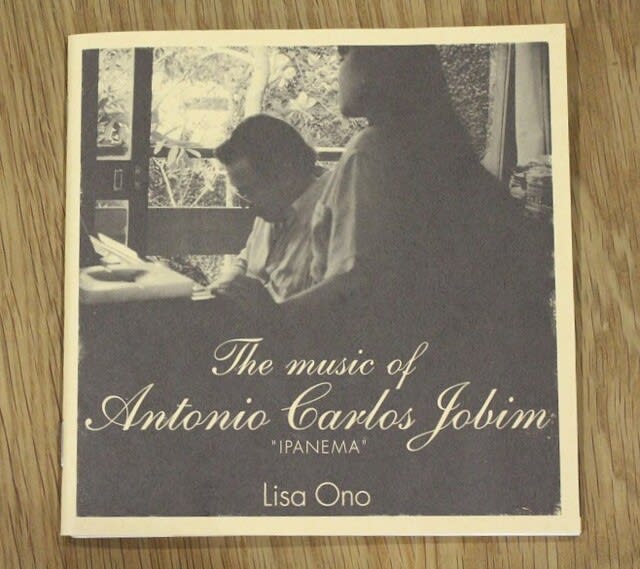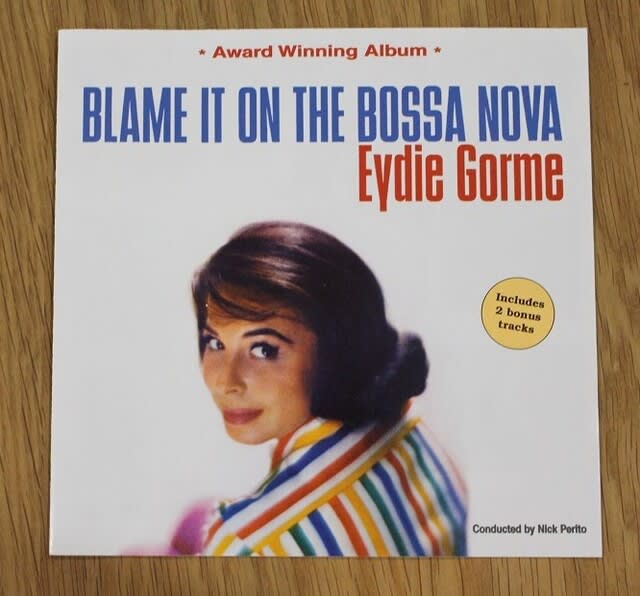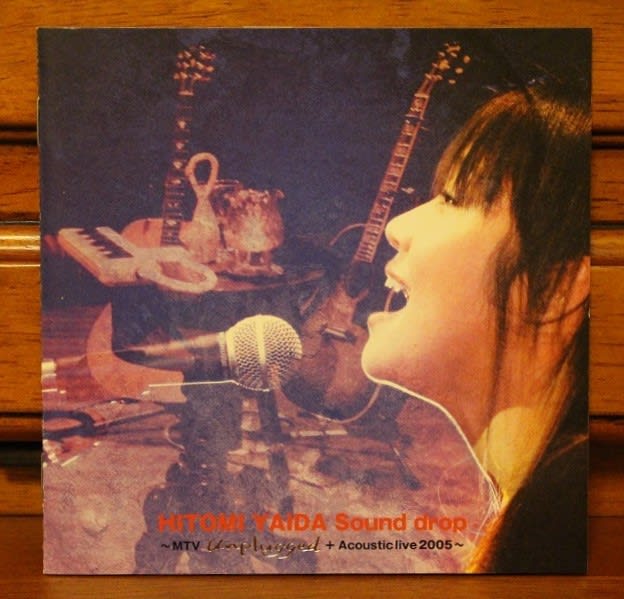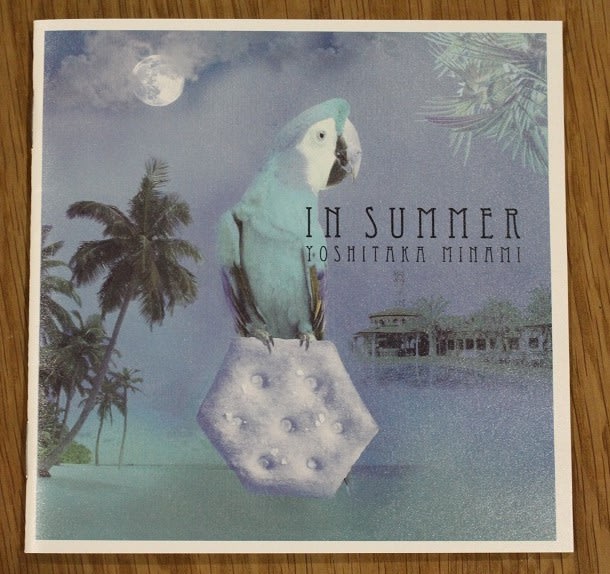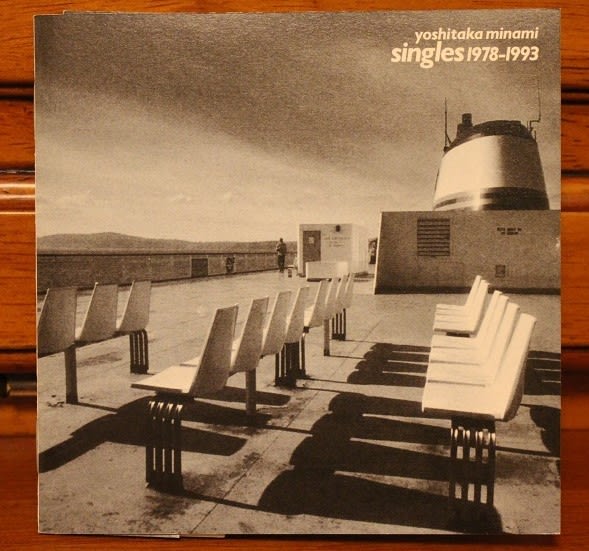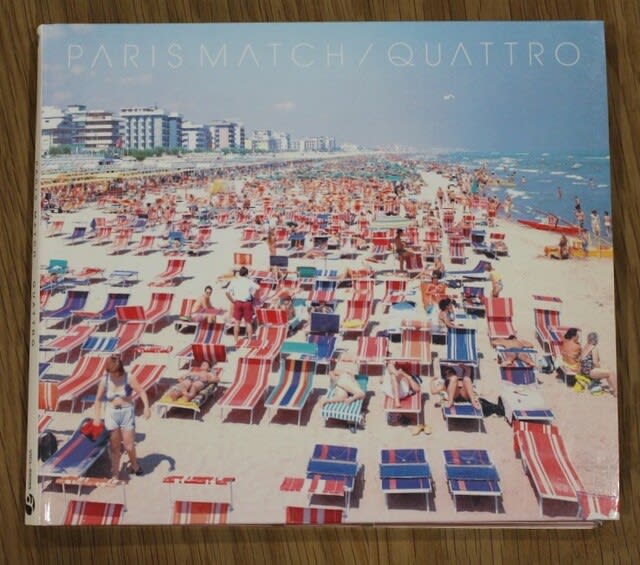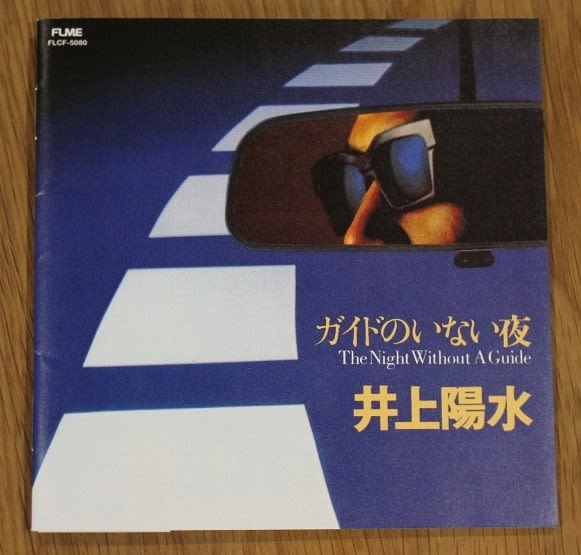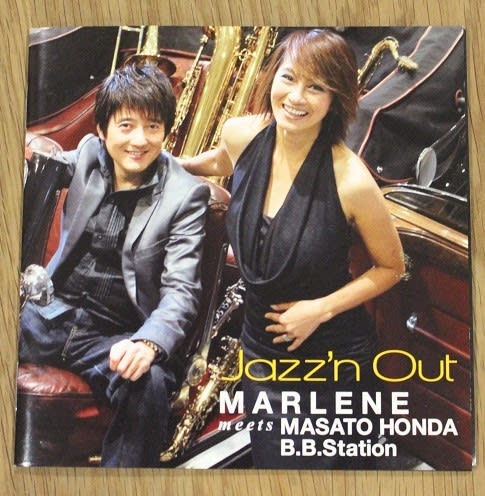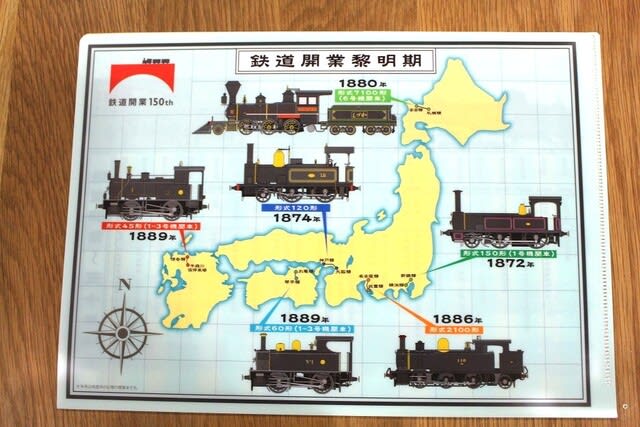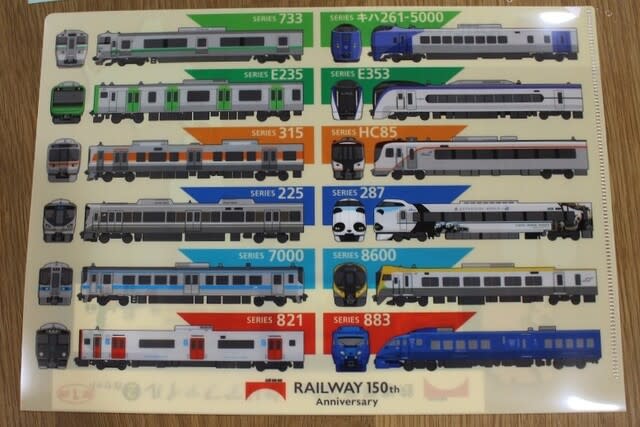F1のシーズンも夏休みに入り、後半戦に向けて一休みというところですが、思いがけずこの本が「復活」していました。それが「F1全史」(三栄)で、このたび刊行された第14集では2016年から2021年までの6シーズンの各レースごとの公式記録、シーズンのハイライト等が掲載されています。
このF1全史という本は、F1が始まった1950年からの記録、シーズンのハイライト等を写真と文章、データでまとめており、巻末には各レースごとの詳細な順位などの記録も掲載されています。レース数が少なかった1950年~1955年は別として5シーズンを区切りに刊行されており、分かっている範囲でレースごとにエントリー、出走したすべてのドライバーの予選、決勝の記録がわかるわけです。もともと歴史好きなものですから、レースの歴史についても大いに興味があり、1950年~1955年をまとめた第1集から2011年~2015年シーズンをまとめた第13集まで買っています。
たいがいは5シーズン経過するとその翌年に「全史」の新刊が出るという感じで、2016年~2020年については2021年に刊行されるのかなと思っていましたら、刊行がありませんでした。もう出ないらしいとか、いろいろ噂は聞こえていたのですが、こうして本屋さんに並んで、私も勇んで買ったわけです。2021年にホンダエンジンが久々にタイトルを獲得したからなのか、詳しいことは分かりませんが、この6シーズンを鳥の目でも虫の目でも楽しめるようになったわけで、執筆陣の皆様、データ提供・監修の林信次さんに感謝というところです。
F1のシーズンは本当に流れが早く感じられ、コロナの混乱の中で過ぎていった2020年シーズンが、何か遠い昔のように感じますし、2017、2018年シーズンは正直なところ自分の記憶からだいぶ薄れております。グランプリが夏休みですから、読むF1をじっくり楽しめそうです。

このF1全史という本は、F1が始まった1950年からの記録、シーズンのハイライト等を写真と文章、データでまとめており、巻末には各レースごとの詳細な順位などの記録も掲載されています。レース数が少なかった1950年~1955年は別として5シーズンを区切りに刊行されており、分かっている範囲でレースごとにエントリー、出走したすべてのドライバーの予選、決勝の記録がわかるわけです。もともと歴史好きなものですから、レースの歴史についても大いに興味があり、1950年~1955年をまとめた第1集から2011年~2015年シーズンをまとめた第13集まで買っています。
たいがいは5シーズン経過するとその翌年に「全史」の新刊が出るという感じで、2016年~2020年については2021年に刊行されるのかなと思っていましたら、刊行がありませんでした。もう出ないらしいとか、いろいろ噂は聞こえていたのですが、こうして本屋さんに並んで、私も勇んで買ったわけです。2021年にホンダエンジンが久々にタイトルを獲得したからなのか、詳しいことは分かりませんが、この6シーズンを鳥の目でも虫の目でも楽しめるようになったわけで、執筆陣の皆様、データ提供・監修の林信次さんに感謝というところです。
F1のシーズンは本当に流れが早く感じられ、コロナの混乱の中で過ぎていった2020年シーズンが、何か遠い昔のように感じますし、2017、2018年シーズンは正直なところ自分の記憶からだいぶ薄れております。グランプリが夏休みですから、読むF1をじっくり楽しめそうです。