高村薫が「グリコ森永事件」をモチーフに描いた傑作小説「レディ・ジョーカー」を読了。いやー、面白いの一言に過ぎるんだけど、読み終わった後に残る何ともいえない後味の悪さはなんだろう。不快というのとは違うすっきりとしなささ、結局、僕らは望むと望まないとに関わらずこの社会にスポイルされていかざろうえないのかという絶望を垣間見たような感覚…
そうなのだ。この物語ではレディ・ジョーカーとそれを追う警察の物語はもちろん、脅迫を受けた側の企業がまさしく企業として生き延びていこうとする姿、レディ・ジョーカーやその背後の闇を追おうとするジャーナリストたちの姿など幾つもの物語が錯綜しているが、高村薫が描いたもの、その恐怖の本質というのは「この社会では『個人』あるいは『個人の意思』というものはそれが自立して存在することはできず、社会を構成する仕組みやシステムの中で絡みとられ、その一部にならざろうえないということなのだ。
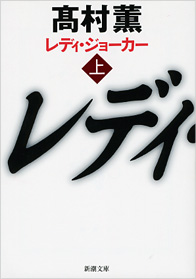


そもそもの発端となった岡村清二の書いた手紙は、決してそこに日の出ビールを脅迫しようなどという意図はなかっただろう。時代が時代であった以上、日の出から実質解雇であったであろうともそこに必要以上に「憎」はない。むしろ自分の生まれ育った「村」や「時代」に対する「悲しみ」や新しい時代が訪れたにも関わらず、その時代の恩恵に預かることなく「犠牲」となった同僚に対する想いであったり、いずれにしろある種のナルシスト的な感傷によってなされたものだった。そうした「個人的な」想いとは別にこの手紙は総会屋に利用され、犯罪の一翼を担うことになる。
秦野浩之は、自分の出生という全く意識の外にあった「過去」、本人にはどうしょうもない「差別」によって息子をうしなうことになる。少なくとも「歯科医」という職業は社会的には勝ち組だろう。息子は東大を卒業しようとしており、そこには明るい未来が開けているはずだった。しかし「被差別」出身という烙印が彼らを絶望へと突き落とす。そしてその「絶望」さえも誰かに利用されることになる。
物井清三は自らの意思で「レディ・ジョーカー」を立ち上げる。それは金のためではなく、本人の憶測に住む「鬼」が成し遂げたものだ。それはやがて半田や布川へと伝播し「レディ・ジョーカー」は20億もの大金を手に入れることになる。完全犯罪。しかし物事はそんなに簡単ではない。物井がはじめた「レディ・ジョーカー」はやがて半田の暴走(暴力への傾倒)を招き、さらには物井らの知らないところで新たなる「レディ・ジョーカー」が動きはじめる。知らず知らずのうちに、「レディ・ジョーカー」は物井から遠いところで独り歩きするのだ。
在日朝鮮人でもある高克己は、結局、より大きな勢力に飲み込まれ、どこにも逃げることが出来なくなっている。
布川淳一は障害児と病床の妻を抱え、身代金を手に入れたにもかかわらず、全てを放り出し逃げ出すことを選ぶ。
城山恭介は企業のトップとしての決断と、姪・佳子への想いと、個人のあり様あるいは人間としての「良心」との間で苦しむことになる。合田のことを「鵺のような人間社会を生き抜いていく欲望を欠いている」としつつも、その「魂」のあり様に心揺さぶられことになる。そしてそのことは、会社を去りゆくものとして、また一個人としての責任の取り方を考えるきっかけとなり、自らのけじめをつける。
しかし自らを犠牲にして企業というものを生存させてきた城山が、ようやく自身を取り戻したにもかかわらず、その結末はあっけないものだった。社会というしがらみの中では、個人など塵のようなものなのか。
根来は日々紙面を埋めるための記事に追われながら、しかしGSCという1つの言葉に吸い寄せられるように兜町ルートの動きを追い続ける。過去の事件、希望のないまま、記者の本能として。根来が感じていた絶望とは何だろう。疑獄事件の真相に近づきそしてその妨害・脅しとしての事故、しかしその犯人が分かっているにも関わらず起訴さえされないという現実。
「自分を包み込んでいるこの時代と社会のトンネルはどこまで続いているのか、もういい加減、空を見たいといった漠とした息苦しさ」
今、ジャーナリストとしての野心をもって取材をつづけていた佐野の失踪に際し、自分に何ができるか――しかしそうした想いもまた「闇」の中に取り込まれてしまうのだ。
この小説の主人公・合田雄一郎はいち早く内部に犯人がいることを見抜く。組織の命令に従い城山の動向を探りながら、あるいは組織内の失敗をなすりつけられながらも、半田の事情聴取をまった合田を待っていたのは、組織防衛のために、あるいは組織内部の論理のために事情聴取を諦めるという現実だ。ここにも個人の尊厳や良心といったものは全く生きていない。
そしてそれは、屈折した半田の警察組織への「憎悪」と対をなすように、合田もまた自身で半田を追い詰めていこうとする。そこには「組織」から外れた者同士が、「(警察組織上の)正義」とか「憎悪」とかを越えて、一個人としての尊厳をかけて戦おうとした。彼らは警察組織にあって同じモノを見ていたのであり、その表裏でもあり、だからこそ共に執拗に向き合っていたのだ。
そして2人の共犯関係は「組織」に対して1つの反撃を試みる。現職警察官が同僚の警察官をナイフで刺し「俺はレディ・ジョーカー」だと名乗るのだ――しかしそれでも警察組織はその組織の論理によって「レディ・ジョーカー」を逮捕しない。
果してこの社会の「悪」とは何なのだろうか。
物井や半田が悪なのか。あるいは高は悪なのか。高を利用しようとした組織が悪なのか。岡田経友会や総会屋が悪なのか。だとしたら警察は正義なのか――いずれもがその通りであり、しかしそれだけでは不十分だろう。
この時代のもつ息苦しさは、岡村清二の時代とは別の意味で、「組織」や「社会」といったものが「個人」のを越えて存在し、個人の意思や良心というものを押さえ込み、あるいは押さえ込まねばならないような状況に追い込まれているためだ。社会といった様々な要素によって構成された存在に個人が取り込まれスポイルされる、そこには明確な「敵」や「悪」の存在が見えるのではなく、獏として存在しているのだ。1人ひとりの個人はその存在の前ではただの弱者でしかない。そんな敵の見えない時代の恐怖をこの小説はうまく描き出したのだろう。
レディ・ジョーカー(上・中・下) / 高村薫
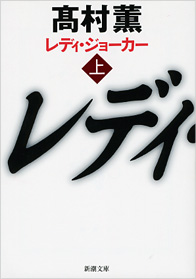


レディ・ジョーカー:高村薫が描いた社会的弱者の復讐劇 - ビールを飲みながら考えてみた…
「闇に消えた怪人-グリコ・森永事件の真相-」/ 一橋文哉 - ビールを飲みながら考えてみた…
そうなのだ。この物語ではレディ・ジョーカーとそれを追う警察の物語はもちろん、脅迫を受けた側の企業がまさしく企業として生き延びていこうとする姿、レディ・ジョーカーやその背後の闇を追おうとするジャーナリストたちの姿など幾つもの物語が錯綜しているが、高村薫が描いたもの、その恐怖の本質というのは「この社会では『個人』あるいは『個人の意思』というものはそれが自立して存在することはできず、社会を構成する仕組みやシステムの中で絡みとられ、その一部にならざろうえないということなのだ。
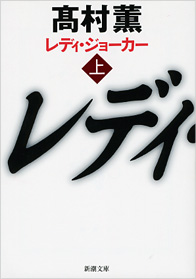


そもそもの発端となった岡村清二の書いた手紙は、決してそこに日の出ビールを脅迫しようなどという意図はなかっただろう。時代が時代であった以上、日の出から実質解雇であったであろうともそこに必要以上に「憎」はない。むしろ自分の生まれ育った「村」や「時代」に対する「悲しみ」や新しい時代が訪れたにも関わらず、その時代の恩恵に預かることなく「犠牲」となった同僚に対する想いであったり、いずれにしろある種のナルシスト的な感傷によってなされたものだった。そうした「個人的な」想いとは別にこの手紙は総会屋に利用され、犯罪の一翼を担うことになる。
秦野浩之は、自分の出生という全く意識の外にあった「過去」、本人にはどうしょうもない「差別」によって息子をうしなうことになる。少なくとも「歯科医」という職業は社会的には勝ち組だろう。息子は東大を卒業しようとしており、そこには明るい未来が開けているはずだった。しかし「被差別」出身という烙印が彼らを絶望へと突き落とす。そしてその「絶望」さえも誰かに利用されることになる。
物井清三は自らの意思で「レディ・ジョーカー」を立ち上げる。それは金のためではなく、本人の憶測に住む「鬼」が成し遂げたものだ。それはやがて半田や布川へと伝播し「レディ・ジョーカー」は20億もの大金を手に入れることになる。完全犯罪。しかし物事はそんなに簡単ではない。物井がはじめた「レディ・ジョーカー」はやがて半田の暴走(暴力への傾倒)を招き、さらには物井らの知らないところで新たなる「レディ・ジョーカー」が動きはじめる。知らず知らずのうちに、「レディ・ジョーカー」は物井から遠いところで独り歩きするのだ。
在日朝鮮人でもある高克己は、結局、より大きな勢力に飲み込まれ、どこにも逃げることが出来なくなっている。
布川淳一は障害児と病床の妻を抱え、身代金を手に入れたにもかかわらず、全てを放り出し逃げ出すことを選ぶ。
城山恭介は企業のトップとしての決断と、姪・佳子への想いと、個人のあり様あるいは人間としての「良心」との間で苦しむことになる。合田のことを「鵺のような人間社会を生き抜いていく欲望を欠いている」としつつも、その「魂」のあり様に心揺さぶられことになる。そしてそのことは、会社を去りゆくものとして、また一個人としての責任の取り方を考えるきっかけとなり、自らのけじめをつける。
しかし自らを犠牲にして企業というものを生存させてきた城山が、ようやく自身を取り戻したにもかかわらず、その結末はあっけないものだった。社会というしがらみの中では、個人など塵のようなものなのか。
根来は日々紙面を埋めるための記事に追われながら、しかしGSCという1つの言葉に吸い寄せられるように兜町ルートの動きを追い続ける。過去の事件、希望のないまま、記者の本能として。根来が感じていた絶望とは何だろう。疑獄事件の真相に近づきそしてその妨害・脅しとしての事故、しかしその犯人が分かっているにも関わらず起訴さえされないという現実。
「自分を包み込んでいるこの時代と社会のトンネルはどこまで続いているのか、もういい加減、空を見たいといった漠とした息苦しさ」
今、ジャーナリストとしての野心をもって取材をつづけていた佐野の失踪に際し、自分に何ができるか――しかしそうした想いもまた「闇」の中に取り込まれてしまうのだ。
この小説の主人公・合田雄一郎はいち早く内部に犯人がいることを見抜く。組織の命令に従い城山の動向を探りながら、あるいは組織内の失敗をなすりつけられながらも、半田の事情聴取をまった合田を待っていたのは、組織防衛のために、あるいは組織内部の論理のために事情聴取を諦めるという現実だ。ここにも個人の尊厳や良心といったものは全く生きていない。
そしてそれは、屈折した半田の警察組織への「憎悪」と対をなすように、合田もまた自身で半田を追い詰めていこうとする。そこには「組織」から外れた者同士が、「(警察組織上の)正義」とか「憎悪」とかを越えて、一個人としての尊厳をかけて戦おうとした。彼らは警察組織にあって同じモノを見ていたのであり、その表裏でもあり、だからこそ共に執拗に向き合っていたのだ。
そして2人の共犯関係は「組織」に対して1つの反撃を試みる。現職警察官が同僚の警察官をナイフで刺し「俺はレディ・ジョーカー」だと名乗るのだ――しかしそれでも警察組織はその組織の論理によって「レディ・ジョーカー」を逮捕しない。
果してこの社会の「悪」とは何なのだろうか。
物井や半田が悪なのか。あるいは高は悪なのか。高を利用しようとした組織が悪なのか。岡田経友会や総会屋が悪なのか。だとしたら警察は正義なのか――いずれもがその通りであり、しかしそれだけでは不十分だろう。
この時代のもつ息苦しさは、岡村清二の時代とは別の意味で、「組織」や「社会」といったものが「個人」のを越えて存在し、個人の意思や良心というものを押さえ込み、あるいは押さえ込まねばならないような状況に追い込まれているためだ。社会といった様々な要素によって構成された存在に個人が取り込まれスポイルされる、そこには明確な「敵」や「悪」の存在が見えるのではなく、獏として存在しているのだ。1人ひとりの個人はその存在の前ではただの弱者でしかない。そんな敵の見えない時代の恐怖をこの小説はうまく描き出したのだろう。
レディ・ジョーカー(上・中・下) / 高村薫
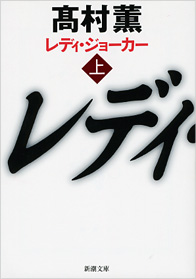


レディ・ジョーカー:高村薫が描いた社会的弱者の復讐劇 - ビールを飲みながら考えてみた…
「闇に消えた怪人-グリコ・森永事件の真相-」/ 一橋文哉 - ビールを飲みながら考えてみた…










ただひとつだけどうしても気になったことが。
ならざろうえない
成らざるを得ないのことだと思いますが、二度出てきたので気になってしまいました。
差し出がましくてもうしわけありません。