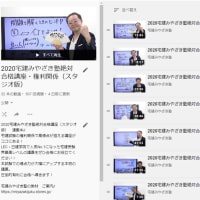2017 宅建試験合格体験記 吉川 隆文 様
※後日、図表の追加、加筆等することもあります。ご了承ください。
ちょっと気が早いのですが、
合格確実なので、公開させていただきますね(*^^)v
吉川さん、43点、おめでとう!
みやざき塾を合格にお役立ていただき、ありがとうございました!
他の資格も取りながらの戦い、ほんとよく頑張りましたね!
合格発表を楽しみにしましょう♪
月曜日、昨年合格者の森さんと3人で合格祝いのランチ楽しみにしております!(^^)!
宅建総研(みやざき塾) 宮嵜晋矢
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
合格体験記 吉川隆文
平成27年度から受験を始め、今年の受験まで計3回の試験を経験致しました。みやざき先生には28年度から2年間live講義にて直接の御指導を頂きました。
実家の賃貸マンションの管理業を引き継ぐため、宅建の知識を勉強しておいた方がよいといわれ、受験を決意したのが始まりです。
この3年間で、どんな知識と考え方を身に付けていったかの変遷を、来年以降に受験される皆様にお伝えできればと思い、拙い経験ながら合格までの勉強記録を提供させて頂きます。
① 27年度の本試験とみやざき先生との出会い
27年当時は、別の仕事をしており、勉強を本格的に始めた時期が8月のお盆過ぎから。
法律関係の知識はゼロからのスタートでした。本試験までの時間が限られていることもあり、どこから手を付けるべきか自分なりに問題の構成を分析して、『同じ分野から20問出る宅建業法』にまずは目標を定めました。そのほかに、特に勉強しないでも行けるかと思っていたのが、得点源としてカウントしていた5問免除の土地(問49)でした。市販の解説書と10年分の過去問を用意して勉強を始めたのですが、何しろ解説にかいてある文章が飲み込めなくて勉強が全然進まなかったのです。これはいかんと思い、何か動画解説のようなものはないかと思ってYoutubeで探していたところ、権利関係以外の法令、宅建業法、5問免除の勉強で勝負できるとおっしゃるみやざき先生の動画にたどり着きました。自分で見定めた攻略目標と先生が狙うべき得点源として挙げられていたのがまさに宅建業法で一致していたこともあり、そこからは動画を繰り返しみつつ、過去問を勉強して試験当日を迎えました。そこで合格できれば奇跡の大逆転だったのですが、そうは問屋が卸さず、過去問題にない内容が出題されて動揺し、なすすべもなく試験終了の時を迎えてしまいました。宅建業法が確か9点、権利関係は完全なすごろく状態で解答をマークして7点分稼ぎはしたものの、合計23点で沈没しました。時間が足りず、知識を整理して繰り返し確認することができず、結局は過去問の知識を無理やり覚えることに走ったことで必然の結果でした。
終わってみて、印象に残っていたのは試験に落ちたことよりも90分あまりで見事に整理して宅建業法を講義されていた先生の動画でした。もし、先生のように知識を整理してまとめていけていれば、どんな結果になったんだろうという疑問だけが残りました。
来年は是非とも直接御指導を仰いで入念な準備をしよう、と思い切ってみやざき塾の門を叩きました。
② みやざき塾で迎えた28年度本試験
1月から塾が始まり、7月までは月2回ペースでlive講義があるため、講義を聞いては一問一答を繰り返すのが勉強の中心でした。方針としては、前年と変わらず、宅建業法・法令制限・税について十分な準備をして確実に得点できるように勉強を進める方針で臨みました。この年については、他にも資格試験を受験しておりました関係で、権利関係は一切スルーを決め込むつもりでいたのですが、先生のlive講義を聞いていく中で、実は民法のルールは単純であるということを繰り返し、おっしゃっておられたのが印象に残りました。即ち、1.いい人と悪い人の争いはいい人が勝つ、2.いい人といい人の争いは早い者勝ちの2点に行きつくということです。言わば、権利関係は知識でなく、常識で解く。問題は知識で解くのが当たり前だと思っていた私には新鮮な驚きでした。この時、権利関係の勉強に少し向かい合っていたら、その後の未来は変わっていたものになったかも知れません(笑)。
8月に入り、勉強も一通り終わって、模試と過去問が勉強の中心になってくると、いわゆる合格点には達するレベル(35点以上40点未満)で点数が取れており、「ジ・オープン」では40点を達成しておりました。このときは、知識より常識で解く解き方で権利関係もいい感じで解けていたので本試験もこれで行けると思って、時々カラー板書で確認する程度で、特に準備はしなかったのです。法令制限・税その他・宅建業法については一問一答を8週以上繰り返し、十分な準備が出来たと思って平成28年度の本試験当日を迎えました。
5問免除 → 宅建業法 → 法令制限 と問題を解いていく中で、ある種の違和感を感じていました。やけに易しい、するする解けてしまっている、これはどういうことなんだろう?去年の試験と比べてこんなに傾向が変わることがあるものなのかと次第に動揺が広がっていきました。最初は、権利関係には手を出さないつもりでいたのですが、問題を読んでみて驚きました。ほぼほぼカラー板書で出ている内容のことがそのまま聞かれていたのです。慌てて、カラー板書の知識を思い出そうとしつつ、権利関係の問題を解き出しましたが、事前準備が全く足りておらず、どうにもなりませんでした。
25年~27年における権利関係の難化傾向が見事に変わってしまっていました。この変化は動揺するには十分で、法令制限や宅建業法などの確認がおろそかになった結果、最終的に32点、合格点に3点足りず、涙を飲みました。
なぜ、失敗に終わったのだろう?勉強のやり方にまずさはなかったか、自問自答を繰り返しました。29年度に向けた試験対策講義が始まる12月まで悶々としておりました。
③ 29年度本試験
圧倒的な難しさでねじ伏せられた27年度の本試験に比べて、28年度の試験は難しい問題が出るものと思い込んで、固さがあって臨んだ結果、肩すかしを食らう格好での敗北でした。硬軟自在に操ってくる本試験問題に対してどんな準備をすべきか、一から準備と対策を考えることから29年度の取り組みが始まりました。
28年度の勉強から変えたのは以下の内容になります。
1. 権利関係の準備
それまで食わず嫌いで手つかずだった権利関係についても一から準備をすることにしました。重要だったのは、先生が講義などで常々言われていたことですが、登場人物の相関関係など明確に図を描く練習をすることでした。まずは、宅建総研の大きなテキストにある図をなぞることから始めて、慣れてきたら、自分なりの図を描く。この練習を繰り返し行いました。試験で言えば、問題文を登場人物を矢印で繋いでいく流れ図に置き換える作業です。これによって、誰と誰が対立しているのか、悪いのは誰か?原因は何なのか?文章より、明確に見える形にすることが可能になります。意思表示・代理・抵当権・物権変動・相続・賃貸借などほぼほぼ試験に優先して取り組むべきテーマで、大変有効でした。次に、テキストを見ながら一問一答を使ってテキストの内容を確認する。これをlive講義が終わって次のlive講義がある2週間の間に、5週ほど繰り返しました。2月~4月にかけての取り組みです。
不動産登記法については、教科書以外にインターネットの画像検索などを使用して勉強しました。信託の登記など、教科書外のテーマでも、司法書士事務所のホームページなどで詳しい解説を確認できました。一つ一つの知識を抑えるのでなく、制度の目的やテーマ全体の趣旨を流れに沿って理解することを優先して努めました。
2. 法令制限その他・宅建業法
法令制限その他については4月~5月、宅建業法については6月~7月までLive講義がありました。やはり、live講義間の2週間内で大きなテキストを見ながら、一問一答で一つ一つ確認することを繰り返し行い、5週ほど繰り返しました。インターネット画像検索や、先生からお勧めのあったイラスト中心の書籍を多用して勉強しました。画像検索などで実例を調べることが最も多かった分野でした。また、恐らくは、都市計画法の理解が最難関になることが多いのではないかと思われます。大きな流れに沿ったまちづくりのためのルールを理解することとと細かい知識を正確に抑えることが必要なテーマだからです。ここでは、無理やり知識を詰め込まず、まずは、おおまかな制度趣旨を流れに沿って理解することを心掛けて準備しました。結果として例えば準都市計画区域など単体で知識として抑えるのでなく、まちづくりにおけるコンセプトの一つとして理解し、まちづくりの一つの流れに沿ったお話として他の人に説明できるようなイメージを心掛けました。
宅建業法についても、大きなテキストで制度趣旨と目的を理解し、その後一問一答を使って、テキストの内容を確認していく作業を5週ほど繰り返しました。
8月の5問免除対策を含めたここまでが、第一の準備期間になります。昨年度からの勉強の変化をまとめますと、
①一問一答などただ問題を繰り返すのでなく、一問一答を補助的に使ったテキストの見直しの繰り返し
②権利関係を中心とした積極的な図描き練習
③一つ一つの知識を細かく抑えるより、大まかな全体の流れ、趣旨の理解に努める。
昨年の取り組みでは一問一答ををただ繰り返すことで安心してしまっていましたが、学習の中心をテキストに置いて繰り返すというのが一番大きな変化でした。ここまでの理解の定着度合を8月以降の模試・過去問特訓を利用してその都度、確認しました。
4. 特訓・模試の取り組みと試験直前期
8月からはこれまでの理解度合の定着を確かめるために、模試、過去問を解いて確認します。この頃、確認の対象を大きなテキストからカラー板書中心に移行しました。ここで、それぞれの分野の間違えたテーマを抽出し、間違った原因を検証して正しい理解をテキストで再度確認する作業を繰り返します。間違えたところを1.宅建業法・2.法令制限その他・3.権利関係の優先順位で確認しては、言わば穴を埋めなおす作業を丁寧に繰り返す。このことで点数の推移が1回目のお盆特訓の時には、4回の模擬試験で36~39点だったのが、10月に入ってから平成17年度から28年度までの過去問を1日2年分、1回1時間30分ペースで解いたところ、44点以上と着実に得点の上積みができ、正しく理解できていることの確認にもなって、自信がつきました。一見すると、去年の点数の傾向と一致するのですが、理解の定着という点においてものすごく大きな差がついたと今ははっきり感じます。
また、間違えたテーマに関してはその知識の部分だけでなく、カラー板書と一問一答を使って、テーマ自体を再度確認しました。
上記の過去問特訓と並行して、宅建業法については弱点を中心に、カラー板書の図表をノートに繰り返し描いて、いつでも思い出せるように準備をし、どうしても弱点として残ったところに、最終的にカラーチェックを行いました。
今年の準備に関してはテキストとから始まり、最終的にはカラー板書1本に絞って、特に宅建業法を中心に27ページ分についてはいざとなれば暗記する、逆に言えば、完璧に覚える部分をカラー板書の範囲内に絞って集中的に繰り返すぐらいの心積もりで準備しました。
5. 29年度本試験
当日は、法令制限→税・地価公示→宅建業法→5問免除→権利関係の順で解きました。今年の問題は出題の順序が変わっていたり(問15:都市計画法、国土利用計画法→農地法)、細かい知識とカラー板書にあったような定番知識が混在する問題内容の印象を受けました。問題の解きにくさに関しては法令制限、税・地価公示の分野で特に顕著であったように思います。宅建業法は、カラー板書内の知識で十分対応可能でしたが、問題文の細かいところでの読みとばし、勘違いなどで2問ミスがありました。五問免除は普通かむしろ易しめで、権利関係については中には難しめの問題もありましたが、カラー板書の基本的な知識で解ける問題も多くありました。最終的には43点を取ることができました。
6. 最後に
3度の受験を経験した今、振り返ってみますと本試験の問題の解き方で必要なこととして、
①正確に○×判断を下せるように知識の精度を高める
②法や制度の主旨から考えて、内容が則っている内容なのか、そうではないのかを判断して解く
以上の2点に集約されると思います。
①に関しては2月~10月の試験直前期までにテキストや一問一答・live講義やDVD教材を正しく繰り返し使いこなすことでその精度が磨かれていきます。問題だけの繰り返しは避け、テキストを見ながら一問一答を解く方が良いです。ここには大きな違いがありました。問題はテーマの一部分を切り取った物であり、それだけ繰り返しても制度全体の理解にはつながらないからです。2月~8月前半の期間に、宅建総研テキストを中心に、わからないところをインターネットの実例画像検索などで詳しく、広く浅く、丁寧に学習する。本試験そのものに役立つことはなくとも、制度の全体を把握する上では十分助けとなるものであり、知識の根がしっかり張ります。そして、例え忘れたとしても、お盆以降に、カラー板書を見返すことで思いだし、更には試験に必要な知識として集約され、試験の際に効率良く引き出すことが可能になります。結果として、○×判断のための時間がかからなくなるので全体の試験時間の短縮に大いに貢献しました。特にカラー板書の知識を正確に思い出せるようになるまで高めることで、最終的には、大部分の本試験過去問に対応できることを今回の試験準備で自分は確信しました(いずれの年度分も40点以上は簡単に超えられるようになります)。このことは声を大に皆様にお伝えしたいと思います。最終的に覚えなければならなかった知識の範囲は模試で出てくるような難解な問題の知識でなく、カラー板書の範囲内です。
しかし、本試験に臨むうえでどうしても出てくるのが過去問にない初登場の内容が聞かれる問題で、これは①の力だけでは解けません。②が重要で、これはみやざき先生に指導を受けるうえでの真のメリットであると思います。ただ、普段の学習では過去問を中心に繰り返すため、実感しにくいのではないかということです。つまり本試験で試すしかないのですが、敢えて言うなら、いざ本番に臨んで知識を捨てる勇気を持てるかどうかでしょうか?今回の問題で言えば、問20の宅造法、問22の諸法令問題についてはこの解き方でしか、正解に至る道はなかったのではないかと思えます。知識に頼った解き方ができない分、考え方のプロセスを自分で組み立てる必要があり、それが正しいかどうか、正解発表までは不安でたまりませんでしたが、答えが合っていた時の爽快感は何事にも代えられません。
出題される知識の内容はどこまでも細かくなり得るものであり、それと追いかけっこをしても、追いつけるはずがなく、やがて消耗してしまう。それよりは、法律ができた背景、目的、主旨を理解して問題文の内容がそれに合致しているのかを判断できるようになりましょう。先生が講義を通しておっしゃられたかったことの意味がこれなんじゃないかと感じられたという意味で、去年でなく今年の合格でよかったのだとはっきり思います。
自分の宅建試験への取り組みは年ごとに傾向を変えて現れる問題に、その都度翻弄されては落ちて勉強方法を修正することの繰り返しでした。その中でも変わることなく、常に応援して下さったみやざき先生のおかげで、法律知識ゼロの状態から、9割近くの高得点を得るまでにポテンシャルを引き上げて下さいました。法律の世界への入門として最初にみやざき先生のお教えに触れることができたのは宅建試験だけでなく、今後の仕事を考えるうえでも幸運でした。また、何よりも法律に関しては門外漢であった私に、法律は常識でできていることをわかりやすく丁寧に解説いただいた事で、高かった敷居を取り除いてくれたのも一生の財産になりました。今後の資格勉強や仕事への携わり方に学んだことを活かしていきます。
すでに、権利関係が難化していた頃の傾向と変わりつつあり、今後の試験もどこが難しく出てくるか益々読めないものになってきていると思います。これから受験される皆様に置かれましては、勉強の負担など大変でしょうが、どうか私や他の合格者の皆様がそうであったようにみやざき先生を信じてあきらめることなく、合格への道を追求していって頂きたいと思います。その中で、私の失敗談や挫折経験、その折に変えていった学習の取り組み内容など参考になる部分がございましたら、大いなる幸いです。最後にみやざき塾生らしく(笑)、図表に学習記録をまとめたものをお示しして、自らの体験記の締めとさせて頂きます。
大変長くなって申し訳ありませんでした。最後までお読みいただき、どうもありがとうございました。