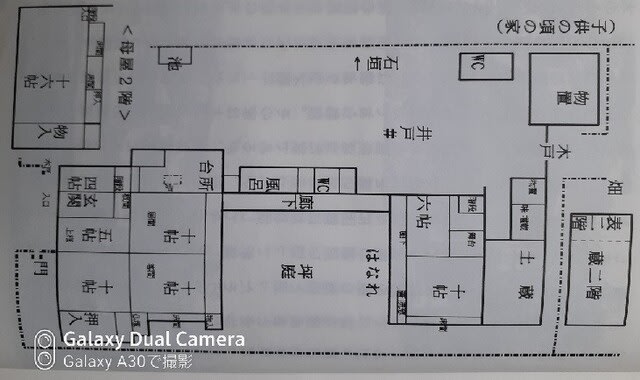「台所」
9帖分の広さでラワン材張り
その真ん中より北寄りに囲炉裏(ヒジロといった)
北側に造り付の戸棚・流し台
南にやや広く そこに卓袱台を置いて食事をした
*右の図は僕が書き起こしたが 遠い記憶で正確ではないかも


上は勿論 吹き抜けで太い煙突があった
氷の塊を一番上に入れて使う 冷蔵庫もあった
囲炉裏は火床を半月型の銅壺で囲み常時 湯を沸かし
上には自在鍵 一隅に飯炊き用の鉄の竈 其の対角に七輪が置いてあった
荒神様は西側の壁に東向きにお祀りした
「太鼓橋」
庭には座視に繋がる やや傾斜のかかった太鼓橋のような廊下があった
母屋から出ると すぐ左に「風呂場」 その向こうに「大小便所」があった
渡り廊下は坪庭側に手すりがあるのみで
戸は無いから 屋根があるだけで 戸外に等しいから
便所や風呂へは一端母屋から外に出ることになるわけだ
勿論 母屋から出て最初の柱に廊下全体の電灯のスウィッチがあった
*風呂は薪で沸かして 水はホ-スで入れていたと思います
廊下が少し傾斜していたように 風呂場の板の間(洗い場)も傾斜していた
余り 風呂に入ったという記憶が無い
というか本当に 小学校の2年生までは 病気がちで外で遊ぶ記憶が無い
小学校二年の時は 半年以上も休んでしまい
三年で東京に出てきたときに 二年生をもう一度やってはどうかと
進められたほどでした


風呂場の前は雪が降った時 スキ-をして遊んでいたから
案外と広い遊び場