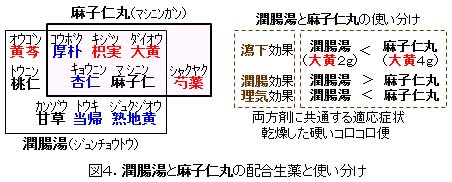次が二朮湯です。
これも先程話した半夏白朮天麻湯とほとんど同じです。
半夏白朮天麻湯は水の病証で、眩暈というような感じで来ているのですが、
そういうところに来ないで肩に来てしまったのです。
もともと太陰の人だから、どちらかといったらうつ的で静かな人が多いです。
塩分の取り方は多く、そして水が下げられなくなって、
でも耳まで上がって眩暈というところまでは水が上がらないで、
肩関節にたまるという状態です。
これは麻黄も附子も入っていないのですが、
四十肩、五十肩には本当によく効きます。
これだけで、麻黄剤も附子剤もいらないことが非常に多いのです。
要するに水を動かす薬と、後は漢方には珍しく鎮痛剤です。
本当に鎮痛剤が入っています。
まあNsaidsとどう違うのか、私もよく分からないのですが、
これらの薬はほとんど鎮痛以外にはあんまり使わないです。
それでも、どちらかといったら温める薬が多いから、
やはり西洋医学の鎮痛剤とはちょっと違うのでしょうね。
ほとんどニ朮湯以外で使っていないですね。
薬の特徴が私も解らないのです。でも本当に面白い薬です。
四十肩、五十肩といいますけれども、いつも言うように、
水の病証というのは、体の中の水分含量が変わるときに出てくる
みたいです。そして、今人間は何か若返ってきているのです。
四十肩、五十肩という言葉はもう合わないみたいです。
整形の先生自体がそう言います。
今どのくらいを中心に出てくるかというと、50代の後半から
70代の前半に出てきます。だから7掛けの法則なのでしょうね。
例えば60歳を7掛けすると42歳でしょう。
75歳を7掛けすると五十数歳になりますよね。
だから昔、四十肩、五十肩といわれていたからと、
その目で見ていると見誤ります。
肩関節の症状を特に40代で訴えてきた場合には、
逆に違う病気かもしれないと思った方がいいかもしれません。
リウマチ性のものだとか、労働過多で、
肩の筋肉の断裂などを起こしている例があります。
そうすると、これも鑑別は水が溢れているかどうかなのです。
痛みですから、やはり葛根湯五苓散でも痛みは完全には取れません。
まあ、葛根加朮附湯と五苓散だったらもうちょっといいかもしれません。
それで鑑別診断はできます。
少なくとも頓服させても肩の動きはよくなります。
これは、耳鍼が非常に簡単です。
太陰だから、肺と脾が虚していて、当然肝が上がりますので、
肝実脾虚肺虚で取ります。後は痛みですから、神門と枕を取ります。
それに肩の3点(鎖骨、頚、肩)を取ります。
そして炎症を抑え、水を引くために、内分泌と腎上腺を取ります。
最初、耳の鍼の場合は必ずその痛い側を取ります。
耳の鍼は同側の方がよく効きます。
体の鍼は、まあ極端なことを言ったら、
右肩を痛がっているときは左の足を重点的に取るのです。
体鍼で、陰陽五行で取る場合もありますし、
一林先生が来ているときに1回だけやりましたが、
反対側の足の王穴(おおけつ)というのを長い鍼で刺したりします。
非常に簡単です。
今の取り方で、その場で動かしてごらんと言って、動かなかったら
皆さんの診断が間違っているのです。
その場で動きます。その場で回るようになったと言います。
本当に難しいものではありません。
それで合ってしまえば、後はニ朮湯でいいわけです。
何の難しさもありません。
リウマチなどでしたら葛根加朮附湯や薏苡仁湯を
主にすることが多いのですが、
四十肩、五十肩に関してはまずほとんど、ニ朮湯だけで
やっているような気がします。どうしても冷えが強い人に
附子を加えたりすることはあります。
これも本当に際物の薬です。
逆に言えば他の疾患にはほとんど使いません。
例えばリウマチによるものとか、肩の使い過ぎによって起こる肩の痛みに
ニ朮湯を出しても全然効きません。
起こっている痛みの原因の性質が全く違いますので当たり前のことですね。
肩関節周囲炎という格好で来る方は結構多いですよ。
これは耳の鍼で、診断即治療につなげられる一番の症例です。
そして、こちらが胃を痛くするような重い病気でもないから、
案外気楽にやれます。
あまり重い病気を最初から何でもやろうとすると、
本当に胃が痛くなる思いをしますね。
体力の虚実を問わないと書いています。対症的にというか、
もう病名診断的に診て、水が溢れているなら、
それでほとんど投与して構わないし、そのときに脈を取ってみれば、
肺か脾かどちらかにその季節の脈、あるいは
季節の初めじゃないときには、最後まで残る脈があります。
だから、それで自分の診断技術を上げていってください。
別にあまり難しい話ではないのです。
第21回「さっぽろ下田塾」講義録
http://potato.hokkai.net/~acorn/sa_shimoda21.htm

https://www.kigusuri.com/kampo/kampo-care/019-22.html