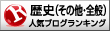「将棋にうつつを抜かしてるからなんじゃないの…!」
会うたびに、やせちゃってるョ…いえね、どうも顔だけがやせていくようだ…寝不足?…いやー、信長君より長生きしつつあるから、お年柄なンじゃないかねぇ…という友人との会話を、一家のものに伝え述べたら、そう言われた。
なにぃ、あたしゃ、将棋にうつつなんぞ抜かしてませんよ、戦国鍋TVにうつつを抜かしている、と言われりゃ、ああそうか~~と諸手を挙げて投降するけど。
うつつを抜かしたあまり本業に支障をきたして、好きになったものが自分の堕落の原因であるかのように、そう悪しざまに言われるのは絶対に嫌だから、私は意地でも、家では将棋を指さないのである。魂の先生にも誓った。
私が将棋に開眼したきっかけともなった先生と、ある時ちょっと言葉を交わす機会を得て…その直前に私は先生が、目隠し将棋で勝利する場に居合わせたので、先生の頭の中って一体どうなってるんでしょう…と愚にもつかない感想を述べた。
先生は自嘲気味に自分をして「将棋マシンですから」と、朗らかにおっしゃった。
その瞬間、私はグワシと心臓を鷲掴みにされ、チェブラーシカのようにバッタリ倒れた(チェブラーシカはロシア語でバッタリ倒れ屋さん、という意味らしい)。胸がキュンとするのと頭をハンマーで殴られるのが同体…クリスティ『オリエント急行殺人事件』の特定できない致命傷のような…とにかく桶狭間の今川義元が輿から転げ落ちたが如く、いわく言い難い衝撃を受けて、姉川の河原の屍か、顔半分ほど、水の流れにしばらく浸かっていた。
ああ…そうだ、そうなのだ。私も「三味線マシンですから」と、明るい太陽の下で、朗らかに言えるような人間にならないといけないのだ…それまで、どうしてもその先生に将棋を教えていただきたいと生半可な弟子入り志願のような淡い望みを抱いていたが、三味線マシンですから、と、ひと様に言えるその日まで、私は絶対に家では将棋を指さないぞと、お天道様に…八幡さまの弓矢に誓い、われに七難八苦を与え給えと、山中鹿之助スタイルで月に祈ったのだった。……ほんまでっせ。
私には出来ごころなんぞというものはない。常に本気だ。ほんの思いつき…はあるかもしれないけど。
そんなわけで、私は深く将棋に心奪われながらも、家のものから勘当を受けたことは一度もないのである。
「キュウリ切ってカンドウだ」という、このセリフ。今だと、旬のみずみずしい胡瓜を切ってみたら、うす緑があまりに美しくて感動した…なのかなぁ。そういえば昔、板前のバイトをしていた友人が、鍋パーティで「うざく和え」をつくってくれて、キュウリが見事に蛇腹に切ってあって、ものすごく感動したことがあったけど。
キュウリは、旧離。久離とも書く。簡単にいえば勘当されることですね。江戸時代は連座制だったので、親族の誰かが悪いことをすると、一族郎党、処罰される。それを回避するための家族法で、家出なんかしちゃった虞犯青少年を、年長者が縁を切って、あらかじめ奉行所に願い出て、久離帳というのに登録してもらえば、連帯責任を免れる。
田畑を放棄して江戸に流れてきた農民を、故郷に帰す「旧里帰農令(きゅうりきのうれい)」の旧里、ふるさとの意味とは、ちょと違う。
近松門左衛門の『冥途の飛脚』には、この「久離切って…」という言葉が、頻繁に出てくる。
私は心中物が好きではない。むしろ嫌いで、ヤサ男が遊ぶ金欲しさに使い込みした挙句、自分の非力さに、どうしょうどうしょう…と呟いているのを見ると、しっかりしろ!と後ろ頭を草履でひっぱたきたくなる性分だ。
で、文楽で近松特集が組まれると、勘弁してくれ…と妙に毛嫌いしていたのだが、先日、こいつあぁ宗旨を変えざァなるめぇ…という感動の名作を観た。
マーティ・グロス監督が1979年に製作した『冥途の飛脚』。三十年前の、先代、そして脂の乗り切った当代のお師匠さん方の芸もさることながら…男女間の愚かしい恋愛劇であるだけでなく、親子の情愛という普遍のテーマをも描いているのだ、ということに、私は突然気がついた。何回となく観た新口村であったのに、まったく分かっていなかったこの浄瑠璃の魅力を、私はマーティ監督の眼を通して、改めて知ることができたのだ。
実の父親が養子先の親に遠慮して、血を吐く態でその胸中を吐露する。こういう義理の立て方、というのは、欧米化した現代人には分からないだろうなぁ…。
不覚にも涙があふれそうになり、この、親子の情愛ってやつで、もう十数年前、焼け野のキギス、夜の鶴…忠臣蔵九段目で、客席のいちばん前で号泣して、舞台の菊五郎をたじろがせたことを想い出した。あの時の加古川本蔵は、今は亡き十七代目羽左衛門だった。
そして、この感動体験に続く五月の東京での文楽公演。
津駒大夫・寛治師匠の「新口村」に、私は号泣した。それまで熱演が際立って、どうしてか浮いた感じになってしまうことの多かった津駒大夫の語りを、空二(からに)の艶やかな音色だけで観客の魂を持っていく寛治師匠の三味線が、余すところなく受け止めていて、私はもう初めて、新口村でこんなにも泣いた。
義太夫における三味線と太夫は、どちらかが過分になっても成立しない、絶妙なバランスで成り立っている芸なのだと、改めて思い至った。
将棋にも、芸達者な受け師の先生がいらっしゃるけれども。
会うたびに、やせちゃってるョ…いえね、どうも顔だけがやせていくようだ…寝不足?…いやー、信長君より長生きしつつあるから、お年柄なンじゃないかねぇ…という友人との会話を、一家のものに伝え述べたら、そう言われた。
なにぃ、あたしゃ、将棋にうつつなんぞ抜かしてませんよ、戦国鍋TVにうつつを抜かしている、と言われりゃ、ああそうか~~と諸手を挙げて投降するけど。
うつつを抜かしたあまり本業に支障をきたして、好きになったものが自分の堕落の原因であるかのように、そう悪しざまに言われるのは絶対に嫌だから、私は意地でも、家では将棋を指さないのである。魂の先生にも誓った。
私が将棋に開眼したきっかけともなった先生と、ある時ちょっと言葉を交わす機会を得て…その直前に私は先生が、目隠し将棋で勝利する場に居合わせたので、先生の頭の中って一体どうなってるんでしょう…と愚にもつかない感想を述べた。
先生は自嘲気味に自分をして「将棋マシンですから」と、朗らかにおっしゃった。
その瞬間、私はグワシと心臓を鷲掴みにされ、チェブラーシカのようにバッタリ倒れた(チェブラーシカはロシア語でバッタリ倒れ屋さん、という意味らしい)。胸がキュンとするのと頭をハンマーで殴られるのが同体…クリスティ『オリエント急行殺人事件』の特定できない致命傷のような…とにかく桶狭間の今川義元が輿から転げ落ちたが如く、いわく言い難い衝撃を受けて、姉川の河原の屍か、顔半分ほど、水の流れにしばらく浸かっていた。
ああ…そうだ、そうなのだ。私も「三味線マシンですから」と、明るい太陽の下で、朗らかに言えるような人間にならないといけないのだ…それまで、どうしてもその先生に将棋を教えていただきたいと生半可な弟子入り志願のような淡い望みを抱いていたが、三味線マシンですから、と、ひと様に言えるその日まで、私は絶対に家では将棋を指さないぞと、お天道様に…八幡さまの弓矢に誓い、われに七難八苦を与え給えと、山中鹿之助スタイルで月に祈ったのだった。……ほんまでっせ。
私には出来ごころなんぞというものはない。常に本気だ。ほんの思いつき…はあるかもしれないけど。
そんなわけで、私は深く将棋に心奪われながらも、家のものから勘当を受けたことは一度もないのである。
「キュウリ切ってカンドウだ」という、このセリフ。今だと、旬のみずみずしい胡瓜を切ってみたら、うす緑があまりに美しくて感動した…なのかなぁ。そういえば昔、板前のバイトをしていた友人が、鍋パーティで「うざく和え」をつくってくれて、キュウリが見事に蛇腹に切ってあって、ものすごく感動したことがあったけど。
キュウリは、旧離。久離とも書く。簡単にいえば勘当されることですね。江戸時代は連座制だったので、親族の誰かが悪いことをすると、一族郎党、処罰される。それを回避するための家族法で、家出なんかしちゃった虞犯青少年を、年長者が縁を切って、あらかじめ奉行所に願い出て、久離帳というのに登録してもらえば、連帯責任を免れる。
田畑を放棄して江戸に流れてきた農民を、故郷に帰す「旧里帰農令(きゅうりきのうれい)」の旧里、ふるさとの意味とは、ちょと違う。
近松門左衛門の『冥途の飛脚』には、この「久離切って…」という言葉が、頻繁に出てくる。
私は心中物が好きではない。むしろ嫌いで、ヤサ男が遊ぶ金欲しさに使い込みした挙句、自分の非力さに、どうしょうどうしょう…と呟いているのを見ると、しっかりしろ!と後ろ頭を草履でひっぱたきたくなる性分だ。
で、文楽で近松特集が組まれると、勘弁してくれ…と妙に毛嫌いしていたのだが、先日、こいつあぁ宗旨を変えざァなるめぇ…という感動の名作を観た。
マーティ・グロス監督が1979年に製作した『冥途の飛脚』。三十年前の、先代、そして脂の乗り切った当代のお師匠さん方の芸もさることながら…男女間の愚かしい恋愛劇であるだけでなく、親子の情愛という普遍のテーマをも描いているのだ、ということに、私は突然気がついた。何回となく観た新口村であったのに、まったく分かっていなかったこの浄瑠璃の魅力を、私はマーティ監督の眼を通して、改めて知ることができたのだ。
実の父親が養子先の親に遠慮して、血を吐く態でその胸中を吐露する。こういう義理の立て方、というのは、欧米化した現代人には分からないだろうなぁ…。
不覚にも涙があふれそうになり、この、親子の情愛ってやつで、もう十数年前、焼け野のキギス、夜の鶴…忠臣蔵九段目で、客席のいちばん前で号泣して、舞台の菊五郎をたじろがせたことを想い出した。あの時の加古川本蔵は、今は亡き十七代目羽左衛門だった。
そして、この感動体験に続く五月の東京での文楽公演。
津駒大夫・寛治師匠の「新口村」に、私は号泣した。それまで熱演が際立って、どうしてか浮いた感じになってしまうことの多かった津駒大夫の語りを、空二(からに)の艶やかな音色だけで観客の魂を持っていく寛治師匠の三味線が、余すところなく受け止めていて、私はもう初めて、新口村でこんなにも泣いた。
義太夫における三味線と太夫は、どちらかが過分になっても成立しない、絶妙なバランスで成り立っている芸なのだと、改めて思い至った。
将棋にも、芸達者な受け師の先生がいらっしゃるけれども。