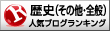※まずは、話の前段として、昨年11月11日付で書き起こしつつもアップできずにいた原稿からお届けすることをお許しくださいませ。
このところの私のひそかな愉しみは狂言方、山本東次郎さんの追っかけである。
山本東次郎さんは、昭和12年、大蔵流の狂言方のお家に生まれた。我が愛する杉並能楽堂にお住まいである。
日和が好い折の催し物は必ず束になってやってきて(世間的な好日は1か月に4日しかない日曜日、そこに夥しい量の集中するという悲劇…)、生業とする演奏会と重なったりして、自分が見たい聞きたい…!!と思う舞台にはなかなか行けない。それを潜り抜けて訪う心の充電、充足時間は甘露のひと時である。
能楽には三味線がないので、とても癒される。どうしても三味線が付随する舞台だと職業意識で聴いてしまうので、純粋に趣味的な立場で味わえることがない。
そして私の大好きな、古き美しき、やまとかなぶみ…日本の言葉の数々。
(能とのかかわりは本稿「蟇股(かえるまた)」をご参照いただけましたら嬉しく存じます)
20世紀はぽちらぽちらと、21世紀になってからは足繁く通う能楽堂。私の個人的趣味とは別のところに、昭和から平成にかけて狂言ブームというものが何度かあった。しかし、私にはどの狂言方の舞台もさして面白く思えなかった。ゆえに観能の合間の休憩時間として席を外していることが多かった。それが、である。
西暦2000年を過ぎて間もなくのこと、千駄ヶ谷の国立能楽堂で(当時は、国立らしく安価で能と狂言1番ずつという手軽に鑑賞できるシステムがあった)、山本家の「土筆(どひつ)」に廻りあった。
かつてないほど、私は狂言を面白く感じた。
それ以来、山本東次郎さんの名を目にすると、あまり触手の動かない会でも出掛けていくようになったのだ。
※※さて、ここまでが、「月見座頭の展開」というタイトルで下書き保存していた部分であります。何を書きたかったのかは、はっきりこの頭に蘇ってきたのですが、きちんと纏め上げるには時間がちょと足りない。なぜ足りないかといえば、今日の余韻をまずは書き留めたい、というわけで、「霜夜狸」のお話をすることをお許し下さいませ。
東次郎さんは、虚空に世界を創出する名手、魔術師である。
あるときの杉並能楽堂での「木六駄」で私は、東次郎さんの太郎冠者が指す手に、曇天にちらほらと舞う小雪を見た。
近い記憶では去る6月観た「鎌腹」の道行でも、東次郎さんが科白で景色を口にするとき、魔法のように私の目の前には同じ風景が広がるのだ。
これは同じ科白を、日々弛まぬ鍛錬をして精進している最中の壮年期のものでもなかなか現出できない、修業とともにあるご自身が、年を重ねて涵養され、身の内に積み重なった部分からそれと巧まずして顕れてくるものなのだと思う。
うららかな11月3日文化の日、冠婚葬祭のすべてを家人に託して、私はいそいそと丸ノ内線に乗り換えた。
杉並能楽堂での山本会。本日は狂言が3番。
最後に上演された「霜夜狸」は、原作が宇野信夫(実はもう25年以前、歌舞伎座と前進座とで偶々近い期間に上演された「怪談蚊喰鳥」の印象深い余談があるのだけれど、それはまたの機会に)、それを故あって一昨年新作として東次郎さんが改作、初演なさったものであった。今回二度目の上演である。私は今日が初見だった。
霜月の寒い晩、野守(山番)の東次郎さんのところに、囲炉裏の火に当たらせてくれと狸が訪うてくる。そこで山守は20年前に戦で亡くなった息子に化けることを所望し、平重盛が狸を助けた話などをしつつ、四月一冬を仲良く過ごす。日が温み芽吹き時の春になると狸は仲間のところへ帰って行った。そしてまた霜月の凍える晩にやって来て、山守の小屋で一冬を過ごす。
こうして、山守老人が太郎と呼ぶ狸と心通わせるようになって三度春が過ぎ、四度目の木枯らしが吹く冬を迎えたが、今日来るか明日来るかと待つうち、太郎狸は来ぬまま、とうとう春になってしまった。
どうしたかなぁ…と太郎狸を案じつつ、清々しい春の気配を含む若々しい野山に出で、風に舞う花びらを見つける。おや、こんなところに桜の木があったかしらん、と、のどかな春の訪いをことほいで、東次郎さんの山守は、古今集の紀貫之の歌、
吹く風と 谷の水とし なかりせば 深山(みやま)隠れの 花を見ましや
を口ずさみながら、野山の谷の湧き水を汲むのである。
そのとき私は、たぶん、志ん生を呼んでは大津絵を聞いて号泣していたという晩年の小泉信三になっていた。
もちろん、東次郎さんは別に声を震わせるでもなく悲しい顔をするでもなく、きちんと狂言の様式にのっとって、ただ古歌を詠いながら、淡々と温水を汲むのである。
その、溌溂とした朗らかな春の日差しの中にあって、老人が独り抱え込む壮絶な孤独感を思うと、私はたまらなくなって泣いてしまったのだ。
一度息子を失い、今また息子の化身でもある太郎狸をも失ってしまった…と思う老人の絶望感。
明るい春の光を浴びながら水を汲む、その対比の中で老人の心の無残は酷なほど際立ち、私は終演後またまた化粧室にて顔を直す羽目になった。
くだくだしい心理描写や説明の科白を持たない狂言だからこそ、なおさら、観る者の胸に迫ってくるのだ。
終盤、物語はさらなる展開を見せ、数多い狂言の番組の中でも、自分は能よりの狂言が好きである、と東次郎さんがおっしゃった面白い趣向で、見所の者にさまざまな想いを残して終演する。
杉並能楽堂の蟇股は、桃太郎に似ている。
我が幼年期よりの心の友・武井武雄の、桃から勢いよく飛び出したところの桃太郎の絵に…それが正しい記憶なのかは不明であるが、両手両足を天の字にかっぱと広げて、現世に飛び出た姿によく似ているのである。
この能舞台を太平洋戦争の空襲から死守された御父君とのエピソードを、山本会や講演などで伺っていた私には、ここを揺籃として育ってこられた東次郎さんの「霜夜狸」を、この杉並能楽堂で見られたことは、さらに一入の感慨でもあった。
このところの私のひそかな愉しみは狂言方、山本東次郎さんの追っかけである。
山本東次郎さんは、昭和12年、大蔵流の狂言方のお家に生まれた。我が愛する杉並能楽堂にお住まいである。
日和が好い折の催し物は必ず束になってやってきて(世間的な好日は1か月に4日しかない日曜日、そこに夥しい量の集中するという悲劇…)、生業とする演奏会と重なったりして、自分が見たい聞きたい…!!と思う舞台にはなかなか行けない。それを潜り抜けて訪う心の充電、充足時間は甘露のひと時である。
能楽には三味線がないので、とても癒される。どうしても三味線が付随する舞台だと職業意識で聴いてしまうので、純粋に趣味的な立場で味わえることがない。
そして私の大好きな、古き美しき、やまとかなぶみ…日本の言葉の数々。
(能とのかかわりは本稿「蟇股(かえるまた)」をご参照いただけましたら嬉しく存じます)
20世紀はぽちらぽちらと、21世紀になってからは足繁く通う能楽堂。私の個人的趣味とは別のところに、昭和から平成にかけて狂言ブームというものが何度かあった。しかし、私にはどの狂言方の舞台もさして面白く思えなかった。ゆえに観能の合間の休憩時間として席を外していることが多かった。それが、である。
西暦2000年を過ぎて間もなくのこと、千駄ヶ谷の国立能楽堂で(当時は、国立らしく安価で能と狂言1番ずつという手軽に鑑賞できるシステムがあった)、山本家の「土筆(どひつ)」に廻りあった。
かつてないほど、私は狂言を面白く感じた。
それ以来、山本東次郎さんの名を目にすると、あまり触手の動かない会でも出掛けていくようになったのだ。
※※さて、ここまでが、「月見座頭の展開」というタイトルで下書き保存していた部分であります。何を書きたかったのかは、はっきりこの頭に蘇ってきたのですが、きちんと纏め上げるには時間がちょと足りない。なぜ足りないかといえば、今日の余韻をまずは書き留めたい、というわけで、「霜夜狸」のお話をすることをお許し下さいませ。
東次郎さんは、虚空に世界を創出する名手、魔術師である。
あるときの杉並能楽堂での「木六駄」で私は、東次郎さんの太郎冠者が指す手に、曇天にちらほらと舞う小雪を見た。
近い記憶では去る6月観た「鎌腹」の道行でも、東次郎さんが科白で景色を口にするとき、魔法のように私の目の前には同じ風景が広がるのだ。
これは同じ科白を、日々弛まぬ鍛錬をして精進している最中の壮年期のものでもなかなか現出できない、修業とともにあるご自身が、年を重ねて涵養され、身の内に積み重なった部分からそれと巧まずして顕れてくるものなのだと思う。
うららかな11月3日文化の日、冠婚葬祭のすべてを家人に託して、私はいそいそと丸ノ内線に乗り換えた。
杉並能楽堂での山本会。本日は狂言が3番。
最後に上演された「霜夜狸」は、原作が宇野信夫(実はもう25年以前、歌舞伎座と前進座とで偶々近い期間に上演された「怪談蚊喰鳥」の印象深い余談があるのだけれど、それはまたの機会に)、それを故あって一昨年新作として東次郎さんが改作、初演なさったものであった。今回二度目の上演である。私は今日が初見だった。
霜月の寒い晩、野守(山番)の東次郎さんのところに、囲炉裏の火に当たらせてくれと狸が訪うてくる。そこで山守は20年前に戦で亡くなった息子に化けることを所望し、平重盛が狸を助けた話などをしつつ、四月一冬を仲良く過ごす。日が温み芽吹き時の春になると狸は仲間のところへ帰って行った。そしてまた霜月の凍える晩にやって来て、山守の小屋で一冬を過ごす。
こうして、山守老人が太郎と呼ぶ狸と心通わせるようになって三度春が過ぎ、四度目の木枯らしが吹く冬を迎えたが、今日来るか明日来るかと待つうち、太郎狸は来ぬまま、とうとう春になってしまった。
どうしたかなぁ…と太郎狸を案じつつ、清々しい春の気配を含む若々しい野山に出で、風に舞う花びらを見つける。おや、こんなところに桜の木があったかしらん、と、のどかな春の訪いをことほいで、東次郎さんの山守は、古今集の紀貫之の歌、
吹く風と 谷の水とし なかりせば 深山(みやま)隠れの 花を見ましや
を口ずさみながら、野山の谷の湧き水を汲むのである。
そのとき私は、たぶん、志ん生を呼んでは大津絵を聞いて号泣していたという晩年の小泉信三になっていた。
もちろん、東次郎さんは別に声を震わせるでもなく悲しい顔をするでもなく、きちんと狂言の様式にのっとって、ただ古歌を詠いながら、淡々と温水を汲むのである。
その、溌溂とした朗らかな春の日差しの中にあって、老人が独り抱え込む壮絶な孤独感を思うと、私はたまらなくなって泣いてしまったのだ。
一度息子を失い、今また息子の化身でもある太郎狸をも失ってしまった…と思う老人の絶望感。
明るい春の光を浴びながら水を汲む、その対比の中で老人の心の無残は酷なほど際立ち、私は終演後またまた化粧室にて顔を直す羽目になった。
くだくだしい心理描写や説明の科白を持たない狂言だからこそ、なおさら、観る者の胸に迫ってくるのだ。
終盤、物語はさらなる展開を見せ、数多い狂言の番組の中でも、自分は能よりの狂言が好きである、と東次郎さんがおっしゃった面白い趣向で、見所の者にさまざまな想いを残して終演する。
杉並能楽堂の蟇股は、桃太郎に似ている。
我が幼年期よりの心の友・武井武雄の、桃から勢いよく飛び出したところの桃太郎の絵に…それが正しい記憶なのかは不明であるが、両手両足を天の字にかっぱと広げて、現世に飛び出た姿によく似ているのである。
この能舞台を太平洋戦争の空襲から死守された御父君とのエピソードを、山本会や講演などで伺っていた私には、ここを揺籃として育ってこられた東次郎さんの「霜夜狸」を、この杉並能楽堂で見られたことは、さらに一入の感慨でもあった。