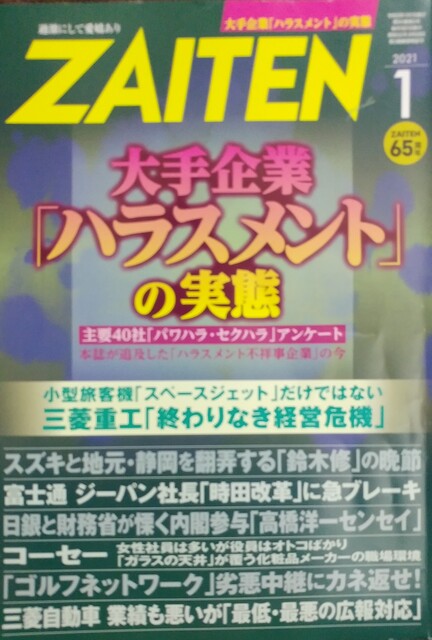ブラックバイトといえば、学生や若いフリーターがターゲットになっていたが、最近では中高年の労働市場でもこの言葉が注目され始めた。薄給で過酷な労働を強いられる50~60代の姿を追った! 本人が告白した驚きの労働環境とは!?
◆暴力と怒号が支配する職場! フルコミ営業職の新聞拡張員
●Mさん・男性(51歳)埼玉県/前職:印刷会社営業
●前職の年収:550万円/現在の年収:320万円
胃がんになって手術し、退院したら前職の印刷会社をクビになっていたというMさん(51歳)。
「体は多少、弱くなってもまだまだ営業職でやれる、という自信があり、ブラックを承知で新聞拡張団の世界に飛び込みましたが、想像以上に壮絶でした。同時期に28人入って、1年後に残ったのは僕ともう1人のみ。理由は激しすぎるノルマ制です」
Mさんの拡張団は、刺青入りと元営業職のリストラ中高年の混成部隊。社会保障も福利厚生も一切ないフルコミ営業職だ。
「上げるカード(契約数)の少ない新人に対して、団長の殴る蹴るは日常茶飯事。僕の場合、週間目標を達成できなかったとき、剃れないバリカンで頭を丸坊主にされました。私物を燃やされたり、真夏に分厚いジャージ着せられて『汗かいて根性入れ直してこい!』なんてやられた者もいる」
リストラ中高年が飛び込んだ「新聞拡張員のブラックな世界」
◆暴力と怒号が支配する職場! フルコミ営業職の新聞拡張員
●Mさん・男性(51歳)埼玉県/前職:印刷会社営業
●前職の年収:550万円/現在の年収:320万円
胃がんになって手術し、退院したら前職の印刷会社をクビになっていたというMさん(51歳)。
「体は多少、弱くなってもまだまだ営業職でやれる、という自信があり、ブラックを承知で新聞拡張団の世界に飛び込みましたが、想像以上に壮絶でした。同時期に28人入って、1年後に残ったのは僕ともう1人のみ。理由は激しすぎるノルマ制です」
Mさんの拡張団は、刺青入りと元営業職のリストラ中高年の混成部隊。社会保障も福利厚生も一切ないフルコミ営業職だ。
「上げるカード(契約数)の少ない新人に対して、団長の殴る蹴るは日常茶飯事。僕の場合、週間目標を達成できなかったとき、剃れないバリカンで頭を丸坊主にされました。私物を燃やされたり、真夏に分厚いジャージ着せられて『汗かいて根性入れ直してこい!』なんてやられた者もいる」
リストラ中高年が飛び込んだ「新聞拡張員のブラックな世界」