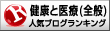花粉症(かふんしょう、hay fever / pollen allergy / pollen disease, 医 pollinosis または pollenosis )とはI型アレルギー(いちがた-)に分類される疾患の一つであり、植物の花粉が、鼻や目などの粘膜に接触することによって引き起こされる発作性反復性のくしゃみ、鼻水、鼻詰まり、目のかゆみなどの一連の症状が特徴的な症候群のことである。枯草熱(こそうねつ)ともいわれる。
そうした症状のうち、くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどはアレルギー性鼻炎(鼻アレルギー)の症状であり、花粉の飛散期に一致して症状がおこるため、季節性アレルギー性鼻炎(対:通年性アレルギー性鼻炎)に分類され、その代表的なものとなっている。目のかゆみや流涙などはアレルギー性結膜炎の症状であり、鼻炎同様に季節性アレルギー性結膜炎に分類される。
広義には花粉によるアレルギー症状すべてをさすこともあるが、一般的には上記のように鼻および目症状を主訴とするものを指す。狭義では鼻症状のみを指し、目症状は結膜花粉症(または花粉性結膜炎)と呼ぶこともある。皮膚症状であれば花粉症皮膚炎(または花粉皮膚炎)、喘息であれば花粉喘息などと呼ぶことが多い。
現在の日本ではスギ花粉によるものが大多数であり、単に花粉症といった場合、スギ花粉症のことを指していることが多い。そのため、本項目の説明もスギ花粉症についてが主となることに注意されたい。
注:hay fever = 枯草熱、pollinosis = 花粉症というように、古語・現代語、一般名・疾病名、の観点で呼び分けることもある。枯草熱も医薬品等の効能に表記されるれっきとした医学(医療)用語であるが、ここでは花粉症で統一する。なお、pollen allergy は花粉アレルギー、pollen disease は花粉病(花粉による疾患)の意である。
歴史
世界史
古代エジプトにおいてハチアレルギー(アナフィラキシーショック)と思われる事例が記録されてはいるが、同じアレルギー疾患の一種である花粉症がいつ頃から出現していたかについては、花粉が肉眼で見ることができないこともあって明確には判っていない。紀元前500年ごろのヒポクラテスの著書『空気、水、場所について』の第三節にさまざまな風土病が述べられているが、季節と風に関係しており、体質が影響し、転地療養が効果的であるということから、現在でいうアレルギー(季節的アレルギー)の機序を考えてよさそうなもの、すなわち現在でいう花粉症もあるかもしれないとの考えもある。ローマ帝国時代の医師ガレヌス(紀元前130年~200年)も花粉症らしい疾患について述べており、紀元前100年ごろの中国の記録にも、春になると鼻水および鼻詰まりがよくあるとのことが示されているという。西暦1000年ごろのアラビアの医師によって、花粉症らしい疾患とその治療法が記録されているともいわれる。
より近代医学的な記録で最古のものは、1565年(一説には1533年)のイタリアの医師 Leonardo Botallus によるものとされる。「バラ熱(Rose cold または Rose fever)」と呼ばれる症状で、記録によれば、その患者はバラの花の香りをかぐとくしゃみやかゆみ、頭痛などの症状をおこすという。原則的にバラは花粉を飛散させないため、花粉症であるとはいいがたいが、現在でも Rose fever は「晩春から初夏の鼻炎」様の意味で Hay fever 同様に用いられることがある。すなわち、バラの花が咲くころに飛散する他の植物花粉による症状であった、あるいはそれも含まれていたことは否定できない。
真の花粉症の最初の臨床記録は、1819年にイギリスの John Bostock が、春・秋の鼻症状、喘息、流涙など、牧草の干し草と接触することで発症すると考えられていた Hay fever と呼ばれる夏風邪様症状について報告したものである。彼自身も長年にわたって症状に苦しめられたというが、有効な治療法は発見できなかったという。ちなみに、彼は最初これを夏季カタルと呼んだ。発熱(fever)は主要な症状ではないので、粘膜の炎症を示すカタルのほうが適切ではあった。この発表後、しばらくの間この症状は「Bostockのカタル」と呼ばれたといわれる(なお、 Hay fever は枯草熱と訳されているが、字義どおり受け取るのであれば、干し草熱のほうが適切であった。Hey とはイネ科の牧草 grass の干し草を指すからである)。そして1831年、同じくイギリスの J.Elliotson により、証明はなされなかったが花粉が原因であろうとの推定がなされた。
その後、イギリスの Charles H. Blackley によって、 Hay fever は気温の変化や花粉が発する刺激性のにおいや毒素などが原因であろうと考えられていた点などが、実験的に否定された。空中花粉の測定、鼻誘発試験や皮膚試験など、現在でも通用する試験を行ってイネ科花粉症を実証し、遅発相反応にさえ言及した著書『枯草熱あるいは枯草喘息の病因の実験的研究』を1873年に著した。これにより Hay fever は Pollinosis (花粉症)と呼ばれるようになった( pollen は花粉のこと)。これらのことから、みずからも花粉症であった Blackley は花粉症の父と呼ばれている。しかし、アレルギーという概念が成立するには20世紀になるまで待たなければいけなかったため、この段階では花粉に過敏に反応する人とそうでない人がいるということのみしかわからなかった。
なお、北アメリカでブタクサが Hay fever の原因であると指摘した報告は1872年になされている。ブタクサは Hay ではないが、すでにその当時は現在でいう花粉症は Hay fever の名で定着していたと考えられる。
日本史
日本においては、1960年代に次々と報告されたブタクサ、カモガヤ、スギ、ヨモギなどによるものが花粉症の始まりである。しかし、その正確な出現時期は判っていない。
たとえばスギ花粉症の発見者である斎藤洋三(当時は東京医科歯科大学所属)は、1963年に鼻や目にアレルギー症状を呈する患者を多く診察したのが花粉症に気づくきっかけとなったというが、過去の記録を調べ、毎年同時期に患者が急増することを確認している。また、1989年に65歳以上の耳鼻咽喉科医師に対してアンケートを行った結果、初めてスギ花粉症と思われる患者に接したのは1945年以前であるとの回答が4.7%あったなど、総合的にみてスギ花粉症の「発見」以前に患者に接していた医師は回答者の4分の1に達したとの調査がある。さらに、高齢の患者を調べたところ、戦前の1940年以前に発症したとみられる患者もいた。
1935年、1939年に空中花粉の測定が行われ、空中花粉数は少なくないが花粉症の原因となる花粉はきわめて少ないと報告された。戦後、進駐軍の軍医により調査がなされ、気候風土などの関係により、日本でのブタクサおよびイネ科の花粉はアレルゲンとして重要ではないと結論した報告が1948年になされた。これらにより、日本における花粉症の研究および患者の発見・報告等が遅れたという指摘がある(ちなみに、1939年の米国帰国者の症例報告では、当地において「バラヒーバー」と診断されたと記録されている。前述の「バラ熱」のことである)。
1960年後半からおよそ10年は帰化植物であるブタクサによる花粉症が多かったが、1970年代中頃からスギ花粉症患者が急増した。特に関東地方共通のできごととして1976年に第1回目の大飛散があり、その後1979年、1982年にもスギ花粉の大量飛散と患者の大量発症があり、全国的ではないにしろ、ほぼこの時期に社会問題として認知されるに至った。
原則的に自然治癒は期待できないため、毎年のように患者数は累積し、現在では花粉症といえばスギ花粉症のことだと思われるほどになっている。花粉症のうちのおよそ80%はスギ花粉症といわれ、新たな国民病とも呼ばれる。
都市化と花粉症
1983年から1985年にかけての児童のアレルギー性鼻炎の疫学調査によって、都市化が進んでいる地域ほど患児が多いという結果が得られたことがある。1996年のスギ花粉症の有病率の調査でも、山村より都市部のほうが高いという結果が出ている。
他にも、山村などの郊外より都市部のほうが花粉症の発症者数が多く、また、山村部では感作率が高くとも発症者はそう多くないなどの調査結果もあるが、サンプルが少ないうえに、その原因をさぐるためのより深い研究などはなされていない。上記、あきる野市と大田区の比較(これにおける83年と85年という、調査年の違うデータをもとに「都市部のほうが多い」との論が展開されたこともある)でもわかるように、郊外のほうが花粉症有病率が高いというデータもあるなど一定しておらず、未だ評価は定まってはいない。
同一地域で考えれば、都市化が進むと患者が多くなる傾向は認められてはいる。それは土の地面が少なくなり、いったんコンクリートやアスファルト面に落ちた花粉が蓄積し、それが二次飛散することによって花粉への曝露が増え、発症者の増加や症状の悪化がおきたと考えても説明がつく。また、交通量が多いところは、車の通行によって路面の花粉が巻き上げられ、空中花粉数が多くなるという説も提唱されている。ビル風などの影響もあると考えられている。都市のヒートアイランド化や砂漠化(低湿度化)によって花粉や粉塵が飛散しやすくなっているとの指摘もある。ヒートアイランド化によっておきる上昇気流は、低層では周囲の花粉を都市部に吸い込む効果をもたらすとの見方もある。
ただし、こうしたメカニズムは、多くは確実には実証されてはいない。また、地域差や経年変化を解釈する場合、一般に郊外ほど都市化の波が遅れてやってくること、花粉量そのものの変化や患者数は累積するという点、近年は地域・地方ごとの生活レベルや環境の差が小さくなっていることもあって、こうした調査結果から一定の結論を導くことはむずかしい。さらにいえば、花粉飛散数の調査というのはいくつかの手法があり、特定の装置に落下・付着した花粉数を測定しても、それはいつまでも空中を漂い続ける花粉を測定していることにはならないことや、ビルの屋上などでの計測は、必ずしも市民が生活している環境中の花粉を測定していることにはならないことにも注意が必要である。
花粉症の症状
主な症状は、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみとされ、一般に花粉症の4大症状と呼ばれる(耳鼻科領域においては、目のかゆみを除外したものを3大症状と呼んでいる)。
しかし、ほかにも多様な症状があり、目の異物感や流涙、目やに、喉のかゆみや痛み、咳などもよくみられる。耳の奥のかゆみ、頭痛や頭重感、微熱やだるさなどの全身症状を呈する場合もある。口から入った花粉や花粉を含んだ鼻水を飲み込むことにより、消化器症状が出る場合もある。目の周りや目の下、首筋などによくみられる炎症などの皮膚症状は、花粉症皮膚炎と呼ばれることもある。
以下に、ある統計による花粉症の症状の頻度を示す。
くしゃみ 92.0%
水性鼻汁 86.0%
鼻閉 74.0%
眼症状 84.0%
咽頭かゆみ 34.0%
皮膚かゆみ 16.0%
喘鳴 08.0%
頭痛 12.0%
上記の統計は耳鼻咽喉科領域からみたものであり、眼科領域からみると、およそ75%が鼻症状を合併しているという。すなわち、目症状を呈している患者のうち、4人に1人は目症状のみであるとの報告もある。このように典型的ではない症状を呈する患者の診断はややむずかしくなる。
これら一連の症状によって、睡眠不足、集中力欠如、イライラ感、食欲不振等も生じてくる。うつなど心理的影響を呈する場合もある。鼻詰まりによってにおいがわからなくなることや、口呼吸をするため喉が障害されることも多い。後鼻漏と呼ばれる喉に流れる鼻汁により喉がいがいがする、咳や痰が出るなどのこともある。不適切にコンタクトレンズを使用している場合、巨大乳頭結膜炎などにもなり得る。とくに小児の場合、かゆみなどから鼻をいじることが多く、鼻血の原因になることも少なからずある。これらは二次的な症状である。
こうした一次的および二次的症状により、バイタリティー(生命力)は大きく低下し、QOL(クオリティー・オブ・ライフ)は障害される。とくにQOLに大きく影響するのは鼻詰まりである。
水のようなさらさらした鼻水と目のかゆみが特徴的であり、感染症である鼻風邪との鑑別点になる。鼻風邪であれば、一般的には目のかゆみはなく、数日のうちに鼻水は粘性の高いものになり、さらに黄色や緑など色のついたものとなる。また、屋外のほうが花粉が多いため、おのずと症状も強くなるという点も風邪との違いである。
患者により、くしゃみや鼻水がひどいタイプと、鼻詰まりがひどいタイプ、両方ともひどいタイプなどに分けられる。症状の程度も個人により異なる。そうした症状のタイプと重症度により、適した治療(薬剤)なども異なってくる。目の症状の重症度などによっても治療法は異なる。これらの重症度などはくしゃみの頻度などを花粉症日記に記録してスコア化することによって調べることができる。同じ花粉飛散量であっても、このように症状の程度が異なるほか、どの程度の花粉で症状が出るかの敏感さも個人によって異なる。
なお、花粉飛散量が2倍になったからといって、症状も2倍ひどくなるわけではない。簡単には、飛散量が1桁上がると症状は1段階ひどくなると思って大きな間違いではない。
多量の花粉に曝露されると症状も悪化するが、少量であっても連続すると重症化していく。
また、いったん最重症化すると、少々の花粉量の変化では症状は変化しなくなる傾向があり、花粉飛散期が終了しても、症状はなかなか改善しない。
花粉のアレルゲン性の高さも異なり、花粉の種類と量によっては、まれにアナフィラキシーショックを起こすこともある。重症者や、とくに喘息の既往症のある患者は、はげしい呼吸によって多量の花粉を吸引するおそれがあるような運動はなるべくさけるべきである(幸いにもスギ花粉のアレルゲン性はそう高くはない)。
目覚めのときに強く症状が出ることもあり、俗にモーニングアタックといわれる。就寝中に吸い込んだ花粉が目覚めとともに症状を引き起こしたり、自律神経の切り替えがスムーズにいかないのが、鼻粘膜における高まった過敏性とあいまって症状が出ると考えられている。緊張すると症状がおさまる、リラックスすると症状が出てくるなどのことも、自律神経のバランスの具合によって説明されている。リラックス時や就寝時には副交感神経が優位となるが、その場合に症状が出やすいという(なお、自律神経の影響を強く受ける、すなわち鼻における自律神経失調症ともいうべき症状は血管運動性鼻炎といい、一般に気温差などにより鼻水が多く出るのが特徴である。花粉症にこれが合併している場合もあるとの考えもある)。
副鼻腔炎などが合併することがあるので注意が必要である。これは風邪と同様に鼻汁が粘度の高いものになり、眉間や目の下など、顔の奥の部分に重い痛みなどを感じることが特徴であるが、そうした症状を感じないこともある。後鼻漏もおきやすい。後鼻漏による鼻水が気道に入ると気管支炎の原因ともなり得る。検査方法も適した薬剤も異なるので、症状が変化した場合には早めに医療機関に受診することがだいじである。とくに副鼻腔炎は小児に多いといわれる。
スギ花粉飛散の前から症状を呈する患者も多くいるが、実際にごく微量の花粉に反応している場合だけでなく、季節特有の乾燥や冷気によるものもあると考えられている。患者はそれらしい症状を感じるとすべて花粉のせいにしがちであるが、自己診断は禁物である。
花粉症の原因
花粉症は、患者が空中に飛散している植物の花粉と接触した結果、後天的に免疫を獲得し、その後再び花粉に接触することで過剰な免疫反応、すなわちアレルギー反応を起こすものである。アレルギーの中でも、IgE(免疫グロブリンE)と肥満細胞(マスト細胞)によるメカニズムが大きく関与する、即時型のI型アレルギーの代表的なものである。
ちなみに、当時レアギンと呼ばれていたものがIgEであることを発見したのは日本人の石坂公成、照子夫妻であり、1966年のことである。財団法人日本アレルギー協会により、発見日である2月20日は「アレルギーの日」と定められ、その前後1週間は「アレルギー週間」とされた。現在では、この週間に各地でアレルギーに関する講演会などさまざまな催しが行われている。
花粉症増加の原因
花粉症の患者では、原因植物の花粉に対するIgE量が多いことは明らかであり、これがアレルギーを起こす直接の原因である。しかしながら、花粉症の原因となる花粉と接触してもすべての人が花粉症になるわけではなく、IgEが多くても発症しない人がいる。またIgEの量と重症度とは必ずしも相関しない。なぜこうしたことがあるかについては、遺伝要因(遺伝的素因)や環境要因などさまざまな要因の関与が考えられている(すなわち花粉症は多因子疾患である)が、全貌は明らかになっていない。
遺伝要因については、広く体質(いわゆるアレルギー体質)と呼ばれるものが相当する。しかし広義の体質は、遺伝による体質と、出生後に後天的に獲得した体質とが混同されているため、これらは分離して考える必要がある。
アレルギーになりやすい遺伝的素因、すなわちIgEを産生しやすい体質は劣性遺伝すると考えられており、それを規定する候補遺伝子は染色体11qや5qなどに存在するといわれるが確証はない。こうした遺伝的要因については、IgE産生に関わるもののほか、各種のケミカルメディエーター遊離のしやすさや受容体の発現のしやすさの違いなども考えられている。どんな物質に対してアレルギーを起こすかということも、遺伝的に規定されているとの説もある。
環境要因については社会のあり方とも関係するため、さまざまな思惑による俗説が多く流布しているが、ここでは主に近年になって花粉症を含めたアレルギー人口が増加した原因を説明する説に触れる。特にスギ花粉症においてもっとも重要かつ第一義的な原因とされる、花粉飛散量そのものの増加という環境要因については、他の項にゆずる。
なお、花粉症についての調査ではないが、両親ともアレルギーではない場合に子どもがアレルギーになる率は26.7%、両親ともアレルギーの場合は57.4%、母親または父親がアレルギーだと44.8/44.1%との数字がある。他のいくつかの調査でもほぼ同様である。
僕は「アトピー」のせいか、「花粉症」に罹らない。でも「花粉症」の人を傍から見ていると、何かしてあげたい気持ちになる。「アトピーの患者の気持ちは罹った人しか分からない」のと同様、「花粉症」の人達の辛苦も身をもって体験していない僕にはどうしても分からない部分が出てくる。













そうした症状のうち、くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどはアレルギー性鼻炎(鼻アレルギー)の症状であり、花粉の飛散期に一致して症状がおこるため、季節性アレルギー性鼻炎(対:通年性アレルギー性鼻炎)に分類され、その代表的なものとなっている。目のかゆみや流涙などはアレルギー性結膜炎の症状であり、鼻炎同様に季節性アレルギー性結膜炎に分類される。
広義には花粉によるアレルギー症状すべてをさすこともあるが、一般的には上記のように鼻および目症状を主訴とするものを指す。狭義では鼻症状のみを指し、目症状は結膜花粉症(または花粉性結膜炎)と呼ぶこともある。皮膚症状であれば花粉症皮膚炎(または花粉皮膚炎)、喘息であれば花粉喘息などと呼ぶことが多い。
現在の日本ではスギ花粉によるものが大多数であり、単に花粉症といった場合、スギ花粉症のことを指していることが多い。そのため、本項目の説明もスギ花粉症についてが主となることに注意されたい。
注:hay fever = 枯草熱、pollinosis = 花粉症というように、古語・現代語、一般名・疾病名、の観点で呼び分けることもある。枯草熱も医薬品等の効能に表記されるれっきとした医学(医療)用語であるが、ここでは花粉症で統一する。なお、pollen allergy は花粉アレルギー、pollen disease は花粉病(花粉による疾患)の意である。
歴史
世界史
古代エジプトにおいてハチアレルギー(アナフィラキシーショック)と思われる事例が記録されてはいるが、同じアレルギー疾患の一種である花粉症がいつ頃から出現していたかについては、花粉が肉眼で見ることができないこともあって明確には判っていない。紀元前500年ごろのヒポクラテスの著書『空気、水、場所について』の第三節にさまざまな風土病が述べられているが、季節と風に関係しており、体質が影響し、転地療養が効果的であるということから、現在でいうアレルギー(季節的アレルギー)の機序を考えてよさそうなもの、すなわち現在でいう花粉症もあるかもしれないとの考えもある。ローマ帝国時代の医師ガレヌス(紀元前130年~200年)も花粉症らしい疾患について述べており、紀元前100年ごろの中国の記録にも、春になると鼻水および鼻詰まりがよくあるとのことが示されているという。西暦1000年ごろのアラビアの医師によって、花粉症らしい疾患とその治療法が記録されているともいわれる。
より近代医学的な記録で最古のものは、1565年(一説には1533年)のイタリアの医師 Leonardo Botallus によるものとされる。「バラ熱(Rose cold または Rose fever)」と呼ばれる症状で、記録によれば、その患者はバラの花の香りをかぐとくしゃみやかゆみ、頭痛などの症状をおこすという。原則的にバラは花粉を飛散させないため、花粉症であるとはいいがたいが、現在でも Rose fever は「晩春から初夏の鼻炎」様の意味で Hay fever 同様に用いられることがある。すなわち、バラの花が咲くころに飛散する他の植物花粉による症状であった、あるいはそれも含まれていたことは否定できない。
真の花粉症の最初の臨床記録は、1819年にイギリスの John Bostock が、春・秋の鼻症状、喘息、流涙など、牧草の干し草と接触することで発症すると考えられていた Hay fever と呼ばれる夏風邪様症状について報告したものである。彼自身も長年にわたって症状に苦しめられたというが、有効な治療法は発見できなかったという。ちなみに、彼は最初これを夏季カタルと呼んだ。発熱(fever)は主要な症状ではないので、粘膜の炎症を示すカタルのほうが適切ではあった。この発表後、しばらくの間この症状は「Bostockのカタル」と呼ばれたといわれる(なお、 Hay fever は枯草熱と訳されているが、字義どおり受け取るのであれば、干し草熱のほうが適切であった。Hey とはイネ科の牧草 grass の干し草を指すからである)。そして1831年、同じくイギリスの J.Elliotson により、証明はなされなかったが花粉が原因であろうとの推定がなされた。
その後、イギリスの Charles H. Blackley によって、 Hay fever は気温の変化や花粉が発する刺激性のにおいや毒素などが原因であろうと考えられていた点などが、実験的に否定された。空中花粉の測定、鼻誘発試験や皮膚試験など、現在でも通用する試験を行ってイネ科花粉症を実証し、遅発相反応にさえ言及した著書『枯草熱あるいは枯草喘息の病因の実験的研究』を1873年に著した。これにより Hay fever は Pollinosis (花粉症)と呼ばれるようになった( pollen は花粉のこと)。これらのことから、みずからも花粉症であった Blackley は花粉症の父と呼ばれている。しかし、アレルギーという概念が成立するには20世紀になるまで待たなければいけなかったため、この段階では花粉に過敏に反応する人とそうでない人がいるということのみしかわからなかった。
なお、北アメリカでブタクサが Hay fever の原因であると指摘した報告は1872年になされている。ブタクサは Hay ではないが、すでにその当時は現在でいう花粉症は Hay fever の名で定着していたと考えられる。
日本史
日本においては、1960年代に次々と報告されたブタクサ、カモガヤ、スギ、ヨモギなどによるものが花粉症の始まりである。しかし、その正確な出現時期は判っていない。
たとえばスギ花粉症の発見者である斎藤洋三(当時は東京医科歯科大学所属)は、1963年に鼻や目にアレルギー症状を呈する患者を多く診察したのが花粉症に気づくきっかけとなったというが、過去の記録を調べ、毎年同時期に患者が急増することを確認している。また、1989年に65歳以上の耳鼻咽喉科医師に対してアンケートを行った結果、初めてスギ花粉症と思われる患者に接したのは1945年以前であるとの回答が4.7%あったなど、総合的にみてスギ花粉症の「発見」以前に患者に接していた医師は回答者の4分の1に達したとの調査がある。さらに、高齢の患者を調べたところ、戦前の1940年以前に発症したとみられる患者もいた。
1935年、1939年に空中花粉の測定が行われ、空中花粉数は少なくないが花粉症の原因となる花粉はきわめて少ないと報告された。戦後、進駐軍の軍医により調査がなされ、気候風土などの関係により、日本でのブタクサおよびイネ科の花粉はアレルゲンとして重要ではないと結論した報告が1948年になされた。これらにより、日本における花粉症の研究および患者の発見・報告等が遅れたという指摘がある(ちなみに、1939年の米国帰国者の症例報告では、当地において「バラヒーバー」と診断されたと記録されている。前述の「バラ熱」のことである)。
1960年後半からおよそ10年は帰化植物であるブタクサによる花粉症が多かったが、1970年代中頃からスギ花粉症患者が急増した。特に関東地方共通のできごととして1976年に第1回目の大飛散があり、その後1979年、1982年にもスギ花粉の大量飛散と患者の大量発症があり、全国的ではないにしろ、ほぼこの時期に社会問題として認知されるに至った。
原則的に自然治癒は期待できないため、毎年のように患者数は累積し、現在では花粉症といえばスギ花粉症のことだと思われるほどになっている。花粉症のうちのおよそ80%はスギ花粉症といわれ、新たな国民病とも呼ばれる。
都市化と花粉症
1983年から1985年にかけての児童のアレルギー性鼻炎の疫学調査によって、都市化が進んでいる地域ほど患児が多いという結果が得られたことがある。1996年のスギ花粉症の有病率の調査でも、山村より都市部のほうが高いという結果が出ている。
他にも、山村などの郊外より都市部のほうが花粉症の発症者数が多く、また、山村部では感作率が高くとも発症者はそう多くないなどの調査結果もあるが、サンプルが少ないうえに、その原因をさぐるためのより深い研究などはなされていない。上記、あきる野市と大田区の比較(これにおける83年と85年という、調査年の違うデータをもとに「都市部のほうが多い」との論が展開されたこともある)でもわかるように、郊外のほうが花粉症有病率が高いというデータもあるなど一定しておらず、未だ評価は定まってはいない。
同一地域で考えれば、都市化が進むと患者が多くなる傾向は認められてはいる。それは土の地面が少なくなり、いったんコンクリートやアスファルト面に落ちた花粉が蓄積し、それが二次飛散することによって花粉への曝露が増え、発症者の増加や症状の悪化がおきたと考えても説明がつく。また、交通量が多いところは、車の通行によって路面の花粉が巻き上げられ、空中花粉数が多くなるという説も提唱されている。ビル風などの影響もあると考えられている。都市のヒートアイランド化や砂漠化(低湿度化)によって花粉や粉塵が飛散しやすくなっているとの指摘もある。ヒートアイランド化によっておきる上昇気流は、低層では周囲の花粉を都市部に吸い込む効果をもたらすとの見方もある。
ただし、こうしたメカニズムは、多くは確実には実証されてはいない。また、地域差や経年変化を解釈する場合、一般に郊外ほど都市化の波が遅れてやってくること、花粉量そのものの変化や患者数は累積するという点、近年は地域・地方ごとの生活レベルや環境の差が小さくなっていることもあって、こうした調査結果から一定の結論を導くことはむずかしい。さらにいえば、花粉飛散数の調査というのはいくつかの手法があり、特定の装置に落下・付着した花粉数を測定しても、それはいつまでも空中を漂い続ける花粉を測定していることにはならないことや、ビルの屋上などでの計測は、必ずしも市民が生活している環境中の花粉を測定していることにはならないことにも注意が必要である。
花粉症の症状
主な症状は、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみとされ、一般に花粉症の4大症状と呼ばれる(耳鼻科領域においては、目のかゆみを除外したものを3大症状と呼んでいる)。
しかし、ほかにも多様な症状があり、目の異物感や流涙、目やに、喉のかゆみや痛み、咳などもよくみられる。耳の奥のかゆみ、頭痛や頭重感、微熱やだるさなどの全身症状を呈する場合もある。口から入った花粉や花粉を含んだ鼻水を飲み込むことにより、消化器症状が出る場合もある。目の周りや目の下、首筋などによくみられる炎症などの皮膚症状は、花粉症皮膚炎と呼ばれることもある。
以下に、ある統計による花粉症の症状の頻度を示す。
くしゃみ 92.0%
水性鼻汁 86.0%
鼻閉 74.0%
眼症状 84.0%
咽頭かゆみ 34.0%
皮膚かゆみ 16.0%
喘鳴 08.0%
頭痛 12.0%
上記の統計は耳鼻咽喉科領域からみたものであり、眼科領域からみると、およそ75%が鼻症状を合併しているという。すなわち、目症状を呈している患者のうち、4人に1人は目症状のみであるとの報告もある。このように典型的ではない症状を呈する患者の診断はややむずかしくなる。
これら一連の症状によって、睡眠不足、集中力欠如、イライラ感、食欲不振等も生じてくる。うつなど心理的影響を呈する場合もある。鼻詰まりによってにおいがわからなくなることや、口呼吸をするため喉が障害されることも多い。後鼻漏と呼ばれる喉に流れる鼻汁により喉がいがいがする、咳や痰が出るなどのこともある。不適切にコンタクトレンズを使用している場合、巨大乳頭結膜炎などにもなり得る。とくに小児の場合、かゆみなどから鼻をいじることが多く、鼻血の原因になることも少なからずある。これらは二次的な症状である。
こうした一次的および二次的症状により、バイタリティー(生命力)は大きく低下し、QOL(クオリティー・オブ・ライフ)は障害される。とくにQOLに大きく影響するのは鼻詰まりである。
水のようなさらさらした鼻水と目のかゆみが特徴的であり、感染症である鼻風邪との鑑別点になる。鼻風邪であれば、一般的には目のかゆみはなく、数日のうちに鼻水は粘性の高いものになり、さらに黄色や緑など色のついたものとなる。また、屋外のほうが花粉が多いため、おのずと症状も強くなるという点も風邪との違いである。
患者により、くしゃみや鼻水がひどいタイプと、鼻詰まりがひどいタイプ、両方ともひどいタイプなどに分けられる。症状の程度も個人により異なる。そうした症状のタイプと重症度により、適した治療(薬剤)なども異なってくる。目の症状の重症度などによっても治療法は異なる。これらの重症度などはくしゃみの頻度などを花粉症日記に記録してスコア化することによって調べることができる。同じ花粉飛散量であっても、このように症状の程度が異なるほか、どの程度の花粉で症状が出るかの敏感さも個人によって異なる。
なお、花粉飛散量が2倍になったからといって、症状も2倍ひどくなるわけではない。簡単には、飛散量が1桁上がると症状は1段階ひどくなると思って大きな間違いではない。
多量の花粉に曝露されると症状も悪化するが、少量であっても連続すると重症化していく。
また、いったん最重症化すると、少々の花粉量の変化では症状は変化しなくなる傾向があり、花粉飛散期が終了しても、症状はなかなか改善しない。
花粉のアレルゲン性の高さも異なり、花粉の種類と量によっては、まれにアナフィラキシーショックを起こすこともある。重症者や、とくに喘息の既往症のある患者は、はげしい呼吸によって多量の花粉を吸引するおそれがあるような運動はなるべくさけるべきである(幸いにもスギ花粉のアレルゲン性はそう高くはない)。
目覚めのときに強く症状が出ることもあり、俗にモーニングアタックといわれる。就寝中に吸い込んだ花粉が目覚めとともに症状を引き起こしたり、自律神経の切り替えがスムーズにいかないのが、鼻粘膜における高まった過敏性とあいまって症状が出ると考えられている。緊張すると症状がおさまる、リラックスすると症状が出てくるなどのことも、自律神経のバランスの具合によって説明されている。リラックス時や就寝時には副交感神経が優位となるが、その場合に症状が出やすいという(なお、自律神経の影響を強く受ける、すなわち鼻における自律神経失調症ともいうべき症状は血管運動性鼻炎といい、一般に気温差などにより鼻水が多く出るのが特徴である。花粉症にこれが合併している場合もあるとの考えもある)。
副鼻腔炎などが合併することがあるので注意が必要である。これは風邪と同様に鼻汁が粘度の高いものになり、眉間や目の下など、顔の奥の部分に重い痛みなどを感じることが特徴であるが、そうした症状を感じないこともある。後鼻漏もおきやすい。後鼻漏による鼻水が気道に入ると気管支炎の原因ともなり得る。検査方法も適した薬剤も異なるので、症状が変化した場合には早めに医療機関に受診することがだいじである。とくに副鼻腔炎は小児に多いといわれる。
スギ花粉飛散の前から症状を呈する患者も多くいるが、実際にごく微量の花粉に反応している場合だけでなく、季節特有の乾燥や冷気によるものもあると考えられている。患者はそれらしい症状を感じるとすべて花粉のせいにしがちであるが、自己診断は禁物である。
花粉症の原因
花粉症は、患者が空中に飛散している植物の花粉と接触した結果、後天的に免疫を獲得し、その後再び花粉に接触することで過剰な免疫反応、すなわちアレルギー反応を起こすものである。アレルギーの中でも、IgE(免疫グロブリンE)と肥満細胞(マスト細胞)によるメカニズムが大きく関与する、即時型のI型アレルギーの代表的なものである。
ちなみに、当時レアギンと呼ばれていたものがIgEであることを発見したのは日本人の石坂公成、照子夫妻であり、1966年のことである。財団法人日本アレルギー協会により、発見日である2月20日は「アレルギーの日」と定められ、その前後1週間は「アレルギー週間」とされた。現在では、この週間に各地でアレルギーに関する講演会などさまざまな催しが行われている。
花粉症増加の原因
花粉症の患者では、原因植物の花粉に対するIgE量が多いことは明らかであり、これがアレルギーを起こす直接の原因である。しかしながら、花粉症の原因となる花粉と接触してもすべての人が花粉症になるわけではなく、IgEが多くても発症しない人がいる。またIgEの量と重症度とは必ずしも相関しない。なぜこうしたことがあるかについては、遺伝要因(遺伝的素因)や環境要因などさまざまな要因の関与が考えられている(すなわち花粉症は多因子疾患である)が、全貌は明らかになっていない。
遺伝要因については、広く体質(いわゆるアレルギー体質)と呼ばれるものが相当する。しかし広義の体質は、遺伝による体質と、出生後に後天的に獲得した体質とが混同されているため、これらは分離して考える必要がある。
アレルギーになりやすい遺伝的素因、すなわちIgEを産生しやすい体質は劣性遺伝すると考えられており、それを規定する候補遺伝子は染色体11qや5qなどに存在するといわれるが確証はない。こうした遺伝的要因については、IgE産生に関わるもののほか、各種のケミカルメディエーター遊離のしやすさや受容体の発現のしやすさの違いなども考えられている。どんな物質に対してアレルギーを起こすかということも、遺伝的に規定されているとの説もある。
環境要因については社会のあり方とも関係するため、さまざまな思惑による俗説が多く流布しているが、ここでは主に近年になって花粉症を含めたアレルギー人口が増加した原因を説明する説に触れる。特にスギ花粉症においてもっとも重要かつ第一義的な原因とされる、花粉飛散量そのものの増加という環境要因については、他の項にゆずる。
なお、花粉症についての調査ではないが、両親ともアレルギーではない場合に子どもがアレルギーになる率は26.7%、両親ともアレルギーの場合は57.4%、母親または父親がアレルギーだと44.8/44.1%との数字がある。他のいくつかの調査でもほぼ同様である。
僕は「アトピー」のせいか、「花粉症」に罹らない。でも「花粉症」の人を傍から見ていると、何かしてあげたい気持ちになる。「アトピーの患者の気持ちは罹った人しか分からない」のと同様、「花粉症」の人達の辛苦も身をもって体験していない僕にはどうしても分からない部分が出てくる。