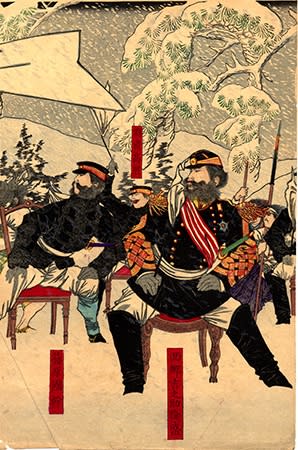
大河『西郷どん』☆「琉球出兵」と「薬売の越中さん」前編の続きです。
 | 島津斉彬 (シリーズ・実像に迫る11) |
| 松尾千歳 | |
| 戎光祥出版 |
上の「島津斉彬」は、尚古集成館館長 ・松尾千歳氏の著作です。
こちらも、とてもわかりやすくまとめられていますので、前回ご紹介いたしました芳即正氏の「島津斉彬」とともに、参考にさせていただきながら、話を進めたいと思います。
 | 島津斉彬 (人物叢書) |
| クリエーター情報なし | |
| 吉川弘文館 |
まず、なぜ、斉興はなかなか隠居しなかったのか?です。
答えは簡単です。
従三位になりたかったから!!!なんです。
前回、斉興には叔母にあたる茂姫が従一位で、夫の将軍と同じ高位だった、と書きました。臣下として、従一位は最高位です。
従三位にになれる大名は、清水徳川家(御三卿の一つ)くらい、でして、島津家は通常、従四位下まで、です。
ただし、例外として、江戸時代初期、藩主としては初代となります家久と、将軍御台所の父親でした重豪だけは、従三位にまで昇進していました。
昇進条件として、長年藩主の座にいたことがあげられることもあり、斉興としましては、できるだけ長く、藩主でいたかったわけなんです。
斉興は伯母が将軍御台所でしたし、祖父の重豪は将軍家に金をばらまいていましたし、おそらくはずいぶんと、将軍家から丁寧に扱われていたことと思われます。
そのせいなのか、なんなのか、「自分は高貴である」という思い込みが、激しかったんですね。
 | 近世日本の歴史叙述と対外意識 |
| クリエーター情報なし | |
| 勉誠出版 |
上の「近世日本の歴史叙述と対外意識」に「硫黄島の安徳天皇伝承と薩摩藩・島津斉興」という論文があります。
これによりますと、なんと! 斉興は祈る藩主だったんだそうです。
えーと、ですね。島津氏は、もともと鎌倉幕府の御家人であると同時に、京の近衛家(五摂家の一つ)にゆかりのある、惟宗氏であったといわれます。
ところが、いつしか島津家には、「実のところ島津の祖は源頼朝の落とし胤であった」、という伝説ができあがるんですね。
これはおそらく、徳川家が、源義重の子孫だと称し、清和源氏新田流を名乗ったことに、対抗したのではないかと推察されます。
清和源氏といいますのは、平安時代前期の清和天皇の子や孫たちのうち、臣籍降下して「源」(みなもと)を名乗った人々の子孫です。
その中から、武士団を率いる家が生まれ、平安時代後期の源義家(八幡太郎)は、武勇をうたわれ、新興武士勢力を形成しました。鎌倉幕府の源頼朝、室町幕府の足利尊氏と、武家政権を樹立した将軍は、二人とも義家の子孫です。そして、徳川家が名乗った新田氏は、足利氏と祖先を同じくしていまして、徳川家も結局、八幡太郎の子孫だと自称したわけです。
で、ですね。源頼朝は八幡太郎の直系、嫡流の子孫でして、史実として頼朝以降、直系は絶えましたが、もしも落とし胤の子孫がいたとすれば、足利や新田よりも、武家の棟梁を名乗るにふさわしい、という物語が成立するんですね。
それどころか!!! 島津家に極秘に伝わったとされる話では、です。なんと!!! 「皇祖ニニギノミコトは、三種の神器とともに祈祷の秘法を授かって、天孫降臨し、歴代天皇は代々、皇位継承のたびにそれを伝えていたが、清和天皇は、生後3ヶ月で即位した陽成天皇が粗暴であることを憂えて、清和源氏の祖である皇子に秘法を伝え、秘法は天皇家を離れ、源家の正統が伝えるものとなった。島津家は源家の正統であるがゆえに、代々当主が秘法を伝え、修業してきたのであり、わたし(斉興)もそうしているのである」ということでして、これでは、「島津家は徳川家より上」どころか、「現在の天皇よりも、島津家こそが正統に皇位を継承する資格がある!」と、言っているに等しくないですか?
こういったことが実は、斉興が書いた文書にあるのだそうでして、もうもう、お口あんぐり、です。
まあ、ですね。天孫降臨から神武東征までの日本神話は、島津家の勢力圏である南九州が舞台ですけどねえ。それにいたしましても。
天皇のお役目は、かなり昔から、国家安泰のために祈ることだと認識されていまして、斉興の認識では、薩摩藩主こそがその祈りの主体であるべき、ということに、必然的になるわけです。
ところがこの斉興の自己評価と、せいぜいが従四位下という実際の朝廷での地位には、大きな乖離があります。
「だからせめて従三位に!!!」って、ことだったらしいのですが。
もうね、なんといいますか。
うーん。いや、こうなってきますと、ドラマの島津斉興は、かなりイメージがちがいます。
鹿賀丈史よりも、いまは亡き平幹二朗が似合ってた感じですねえ。
平幹二朗が斉興で、斉彬が息子の平岳大だと、イメージぴったり、だったんですけどねえ。
どうも私、渡辺謙の斉彬というのも、ピンときません。野性的すぎて、品がないんですよねえ。
せめて、平岳大の斉彬だけでも見たかったなあ、と。
さて。では、お由羅騒動とは、いったいなんだったのか?です。
一言でいえば、琉球開国問題をきっかけとした、斉興、斉彬の親子喧嘩です。
そして、琉球開国問題がなぜ起きたか、といえば、アヘン戦争の結果、西欧諸国が清国に拠点を得たからです。
アヘン戦争が起こる3年前、イギリスでは、若きヴィクトリア女王が即位しました。
リーズデイル卿とジャパニズム vol8 赤毛のいとこに書いた時期でして、幕末、日本で活躍するイギリス外交官・アルジャーノン・バートラム・ミットフォードをはじめ、土方歳三、五代友厚、井上馨、徳川慶喜、桐野利秋、後藤象次郎たちが、産声をあげたころ、です。
フランス革命からナポレオン戦争にいたる動乱、そして産業革命を経て、イギリスは圧倒的な経済、軍事、政治力で、世界システムのヘゲモニーを握ろうとしていました。
イギリスVSフランス 薩長兵制論争5には、以下のように書きました。
第2次百年戦争と呼ばれる18世紀の百年間、イギリスはフランスとシーソーゲームをなしつつ、世界帝国を築き上げていきました。前回にも書きましたように、それは、主には海軍力によるものでして、植民地における英仏対戦にまで言及していく必要があるのですが、それは置いておきます。
この「植民地における英仏対戦」は、アメリカ大陸における戦いについて書いたのですが、同時にインドでも、英仏は対立していました。
7年戦争に連動して、イギリス東インド会社が、フランス東インド会社のインドにおける覇権を打ち破り、インド植民地化への道を開きます。
 | 興亡の世界史 東インド会社とアジアの海 (講談社学術文庫) |
| クリエーター情報なし | |
| 講談社 |
上の「興亡の世界史 東インド会社とアジアの海」、著者の羽田正氏は近世イスラーム史がご専攻だそうですが、19世紀初頭、アヘン戦争までのアジア交易の状況を、わかりやすくまとめてくれています。
16世紀、スペイン人はアメリカ大陸から太平洋を越えてフィリピンに到着し、ポルトガル人はアフリカ南端の喜望峰を経てインド、そしてアジア各地に到達し、やがて、「人とモノによる地球の一体化を実現」しました。
いわば、地球を一周、あるいは半周して、大陸から大陸へ、人とモノの長距離移動を常態化したわけです。
とはいえ、ポルトガル人の海の覇権は、それほど長く続いたわけではありません。
当時の船旅は、相当な危険を伴いました。王室が投資し、一攫千金を狙う命知らずの商人が船を動かし、ならず者や罪人たちが兵士となって、アジアへ来たわけなのですが、女性が伴われることはまれでしたし、彼らの多くは現地女性と結ばれて土着化し、貿易も私貿易となって、本国との関係は薄れていったのです。
そして17世紀、新興商業国家、オランダとイギリスの商船が、アジアの海に乗り出してきます。
この2国で、アジア交易のために誕生しましたのが、東インド会社です。
後を追って、フランス東インド会社が生まれ、さらには、短期間ながら、スウェーデン東インド会社、デンマーク東インド会社も活動しました。
この場合の「東インド」とは、アラビア半島、東アフリカ、インド、そして東南アジア、中国、日本も含まれる広範な地域です。
つまり、東インド会社とは、「東洋との交易で収益をあげることを目的にした株式会社」でした。
莫大な利益を生み出す東洋交易は、さまざまな危険ととなりあわせで、多大な資本金を必要としていました。そのために、株式を発行し、安定した資本を得る方式が採用されたわけです。
しかし、またこの株式会社は、王室と政府により、東洋貿易の独占権を与えられていまして、本国政府とは別に、出先の交渉相手の政府と交渉する外交権のようなものも、認められていました。
つまりオランダ東インド会社は、独自の判断で、江戸幕府と交渉することができた、というわけです。で、そのオランダ東インド会社の本拠は、バタヴィア(現インドネシアのジャカルタ)でしたが、独自に軍隊を持っていて、場合に応じて、軍事力行使も辞さない、戦う株式会社でもありました。
長崎は、そもそもポルトガル交易のために開かれた港町でしたが、江戸時代、幕府は、西欧諸国の中では、宗教を持ち込まないオランダの東インド会社にかぎって、長崎での交易を許可します。
長崎は天領となり、それまで交易に携わっていた日本人たちは、通訳をも含めて、幕府の下級役人となり、幕府は効率的な管理貿易を行いました。
長崎・出島のオランダ商館長は、毎年、江戸の将軍に挨拶に出向くことが求められ、もちろん、兵士の駐留は認められません。それどころか、長崎へ入港するオランダ船は、大砲を外してはじめて、陸揚げが許されました。
18世紀に入り、幕府の統制はさらに徹底し、羽田正氏によれば、「それは、現地政権がその国の海外貿易全般と人の出入りを完全に掌握し、管理するという当時の世界で唯一の体制」となりました。
一方、ですね。明から清へと王朝が変わった中華帝国ですが、これも、管理交易をめざしていました。
しかし、清朝の支配者は、内陸から勃興した女真族。海外交易をしていたのは、沿岸部に住む商人、漁民たちです。
したがいまして、清朝の管理は間接的で、江蘇・浙江・福建・広東に、海関を設け、特定の仲介商人(牙行)に取り引きと課税を請け負わせることで、行われていました。(村上衛著「海の近代中国」P.29)
しかし、西洋の商人たち、つまりは東インド会社に対する管理は強く、貿易港は広州一港で、滞在は貿易期間(9月から翌年3月)のみ。軍船の入港は禁じられ、行動も大きく制限されていて、その点では、日本の長崎におけるオランダ交易管理に似ていました。
そうした理由も、基本的には、キリスト教の伝搬とその影響を危惧して、ということでして、これも日本との共通項です。
1776年、イギリスのアダム・スミスは、「国富論」において、以下のように、東インド会社を強く批判します。
「東インド会社のような独占企業はあらゆる面で有害であり、それが設立された国に多かれ少なかれ不利益をもたらし、その支配を受けるようになった国の住民には、破壊的な打撃を与えるのである」(山岡洋一訳)
実際に、ですね。国富論が出版されました前年に、アメリカ独立戦争は勃発していますが、その前哨戦とも言えるボストン茶会事件(1773年)は、イギリス東インド会社がらみで起こりました。
イギリス東インド会社は、清朝中国から仕入れたお茶をアメリカで販売していましたが、高価すぎまして、アメリカの商人たちは、自然とオランダ・フランスの東インド会社から仕入れるようになっていたんですね。
で、在庫をかかえ、経営不振に陥っていましたイギリス東インド会社のために、イギリス政府は、アメリカほか植民地での茶の独占販売権をイギリス東インド会社に与え、その代わりに、相場よりも安く売らせることとしました。
イギリス政府は、確実に植民地での物品税を得るためにそうしたわけですが、それが多大な反発を招きます。
そもそも、イギリス東インド会社の販売価格が高価に過ぎたからこそ、アメリカ商人たちは、ひそかに他から茶を仕入れ、販売して儲けていたわけですし、本国と植民地の貿易と課税のあり方が、大きな問題となったわけです。
アメリカの独立、続くフランス革命によって、実際、特権商人の独占交易は、ヨーロッパ諸国のありようとはそぐわないものとなり、革命の最中にフランス東インド会社が消滅し、ついでオランダ東インド会社も形をかえます。
そして、産業革命が起こったイギリスでは、資本家の数が増加し、また船旅の安全性も向上して、東洋交易に資本を投じる人々の数が劇的に増えます。ここで、「自由貿易こそが国を富ませる」といいます、アダム・スミスの国富論が出てくるわけです。
国家の利益と東インド会社の利益が一致しなくなりました結果、イギリス東インド会社のインド、清国との独占交易は廃止されることとなりました。
しかし、ですね。新興の貿易商人たちにとって、清国の貿易制限、欧米人に加えられました規制は、おおよそ馬鹿馬鹿しいものでした。その後ろ盾となって、自由貿易を推進していましたイギリス政府は、インドでは強大な支配権を握るようになっていましたし、清朝のやり口を、時代錯誤で、尊大にすぎるものと受け取るようにもなっていました。
一方、清朝の方も、沿岸民の交易の取り締まりは、すこぶる困難になっていました。
アヘンの密売が増加したのは、もちろん、イギリス東インド会社が持ち込み量を増やしたから、でしたけれども、需要があったから増やしたわけでして、清がアヘンの取り締まりを強化した1838年以前、すでに東インド会社は清との独占取り引きの中止を余儀なくされていました。
結局、清朝のアヘン取り締まりは、少々乱暴な欧米商人の取り締まり強化におよび、イギリスはまたそれを口実に、清国におきます商業活動の自由(イギリスにとっての)を得ようと、艦隊を派遣し、対立は深まって、開戦におよびました。アヘン戦争です。
ここで、明確になりましたのは、産業革命と戦乱を経て、世界の海を席巻するようになりましたイギリス海軍と、防衛する清国の、目のくらむような軍事力の格差です。
主にイギリス東インド会社が派遣しました蒸気船は、まだ初期のもので、喫水の浅い小型の外輪船でしたけれども、大砲を50門以上積んだ大型帆船を、曳航して河川を上り、内陸部を攻撃することが可能でした。イギリス艦隊は、長江の河口から250キロ上流の鎮江を陥落させ、南京にまで到達して、勝利を決定的なものにしました。(「日蘭関係史をよみとく 下巻 運ばれる情報と物」西澤美穂子著「第3章 蒸気船の発達と日蘭関係」p92)
イギリス軍の目標となりました清朝側の防御拠点、砲台などは、イギリス軍が行動開始したその日のうちに、ほとんどすべてが陥落し、イギリス側の損害はごく軽いもので、しかも陸戦においても、イギリス軍(主にインド兵です)の圧勝でした。(村上衛著「海の近代中国」P.106)
結果、1842年に締結された南京条約により、イギリスは賠償金、香港の割譲、広州、福州、厦門、寧波、上海の開港、自由貿易、治外法権を得て、清は関税自主権を失います。
そして2年後、アメリカ、フランスは、続いて、ほぼイギリスと同じ条件で、清国と通商条約を結びます。
地図をご覧になってみてください。
それまで開港していた広州は、台湾よりも南ですが、福州、厦門、寧波と北に連なり、上海にいたっては、日本の長崎まで、ごく簡単に来れてしまいます。
開港地では、水、食料、石炭などの補給もできますし、早急に、艦船を修理するためのドックも造られたはずです。
といいますのも、開港により、小さな港の漁民たちは密貿易にかかわり辛くなり、清国沿岸に跋扈する海賊が急増しまして、イギリスはやがて、開港地に海軍を常駐させることともなったわけです。
そして、弘化元年(1844年)、清国に開港場を得たフランスは、直後に琉球に軍艦を派遣し、開国を迫りました。
アヘン戦争の噂は、オランダおよび清国の商人たちから、逐一、日本に伝えられていて、直後に、識者による「鴉片始末」というアヘン戦争の論評も書かれました。つい目と鼻の先の上海に補給基地を得た欧米の艦船が、清国を打ちのめした圧倒的な軍事力で迫ってくることに、多くの日本人が危機感を抱いた矢先です。
フランス船は、いったんは引きましたが、カトリック神父と通訳を那覇に残していきましたし、翌年には再び3隻の艦隊が那覇に現れ、通商を要求します。
弘化3年(1846年)、斉彬は、世子の身分で薩摩へお国入りをしますが、これは、琉球開国問題を処理するため、でした。
この年、調所広郷は、フランス艦隊の来航を幕府に届け、「千数百人派兵して防備は固めますが、最悪の場合、通商だけは認めてください」と申し出て、老中阿部正弘の許可を得ますが、阿部はすでに世子斉彬と懇談していて、事情は呑み込んでいました。
斉彬の見解は、「琉球は建前上日清両属の地で、武備もなく、通商でも許さなければ滅びる。できれば、清国の福建か小島で通商を許す、ということで収めたい」ということでして、琉球本土への欧米人の滞留は避け、なんとか植民地化を防ごうとしていました。
しかし、調所が幕府に派兵を約束したのは虚言でして、幕府隠密の手前、山川港まで人数を出し、派兵のふりをして、引き上げさせました。
斉興は、ちょうど従三位昇進を願い出ていまして、近々それが叶うと勝手に思い込んでいましたので、自分は江戸にいたいし、琉球問題などは斉彬に任せようと、異例の世子の藩地入りを幕府に願い出ました。
斉彬はもちろん、老中の阿部とも相談していて、自分が問題処置の指揮をとるべく藩地入りしたわけですが、これが、思うようにはできなかったんです。
世子・斉彬は、生まれてからずっと江戸にいて、藩地にはそれまで、一度しか足を踏み入れたことがありません。
帰ってみれば、調所の威光はすみずみまで行き渡っていまして、斉興家臣団はその意のままに動き、斉彬はまったく手の出しようもありませんでした。
この当時の幕府の隠密はものすごいものでして、調所の派兵が見せかけでしかないことなど、薩摩藩の弱みを幕府はしっかりとつかみました。
調所はじめ斉興家臣団にしましても、アヘン戦争の衝撃を、まったく感じていなかったわけではありません。
洋式砲術を採用し、沿岸要所に台場を設け、火薬を洋式で製造するなど、他藩とくらべれば、かなり早い取り組みでした。
しかし、芳即正氏によれば、斉彬は帰藩の翌年、調所が行った給地高改正と軍制改革について、強く非難しているといいます。
薩摩藩では、家禄の売買を許していて、その結果、軍役動員を命じれば、応じきれない者がでるおそれが強かったんですね。
といいますか、応じきれない現実があり、だからこそ薩摩は、派兵したくても派兵できなかったわけでして、給地高改正を行い、軍務に応じきれない困窮者を無くそうと、一応は努力します。
調所にしましても、藩兵全員に鉄砲を持たせて西洋式の歩兵とする軍制改革を、考えていなかったわけではなかったのですが、ただ、そのやり方が、斉彬の目から見れば、成果の上がらないものと見えたのでしょう。
すぐに動員可能なまとまった軍勢、それも鉄砲を持った西洋式の歩兵軍団をつくろうと思えば、これは徹底した藩政改革が必要となってきますし、藩士への手当など、莫大な資金も必要となってきます。
つまり従来の調所の節約路線でできることではなく、斉彬は、自らが藩主の座に着かない限り、日本が迎えようとしています未曾有の危機に、適切に対処することはできない、と思ったわけです。
そして、動員される側の藩士が、海から日本に迫りつつある危機を知らないはずもなく、斉彬の路線を支持する一般の藩士が、多数出て来ました。
一方、調所を筆頭とします斉興家臣団にとりましては、斉彬も、それを熱烈に支持する藩士たちも、とても危ういものと思えてきたわけです。
斉興はもちろん、調所と自らの家臣団を信頼していたわけなのですが、自身が精を出したのは祈祷です。
なにしろ、「島津家の方が正統な皇統!」くらいなことを思っていますし、帝のもっとも大切なお役目は国家の安寧を祈願することですから、琉球に来た西洋人を呪詛したわけです。
ところがそのことから、斉彬支持派の藩士たちは、斉彬とその子供たちへの呪いの祈祷が行われている、と誤解します。斉彬その人も一時、そう信じたりもしまして、親子の関係はこじれにこじれました。
で、実のところ、お由羅は、少々神がかりな藩主・斉興の気に入りの側室だっただけではないのでしょうか。
えーと、ですね。だから、琉球を薩摩が支配し、幕府の勢力下にあることは日本中に知れた話でして(琉球の朝貢使節が、琉球国王即位と幕府将軍襲職の際、ほぼ一年がかりで江戸へ出向いていました)、しかも、フランスの軍艦もイギリスの軍艦も、無事那覇に入港し、なんの攻撃も受けていないんです。
だからこそ、ジョン万は、無事故郷に帰るために、狙って、琉球に上陸したわけですし、斉彬が藩主となった薩摩は、詳しい海外情勢を聞くために、賓客待遇でもてなしました。牢屋なんて、ありえんですわ。
そして、次回よーやく、西郷隆盛に話を進めたいと思います。


















(と思ったら村上衛氏の「海の近代中国」は私も一年前に借りて読んでました。さすがに全ページを精読した訳ではないですけど)
斉興の人物像も面白いですね。現在の皇室と島津家の繋がりを考えますと、一層感慨深いものがあります。
>この当時の幕府の隠密はものすごいものでして、調所の派兵が見せかけでしかないことなど、薩摩藩の弱みを幕府はしっかりとつかみました。
なんとなく「薩摩飛脚」というイメージが強いせいか、薩摩は情報漏洩に厳しい国というイメージを抱いていましたが、当時の幕府の隠密は凄かったんですね。
ちなみに、おそらく郎女さんもご存じの通り、現在の『西郷どん』は歴史ドラマというよりも「恋とスリルとサスペンス、あと涙(肉親の情とか)とコメディをちょっと加えたファンタジードラマ」といった状態になっておりますから、あまりこちらで多くを語るのは難しいかも知れませんねえ。まさかあの『花燃ゆ』を下回る代物になるとは思いませんが、先が思いやられます。
ドラマの進み具合が非常に遅いのは、多分歴史要素は「特番」である程度端折るつもりなのだろう、と私は思ってます。
NHK大河初試み「西郷どん」50話中3本を特番へ 2017年12月6日
https://www.nikkansports.com/entertainment/news/201712060000670.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=nikkansports_ogp
実は、単に渡辺謙の出番を引っ張りたいだけなのかも知れませんけど。
このドラマが「花燃ゆ」ほどイラつかないのは、私にとっては、恋愛ドラマとしてはだいぶんマシに思えるからです。「花燃ゆ」は、普通の恋愛、人情ドラマとして見ても、最低最悪でした。
うーん。次回からは気楽な感想文にしようと思うのですが、やはりなんだかんだで、歴史調べをやってしまいそうな気もします(笑)
文章にまとめることで、自分の頭の中に入れようと、いわば私自身の覚え書きのようなものとして書いているのですが、読んでいただければ嬉しいです。