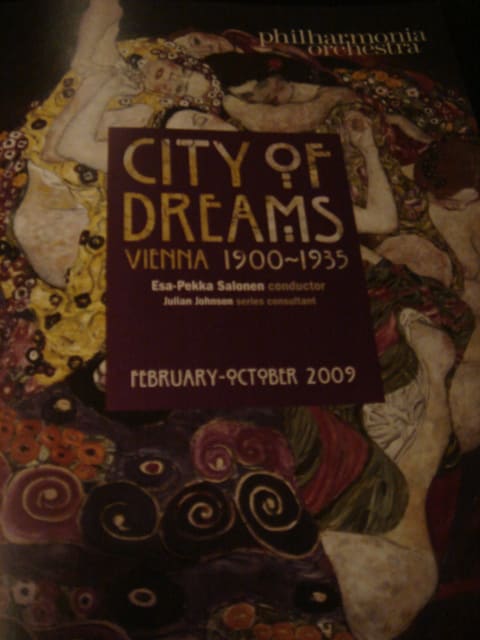ロンドンのナショナルギャラリーで6月7日までピカソ展が開催されている。
http://www.nationalgallery.org.uk/exhibitions/picasso/default.htm
今年の初めにParisでピカソ展を見損なったので、これは見逃してはならない、と出掛ける。
チケットは時間制で、午後4時頃到着したときには既に「本日分売り切れ」とあった。もともと、通し券(30ポンドで期間中何度でも入場できる)を購入するつもりでいたので、尋ねてみると、それならばOKということで購入。普通のチケットが12ポンドなので、3回通えば元が取れることになる。
さて、内容であるが、展示は6つの部屋から成っていて、
1. Self Portrait
2. Models and Muses: Nudes
3. Characters and Types
4. Models and Muses: The Pensive Sitter
5. Still Life
6. Variations
今日の一枚は、これ。
ピカソの最初の妻、オルガの肖像。ピカソの死まで彼の手元にあったらしい。
4の部屋に入ると正面に飾られていて、あまりの美しさに、まるで毒気に当てられたかの如く目が離せなかった。特に顔の左側、目の下の辺りのハイライトの部分。とりわけ細密に描かれているのではなく、化粧崩れしているようなタッチなのだけれど、その色の美しさや、絵画独特の、見せる部分とそれ以外の対比、人間の眼の錯覚の利用など、どれほど眺めても飽きることがなかった。
これを観て、アルルカンの絵を思い出した(調べてみると、両方とも1923年に描かれていた)。中学の教科書にアルルカンが載っていて、これを模写した記憶がある。家庭科室横の廊下に飾られたあの絵、今見てみたい(相当自信過剰?)。それにしても、日本の教育も捨てたものではない。思わず子供の頃の美術や音楽の先生を思い出して感謝してしまった。まあ、こちらに生まれていたら、ナショナルギャラリーや、ピカソ美術館、オルセー、ルーブルで本物を見ながら模写できたのだろうけれど!
Variationsの部屋のManetの作品を参考にしたものは、幾ら天才ピカソといってもねぇ、というのは素人感想か。とにかく今日は、他の全作品とオルガ一枚、どちらを選ぶ?ときかれても、「オルガ!」と答えたいほどにこの作品にはまった。
通し券、次回はどの絵に魅かれるだろう?やっぱりオルガ?