齋藤雅文 作
九代琴松 演出(←松本幸四郎さん)
 出演
出演 
中村仲蔵…松本幸四郎(森田座の座頭)
中村此蔵…市川染五郎(仲蔵の愛弟子)
河竹新七…大谷友右衛門 (狂言作者)
中村里好…上村吉弥(森田座の立女形)
森田勘弥…片岡秀太郎(森田座の座元)
 あらすじ
あらすじ 
安永元年十一月、江戸森田座の顔見世興行の初日。
大部屋俳優から看板役者にまでのぼりつめた中村仲蔵は、初の座頭をつとめるまでに出世していました。
しかし、仲蔵が憧れていた座頭の立場は、「金を巡る狂気」「芸への嫉妬」「様々な策謀や葛藤」など、想像を絶する世界でした。
そんな中、森田座で忠信役の役者が自殺、そして、その代役も何者かに舞台の下の奈落へ突き落とされ舞台に立てなくなるという事件が起こります。
仲蔵は代役に此蔵を抜擢し、此蔵は師匠の期待に応え、見事に演じきります。
謎の事件を探っていた此蔵は、真相をつきとめます。
しかし、ここから仲蔵と此蔵の関係が絡み合いながら、悲しい結末へと進んでいくのです…








23日に松竹座で「夢の仲蔵千本桜」を見ました。
「良かった」「悪かった」「中途半端」など、色々な意見が出ていたので、期待の中に少しの不安を抱えての観劇となりました
今回も私の指定席 3階席です。上から見下ろす形なので、舞台を広い範囲で見ることが出来ました。
開演前の注意事項のアナウンス
お馴染みの「開演中の写真撮影、ビデオ撮影、…固くお断りします。」
『
 この声は
この声は 』
』
そうなんです。幸四郎さん自らがアナウンスされていました。
こういう事って、ありそうでないですよね。九代琴松としての演出でしょうか?
今回の目玉は、舞台が歌舞伎が行われている森田座で、お芝居の中に歌舞伎が出てくるという「劇中劇」です。
義経千本桜の名場面がたくさん出てきました
「劇中劇」のため、一部分だけなので、義経千本桜を知らない人には、中途半端に思えたかも知れません。
いつもなら「高麗屋 」とかかる大向こうさんの声も、この日は劇中の屋号である「栄屋
」とかかる大向こうさんの声も、この日は劇中の屋号である「栄屋  」が多かったです。なんだか私も森田座の観客の一人になった気分になりました
」が多かったです。なんだか私も森田座の観客の一人になった気分になりました
華やかな舞台、様々な人間模様をうつしだす薄暗い楽屋、闇の世界である奈落を、廻り舞台やセリ(大道具や人物を上下させるもの)を上手く使って演出されていました。
楽屋の場面では、日頃見ることの出来ない、役者の姿、関係する人々の動き(座元、帳元、出番を知らせに来る人、化粧台を用意する人など)、仲蔵が衣装をつけるところも見ることが出来ました
このお芝居、染五郎さんが実に素晴らしかったです。
やはりこの人は舞台が一番です。
とっても生き生きしていて、輝いています
私が知る限り、2回早替わりがあったのですが、全然見抜けませんでした
「四の切」ではワイヤーを使って、軽やかに狐になっていました。宙乗りもあったので、このときだけ3階席は特等席になりました
此蔵が奈落で殺人を犯す場面。人を殺し、その直後に闇の世界奈落からスッポンで華やかな舞台へ上がった時のあの顔は、3階からでもすごい殺気が伝わってきてゾクゾクしました
劇中劇の義経と忠信(主従)、仲蔵と此蔵(師弟)、そして幸四郎と染五郎(親子)、この3つがリンクしていて、奥の深いドラマになっています。
この役は幸四郎さんと染五郎さんにしか出来ないような気がします。
改めて、この親子を見直しました。
本当に素晴らしかったです
九代琴松 演出(←松本幸四郎さん)
 出演
出演 
中村仲蔵…松本幸四郎(森田座の座頭)
中村此蔵…市川染五郎(仲蔵の愛弟子)
河竹新七…大谷友右衛門 (狂言作者)
中村里好…上村吉弥(森田座の立女形)
森田勘弥…片岡秀太郎(森田座の座元)
 あらすじ
あらすじ 
安永元年十一月、江戸森田座の顔見世興行の初日。
大部屋俳優から看板役者にまでのぼりつめた中村仲蔵は、初の座頭をつとめるまでに出世していました。
しかし、仲蔵が憧れていた座頭の立場は、「金を巡る狂気」「芸への嫉妬」「様々な策謀や葛藤」など、想像を絶する世界でした。
そんな中、森田座で忠信役の役者が自殺、そして、その代役も何者かに舞台の下の奈落へ突き落とされ舞台に立てなくなるという事件が起こります。
仲蔵は代役に此蔵を抜擢し、此蔵は師匠の期待に応え、見事に演じきります。
謎の事件を探っていた此蔵は、真相をつきとめます。
しかし、ここから仲蔵と此蔵の関係が絡み合いながら、悲しい結末へと進んでいくのです…








23日に松竹座で「夢の仲蔵千本桜」を見ました。
「良かった」「悪かった」「中途半端」など、色々な意見が出ていたので、期待の中に少しの不安を抱えての観劇となりました

今回も私の指定席 3階席です。上から見下ろす形なので、舞台を広い範囲で見ることが出来ました。
開演前の注意事項のアナウンス

お馴染みの「開演中の写真撮影、ビデオ撮影、…固くお断りします。」
『

 この声は
この声は 』
』そうなんです。幸四郎さん自らがアナウンスされていました。
こういう事って、ありそうでないですよね。九代琴松としての演出でしょうか?
今回の目玉は、舞台が歌舞伎が行われている森田座で、お芝居の中に歌舞伎が出てくるという「劇中劇」です。
義経千本桜の名場面がたくさん出てきました

「劇中劇」のため、一部分だけなので、義経千本桜を知らない人には、中途半端に思えたかも知れません。
いつもなら「高麗屋
 」とかかる大向こうさんの声も、この日は劇中の屋号である「栄屋
」とかかる大向こうさんの声も、この日は劇中の屋号である「栄屋  」が多かったです。なんだか私も森田座の観客の一人になった気分になりました
」が多かったです。なんだか私も森田座の観客の一人になった気分になりました
華やかな舞台、様々な人間模様をうつしだす薄暗い楽屋、闇の世界である奈落を、廻り舞台やセリ(大道具や人物を上下させるもの)を上手く使って演出されていました。
楽屋の場面では、日頃見ることの出来ない、役者の姿、関係する人々の動き(座元、帳元、出番を知らせに来る人、化粧台を用意する人など)、仲蔵が衣装をつけるところも見ることが出来ました

このお芝居、染五郎さんが実に素晴らしかったです。
やはりこの人は舞台が一番です。
とっても生き生きしていて、輝いています

私が知る限り、2回早替わりがあったのですが、全然見抜けませんでした

「四の切」ではワイヤーを使って、軽やかに狐になっていました。宙乗りもあったので、このときだけ3階席は特等席になりました

此蔵が奈落で殺人を犯す場面。人を殺し、その直後に闇の世界奈落からスッポンで華やかな舞台へ上がった時のあの顔は、3階からでもすごい殺気が伝わってきてゾクゾクしました

劇中劇の義経と忠信(主従)、仲蔵と此蔵(師弟)、そして幸四郎と染五郎(親子)、この3つがリンクしていて、奥の深いドラマになっています。
この役は幸四郎さんと染五郎さんにしか出来ないような気がします。
改めて、この親子を見直しました。
本当に素晴らしかったです













 午後6時半。蕾は閉じています
午後6時半。蕾は閉じています
 午後7時半。少し開いてきました
午後7時半。少し開いてきました
 午後8時。中が少し見えます
午後8時。中が少し見えます
 午後8時半。あともう少し
午後8時半。あともう少し
 午後9時。見事花開きました
午後9時。見事花開きました
 」と合わせたかのように、一緒に誇らしく咲いていました。
」と合わせたかのように、一緒に誇らしく咲いていました。





 =3
=3


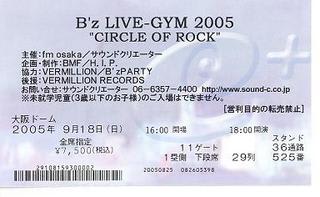
 。
。






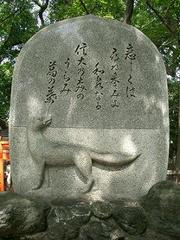




 』
』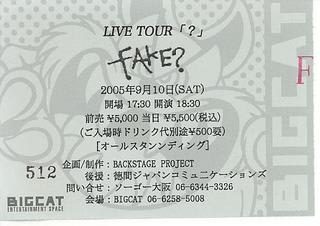



 )
)
 、なんとか最後までもってくれました。
、なんとか最後までもってくれました。
 INORANのギターの音色は最高です。)
INORANのギターの音色は最高です。) )
) TourbillonのHPで「HEAVEN」の曲とPVが、ちょこっと試聴&見ることができます。
TourbillonのHPで「HEAVEN」の曲とPVが、ちょこっと試聴&見ることができます。



 (苔がビッシリです。)
(苔がビッシリです。)



