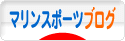豊岡市の旧豪農家、平尾源太夫邸 が本日一般公開されました。
以前から一度中が見てみたいと思っていたので友人を誘って行って来ました。
豊岡市HPから引用
平尾家は、江戸時代、元禄期から土地の集積をはじめ、幕末に至る約180年間で、実に207町歩という広大な面積の田畑を有する但馬最大の地主でした。
一般農民が領主に対する年貢米に困って平尾家を頼り、その代償として土地の「永代譲渡」をしたものが元になったようです。
平尾家は、このように近世以来の当地の名家であり、農地解放以前は但馬地方では最大、県下でも屈指の大地主でした。敷地は森尾の集落の中央に位置し、一般の民家は川沿いに建っていますが、平尾家は敷地内に川を取り込んでいます。
川に面して川井戸が設けられ、その後方に主屋が川に並行して建ち、主屋の上手には本蔵、さらにその上手には離れ座敷が建ち、また、敷地の周囲は隠居部屋や蔵や小屋が建っています。さらに、主屋上手の前方は板塀で囲って庭園をつくり、離れ座敷背面にも庭園を備えています。主屋の建立年代は、手斧初の時に作られた札により明治28年11月14日に着手され、その数年後に完成したと推定されます。大工は西田磯治氏、豊岡の宮大工と伝えられています。磯治氏は、大屋町の鎌田家(「兵庫県住宅100選」)も造ったとされ、近辺の豪邸をいくつか手掛けてきたと言われています。
架構(屋根構造)は、伝統的な和小屋と推定されますが、下手土間側の屋根を切妻造りとして、妻に疑似トラスを見せており、新様式を積極的に取り入れている様子がうかがえます。
主屋は、吟味された良材をふんだんに使用している上に、権(床などの化粧横木)、鴨居(引戸などの上部の横木)、長押(柱と柱をつなぐ水平材)、建具等を漆塗りとしたり、手の込んだ仕事がなされ、しかも現在でもほとんど狂いがありません。明治期の建物らしく、江戸時代とは異なった要素が認められ、明治期の住宅の様相をよく示し、その時代を反映しています。
「新緑の史跡と旧家を訪ねて」 豊岡市出土文化財管理センター
 写真いっぱいアップします。
写真いっぱいアップします。
































ではでは
カニ料理 兵庫城崎温泉おすすめの/花香る静寂の宿 湯楽
↓ランキングに参加しました。クリックお願いします。