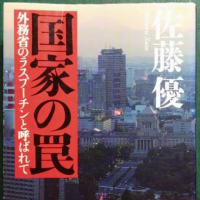石橋湛山の政治思想には、私も賛同します。
湛山は日蓮宗の僧籍を持っていましたが、同じ日蓮仏法の信奉者として、そのリベラルな平和主義の背景に日蓮の教えが通底していたと思うと嬉しく思います。
公明党の議員も、おそらく政治思想的には共通点が多いと思うので、いっそのこと湛山議連に合流し、あらたな政治グループを作ったらいいのにと思ったりします。
そこで、石橋湛山の人生と思想について、私なりの視点から調べてみました。
まずは、定番というべきこの本から。
増田弘『石橋湛山』(中公新書、1995.05)
目次)
□はじめに
□第1章 幼年・少年・青年期
■第2章 リベラリズムの高揚
□第3章 中国革命の躍動
□第4章 暗黒の時代
□第5章 日本再建の方途
□第6章 政権の中枢へ
□第7章 世界平和の実現を目指して
□おわりに
第2章 リベラリズムの高揚
□1)文芸・思想・社会批評... 『東洋時論』(1)
□2)政治・外交批評...『東洋時論』(2)
□3)日米移民問題...我れに移民の要無し
□4)第一次世界大戦参戦問題... 青島は断じて領有すべからず
■5)21ヵ条要求問題...干渉好きの日本人
□6)シベリア出兵問題... 過激派(ボルシェビキ)を援助せよ
□7)パリ講和問題... 袋叩きの日本
□8)普選運動・護憲運動... 不良内閣を打倒せよ
□9)早稲田大学騒動
5)21ヵ条要求問題...干渉好きの日本人
この間、加藤外相は小池張造政務局長に対し、中国に要求する諸項目の原案作成を命じた。当初は山東ならびに満州方面の利権に関する10ヵ条程度を予定していたが、陸軍、元老、財界等の方面から多種多様の要求が外務省に持ち込まれ、結局21ヵ条にまで膨れ上がった。
青島陥落直後の1914年(大正3)11月11日、大隈内閣は対中国交渉の訓令案を承認し、この訓令を得た日置益駐華公使は、翌15年(同4)1月18日、袁世凱大総統を訪問して要求書を手交した。その要求書は、第一号山東省に関する4ヵ条、第二号南満州および東部内蒙古に関する7カ条、第三号漢治萍公司に関する2ヵ条、第四号中国の沿岸不割譲に関する1ヵ条、第五号中国の一般的事項に関する7ヵ条から成っていた。
以後両国政府は、2月2日から4月26日まで、北京で25回に及び内容を討議した。この間中国側は、満州の租借地と鉄道の期限延長を承認した以外には、日本案に強く反発したため、4月末、交渉は完全に行き詰まった。大戦に忙殺されたヨーロッパ列強は日本の強圧的姿勢を黙認したが、いまだ参戦していないアメリカは中国側を擁護し、日本を牽制した。5月7日、日本政府は局面打開のため、ついに最後通牒(ただし元老山県の忠告を容れて悪評高い第五号の7条項を削除したもの)の提出に踏み切った。9日、止むなく中華民国政府はこれを受諾し、ようやく交渉は妥結した。こうして条約および交換公文が25日に調印され、6月8日に批准交換が行なわれて、この一大外交問題は決着をみた。
さて日本の言論界では、わが方の要求を当然視するムードが一般的であった。ところが交渉過程で日本政府が中国側の抵抗を前にして譲歩していき、当初の要求から後退していくと、次第に政府の軟弱な態度を批判する論調へと傾き、条約締結時には、原案から隔たった条約内容を否定する空気が強まった。たとえば、日本の大戦参戦を是として対独戦勝利に「狂喜」した『東京朝日』は、今回の要求を肯定して政府の立場を擁護したが、日中交渉が長期化すると、2月6日、中国側は「我国の真意を誤解し、我国の野心を猜疑」するが、日本側は満州問題など長年の懸案を根本的に解決しようとしているにすぎないから、北京政府も誠意をもってこれを迎え、日中両国の親交を維持するために速やかに同意すべきであると主張した。そして最終段階では、「頑冥にして誠意なき支那の当局者」に対しては「断乎として別個の手段を講ずる」以外にないと断言し(4月23日)、最後通牒によって交渉が妥結すると、同紙はこれを「大に祝賀」した。ただし妥結の内容に関しては、4月26日の日本側修正案(青島還付および東部内蒙古と南満州との切り放し等)を「無用」とし、また最後通牒提出の際の第五号条項放棄を批判して、「今回の落着が、国民に少なからざる不満足を与へたるを信じ、現内閣の責任を問ふと同時に、無責任なる元老の掣肘(せいちゅう)を大に遺憾とせざる能はず」と論じた(5月10日)。
一方、大正デモクラシーの寵児ともいうべき東京帝国大学教授の吉野作造は、6月に刊行された著書『日支交渉論』で、諸列強が中国内部にそれぞれ勢力を扶植している現況では、もっとも中国と関係の深い日本が「独り指を咬へて傍観して居る事」はできない、つまり「已むを得ず列国と同様に支那に於て専属的排他的の勢力範囲を得ることに努力せねばならぬ」と日本の基本方針に触れた上で、「今度の要求は大体に於て最小限度の要求であり、日本の生存のためには必要欠くべからざるものであった」と認め、それゆえ「第五項(号)の削除は、甚だ之を遺憾とする」と総評した。
では『新報』の湛山はどのように論評したであろうか。まず2月5日号社説「第二の露独たる勿れ」(『全集①』)で、今回の要求に踏み切った日本政府の本意を「朝鮮同様、満州を我が領土に併合する」ことにあると断定し、それはわが国の運命にとって「由々敷き問題」であり、「無謀の挙、我が国をして第二の独逸、第二の露国」化するものであると非難した。その理由は、他国民の領土を「割取する」ことほど、国際関係を不安定に陥れ、衝突の原因を紛起せしめるものはないからである。もしも今日本が独露両国に代わって同地を領有し、「傍若無人の振舞」をすれば、その結果は、独露の場合と同様、やがて日本は世界から孤立し、頭を叩かれ、放逐せられ、幾十億を投じた経営はことごとく没収されることになるだろうと予想した。それゆえ、わが政府は「満蒙問題並に青島問題に関しては、何卒、国家の為めに、誤れる輿論を排斥し、其の永久占領を企てないようにしてほしい」、もしまた「永久占領の立場で交渉を進めつつあるなら、須らく撤回して貰いたい」と大隈内閣、とくに加藤外相に要望した。
湛山はこのように日中交渉の進展を冷ややかに見守ったのである。たとえば、3月5日号小評論「干渉好きな国民」(『全集②』)では、日本国民ほど干渉好きの国民はいないと指摘し、この際青島も満州も旅順も、その他一切の利権を挙げて返還したい、同時に世界の列国にもわが国と同様の態度へと向かわせたい、そして「支那をして自分の事は自分で一切処理するようにせしめたい。日本の為め、支那の為め、世界の為め、これに越した良策は無い」と説いた。また同月15日号小評論「無理推しの報い」(『全集②』)では、日中交渉が円満に行かないとか、中国で排日思想が高まるとかの罪はすべて我が方にある、「先ず彼を尊敬せよ、而して無理推しを絶対に廃(や)めよ」と主張した。さらに4月5日号小評論「対外交の失敗」(『全集②』)で、日本軍の出兵の噂を取り上げ、強く出ることはますます外交を失敗に終らすものである、「大隈内閣、加藤外相は、今以って之れを悟らず、相変らずの手段に出た、……それでは外交でも何んでもない。熊公、八公の遣(や)る事だ。之れが失敗でなくして何であろう」と厳しく日本政府を糾弾した。
しかし最終的に交渉は妥結し、条約および公文が調印された。湛山は交渉結果を否認した上で、日本の今後の在り方を次のように論じた。「隣り同志が互に親善でなければならぬ、礼節を守らなければならぬと云うは、決して個人間のみの事ではない。国と国との関係に於いても亦之れと同様の態度を取らなければ、各国民の生活は永遠に幸福なるを得ない。……吾輩は此の点から見て、大隈内閣の先頃支那に対して取った態度は、明かに自国の利益を無視し、阻害したものと思う」(6月5日号社説「日支親善の法如何」『全集①』)。また新条約が調印されると、「随分つまらぬ、併し独立国たる支那としては許し難き要求七個条」を並べた第五号の削除を「幸い」とした上で、日本が獲得した南満州などの利権9件をすべて「無用」であると指摘し、「隣邦支那が速かに富強となることは、やがて我れの富強を増す原因である。然るに此の原因を、今度の新条約は遮断した、即ち我が富強となるを妨げた故である。吾輩は斯くの如く観察し、畢竟此のたびの日支交渉は根本的に大失敗と断ずる者である」と総括し、大隈内閣の退陣を迫った(同月15日号社説「日支新条約の価値如何」『全集①』)。
湛山の一連の主張と警告は、その後現実のものとなった。日本の21カ条要求を転機として中国ナショナリズムは一段と排日色を濃くし、日中関係は悪化の一途を辿っていくのである。
(以下省略)
【解説】
ただし元老山県の忠告を容れて悪評高い第五号の7条項を削除した
「21ヵ条要求問題」……日本史の授業で習いましたね。
第一次世界大戦がヨーロッパで繰り広げられているときに、日本は日英同盟を口実にドイツに宣戦布告して、ちゃっかりドイツの利権を奪ったという火事場泥棒のような行為。
でも、最近まで知りませんでしたが、元老山県は、意外にもこの21ヵ条の要求には反対だったとのことです。
週刊ポストでの連載「逆説の日本史」で、井沢元彦さんがそんなことを書いていましたね。
湛山の一連の主張と警告は、その後現実のものとなった。日本の21カ条要求を転機として中国ナショナリズムは一段と排日色を濃くし、日中関係は悪化の一途を辿っていくのである。
日本中が帝国主義的興奮の中、湛山はきわめてリベラルで、合理的な指摘をしています。
その後の歴史は、湛山の予想が正しかったことを証明するのです。
獅子風蓮