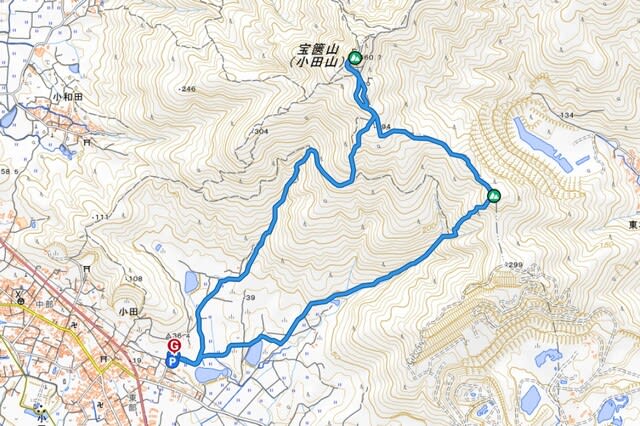今日2つめの記事を上げている。(1つめの記事は⇒こちら)
7時過ぎに降った雹(ひょう)・霰(あられ)は20~30分ほどで止んだものの、その後雪に変わった。
この季節に降る雪はすぐに解ける。淡雪である。芝生にとっては恵みの降水である。

花壇の花は家の庇に守られ、雹の被害はなかった。庇の下に置いているサボテンやポットの花に、雹はほとんど当たっていない。

クリスマスローズも影響はなさそうだ。パンジーとティタティタ・スイセンの花の一部が傷ついたが、大きな影響は出ていない。
昨日咲き始めたユスラウメは、寒さのせいで花数が少なく、影響はほとんどないと思う。

7時過ぎに降った雹(ひょう)・霰(あられ)は20~30分ほどで止んだものの、その後雪に変わった。
この季節に降る雪はすぐに解ける。淡雪である。芝生にとっては恵みの降水である。

花壇の花は家の庇に守られ、雹の被害はなかった。庇の下に置いているサボテンやポットの花に、雹はほとんど当たっていない。

クリスマスローズも影響はなさそうだ。パンジーとティタティタ・スイセンの花の一部が傷ついたが、大きな影響は出ていない。
昨日咲き始めたユスラウメは、寒さのせいで花数が少なく、影響はほとんどないと思う。