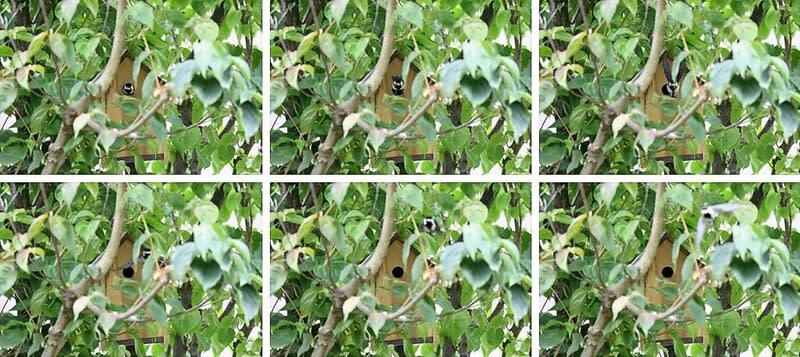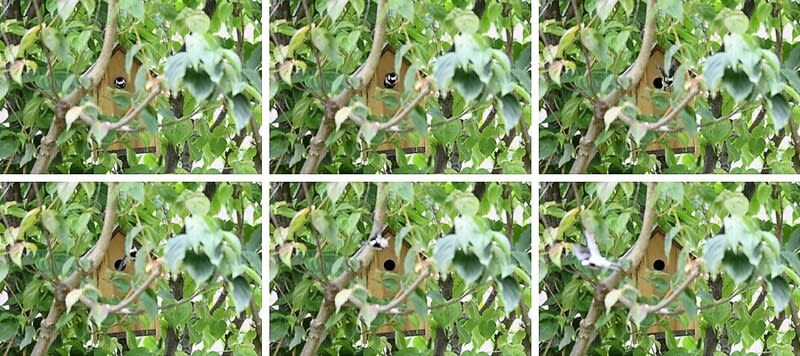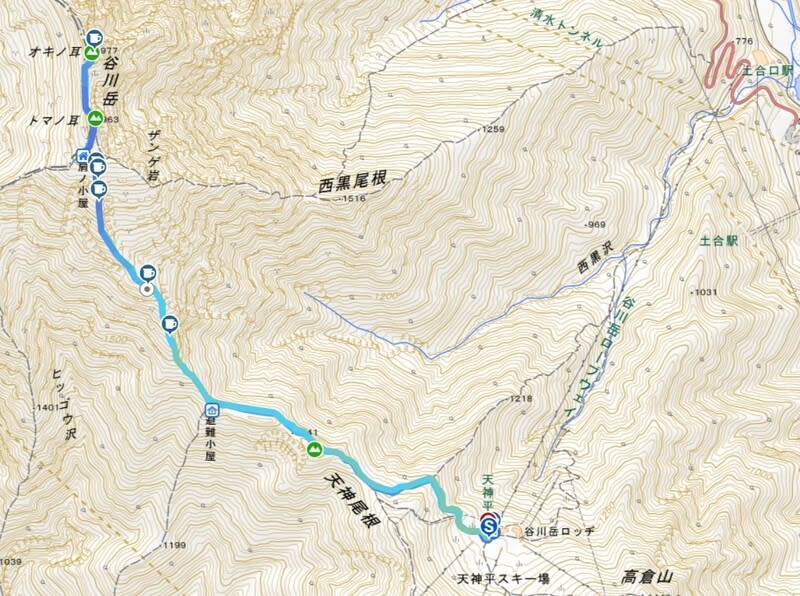花と野鳥と、虫もいっぱいだった高妻山ハイキング - その① からの続きです。
滑滝を登り終えると、登山道は沢を詰めていく。


そして、どの沢詰めでも最後に尾根に出るには急登が待っている。ここもその例外ではなかった。
先ほどの滑滝から、その様子がうかがい知れていた。


沢の奥には、大きな一枚岩が待っていて、滝が流れ落ちるのが見えた。この一枚岩は帯岩と呼ばれていて、滝には不動滝の名がついている。
登山道は、この帯岩の上をトラバースする、このコース随一の危険個所だ。
でもその前に、沢を詰めたところにお花が咲いていたので、それを見て落ち着こう。
久しぶりに見たので名前を思い出せなかったが、ノビネチドリ(ラン科テガタチドリ属)のようだった。

この植物は、先ほど観たオククルマムグラとは違い、7枚の葉が輪生している(オククルマムグラは必ず6枚)。クルマバソウ(アカネ科ヤエムグラ属)のようだ。

こちらも、カラマツソウではなく、ミヤマカラマツ(キンポウゲ科カラマツソウ属)のようだ。僅かに標高を上げていくだけで、植生が変わっていくのが面白い。

さて、いよいよ帯岩のトラバースである。落ちたら大けがが免れないので、鎖からは手を離せない。


50mほどのトラバースを終えると、このコース最後の水場となる氷清水が待っていた。とても冷たく、美味しい水だった。ボトルにこの水を満たした。

水場の先に白い花が咲いていた。2種類の花が咲いている。ミヤマハタザオ(アブラナ科シロイヌナズナ属)とズダヤクシュ(ユキノシタ科ズダヤクシュ属)のようだ。

黄色い花も咲いていた。初めて観るが、オオダイコンソウ(バラ科ダイコンソウ属 )のようだ。

そして、ニリンソウ(キンポウゲ科イチリンソウ属)の群落が現れた。

ニリンソウを見た後、すぐに戸隠山縦走路との分岐に当たる一不動に着いた。時刻はすでに6時56分になっていて、計画より30分近く遅れていた。


一不動にお参りする。

近くフウロソウの仲間と、ヤマオダマキが咲いていた。このフウロソウの仲間は、シロバナタカネグンナイフウロ(フウロソウ科フウロソウ属)というようだ。初めて観る花だった。



こちらはお馴染みのゼンテイカ(ワスレグサ科ワスレグサ属)だ。shuのプロファイル写真にも使わせていただいている。
今年初めてゼンテイカを観た。

続いてはアザミの仲間だ。アザミの仲間は種類が多く、調べ切れていない。

ハクサンチドリ(ラン科ハクサンチドリ属)も現れた。この山には、なんとラン科の植物が多いことだろう。

樹木ではベニサラサドウダン(ツツジ科ドウダンツツジ属)がたくさんあって、どの樹もたくさんの花を咲かせていた。
たくさん写真を撮ったが、載せるのは1枚にしておこう。

道ばたにマイヅルソウ(キジカクシ科マイヅルソウ属)が現れた。この花が見られると、ゴゼンタチバナやツマトリソウも咲いていることが多い。

おっと、イブキジャコウソウ(シソ科イブキジャコウソウ属)が咲いていた。この山は高山植物の見本園のようだ。

続いては、大好きなアカモノ(ツツジ科シラタマノキ属)。この後道ばたにアカモノが先並ぶアカモノロードも出てくるが、先ずは最初に撮った写真だ。

こちらはミヤマクワガタ(オオバコ科クワガタソウ属)で、戸隠山で産したものが基本標本となっている。

いよいよゴゼンタチバナ(ミズキ科ミズキ属)が現れた。後ほど群落の様子もご覧いただくが、先ずは最初に撮った写真だ。

こちらはゼンテイカの群落。
実は、この辺りで雨が強くなり、雷も聞こえてきたので、森の中で一時雨宿りした。撤退するにしても五地蔵山まで進み、弥勒新道を下山するしかない。

幸い雷は遠ざかり、雨も弱くなった。
ヨツバシオガマ(ハマウツボ科シオガマギク属)だ。この後、道端にたくさん咲いていた。

こちらはウスユキソウ(キク科ウスユキソウ属)のようだ。実は、花が開く前のウスユキソウを観るのは初めてだった。現在の分類では、ミネウスユキソウはウスユキソウと同一種とされている。


こちらは、咲き始めたばかりのウラジロヨウラク(ツツジ科ヨウラクツツジ属)のようだ。

三文殊まで来た。祠の前で帽子を取り、一礼して通過した。二釈迦は気づかずに通り過ぎたようだ。お釈迦様に申し訳ない。

イワカガミ(イワウメ科イワカガミ属)が現れた。

ユキザサ(キジカクシ科マイヅルソウ属)のようだ。

ゴゼンタチバナの群落だ。この後、道端にマイヅルソウやゴゼンタチバナが咲き並んでいた。

再びゼンテイカの群落だ。雨は上がっても、霧は晴れない。

数は少ないが、ヤマツツジ(ツツジ科ツツジ属)も咲いていた。

ナナカマド(バラ科ナナカマド属)も所々で観られた。

四普賢まで来た。このまま晴れてくれるとよいのだが。

ツマトリソウ(サクラソウ科ツマトリソウ属)が現れた。数は多くないが、この後も所々で咲いていた。

そして、図鑑で見覚えのある、希少種のランが突然現れた。しかも固まって咲いていた。キバナノアツモリソウ(ラン科アツモリソウ属)だ。
実物を観るのは初めてだった。



ずいぶんお花を観てきたが、記事が長くなったので、続きは明日とさせていただきたい。
花と野鳥と、虫もいっぱいだった高妻山ハイキング - その③ に続く。
2022/06/27
滑滝を登り終えると、登山道は沢を詰めていく。


そして、どの沢詰めでも最後に尾根に出るには急登が待っている。ここもその例外ではなかった。
先ほどの滑滝から、その様子がうかがい知れていた。


沢の奥には、大きな一枚岩が待っていて、滝が流れ落ちるのが見えた。この一枚岩は帯岩と呼ばれていて、滝には不動滝の名がついている。
登山道は、この帯岩の上をトラバースする、このコース随一の危険個所だ。
でもその前に、沢を詰めたところにお花が咲いていたので、それを見て落ち着こう。
久しぶりに見たので名前を思い出せなかったが、ノビネチドリ(ラン科テガタチドリ属)のようだった。

この植物は、先ほど観たオククルマムグラとは違い、7枚の葉が輪生している(オククルマムグラは必ず6枚)。クルマバソウ(アカネ科ヤエムグラ属)のようだ。

こちらも、カラマツソウではなく、ミヤマカラマツ(キンポウゲ科カラマツソウ属)のようだ。僅かに標高を上げていくだけで、植生が変わっていくのが面白い。

さて、いよいよ帯岩のトラバースである。落ちたら大けがが免れないので、鎖からは手を離せない。


50mほどのトラバースを終えると、このコース最後の水場となる氷清水が待っていた。とても冷たく、美味しい水だった。ボトルにこの水を満たした。

水場の先に白い花が咲いていた。2種類の花が咲いている。ミヤマハタザオ(アブラナ科シロイヌナズナ属)とズダヤクシュ(ユキノシタ科ズダヤクシュ属)のようだ。

黄色い花も咲いていた。初めて観るが、オオダイコンソウ(バラ科ダイコンソウ属 )のようだ。

そして、ニリンソウ(キンポウゲ科イチリンソウ属)の群落が現れた。

ニリンソウを見た後、すぐに戸隠山縦走路との分岐に当たる一不動に着いた。時刻はすでに6時56分になっていて、計画より30分近く遅れていた。


一不動にお参りする。

近くフウロソウの仲間と、ヤマオダマキが咲いていた。このフウロソウの仲間は、シロバナタカネグンナイフウロ(フウロソウ科フウロソウ属)というようだ。初めて観る花だった。



こちらはお馴染みのゼンテイカ(ワスレグサ科ワスレグサ属)だ。shuのプロファイル写真にも使わせていただいている。
今年初めてゼンテイカを観た。

続いてはアザミの仲間だ。アザミの仲間は種類が多く、調べ切れていない。

ハクサンチドリ(ラン科ハクサンチドリ属)も現れた。この山には、なんとラン科の植物が多いことだろう。

樹木ではベニサラサドウダン(ツツジ科ドウダンツツジ属)がたくさんあって、どの樹もたくさんの花を咲かせていた。
たくさん写真を撮ったが、載せるのは1枚にしておこう。

道ばたにマイヅルソウ(キジカクシ科マイヅルソウ属)が現れた。この花が見られると、ゴゼンタチバナやツマトリソウも咲いていることが多い。

おっと、イブキジャコウソウ(シソ科イブキジャコウソウ属)が咲いていた。この山は高山植物の見本園のようだ。

続いては、大好きなアカモノ(ツツジ科シラタマノキ属)。この後道ばたにアカモノが先並ぶアカモノロードも出てくるが、先ずは最初に撮った写真だ。

こちらはミヤマクワガタ(オオバコ科クワガタソウ属)で、戸隠山で産したものが基本標本となっている。

いよいよゴゼンタチバナ(ミズキ科ミズキ属)が現れた。後ほど群落の様子もご覧いただくが、先ずは最初に撮った写真だ。

こちらはゼンテイカの群落。
実は、この辺りで雨が強くなり、雷も聞こえてきたので、森の中で一時雨宿りした。撤退するにしても五地蔵山まで進み、弥勒新道を下山するしかない。

幸い雷は遠ざかり、雨も弱くなった。
ヨツバシオガマ(ハマウツボ科シオガマギク属)だ。この後、道端にたくさん咲いていた。

こちらはウスユキソウ(キク科ウスユキソウ属)のようだ。実は、花が開く前のウスユキソウを観るのは初めてだった。現在の分類では、ミネウスユキソウはウスユキソウと同一種とされている。


こちらは、咲き始めたばかりのウラジロヨウラク(ツツジ科ヨウラクツツジ属)のようだ。

三文殊まで来た。祠の前で帽子を取り、一礼して通過した。二釈迦は気づかずに通り過ぎたようだ。お釈迦様に申し訳ない。

イワカガミ(イワウメ科イワカガミ属)が現れた。

ユキザサ(キジカクシ科マイヅルソウ属)のようだ。

ゴゼンタチバナの群落だ。この後、道端にマイヅルソウやゴゼンタチバナが咲き並んでいた。

再びゼンテイカの群落だ。雨は上がっても、霧は晴れない。

数は少ないが、ヤマツツジ(ツツジ科ツツジ属)も咲いていた。

ナナカマド(バラ科ナナカマド属)も所々で観られた。

四普賢まで来た。このまま晴れてくれるとよいのだが。

ツマトリソウ(サクラソウ科ツマトリソウ属)が現れた。数は多くないが、この後も所々で咲いていた。

そして、図鑑で見覚えのある、希少種のランが突然現れた。しかも固まって咲いていた。キバナノアツモリソウ(ラン科アツモリソウ属)だ。
実物を観るのは初めてだった。



ずいぶんお花を観てきたが、記事が長くなったので、続きは明日とさせていただきたい。
花と野鳥と、虫もいっぱいだった高妻山ハイキング - その③ に続く。
2022/06/27