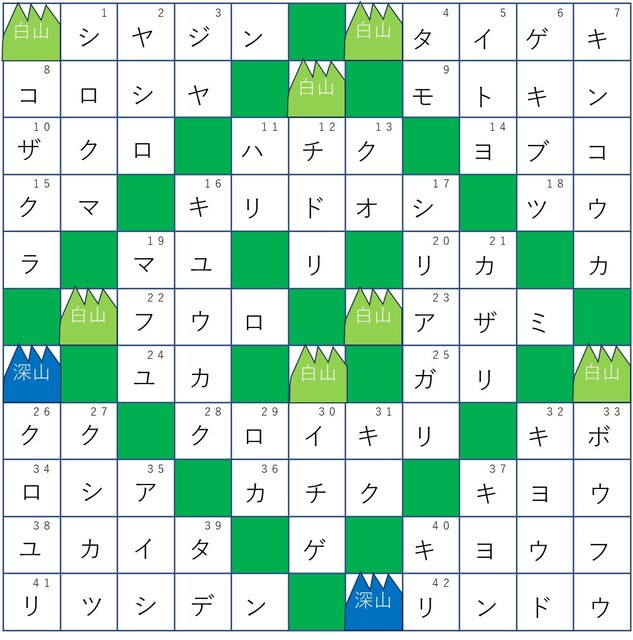この記事は表大雪(旭岳→トムラウシ山)縦走 その⑥(トムラウシ山登頂と南沼の高山植物)の続きです。
7月中旬に3泊4日の日程で、表大雪の旭岳からトムラウシ山までを縦走した。
(地図をクリックすると大きくなります。)

縦走の最終日はトムラウシ山南沼にあるキャンプ指定地からトムラウシ温泉までの10.8kmである。その間のほとんどが下りで、下りの累積標高差が1500mを越えた。登りより下りが苦手な身にとっては、きつい行程だった。
目覚めたときキャンプ場は一面にガスがかかっていた。晴れていれば暗いうちにご来光を観に山頂へ登ることもできたが、山頂は雲の中だった。
正直疲れていたので、登らなくても良かったのは正解だったかもしれない。
朝食・トイレ・撤収を済ませて、キャンプ場を5時13分に出発した。


南沼のキャンプ場からしばらくの間はだらだらとした下りが続いた。お花は既に見慣れたものばかりだった。
・イワイチョウ(岩銀杏、Nephrophyllidium crista-galli 、ミツガシワ科イワイチョウ属の多年草)の葉が鮮やかだった。

・チングルマ(珍車・稚児車、Sieversia pentapetala、バラ科チングルマ属(Sieversia)またはダイコンソウ属(Geum)の落葉小低木)はここでも群落が観られた。

・ウラジロナナカマド(裏白七竃、Sorbus matsumurana、バラ科ナナカマド属の落葉低木)

・イワブクロ(別名タルマイソウ;岩袋、Pennellianthus frutescens、オオバコ科イワブクロ属の多年草)

この縦走で初めて観た綿毛のチングルマ。


・キバナシャクナゲ(黄花石楠花、Rhododendron aureum、ツツジ科ツツジ属シャクナゲ亜属の常緑低木)とエゾコザクラ

・ミヤマオグルマ(深山小車、Tephroseris kawakamii、キク科オカオグルマ属の多年草)

お花の写真を撮っていたので、後から来た人に先に行ってもらった。この日は皆がザックにレインカバーをつけていた。

・エゾコザクラ(蝦夷小桜、Primula cuneifolia、サクラソウ科サクラソウ属の多年草)

・エゾノハクサンイチゲ(蝦夷の白山一花、Anemone narcissiflora. var. sachalinensis、キンポウゲ科イチリンソウ属の多年草)

・エゾイソツツジ(蝦夷磯躑躅・蝦夷石躑躅、Ledum palustre L. subsp. diversipilosum var. yesoense、ツツジ科イソツツジ属の常緑小低木)

岩と池塘と残雪が入り交じった窪地が現れた。トムラウシ公園にさしかかったようだ。先ほどの黄色いレインカバーがもうあんな先へ行っていた。

・エゾノツガザクラ

・エゾコザクラ


・ウラジロナナカマド

・ミヤマバイケイソウ(深山梅蕙草、Veratrum alpestre、ユリ目シュロソウ科シュロソウ属の多年草)の群落


大きな岩を過ぎたところに「トムラウシ公園」の標柱が立っていた。


公園内には奇岩が多い。


振り返って見たトムラウシ公園には、日本庭園的面影があった。

トムラウシ公園を過ぎるとかなりの登り返しとなった。そしてガスが晴れてきた。


・タカネオミナエシ(別名チシマキンレイカ;高嶺女郎花、Patrinia sibirica、スイカズラ科オミナエシ属の多年草)

・イワブクロ

歩きやすい道ばかりでなく、岩場も多かった。


そして岩ゴロゴロの道を下り終えるとトム平に着いた。


トム平付近ではこれまでと違う植物も観られた。
・チシマギキョウ(千島桔梗、Campanula chamissonis、キキョウ科ホタルブクロ属の多年草)


・エゾツツジ(蝦夷躑躅、Therorhodion camtschaticum、ツツジ科エゾツツジ属またはツツジ属の落葉低木)

・イワブクロ(別名タルマイソウ;岩袋、Pennellianthus frutescens、オオバコ科イワブクロ属の多年草)

・ゴゼンタチバナ(御前橘、Cornus canadensis、ミズキ科ミズキ属ゴゼンタチバナ亜属の多年草)

標高1600m地点で大きな岩が連なる所をトラバースし、谷筋に出た。


そこを少し下った所に標柱があった。ここからは沢沿いに下っていく。雪渓を歩けるかと期待していたが、雪はほぼ解けていて歩ける状態ではなかった。


沢沿いに下っていくと、まもなくコマドリ沢分岐に着いた。沢を渡ったところに標柱があった。ここで水を補給した。


コマドリ沢分岐の手前で観たエゾコザクラが、今回の山行でのこの花の見納めとなった。

そしてここから先に観られた花は、高山帯で観られる花から亜高山帯そして山地帯で観られる花に、徐々に変わっていったのが寂しかった。
・オオバミゾホオズキ(大葉溝酸漿、Mimulus sessilifolius、ハエドクソウ科ミゾホオズキ属の多年草)
日本では本州の中部以北の日本海側、北海道に分布し、高山で沢沿いや湿地などの水気のある場所に群生する。

・カラマツソウ(落葉松草、唐松草、Thalictrum aquilegiifolium var. intermedium、キンポウゲ科カラマツソウ属の多年草)

・オガラバナ(麻幹花、Acer ukurunduense、ムクロジ科カエデ属の落葉小高木)

・キタヨツバシオガマ(北四葉塩釜、Pediculais chamissonis var. hokkaidoensis、ハマウツボ科シオガマギク属の多年草)

・ミヤマリンドウ(深山竜胆、Gentiana nipponica、リンドウ科リンドウ属の多年草)

・ハナニガナ(花苦菜、Ixeris dentata var. albiflora f. amplifolia、キク科ニガナ属の多年草)

・ハイオトギリ (這弟切、Hypericum kamtschaticum、オトギリソウ科オトギリソウ属の多年草)
北海道、本州(中部地方以北)の亜高山帯から高山帯の岩礫地や草地などに生育する。

・ハクサンシャクナゲ(白山石楠花、Rhododendron brachycarpum、ツツジ科ツツジ属シャクナゲ亜属の常緑低木)

心配していた右足親指付け根の痛みが出てきた。カムイ天上に着いたら治療しようと頑張って歩いたが長かった。
9時43分にカムイ天上に着いた。靴を脱ぎ痛む部分に痛み止めのテープ(経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤)を貼った。それでも痛むので痛み止めの錠剤を飲んだ。

痛みが何とか治まったので、その後も長い道のりだったが普通に歩けた。10時50分にトムラウシ短縮コース登山口との分岐まで来た。残りは3.9kmで最後に急な傾斜があるが、それまでは緩やかな下りだ。

森の中の道は歩いていて気持ちが良かった。足の痛みもその後は治まってくれていた。

12時33分、無事にトムラウシ温泉登山口に下山した。

4日目に歩いた距離は10.8km、累積標高差は登りが219m・下りが1542mで、歩行時間は途中休憩(32分)を含めて7時間20分だった。
そして4日間を合計すると、歩いた距離は44.7km、累積標高差は登りが2516m・下りが3481mとなった。
憧れていた表大雪の縦走が果たせた。憧れが目標となり、それが果たせた喜びは大きい。今年はまだ行けるが来年は無理だろうと思っていた。しかし実際に歩いてみると、まだ数年は大丈夫なように思う。但し足の痛みはしっかりと治療しなければいけない。専門医に診てもらおうと思った。
表大雪(旭岳→トムラウシ山)縦走 (完)
7月中旬に3泊4日の日程で、表大雪の旭岳からトムラウシ山までを縦走した。
(地図をクリックすると大きくなります。)

縦走の最終日はトムラウシ山南沼にあるキャンプ指定地からトムラウシ温泉までの10.8kmである。その間のほとんどが下りで、下りの累積標高差が1500mを越えた。登りより下りが苦手な身にとっては、きつい行程だった。
目覚めたときキャンプ場は一面にガスがかかっていた。晴れていれば暗いうちにご来光を観に山頂へ登ることもできたが、山頂は雲の中だった。
正直疲れていたので、登らなくても良かったのは正解だったかもしれない。
朝食・トイレ・撤収を済ませて、キャンプ場を5時13分に出発した。


南沼のキャンプ場からしばらくの間はだらだらとした下りが続いた。お花は既に見慣れたものばかりだった。
・イワイチョウ(岩銀杏、Nephrophyllidium crista-galli 、ミツガシワ科イワイチョウ属の多年草)の葉が鮮やかだった。

・チングルマ(珍車・稚児車、Sieversia pentapetala、バラ科チングルマ属(Sieversia)またはダイコンソウ属(Geum)の落葉小低木)はここでも群落が観られた。

・ウラジロナナカマド(裏白七竃、Sorbus matsumurana、バラ科ナナカマド属の落葉低木)

・イワブクロ(別名タルマイソウ;岩袋、Pennellianthus frutescens、オオバコ科イワブクロ属の多年草)

この縦走で初めて観た綿毛のチングルマ。


・キバナシャクナゲ(黄花石楠花、Rhododendron aureum、ツツジ科ツツジ属シャクナゲ亜属の常緑低木)とエゾコザクラ

・ミヤマオグルマ(深山小車、Tephroseris kawakamii、キク科オカオグルマ属の多年草)

お花の写真を撮っていたので、後から来た人に先に行ってもらった。この日は皆がザックにレインカバーをつけていた。

・エゾコザクラ(蝦夷小桜、Primula cuneifolia、サクラソウ科サクラソウ属の多年草)

・エゾノハクサンイチゲ(蝦夷の白山一花、Anemone narcissiflora. var. sachalinensis、キンポウゲ科イチリンソウ属の多年草)

・エゾイソツツジ(蝦夷磯躑躅・蝦夷石躑躅、Ledum palustre L. subsp. diversipilosum var. yesoense、ツツジ科イソツツジ属の常緑小低木)

岩と池塘と残雪が入り交じった窪地が現れた。トムラウシ公園にさしかかったようだ。先ほどの黄色いレインカバーがもうあんな先へ行っていた。

・エゾノツガザクラ

・エゾコザクラ


・ウラジロナナカマド

・ミヤマバイケイソウ(深山梅蕙草、Veratrum alpestre、ユリ目シュロソウ科シュロソウ属の多年草)の群落


大きな岩を過ぎたところに「トムラウシ公園」の標柱が立っていた。


公園内には奇岩が多い。


振り返って見たトムラウシ公園には、日本庭園的面影があった。

トムラウシ公園を過ぎるとかなりの登り返しとなった。そしてガスが晴れてきた。


・タカネオミナエシ(別名チシマキンレイカ;高嶺女郎花、Patrinia sibirica、スイカズラ科オミナエシ属の多年草)

・イワブクロ

歩きやすい道ばかりでなく、岩場も多かった。


そして岩ゴロゴロの道を下り終えるとトム平に着いた。


トム平付近ではこれまでと違う植物も観られた。
・チシマギキョウ(千島桔梗、Campanula chamissonis、キキョウ科ホタルブクロ属の多年草)


・エゾツツジ(蝦夷躑躅、Therorhodion camtschaticum、ツツジ科エゾツツジ属またはツツジ属の落葉低木)

・イワブクロ(別名タルマイソウ;岩袋、Pennellianthus frutescens、オオバコ科イワブクロ属の多年草)

・ゴゼンタチバナ(御前橘、Cornus canadensis、ミズキ科ミズキ属ゴゼンタチバナ亜属の多年草)

標高1600m地点で大きな岩が連なる所をトラバースし、谷筋に出た。


そこを少し下った所に標柱があった。ここからは沢沿いに下っていく。雪渓を歩けるかと期待していたが、雪はほぼ解けていて歩ける状態ではなかった。


沢沿いに下っていくと、まもなくコマドリ沢分岐に着いた。沢を渡ったところに標柱があった。ここで水を補給した。


コマドリ沢分岐の手前で観たエゾコザクラが、今回の山行でのこの花の見納めとなった。

そしてここから先に観られた花は、高山帯で観られる花から亜高山帯そして山地帯で観られる花に、徐々に変わっていったのが寂しかった。
・オオバミゾホオズキ(大葉溝酸漿、Mimulus sessilifolius、ハエドクソウ科ミゾホオズキ属の多年草)
日本では本州の中部以北の日本海側、北海道に分布し、高山で沢沿いや湿地などの水気のある場所に群生する。

・カラマツソウ(落葉松草、唐松草、Thalictrum aquilegiifolium var. intermedium、キンポウゲ科カラマツソウ属の多年草)

・オガラバナ(麻幹花、Acer ukurunduense、ムクロジ科カエデ属の落葉小高木)

・キタヨツバシオガマ(北四葉塩釜、Pediculais chamissonis var. hokkaidoensis、ハマウツボ科シオガマギク属の多年草)

・ミヤマリンドウ(深山竜胆、Gentiana nipponica、リンドウ科リンドウ属の多年草)

・ハナニガナ(花苦菜、Ixeris dentata var. albiflora f. amplifolia、キク科ニガナ属の多年草)

・ハイオトギリ (這弟切、Hypericum kamtschaticum、オトギリソウ科オトギリソウ属の多年草)
北海道、本州(中部地方以北)の亜高山帯から高山帯の岩礫地や草地などに生育する。

・ハクサンシャクナゲ(白山石楠花、Rhododendron brachycarpum、ツツジ科ツツジ属シャクナゲ亜属の常緑低木)

心配していた右足親指付け根の痛みが出てきた。カムイ天上に着いたら治療しようと頑張って歩いたが長かった。
9時43分にカムイ天上に着いた。靴を脱ぎ痛む部分に痛み止めのテープ(経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤)を貼った。それでも痛むので痛み止めの錠剤を飲んだ。

痛みが何とか治まったので、その後も長い道のりだったが普通に歩けた。10時50分にトムラウシ短縮コース登山口との分岐まで来た。残りは3.9kmで最後に急な傾斜があるが、それまでは緩やかな下りだ。

森の中の道は歩いていて気持ちが良かった。足の痛みもその後は治まってくれていた。

12時33分、無事にトムラウシ温泉登山口に下山した。

4日目に歩いた距離は10.8km、累積標高差は登りが219m・下りが1542mで、歩行時間は途中休憩(32分)を含めて7時間20分だった。
そして4日間を合計すると、歩いた距離は44.7km、累積標高差は登りが2516m・下りが3481mとなった。
憧れていた表大雪の縦走が果たせた。憧れが目標となり、それが果たせた喜びは大きい。今年はまだ行けるが来年は無理だろうと思っていた。しかし実際に歩いてみると、まだ数年は大丈夫なように思う。但し足の痛みはしっかりと治療しなければいけない。専門医に診てもらおうと思った。
表大雪(旭岳→トムラウシ山)縦走 (完)