江戸時代から、昭和の頃まで、縁日などで、小屋掛けで見世物小屋が、開かれました。
もちろん近代文明の未だ未発達の時代でした。映画はまだ白黒でしたね。

大阪千里の国立民族学博物館で見世物大博覧会が開催されました。
アメージングショーですね。

テント懸け見世物小屋でしたね。

飲み込んだ金魚を釣り糸をお腹に入れて釣っていた人間ポンプもありましたね。

さまざまな手品師とか、芸人が、見世物の主人公でした。

「足芸」でいろいろな思いものをつま先であやしたり、軽業・曲芸が人気でした。
欧米にまで行って、興業をしていたという。

ラクダも珍獣だったし、へびつかいも街頭で道行く人の目を惹きました。

女軽業師も村のお祭りなどで、小屋掛けしていましたね。宣伝のポスターです。

カメラ撮影が禁止なので、ポスターなどからの取材でした。あと数点あるが、後日です。
















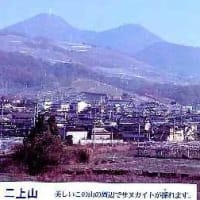
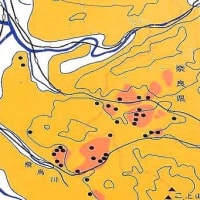


曲芸・今のアニメと違った人の手足で楽しんでたような記憶があります。
面白そうな博覧会ですね。
なんだか懐かしいです
見世物小屋では、中に入らずに、表の看板を眺めていたものでしたよ。
人間ポンプの小屋の前で、変な感覚があったけれど、看板を見ただけででした。
数年後には、B29の爆撃で焼け野原でした。