春を呼ぶ修ニ会の日程がありました。お水取りが済まないと春は来ないと言います。
今日は12日なので、19:30から、お松明が始まります。14:30から講の御籠りの部屋に入ります。待つ間は、一般の参詣場所には出られません。境内を散策して時間つぶしです。

本堂の横に、茶店がありました。右の端に出ていますが行法(ぎょうほう)味噌があり、もろみの味も懐かしい舐め味噌です。

ちょっと購入しました。


本堂の軒に吊るされている「瓜灯篭」と「椿」の土鈴の置物がありました。椿の花は本堂内陣では赤と緑と金色の紙で作られ、本堂の奥にある祭壇に多数飾られている花の一つです。

絵馬が販売されていました。左の絵にある紙製の椿の花は、まさにこれこそが「五色椿」の流れを汲む仏花です。

本堂軒に並ぶ瓜灯篭です。

手ぬぐいが販売されていました。「だったんは聖なる火 迷いを払う」と書かれています。
今夜、深夜を過ぎて、午前3時から本堂奥で、韃靼の祈りが行われます。

こちらは御詠歌で
「ありがたや ふしぎの一か二月堂 若狭の水を むかへたもうぞ」 落款東大寺
こちらは、僧たちが火を囲んで法要する本堂のお勤めを、描いたものです。

東大寺管長の清水公照師の手になる色紙を販売していました。(公照師は、播磨の人で、書写山の麓に作品を数千点展示されています。2007.6/19にアップしています。)

本堂横の斜面では紅梅・白梅が満開でした。

今日は12日なので、19:30から、お松明が始まります。14:30から講の御籠りの部屋に入ります。待つ間は、一般の参詣場所には出られません。境内を散策して時間つぶしです。

本堂の横に、茶店がありました。右の端に出ていますが行法(ぎょうほう)味噌があり、もろみの味も懐かしい舐め味噌です。

ちょっと購入しました。


本堂の軒に吊るされている「瓜灯篭」と「椿」の土鈴の置物がありました。椿の花は本堂内陣では赤と緑と金色の紙で作られ、本堂の奥にある祭壇に多数飾られている花の一つです。

絵馬が販売されていました。左の絵にある紙製の椿の花は、まさにこれこそが「五色椿」の流れを汲む仏花です。

本堂軒に並ぶ瓜灯篭です。

手ぬぐいが販売されていました。「だったんは聖なる火 迷いを払う」と書かれています。
今夜、深夜を過ぎて、午前3時から本堂奥で、韃靼の祈りが行われます。

こちらは御詠歌で
「ありがたや ふしぎの一か二月堂 若狭の水を むかへたもうぞ」 落款東大寺
こちらは、僧たちが火を囲んで法要する本堂のお勤めを、描いたものです。

東大寺管長の清水公照師の手になる色紙を販売していました。(公照師は、播磨の人で、書写山の麓に作品を数千点展示されています。2007.6/19にアップしています。)

本堂横の斜面では紅梅・白梅が満開でした。

















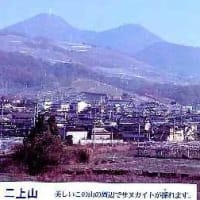
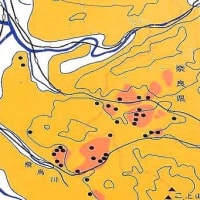


良い時期ですね
さださんの「修二会」は「逢ひみての」というCDに収録されてるみたいです
遭ひみてのですか、ちょっと探してきます。