山之辺の道はそっくり東海自然歩道になっている。
天長元年(824)桓武天皇第7皇子の淳和天皇勅願で、弘法大師が大和(おおやまと)神社の神宮寺として創建した。往時は塔頭48ヶ坊、衆徒300人余名を数えたと言う。
花の寺25か寺の一つで、ヒラドツツジは見事なものである。秋の紅葉も見逃せないポイントである。


かつては七堂伽藍がそろい、多くの建物があった。
右は大門である。釜の口(かまのくち)山長岳寺と門札が出ている。
伝説が残っている。かつて大門の前に刀鍛冶が衆徒相手の営業をしていたと言う。ある時衆徒たちが来て、「ここで作った刀は切れ味が悪い」と言ったので、刀鍛冶は怒って、大門の屋根を支えている肘木を斬ったというのである。それで、この門を「肘切り門」とも言われる。

大門から200m程行くと鐘楼門に出会う。釣鐘をつるための金具がついているので鐘楼門と言う。鐘楼門としては我が国最古の物と言う。国指定重要文化財である。
なかなか風格のある立派な楼門である。

境内にある放生池は静かな佇まいを見せる。人間の為に命を落とした生き物を慈悲の心で放ち、供養する。卒塔婆が中央と両側に計6本立っている。一般に放生会(ほうしょうえ)は8月15日に行われる。

子ども3人に纏わり付かれる地蔵菩薩である。
地獄絵図から読み取ると、子どもが死ぬと、父母の恩に報いずに死んだ為、親への恩返しに河原の石を積む。
夜になると、鬼がやってきて石積みを潰す。「父母が持つ未練の涙がお前達の成仏を妨げるのだ」と鬼は言う。やがて、父母の供養により地蔵菩薩が子ども達を救うと言う。
「一つ積んでは父のため、二つ積んでは母のため・・」とか聞きますね。


左:本堂
右:本尊の阿弥陀如来坐像は水晶の玉眼が入っている。
玉眼の入っている仏像は鎌倉時代のものであるが、この像はさらに古い。鎌倉時代の仏師運慶らは、この像から学んだに違いないと言う。従って、玉眼のある仏像としては最古のものと言えます。


阿弥陀如来の脇侍、観世音菩薩と勢至菩薩は半跏(はんか)像である。
地獄絵の掛軸は縦4m、横1.2mで、9幅ある。一列に並んだ絵図は壮観である。この写真では上部1/3が写っていない。上部には死後に赴く六道の世界での裁判官10人の様子がある。


左:死後乗り越える死天山を降りてくる道が中央に見える。
この山を乗り越える為に、旅の装束を着る。帷子・手っ甲・脚絆・草鞋・杖などを持たせて送るのである。
坂を降りたところにある一本の木は衣領樹と言い、その足元に坐っている二人が見える。赤い服を着た一人は奪衣婆といい、亡者の衣を奪い取る。もう一人は懸枝爺といい、衣を木の上に投げ上げる。
罪の深い者の衣は高い枝に懸かり、善人の衣は低い枝、普通の者の衣は中ほどに懸かる。
その結果、三途(さんず)の川の渡る場所が決まると言う。
橋が見えるだろうか、善人の渡る橋である。その上方で赤いパンツをはいた鬼が槍を持って追い立てているのが悪人の渡る激流である。
船賃として六文銭を入れるというが、この絵図では船は出てこない。
最も下に地蔵菩薩が子供たちを救って、連れて行く図である。
右:焦熱地獄である。罪人を地獄の業火によって焼き焦がす。中央の炎の中をよーく見ると、白い身体の亡者が串刺しにして焼かれる。
炎の左下に串に刺された亡者が見える。炎のすぐ左上では黒い鬼が柱に縛り付けた亡者の舌を抜いている。
この地獄に行くには、生前に、殺生・盗み・邪淫・酒に関する罪を犯すといい。


左:十人の裁判官の長、閻魔大王である。
右:樹上に妙麗の女性がいる。その誘惑に負けた罪人が樹を上って行くと、木の葉が鋭い刃となって、身を切り刻む。それでも上って樹上に着くと、かの女性が樹下にいて、また誘惑する。
身はぼろぼろになるがやめられないという地獄である。
もう地獄を出ましょうか。

この国指定重要文化財の鐘楼門が、西方浄土に沈む太陽を門の彼方から呼び込んでいた。

このテイカカズラの紅葉はなんと美しいことか。生きている証である。
天長元年(824)桓武天皇第7皇子の淳和天皇勅願で、弘法大師が大和(おおやまと)神社の神宮寺として創建した。往時は塔頭48ヶ坊、衆徒300人余名を数えたと言う。
花の寺25か寺の一つで、ヒラドツツジは見事なものである。秋の紅葉も見逃せないポイントである。


かつては七堂伽藍がそろい、多くの建物があった。
右は大門である。釜の口(かまのくち)山長岳寺と門札が出ている。
伝説が残っている。かつて大門の前に刀鍛冶が衆徒相手の営業をしていたと言う。ある時衆徒たちが来て、「ここで作った刀は切れ味が悪い」と言ったので、刀鍛冶は怒って、大門の屋根を支えている肘木を斬ったというのである。それで、この門を「肘切り門」とも言われる。

大門から200m程行くと鐘楼門に出会う。釣鐘をつるための金具がついているので鐘楼門と言う。鐘楼門としては我が国最古の物と言う。国指定重要文化財である。
なかなか風格のある立派な楼門である。

境内にある放生池は静かな佇まいを見せる。人間の為に命を落とした生き物を慈悲の心で放ち、供養する。卒塔婆が中央と両側に計6本立っている。一般に放生会(ほうしょうえ)は8月15日に行われる。

子ども3人に纏わり付かれる地蔵菩薩である。
地獄絵図から読み取ると、子どもが死ぬと、父母の恩に報いずに死んだ為、親への恩返しに河原の石を積む。
夜になると、鬼がやってきて石積みを潰す。「父母が持つ未練の涙がお前達の成仏を妨げるのだ」と鬼は言う。やがて、父母の供養により地蔵菩薩が子ども達を救うと言う。
「一つ積んでは父のため、二つ積んでは母のため・・」とか聞きますね。


左:本堂
右:本尊の阿弥陀如来坐像は水晶の玉眼が入っている。
玉眼の入っている仏像は鎌倉時代のものであるが、この像はさらに古い。鎌倉時代の仏師運慶らは、この像から学んだに違いないと言う。従って、玉眼のある仏像としては最古のものと言えます。


阿弥陀如来の脇侍、観世音菩薩と勢至菩薩は半跏(はんか)像である。
地獄絵の掛軸は縦4m、横1.2mで、9幅ある。一列に並んだ絵図は壮観である。この写真では上部1/3が写っていない。上部には死後に赴く六道の世界での裁判官10人の様子がある。


左:死後乗り越える死天山を降りてくる道が中央に見える。
この山を乗り越える為に、旅の装束を着る。帷子・手っ甲・脚絆・草鞋・杖などを持たせて送るのである。
坂を降りたところにある一本の木は衣領樹と言い、その足元に坐っている二人が見える。赤い服を着た一人は奪衣婆といい、亡者の衣を奪い取る。もう一人は懸枝爺といい、衣を木の上に投げ上げる。
罪の深い者の衣は高い枝に懸かり、善人の衣は低い枝、普通の者の衣は中ほどに懸かる。
その結果、三途(さんず)の川の渡る場所が決まると言う。
橋が見えるだろうか、善人の渡る橋である。その上方で赤いパンツをはいた鬼が槍を持って追い立てているのが悪人の渡る激流である。
船賃として六文銭を入れるというが、この絵図では船は出てこない。
最も下に地蔵菩薩が子供たちを救って、連れて行く図である。
右:焦熱地獄である。罪人を地獄の業火によって焼き焦がす。中央の炎の中をよーく見ると、白い身体の亡者が串刺しにして焼かれる。
炎の左下に串に刺された亡者が見える。炎のすぐ左上では黒い鬼が柱に縛り付けた亡者の舌を抜いている。
この地獄に行くには、生前に、殺生・盗み・邪淫・酒に関する罪を犯すといい。


左:十人の裁判官の長、閻魔大王である。
右:樹上に妙麗の女性がいる。その誘惑に負けた罪人が樹を上って行くと、木の葉が鋭い刃となって、身を切り刻む。それでも上って樹上に着くと、かの女性が樹下にいて、また誘惑する。
身はぼろぼろになるがやめられないという地獄である。
もう地獄を出ましょうか。

この国指定重要文化財の鐘楼門が、西方浄土に沈む太陽を門の彼方から呼び込んでいた。

このテイカカズラの紅葉はなんと美しいことか。生きている証である。
















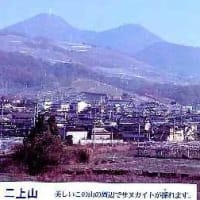
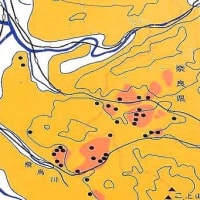


こうして生き方を戒めたんですね~。
大きな掛図です。
常時掛けてあるんでしょうか。
古い仏像もあるんですね。 水晶の玉眼ですか~!
庭の木々が、少しずつ色づいてきたようではありませんか・・・。
かつらは、キレイに紅葉してきましたね。そのうちに葉全部が赤くなるのでしょうね・・・。
大きくて写真は難しい。フラッシュが無ければ撮影はOKです。最近のデジカメはよく撮れるでしょうと和尚が宣う。
和尚の結論は、「地獄極楽この世にある」と、うちのお祖母ちゃんがいつも言っていた言葉でした。