初めの2葉は、以前(2007.2/2)にアップした二月堂です。
左:本堂で、松明が走る回廊が見える。
右:手前が閼伽井屋(あかいや)で若狭(わかさ)井という名の井戸があり、その水をお香水(こうずい)として神に供える。


閼伽井屋の裏に、松明に使う竹が並びます。それぞれ寄進した人の名前を書いて供養します。

閼伽井屋の周囲を、葉守とも言われる柏(かしわ)の葉で取り巻き、中の神聖な井戸を守ります。
屋根の赤い丸印の中を見てください。ここの瓦は鳥の姿です。

拡大しますと、この鳥は鵜です。ここの井戸は若狭井とも言われ、沸いてくる水は若狭(福井県)の国から地下を通って、奈良にやって来ると言われています。
若狭の遠敷(おにゅうう)川から水が流れ込む時に、鵜が水と共に奈良まで流れてきたそうです。
若狭の神宮寺(お水送りの寺)の井戸から、遠敷川の「鵜の瀬」にお香水を流す時、鵜もやってきたそうです。
そして、ここの屋根に止まっていると言います。10日で奈良まで流れて来るというから面白いですね。ロマンがありますね。

さて、二月堂の2月12日は、竹矢来がめぐらしてあります。この斜面の石段を、お香水が登っていきます。

二月堂の回廊から見ると、現在14:30ですが、まだ人はまばらですね。午前3時ごろのお水取りの時に、雅楽を奏するステージが作ってある。

講の人たちが、一夜の休息を取る座敷が並ぶ長屋です。

14時から時が経って、夕陽が美しくなった。西方、生駒山上に沈む夕陽です。


陽がとっぷりと暮れた境内は、ライトが当たって、暗夜に浮かび上がります。


左:本堂で、松明が走る回廊が見える。
右:手前が閼伽井屋(あかいや)で若狭(わかさ)井という名の井戸があり、その水をお香水(こうずい)として神に供える。


閼伽井屋の裏に、松明に使う竹が並びます。それぞれ寄進した人の名前を書いて供養します。

閼伽井屋の周囲を、葉守とも言われる柏(かしわ)の葉で取り巻き、中の神聖な井戸を守ります。
屋根の赤い丸印の中を見てください。ここの瓦は鳥の姿です。

拡大しますと、この鳥は鵜です。ここの井戸は若狭井とも言われ、沸いてくる水は若狭(福井県)の国から地下を通って、奈良にやって来ると言われています。
若狭の遠敷(おにゅうう)川から水が流れ込む時に、鵜が水と共に奈良まで流れてきたそうです。
若狭の神宮寺(お水送りの寺)の井戸から、遠敷川の「鵜の瀬」にお香水を流す時、鵜もやってきたそうです。
そして、ここの屋根に止まっていると言います。10日で奈良まで流れて来るというから面白いですね。ロマンがありますね。

さて、二月堂の2月12日は、竹矢来がめぐらしてあります。この斜面の石段を、お香水が登っていきます。

二月堂の回廊から見ると、現在14:30ですが、まだ人はまばらですね。午前3時ごろのお水取りの時に、雅楽を奏するステージが作ってある。

講の人たちが、一夜の休息を取る座敷が並ぶ長屋です。

14時から時が経って、夕陽が美しくなった。西方、生駒山上に沈む夕陽です。


陽がとっぷりと暮れた境内は、ライトが当たって、暗夜に浮かび上がります。


















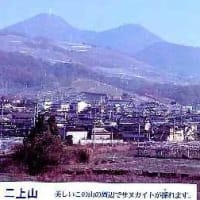
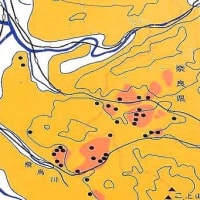


初めて見ました
それから生駒山に沈む夕陽綺麗ですね
ところで さだまさしさんの曲に「修二会」というのがあります
機会があったら聴いてみて下さい
東北の地震は、気が滅入ってしまいそうです。「こんな事をしていていいのだろうか」などと、自然の猛威を感じます。人が奢っていたかも知れませんね。
鵜も一緒に来たのですね。水しぶきまであって、、、二月堂を訪れた時には、気付きませんでした。。
お水取りって、午前2時、3時なのですか。一晩中、、、という行事なのですね。
お水送りがあった後、確か3:00頃から、だったんが始まります。延々と1時間くらいかかります。体力勝負ですね。
これが千数百年続いていたのかと思うと、感動でしたよ。
火は神聖な神ですね。