<これは空想、夢想、妄想の懺悔・告白のような自伝的物語で、2019年5月15日に完成しました。したがって、時制はその当時のものです。>
主な登場人物 <順不同>
山本啓太(主人公) 小出誠一(啓太の同期) 五代厚子(先輩アナウンサー) 江藤知子(同期アナ) 石黒達也(同期アナ) 森末太郎(同期アナ) 木内典子(報道部員) 山本久乃(母) 山本国義(父) 山本国雄(啓太の兄) 陣内春彦社長 星野ディレクター(報道番組) 石浜副部長(報道番組デスク、のちに報道部長) 金森次郎(報道番組) 三雲大輔(ドキュメンタリー班) 蔵原圭一(俳優) 吉永ゆかり(女優) 岡山太郎(ドラマ制作部・ディレクター) 西尾、植木(AD) 蔵原文枝(圭一の妹)ほか
<主な参考文献・ネット資料など>
ピエールとリュース(ロマン・ロラン、渡辺淳訳・鉄筆文庫) ロングラン(村上七郎) メディアの支配者(中川一徳) 昭和史年表(小学館) 昭和史全記録(毎日新聞) 昭和二万日の全記録(講談社) フジテレビジョン開局50年史 開局からの歩み(フジテレビ) タイムテーブルからみたフジテレビ35年史 ウィキペディア全般 放送業界語辞典(ネット) テレビドラマができるまで(東放学園・ネット) 青春の墓標(奥浩平) 吉永小百合ホームページ また逢う日までーピエールとリュース(ロマン・ロラン、窪村義貫訳・明治図書)など



参考文献の一部
〈 前書き〉
老いた山本啓太は時々、昔のことを思い出してみる。人生も終局に近づいてくると、思い出がかえって鮮やかによみがえるようだ。働き盛りの頃は、そんなことに耽る余裕はあまりない。ところが、古希を迎えた頃から思い出す時間が増えてきたようだ。
(1)内勤ニュース班に配属
啓太がFUJIテレビ局(以下、Fテレビとも言う)に入社したのは、もう50年以上も昔のことになる。昭和39年・1964年の春だった。彼はWASEDA大学文学部を卒業してFテレビに入ったのだが、すぐに報道局に配属された。これは啓太が希望した通りの人事だったので、彼は張り切って仕事に取り組もうとした。
ちょうどその年は、東京オリンピックの開催を間近に控えていたので、テレビ局のスポーツや報道などの部門はなにか異様な熱気に包まれていたと思う。ニュースの内勤班に入った啓太も、オリンピック熱に次第に染まっていったようだ。競技そのものはスポーツ局の担当だが、オリンピックの運営や関連施設、社会的な現象などは報道も担当する。
まして新幹線が開通するとか、高速道路やモノレールが完成し、巨大なホテルなどがオープンするとなるとこれはもう大変なことだ。国を挙げての一大プロジェクトである。そうした“オリンピック狂想曲”の中に放り込まれ、啓太は報道部員として揉まれていくことになった。
仕事と言えばニュース原稿を書くことがメインで、外勤記者からの送稿を電話で受けたり、共同や時事など通信社の記事をまとめたり、トピックスを原稿にすることなどが多かった。こうした仕事は慣れてくるとそう難しくはなかったが、アクシデントがよく起きるのは、オンエア(放送中)の時であった。
「おい、山本、世田谷の死亡交通事故の映像は間に合ったのだろうな?」
「ええ、ネガで間に合っているはずです」
ディレクターの藤森が聞くので、啓太はすぐに返事をした。この当時は映像がフィルムで、ポジかネガのチャンネルに分けて送出をしていたのだ。
「そうか、地図だけでなくて良かった。相当な事故現場だったらしいな」
ほっとした表情でそう言うと、藤森がPD席に座る。啓太もすぐ側のAD席に着いた。送り出しをする副調整室(サブ)はスタジオのすぐ上にあるが、ニュースの時間が迫ると、そこは報道部員らで緊迫した雰囲気になるのだ。
放送が開始された。はじめの3項目ぐらいは順調にオンエアされたが、世田谷の交通事故の番になっても、ネガ・チャンネルにフィルムがセットされていない! 啓太はあわててテレシネ装置室にインターカムで連絡する。
「交通事故の映像は入っていないですか!?」
「ああ、まだだよ。ずっと待ってるんだけどね」
テレシネの方からのんびりした声が返ってきた。技術系の人はニュースの切迫感に無頓着のようだ。
「藤森さん、だめです。地図でいかないと・・・」
「なんだ、さっきは大丈夫だと言ったくせに」
藤森PDは軽く舌打ちをして、TD(テクニカル・ディレクター)に地図のテロップに切り替えるよう指示した。その間15秒ぐらいだったろうか、アナウンサーが「しばらくお待ちください」と言ってニュースを中断していた。結局、この時間のロスで放送が“延長”し、最後のCMが入らなかったのである。
「あ~あ、また営業局に謝らないといけないな。山本、もっと早く気がつかないとね」
藤森PDに叱られて、啓太は返す言葉がなかった。フィルム映像の時代はこういうアクシデントがよく起きた。50年前を思い出して、啓太は苦笑いをしたのである。
もっともこの当時は、ニュースはテレビ局が“自前”でやるべきだという意見も強かった。特に報道局では、啓太の上司である稲垣デスク、藤森ディレクターらが「ニュースは商品ではない。Fテレビが自社で提供すべきだ」などと言っていたのだ。だから、CMを軽視するきらいがあったのだろう。
余談だが、CMがAPSという「自動番組制御装置」で必ず入るようになったのは何年か後で、そうなるとニュースだろうが何だろうが、生番組は時間が来れば必ず自動的にカットされるようになった。CMをめぐって営業局とトラブルになることはなくなったのだ。
啓太と同期入社の小出(こいで)誠一が、カメラを持って取材するようになったのもこの頃だった。近い将来、テレビ記者は記事を書くだけでなく、画面に出て話せるように、またカメラ撮影もできなければならないという業務命令があったのである。小出は器用なせいかすぐにカメラに慣れたが、啓太はなかなか上手くなれなかった。
それでも、フィルモ(撮影機)という16ミリフィルムを装着したカメラを持って取材先に出かけた。この撮影機は100フィートのフィルムしか入らないから、撮影時間はわずか3分弱である。後に出てくるビデオカメラとはえらい違いだ。好き勝手に撮っていると、すぐにフィルムがなくなってしまって入れ替えねばならない。

(注・写真は有名なカメラマンのロバート・キャパだが、このような姿勢で当時のカメラ撮影が行われた。おでこにカメラを押し付けると、安定した撮影ができるのだ。)
だから、取材現場の状況を十分に把握して撮影をしていく。そうでないとフィルムが2本、3本とすぐに要ってしまうのだ。もちろん現像には時間がかかるから、1本のフィルムで取材を済ませるのがベストだ。ベテランの上手いカメラマンは、たいていフィルム1本だけで取材を済ませてしまう。
しかし、啓太のような新人はその辺の“コツ”がなかなか呑み込めない。ともすると無駄な撮影に時間とフィルムを使ってしまい、上司のご機嫌を損ねてしまうのだ。そんなある日、撮影デスクの村上から声がかかった。
「山本、明日の午後、日比谷の〇〇会館で皇太子夫妻がセレモニーに出席されるから、撮影を頼むぞ」
村上はそう言って、啓太に取材用の資料を手渡した。
セレモニーの出席者を撮るのは最も簡単な仕事で、たいていは新人カメラマンがすることだ。啓太は気を楽にして、翌日の取材に臨んだのである。何のセレモニーだったか忘れたが日比谷の〇〇会館へ行くと、まもなく皇太子ご夫妻が出席された。ところが、壇上のご夫妻を見上げると、啓太は急に畏れ多くなって近づきがたいものを感じた。
まるで“お雛さま”みたいだ! 美智子妃殿下は特に美しい。しばらくして、撮影許可時間が来た。冒頭の1分ぐらいは撮影して良いので、他社のカメラマンはすぐに皇太子ご夫妻に近づいて「フィルモ」を回す。ところが、啓太は足がすくんで ご夫妻に近づけないのだ。仕方がないのでしばらくロングショットを撮っていたが、気を取り直してご夫妻に近づこうとした。しかし、その時、撮影時間がタイムリミットになったのである。
テレビ局に帰って現像したフィルムを見ると、肝心の皇太子ご夫妻ははるか彼方に“点”のようになって映っている。
「なんだ! こりゃあ・・・」
撮影の村上デスクが、呆れたような怒声を発した。しかし、セレモニーのニュースはやらなければならない。他社のニュースでは両殿下の顔が間近にはっきりと映っているのに、Fテレビのニュースでは、両殿下はまるで“霧の彼方”におわしますように映っていた。啓太はこれには参った。恥をかいて、今度こそきちんと撮影しようと思ったのである。
それ以降、彼は気をつけてカメラ取材をまあまあ無事に済ませたが、せっかく撮ってもオンエアされないことがある。また、放送されても思わぬアクシデントで映らないこともあった。よく起きた事故は、放送中にフィルムがはがれることだ。
その頃、フィルムの編集は「アセトン」という接着剤で貼り合わせていたが、ニュースが追い込みになると、フィルムの“切り貼り”が雑になってくる。映画会社出身の人たちが中心になって編集していたが、中には新人の編集部員もいる。慣れない手付きで切り貼りをしているのだ。
編集したフィルムをリールに巻いてテレシネ装置室に入れたのはいいが、オンエア中に突然 フィルムがはがれたりした。こうなるとニュースは滅茶苦茶になって、収拾がつかなくなる。前のニュースを繰り返したりして、なんとか放送終了まで持っていくのだった。
カメラよりも記者泣かせだったのが、通称「デンスケ」と呼ばれる録音機だろう。重さが9キロ近くもあり、それを肩に担いで録音する。静止している時はまだ良いが、デモの取材など移動する時は重さが肩にズシリと食い込むようだ。ゼンマイ駆動だから、しょっちゅう“手巻き”で動力を確保しておかなければならない。手巻きを忘れると、録音できなくなるのだ。
啓太の先輩はラジオ局出身が多いので、録音もテープの編集も慣れていた。ただし、この編集が面倒くさくて、フィルムと同じように“切り貼り”していくのだ。テープをハサミで斜めに切り、それを白いスプライシングテープでつなぎ合わせていく。不器用な啓太はこの作業が大嫌いだった。非常に細やかな神経が必要で、けっこう時間がかかる。テープの編集が遅れ、オンエアに間に合わなかったことが2~3度あったぐらいだ。
そんな苦しい“修業期間”を経て彼はなんとか仕事をこなしていったが、楽しい時間といえば、やはり同期の面々とおしゃべりをしたり、覚えたてのアルコールで一杯やる時だったろう。啓太の同期でアナウンサーになった江藤知子(ともこ)は、話していると実にざっくばらんで面白い女性だった。
「山本君、少しは仕事 できるようになった?」
“君付け”で上から目線で話しかけてくる。
「知子はどうなんだ? 君の方が心配だよ」
啓太がやり返すが、彼女はまったく気にしない。
「1年間は“試用期間”なのよ。それで駄目だったら、お払い箱になるんですって」
「会社が勝手にクビを切るなんてできないさ~。それより、君はアナウンサーに向いているのかな」
「まあ、失礼ね! これでも大勢の中から採用されたのよ!」
そんな話をしながら、啓太は次第に知子に親近感を持つようになった。
夏になると、開会を10月10日に控えてオリンピック熱ががぜん盛り上がってきた。報道局もオリンピック・チームを編成し、稲垣デスクの下に啓太ら何人もの部員が配属された。やがて特集番組を放送することになり、啓太はオリンピック施設を担当することになった。
そこで、ベテランのカメラマンと一緒に国立競技場や代々木の屋内総合体育館など主な施設を取材して回ったが、今度は自分が下手なカメラで撮ることもなく、記事オンリーだったので気が楽だった。たっぷりと取材して一本の特集にまとめたが、放送前に稲垣デスクが妙なことを言った。
「君の取材は良くできているが、批判的な側面が全然ないね」
「えっ、批判しなければならないんですか? ただの施設の特集だと思いましたが」
「報道はもっと広い見地に立って、いろいろなものを見なければ駄目だよ。まあ、今回はこれでいい。以後、気をつけることだな」
特集は啓太がまとめた通り放送されたが、彼ははじめて報道の難しさを知ったような感じがした。オリンピック熱に煽られていた啓太は、行け行けドンドンという気分に浸っていたのだ。しかし、稲垣に言われて思い当たる節はあった。
例えば1年ほど前、新しい高速道路(4号線)の工事現場となった旧江戸城の跡から、長さ100メートルほどの“謎の地下道”が発見され、考古学者らは喜び勇んで調査を始めた。旧江戸城の構造などを知る上で、非常に重要な手がかりになると思われたのだ。
ところが、オリンピックまでに工事を完成させなければならない道路公団は、その地下道を取り壊した! これには多くの人たちが抗議したが、オリンピックのためには仕方がないという風潮だったので見過ごされた。普段だったら大問題になるところだが、世の中は“オリンピック最優先”になっていたのである。
啓太は稲垣デスクに言われて「なるほど」と思ったが、オリンピック至上主義は変わらなかった。しかし、そういう大プロジェクトの陰に、マイナスの面や被害を受けたり泣き寝入りする人がいることも知ったのである。
ちょうどその頃だったか、撮影の村上デスクが珍しく笑顔を浮かべて啓太に話しかけてきた。
「JALが新しい路線のテスト飛行をやるが、乗ってみないか? 吉永ゆかりも乗るんだって」
えっ、吉永ゆかりもだって!? 吉永と言えばその頃、最も人気のある若手女優で青年たちの憧れの的だった。啓太ももちろん吉永のファン(“ユカリスト”と言う)で、彼女が出る映画はほとんど観ていたのである。こんな“美味しい”話はない。
「ええ、でも僕なんかが乗っても大丈夫なんですか?」
「うん、マスコミ各社への案内だ。誰でもいいんだよ」
村上がそう言うので、啓太は快諾した。あの吉永ゆかりと飛行機に一緒に乗れるなんて・・・しかも、啓太はまだ飛行機に乗ったことがなかった。こんな素晴らしい話はない。JALの宣伝飛行だが、テレビ局に入った冥利に尽きるか。
啓太ははじめそう考えていたが、やがて不思議なことに気分が重苦しくなってきた。どうしてだろう? そう思っているうちに、なにか怖気づいてきたのである。なぜだろう? 吉永ゆかりの幻影が見る見るうちに巨大になり、やがてそれが啓太の心を圧迫してきたのだ。
自分はまだ仕事もロクにできないくせに、そんな美味しい話に乗って良いのか。甘ったれるな! 一人前の報道マンになったら吉永ゆかりと一緒に行動しても良いが、今は早すぎる。そんな理屈をこねて、啓太はJALのテスト飛行に搭乗することを止めた。
彼は「都合が悪くなった」という理由で断ると、代わりに契約アルバイトの学生に行ってもらうことにした。その学生はいつも「Qシート」という番組進行表を書いている仲の良い若者で、彼は嬉しそうな顔をしてテスト飛行に向かったのである。
余談になるが、Qシート(キューシート)というのはフィルムやテロップ、録音テープやCMなど全ての素材の挿入箇所や時間が秒単位で記されており、番組進行にとって最も重要な表である。当時はアルバイト学生がQシートを書いていたが、ある時、バイト料が安いとか待遇が悪いと言って、ほとんどの学生が業務をボイコットしたことがある。
その時は報道部員が全員交代でQシートに取り組んだが、それは面倒臭くて厄介な仕事だった。放送事故も起きたし、つくづく学生たちに頼っていたことを痛感したのだ。
もう1つ、Qというのは英語で「cue」、合図という意味である。放送用語に最も多く出てくる言葉だ。先のQシートだけでなく、スタジオで出演者らに合図や指示を出すのを「Q出し」と言う。これはフロア・ディレクター(FD)がやることだが、報道の記者は原稿の初めに必ず「Q」と書く。
つまり、読み手のアナウンサーに出す「Q出し」の意味だが、アナウンサーに指示をしなくても、原稿の一節、一節ごとにQという印をつけるのだ。啓太は報道局にいる間、アルファベットの「Q」という文字に最も親しむことになった。放送の現場にいる人間は、Qとは切っても切れない関係になるのだ。
余談が長くなったがその頃、啓太たちは昼休みに社員食堂で昼食をとると、あとは会社の3階にある談話室で休憩することが多かった。そういう時はたいてい、職場の同僚や同期入社の仲間とおしゃべりを楽しむのである。アナウンサーの江藤知子ともよく会っていた。彼女とはすっかり仲が良くなっていたのだ。
「山本君、この前、報道の人から面白いことを聞いたのよ」
知子は相変わらず、上から目線ではっきりと言ってくる。
「なんだい? その面白いこととは」
「フフフフ、山本君は時々『ジャマ本』と呼ばれるんですって? 山本がジャマ本になるなんて、上の人はよく見ているのね。ホッホッホッホ」
「誰が言ったんだ? そんなことは気にしてないよ!」
啓太はムッとして答えた。たしかにニュースが追い込みになって忙しい時、新人の彼がウロウロしていると、デスクがいらついてそう呼んだことがある。そんな時は代わりに先輩の報道部員がデスクの所に来るのだが、もう何回か『ジャマ本』と呼ばれた。それを知子は知っていたのか・・・
啓太はすぐに話題を変えようとした。それを察してか、今度は彼女がやや同情っぽい口調で話しかけてくる。
「でも、山本君は真面目だという評判よ。がんばれ、がんばれ」
すっかり知子のペースにはまった感じだ。
「あ~あ、でも何とかなるさ。知子だっていろいろ苦労してるんだろ?」
知子はただニコニコと笑っているだけだった。日焼けした彼女は山登りが趣味だという。小柄で背は高くないがグラマーな感じで、そういう女性を当時はトランジスターグラマー(トラ・グラ)と呼んでいた。
(2)海外ニュース班に移る
そんなある日(8月終わりの頃か)、啓太は報道局内の人事異動で内勤整理班から海外ニュース班へ移された。これは彼にとって意外というか、オリンピックを間近に控えて予想外の異動だった。理由は分からなかったが、たぶん、出来の悪い新入社員は内勤整理から外そうということだったのだろうか。
しかし、もしそうなら海外ニュース班にとっては迷惑な話である。真相は分からないが、とにかく啓太は今で言う「外信部」で働くことになった。同期の小出誠一はそのまま内勤整理に残った。2人は個人的に新宿の居酒屋でささやかな“お別れ会”を開いたのである。
海外ニュース班は10人余りの小さなセクションだったが、仕事量は着実に増えてきているようだ。そう考えれば、啓太の異動も人員の補充ということで納得できるかもしれない。とにかく彼はそこで、慣れない仕事を一から始めたのである。
仕事と言っても、はじめは海外のニュースフィルムの整理が主で、アメリカのAPやUPI、ABCやCBSといった通信社、放送局などの素材を分類したりチェックすることだった。そして、フィルムに添えられたキャプション(説明文)を翻訳し、放送原稿にするのが主な仕事だったろう。啓太は英語があまり得意ではなかったが、辞書を片手に面白い映像のキャプションを原稿に変えていった。
そうしたある日、江藤知子と同期のアナウンサー・石黒達也が、1年先輩の女子アナ・五代厚子を連れて啓太を誘いにきた。昼休みなので、4人は3階の談話室へ向かった。啓太は知子や石黒とはしょっちゅう会っていたが、五代は初めてである。
この談話室は広々として外の眺めが良く、そこにいるだけで心がくつろぐ。椅子やソファーも大きくゆっくりと座れるのだ。4人は雑談に花を咲かせたが、途中で石黒が知子に向かって話しかけた。
「君の“彼氏”は今どういう仕事をしてるの?」
「広告代理店で営業の現場に行ったの。まだ見習い中ね」
啓太は初めて知子に“彼氏”がいることを知った。これは意外だ。こんなにしょっちゅう付き合っているのに、彼女はそのことにまったく触れてこなかったのだ。知子は意図的に隠していたのだろうか?
もっとも、啓太の方もあえて聞こうとはしなかった。知子に彼氏がいるかいないか知りたくもなかったし、もしいれば、自分が少しがっかりするだろうと思ったからだ。ということは、彼は知子に想いを寄せている自分を意識していたのだ。
しかし、そんな話はもちろんこの場でする気はない。啓太は3人のアナウンサー同士の会話を聞いていたが、五代は1年先輩だけあって、後輩の2人に忠告をしたり意見を言うことが多かった。また、自分のペースで会話をリードしていくところもあった。
「今度みんなでジャズを聴きに行かない? 面白いわよ」
「また、厚子さんのお誘いか。山本はまだジャズを聴いたことがないんだろ?」
「もちろん、まだないさ」
石黒が話を振ってきたので、啓太は即座に答えた。
「山本さんは真面目だけど、固いわね~」
厚子が顔を少し“しかめて”言ったので、啓太は不愉快な気分になった。初対面だというのに、彼女は図々しいのではないか。たかが1年先輩なだけだ。放っといてくれと言いたい気持になる。すると、知子がその場を収めるように割って入った。
「厚子さんは大学時代にジャズクラブのメンバーだったのよ。それも、スチール・ギターを弾いていたの。ジャズ演奏の中心ね。だから一緒に聴きに行こうってわけ。山本君も良ければということで、考えておいてくれればいいのよ。私たちは行こうと思うけど」
ジャズの話はそれで終わったが、啓太は、どうして五代厚子が後輩の仲間の中に割り込んで来たのかといぶかしく思った。ただの成り行きだったのだろうが、それとは別に、彼は知子に“恋人”がいそうなことがとても気になってきた。そのことを、いずれはっきりと聞かねばならない。やがて、4人はそれぞれの職場に戻った。
それから数日して、啓太は意を決し江藤知子を談話室に呼んだ。2人だけで話そうとしたのだ。
「君には付き合っている彼氏がいるんだって?」
啓太が単刀直入に聞くと彼女はしばらく黙っていたが、やがて改まったような口調で話し始めた。
「同じ大学で登山クラブにいたの。この前言ったように、彼はH広告代理店に入ったわ。わたしと同期なの。今でも一緒に山登りしているのよ。あとは特にないわ」
知子はそう言うと、もうこれで話すことは何もないという風に視線を外の景色の方へ向けた。
「ふ~ん、そういうことなの」
啓太はそう答えるしかなかった。これ以上聞いても野暮だし、知子をいら立たせるだけだろう。彼は話題を変えて、最近のFテレビのことや報道の状況を一方的に話し始めた。知子は笑みを浮かべて聞いていたが、いつもより口数が少なく相槌を打つ程度だ。どこかよそよそしい態度にも見える。
「君は今日は静かだね。あまりしゃべらないじゃないか」
「そう? そう見えるかしら・・・」
そう言って知子はにっこりとほほ笑んだが、また無口な状態に戻った。啓太は彼女をまじまじと見つめる。小柄だが、がっしりとした体つきは登山で鍛えたせいか。胸や腰はふっくらとして、トランジスターグラマーそのものである。啓太はこういう女性に惹かれるが、大抵の男性がそうなのだろう。
2人は30分ぐらい談話室にいて別れたが、この前、五代や石黒とジャズを聴きに行く話を約束した。ジャズを生で聴いたことがない啓太も今度は乗り気になったのである。 知子に“彼氏”がいることを知って啓太はやや気落ちしたが、彼女への好意は少しも変わらなかった。いや、むしろ強まったのではないか。それが若さというものだろう。
<余談・・・当時のテレビ映像はもちろん白黒(モノクロ)だったが、この年、東京オリンピックを10月に控えて、各局ともにわかに“カラー化”を進めることになった。Fテレビも9月から初めてカラー番組をスタートさせることになる。東京オリンピックはカラー放送の大きな引き金になったのだ。>
その頃、Fテレビでは東京オリンピックの取材と放送の準備で大わらわとなっていたが、報道の海外ニュース班にいる啓太にとってはそれほど忙しくならなかった。せいぜいオリンピック関連のニュースをフォローするだけで、通常の勤務を続けていたのである。
わりと時間があったので、啓太はよくアナウンス室へ遊びに行った。そこで江藤知子や五代、石黒ら顔見知りのアナウンサーと雑談を交わしていたが、用もない啓太が遊びに来るのは当然良い印象を与えなかった。アナウンス室の部長やデスクは、渋い顔つきで啓太を睨みつけたりしたのだ。
彼はそれをあまり気にしなかったが、一方的に知子に好意を寄せているという評判はあちこちに知れ渡った。技術局の同期の榎並伸介とテレシネでばったり顔を合わせたら、榎並が皮肉っぽい口調で語りかけてきた。
「君は“横恋慕”してるんだって? ハッハッハッハッハ」
横恋慕? なんだ、変なことを言うじゃないかと啓太は思ったが、すぐに知子との噂が同期社員の中に行き渡っていることを知った。榎並が横恋慕という言葉を使ったことに啓太は苦笑したが、素知らぬふりをしてその場を立ち去ったのである。
五代厚子らとジャズを聴く日が近づいたが、その前日になって知子が「都合が悪い」と言って断ってきた。啓太は少し不満だったが仕方がない。五代と石黒の3人で聴きに行くことになり、当日、銀座のジャズ・ライブハウスに彼らは出かけた。
ジャズの生演奏を聴くのは初めてだったが、啓太は意外に楽しかった。反対に石黒はどこかつまらなそうな様子だった。厚子は演奏の合い間にあれこれと啓太に話しかけ、ジャズを満喫しているようだ。知っていることを啓太に教え、満足していたのだろう。
演奏会が終わると3人は場所を変え、近くのスナックバーに立ち寄った。ここも厚子の馴染みの店である。彼女を真ん中にしてカウンターに腰を下ろし、カクテルやバーボン・ウィスキーを適当に注文する。
「いや、意外に面白かったね。生でジャズを聴くのは初めてだったから」
啓太が素直にそう言うと、厚子が答えた。
「よかったわ、山本君に喜んでもらって。達也さんはそうでもなかった?」
「う~ん、今日は山本の“お供”だったからな。それに、知子が急に来れなくなったんだもの・・・」
石黒が面白くなさそうに答えた。
それでも3人はカクテルやバーボンの水割りで乾杯すると、あとは雑談に花を咲かせた。ジャズの生演奏ではつまらなそうな表情だった石黒も、おしゃべりとなるとがぜん元気が出てくる。もともと話好きなのだ。
「厚子さんはハワイアンも得意だし、ジャズもよく知ってるな~。山本との話を側で聞いていたら感心しましたよ」
石黒が厚子を持ち上げたので、3人はしばらく音楽の話に夢中になった。厚子がバンドやスチール・ギターなどの話をすると、石黒がよく質問をする。啓太はほとんど聞き役だったが、飽きることがなかった。おしゃべりはいつの間にかアナウンス室のことに移り、石黒が某デスクの対応を批判した。
厚子がそれに答える形で何か話していたが、話題は個々人のアナウンサーのことに移ってきた。
「あ、そうそう、知子はもうすぐ“婚約”するそうだね。厚子さんは何か聞いていないかしら?」
江藤知子の話が出たので、啓太は一瞬、ほろ酔い気分が醒めたような感じがした。
「じかに聞いてないわ。でも、そういうこともあるかも・・・」
厚子が言葉を濁すように答えたので、石黒もそれ以上は知子のことに触れなかった。あとは彼が新入社員の給料や会社の待遇面の話をしたので、啓太も思っていることを率直に話した。初めて月給を受け取った時のことは忘れられないのだ。
「伊勢丹へ行って、シチズンの腕時計と替え上着を買ったら、3万円の初任給は全部なくなりましたよ」
啓太がそう言うと厚子がおかしそうに笑った。そんな雑談が1時間あまり続いただろうか。3人は切りの良いところでスナックバーを後にした。石黒や厚子と別れて1人だけになると、啓太はまた江藤知子のことを思い出した。彼女はもうすぐ“婚約”するのか・・・ 石黒の言った話が耳の奥にこびりついて離れなかった。
<余談・・・その頃の新入社員の初任給は、平均で2万円あまりだったろう。Fテレビの約3万円は相当に高い方だ。当時の最高初任給は「東洋レーヨン」の3万7千円ぐらいだったと記憶している。Fテレビは初任給でベストテンに入っていたが、時間外手当がほぼ“青天井”の先輩局・NIPPONテレビやTOKYO放送に比べ、実収入ではかなり劣っていたと思う。当時は、繊維・紡績関係の会社が高賃金だった。>
8月から9月にかけて、啓太は遅い夏休みを取った。特に予定もなかったので地元・浦和(現さいたま市)の市民プールへ行ったりしていたが、同期の小出誠一と石黒達也は伊豆大島へ泳ぎに行ったという。小出と石黒は仲が良く、遊泳などの趣味も似通っていたようだ。2人から夏休みの話をたっぷりと聞かされた。
気になっていた江藤知子は、例の“彼氏”と北アルプスの奥穂高へ登山に行ったらしい。彼女はもう詳しい話を啓太にしたがらない。明らかに彼を避けている感じだ。啓太は何もかもはっきりさせようとその機会をうかがっていたが、いざとなると彼は動揺して怖気づいてしまうのだ。
しかし、9月に入ったある日、啓太は意を決してアナウンサー室を訪れた。幸い部長やデスクはいないし、数人のアナウンサーがいるだけだ。五代厚子はいなかったが、石黒がちょうど居合わせている。これは好都合だ。啓太は彼に目配せすると、席に座っている知子に声をかけた。
「夏休みは奥穂高へ行ったんだって?」
「・・・」
知子は何も答えずうつむいている。啓太はさらに畳みかけて聞いた。
「いいな~、彼と一緒で。もうすぐ彼と婚約するんだって?」
その途端、知子はきっとなって顔を上げると叫んだ。
「私は“売約済み”よ! 他にいい人がたくさんいるでしょ! そういう人と付き合いなさいよ」
啓太が呆気にとられていると、石黒がこらえ切れずに吹き出した。
「売約済みだって・・・ハッハッハッハッハ」
啓太はそれ以上声をかけることができず、やがてアナウンサー室から立ち去った。江藤知子への淡い恋心は、こうして潰え去ったのだ。彼はそのまま近くのF(エフ)という喫茶室へ向かった。ここはFテレビ本館の2階にある喫茶室で、別館の談話室とともに社員がよく利用する施設である。
啓太は一番空いている奥の座席に座ると、まだ飲みなれないコーヒーを注文した。そして、先ほどの江藤知子とのやり取りを思い出しながら、コーヒーの苦い一杯を味わったのである。
彼は喫茶室の奥で長い間ぼんやりしていた。知子の交際拒絶は、啓太にとって精神的にかなり痛手だった。それも無理はないだろう。彼はよく言えば純情、皮肉っぽく言えば初(うぶ)で奥手だから、相手の反応がストレートに心に響いて傷つく。心に“ゆとり”がないのだ。もちろん啓太でなくても、失恋は誰にとっても辛いものだが・・・
喫茶室で時間を過ごしたあと、彼は職場の海外ニュース班に戻った。すると待ちあぐねたように、デスクの須藤が啓太に声をかけてきた。
「遅いじゃないか。早く海外トピックスを3本ほど用意してくれ。夕方のニュースに入れるんだ」
須藤デスクはそう言うと、外国通信社などのキャプションが入った箱を啓太に手渡した。題名だけは翻訳しているが、中身はこれから訳して放送原稿にしなければならない。しかも、面白いトピックスかどうかは、フィルムを一つ一つチェックしなければならないのだ。これは当たり前の作業だが、海外ニュース班に来た当時は啓太もだいぶ手間取った。翻訳自体に時間がかかって、須藤デスクによく𠮟られたことがある。
「遅い! だいたい君は“コネ”で会社に入ったのか?」
「そんなことはないですよ。ちゃんと試験に受かって入社したんです」
啓太はつい抗弁したが、優秀な須藤デスクは疑わしいという表情を見せていた。テレビ局にはコネ入社の社員がけっこう多いのだ。そんな苦労を重ねて、啓太はようやく翻訳と原稿書きに慣れてきた。彼はキャプションを何枚か選ぶと、フィルム保管室に向かい作業を開始した。










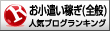















矢嶋さんの場合は一般的からいうとかなり華やかなご職業に感じられますが、そのぶん緊迫感緊張感は大変なものだったでしょうね。
その中で若い主人公が経験していく山あり谷あり?・・・物語は興味をそそります。
エピソードには事欠かない環境ではなかったでしょうか。。。(^_-)-☆
ちょうど東京オリンピックの時に入社したので、なかなか面白かったです。今度のオリンピックはどうなるか・・・ あれから半世紀以上がたっているので興味深いものです。
昔のことを書いていると、いろいろなことが思い出され懐かしくなります。
個人的なことは当然ですが、当時の時代背景や出来事などが蘇ってきますね。そういう意味で参考になってもらえれば幸いです。今後もよろしくどうぞ。