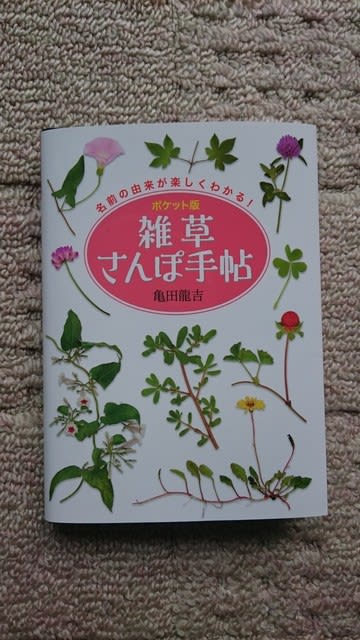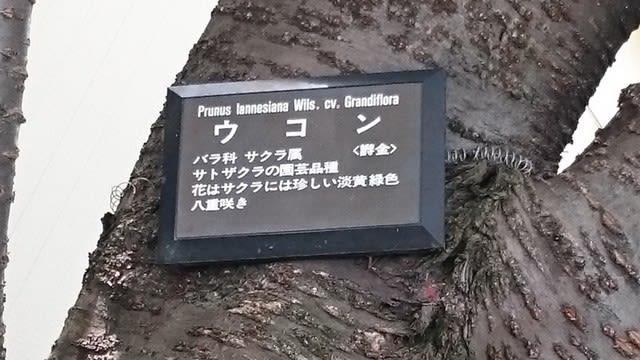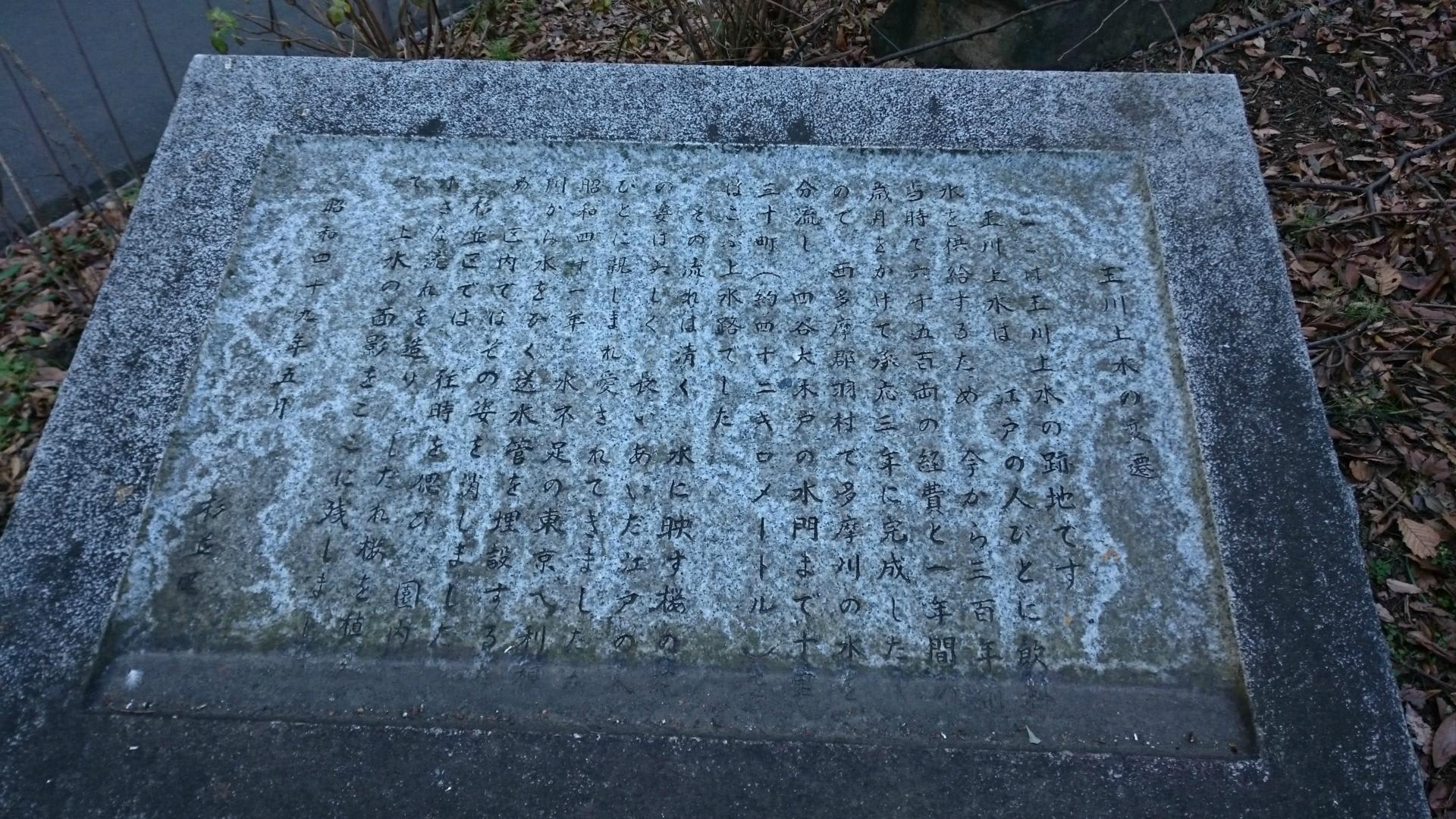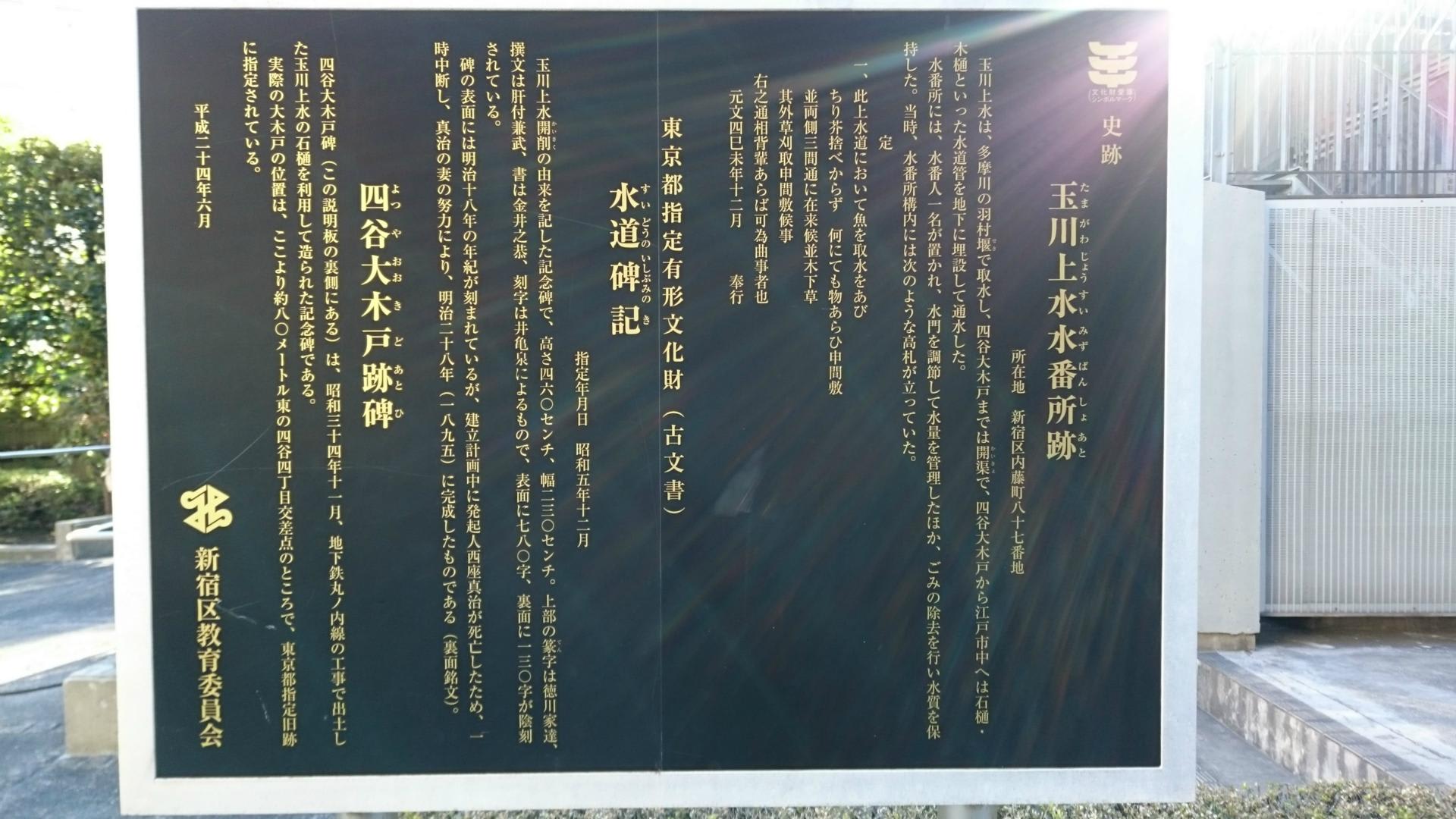平成29年5月8日(月)、久しぶりの早朝散歩です。
コースは八国山の尾根を経て荒畑富士、多摩湖と歩きました。
八国山近くの遊水池に青鷺でしょうか大型の鳥がいました。

八国山の登り口です。

将軍塚近くの特高線の下が伐採されていました。

尾根道の分岐点。
清里ではまだ若葉もでていなかったのに、こちらでは初夏のような感じです。

「ほっこり広場」ではもう咲いていないと思っていた「セリバヒエンソウ」がまだ咲いていました。
嬉しかったですね。

ほっこり広場です。

西武園近くの特高線の下もやはり伐採されていました。

荒畑富士近くの「ドレミの丘公園」です。


荒畑富士と浅間神社です。

ツツジがきれいに咲いていました。

登り口です。

登り口に「猿田彦神社」がありました。

山頂です。

下山道から浅間神社を見たところ。

多摩湖です。
空と多摩湖の水の青がきれいでした。


小学生の遠足でしょうか堰堤を登ってきました。

狭山公園の管理等の近くにアンケート入れの小さな小屋の模型がありました。
今度、小屋の模型を作ってみようと思っています。

北山菖蒲園です。
6月には見物の人たちで賑わいますが、まだ静かな佇まいでした。


約3時間の散歩でした。
新緑の中を歩くのは気持ちがいいものですね。
お疲れ様でした。
コースは八国山の尾根を経て荒畑富士、多摩湖と歩きました。
八国山近くの遊水池に青鷺でしょうか大型の鳥がいました。

八国山の登り口です。

将軍塚近くの特高線の下が伐採されていました。

尾根道の分岐点。
清里ではまだ若葉もでていなかったのに、こちらでは初夏のような感じです。

「ほっこり広場」ではもう咲いていないと思っていた「セリバヒエンソウ」がまだ咲いていました。
嬉しかったですね。

ほっこり広場です。

西武園近くの特高線の下もやはり伐採されていました。

荒畑富士近くの「ドレミの丘公園」です。


荒畑富士と浅間神社です。

ツツジがきれいに咲いていました。

登り口です。

登り口に「猿田彦神社」がありました。

山頂です。

下山道から浅間神社を見たところ。

多摩湖です。
空と多摩湖の水の青がきれいでした。


小学生の遠足でしょうか堰堤を登ってきました。

狭山公園の管理等の近くにアンケート入れの小さな小屋の模型がありました。
今度、小屋の模型を作ってみようと思っています。

北山菖蒲園です。
6月には見物の人たちで賑わいますが、まだ静かな佇まいでした。


約3時間の散歩でした。
新緑の中を歩くのは気持ちがいいものですね。
お疲れ様でした。