11月12日(土) 14時45分~15時25分
9.向峠神楽保存会(岩国市錦町宇佐郷向峠)
黒塚

⬛団体紹介
向峠神楽の起源は、約160年前の江戸時代後期の安政年間(1854年~1860年)と伝えられています。天保の大飢饉(1833年~)を機に向峠地区に水路を整備するため、庄屋・山田利右衛門が、十数年に亘る水路工事を完成させ、その記念に山代神楽を習得し、の若者に教え、秋祭りに奉納したのが始まりとされています。明治二十六年には玖北神官取締支所より神社付神楽の証を得て、他の神社に奉納するようになりました。また、大正初期には島根県より石見神楽を取り入れ、現在の向峠神楽保存会に継承されていきました。現在では若手を中心にして、上は70歳代から下は高校生までの団員で、少数ながら皆が仕事や学校を両立させ、地区に伝わる伝統芸能を守っています。
⬛演目紹介
本日、演じますのは、「黒塚」でございます。那智の阿闍梨祐慶大法印(あじゃりゆうけいだいほういん)が剛力二人を連れて諸国修行の旅の途中に、妊婦で実は白面金毛九尾の悪狐が住むという黒塚にさしかかりましたが日が暮れたので一軒の家に宿をもとめたところ、その家の女主人は喜んで宿をかします。その夜女主人が悪狐となってあらわれ剛力二人は食い殺され法印一人難を逃れます。それを聞いた三浦介と上総介が勅命を受けて那須野に行き悪狐を退治するという物語です。
←8.長野神楽舞保存会
9.向峠神楽保存会
→10.岩国太鼓保存会
民俗芸能まつりトップへ
11月12日
11月13日
9.向峠神楽保存会(岩国市錦町宇佐郷向峠)
黒塚

⬛団体紹介
向峠神楽の起源は、約160年前の江戸時代後期の安政年間(1854年~1860年)と伝えられています。天保の大飢饉(1833年~)を機に向峠地区に水路を整備するため、庄屋・山田利右衛門が、十数年に亘る水路工事を完成させ、その記念に山代神楽を習得し、の若者に教え、秋祭りに奉納したのが始まりとされています。明治二十六年には玖北神官取締支所より神社付神楽の証を得て、他の神社に奉納するようになりました。また、大正初期には島根県より石見神楽を取り入れ、現在の向峠神楽保存会に継承されていきました。現在では若手を中心にして、上は70歳代から下は高校生までの団員で、少数ながら皆が仕事や学校を両立させ、地区に伝わる伝統芸能を守っています。
⬛演目紹介
本日、演じますのは、「黒塚」でございます。那智の阿闍梨祐慶大法印(あじゃりゆうけいだいほういん)が剛力二人を連れて諸国修行の旅の途中に、妊婦で実は白面金毛九尾の悪狐が住むという黒塚にさしかかりましたが日が暮れたので一軒の家に宿をもとめたところ、その家の女主人は喜んで宿をかします。その夜女主人が悪狐となってあらわれ剛力二人は食い殺され法印一人難を逃れます。それを聞いた三浦介と上総介が勅命を受けて那須野に行き悪狐を退治するという物語です。
←8.長野神楽舞保存会
9.向峠神楽保存会
→10.岩国太鼓保存会
民俗芸能まつりトップへ
11月12日
11月13日










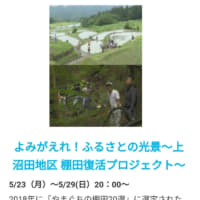









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます