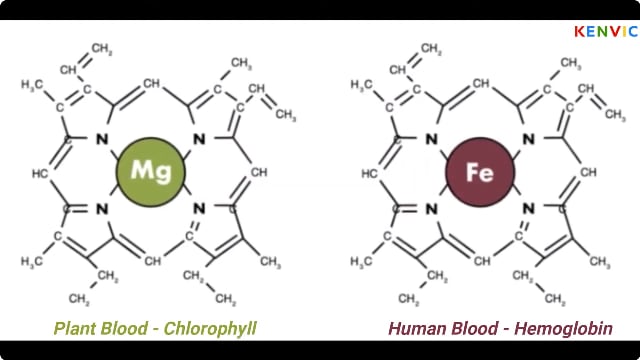今回は、『皇漢医術百話』(木村克己:著、温知社:1936年刊)という本に、フグの毒では人間は死なないということや、逆にフグ中毒で難病が治ってしまうことが書かれているので、詳しくご紹介したいと思います。
それによると、陸軍少将・多賀宗之氏の友人に、数代にわたってフグを研究している広島県在住のフグ研究者がいて、この本の著者である木村克己氏は、その研究者の体験談を多賀氏から聞いたわけですが、その特筆すべき点は以下のようになります。
1.リンパ系関係の疾病を持たない人間は、決してフグ中毒を起こさない。
フグ毒はリンパに作用してその活動を促すので、リンパの活動によって除去せらるべき何物もない時は、中毒症状を起こさないのである。
2.フグ中毒を起こした場合、仮死状態になることがあるが、決して死ぬことはない。
もしリンパ関係の疾病がある者がフグ毒を食べた場合は、活動を促されたリンパは病毒を駆逐しようとして、そのところに烈しい抵抗を生じ、循環系統や、呼吸器や、神経の働きは一時その作用を休止する。これを医者や世間一般の人は中毒で死んだといっているが、それは死んだのではなく、仮死状態になっただけである。仮死状態は3日ないし5日間、多くて1週間位である。しかしながら例外として49日間仮死状態を継続した記録保持者がいる。
3.フグ毒は人間を仮死状態にしてまでリンパに働くが、その作用が済むと人は自然に覚醒する。
仮死状態となった者は、決して強直状態を生じない。また数日以上そのままにしても臭気も発しない。医療を施さず、放置して自然に覚醒するのを待つのが最善である。覚醒時の状態はだれもかれも一様で、醒めると直ぐ両腕を掻く、次に胸を掻く、次に背を掻く、その掻き方は極めて激しく、皮膚が破れるかと思われる程強く掻く、そうして大きな欠伸を幾回となく続ける。
4.これで梅毒ライ病等は奇麗サッパリ治ってしまう。
つまりリンパ系統が猛烈に働いて、体内の毒素を悉く排泄浄化してしまうからで、梅毒やライ病にはこれ程簡単で、かつ偉功ある療法は他に決してない。
5.コレラ、疫痢、チフスその他一切腸の急性疾患には、フグの卵の乾物を服用すると腸のリンパが猛烈に働き、毒素を排泄して全治する。往年コレラ大流行の時は、横浜でその患者を見つけ次第服用させて治した。
6.ある梅毒の患者があった。これはフグを食べて若干日仮死すれば必ず治るのであるが、勧めるわけにもならず、そこでフグの黒焼を久しく連服させたら、身体中に腫物が出来た。それを松葉でつぶしつつ経過させたら、その後腫物全部カサブタとなり、更に剥離して全治した。
7.癌は如何なる種類のものでも、フグの中毒で仮死状態になったものについて見れば、癌の部分と健康部との境界に皮膜が出来て自然に脱落するもので、これは胃癌なら大便の中から、子宮癌なら月経と一緒に、排泄された癌腫の脱落片を発見する事によって証明される。
以上です。
なお、誤解のないように説明しておきますが、ここで私が言いたいのは、がんを治すためにフグを食って仮死状態になれということではありません。
そうではなく、フグ中毒の場合、身体が毒に対処しているうちに腫瘍が自然に剥がれ落ちてしまうわけですから、がんはフグの毒に比べたらささいなことだということです。
ですから、がんを宣告されても動揺することなく、むしろ生活習慣を見直す絶好の機会を得たことを喜んで、本ブログでご紹介している対処法をできるだけ多く実行するようにしていただきたいのです。
なお、フグの毒では人間は死なないという主張はそのまま信じるわけにはいかないので、いろいろと調べてみたところ、『天城の山の物語 猫越峠 わさび沢』(野木治朗:著、俳句研究社:1964年刊)という本に、フグ毒で死亡診断後6日目に生き返った実話が紹介されていました。
それによると、酒の肴にフグの素人料理を食べた5人が全員中毒を起こし、全身がケイレンして体は硬直し、皮膚が紫色に変わって、これを診た医師は、死亡したものと判定して、何等手を下さなかったそうです。
ところが、唯一人、その場でフグを食べなかった人物がいて、彼は桑畑に5人分入れる穴を一つ一つ堀り、棒鱈のように堅くなった5人の体を埋めて首から上だけ地上に出し、石の枕をあてがったそうです。
そして、5日間、桑の木を燃やして煙をあげ火をたやさないようにし、その間ろくに眠らず、めしも食ったり食わなかったりと大変苦労したのですが、6日目の朝、石を枕にして埋まっていた男等の顔がそろって素顔になり、その日のうちに真ン中の男の眼玉が動き出し、それと前後して、全部の者が息を吹き返したのだそうです。
これに関しては、『斯くして全快すべき肺自己療養法』(上野実雄:著、天然療養社:1918年刊)という本に、淡路島の近海では、漁師がフグの中毒で苦しむときは、海岸の砂を掘って、首から下を数時間生き埋めにすることによって再生したことが書かれているので、フグ中毒患者を土に埋める治療法は広く知られていたのかもしれません。
また、フグ中毒に限らず、医師から死亡判定された人が生き返ったというニュースは時々目にすることがありますから、木村氏の話もある程度信用してもよいのではないかと思われますし、死者を葬る場合は、生き返る可能性を常に考慮しておく必要があるようです。
ところで、『損害賠償 被害者救済の法律』(加藤了:著、日本経済新聞社:1982年刊)という本によると、昭和50年1月15日夜、京都南座の初春公演に出演していた人間国宝の歌舞伎俳優、8代目・坂東三津五郎が、ひいき筋の会社役員ら5名と一緒にフグ料理店にフグを食べに行き、結局彼だけがフグ中毒となり、翌16日午前4時40分ごろ死亡するという事件があったそうです。
この場合、もし『皇漢医術百話』を読んでいる人が周囲にいて、1週間ほど死体を放置して様子を見ていたら、違った結果になっていたかもしれませんね。

にほんブログ村